2020年05月22日
キャリアについて考える意味 Vol.4
~ 社会環境変化について ~
■トヨタ自動車社長のコメントが物議をかもしている
昨年5月、日本自動車工業会の豊田章男 会長(トヨタ自動車 代表取締役社長)は会見で、「日本の“終身雇用”を守っていくのが難しい局面に入ってきた」と話した。
“終身雇用”を巡っては、経団連 中西宏明会長(日立製作所 会長)の「企業からみると、従業員を一生雇い続ける保証書を持っているわけではない」、経済同友会 桜田謙悟代表幹事(SOMPOホールディングス 代表取締役社長兼CEO)の「“終身雇用”という制度は、『制度疲労』を起こしている可能性がある」等、経済界の重鎮が終身雇用見直し論ともとれる発言をしている。
マスメディアやSNS上では、「“終身雇用”の崩壊で若手社員の給与はアップする」vs「長期雇用は“雇用制度”ではなく“経営家哲学”だ!」他…、賛否両論が渦巻いている。
■“事実”で語ろう!?
ここでは、“終身雇用”の賛否は置いといて、事実を共有しておきたい。平成30年1月発表の内閣府の資料(日本経済2017-2018)によると、男性の場合、初職(学校卒業後はじめて就いた仕事)が正社員である割合は79%。そのうち一度も退職することなく“終身雇用”パスを歩んでいる(退職回数0回)のは、30代で48%、40代で38%、50代で34%。わかりやすく言うと、50代で初職の会社に勤め続けている人は、79%×34%≒26.9%、同年代の男性の4人に一人ということになる。
女性の場合、初職が正社員である割合は76%と男性と大きな違いは無いが、“終身雇用”パスを歩んでいるのは50代で7%程度(76%×7%≒5.3%)。つまり“終身雇用”パスを歩んでいるのは、同年代の女性の20人に一人ということになる。女性の場合は、仕事を辞めちゃう人の割合も高そうだ。
ボクは政治家でもないし、学校の先生でも無いので、“日本型雇用慣行”や“終身雇用”について、自身の考えを語るつもりはないけれど、事実を知っとくことは大切だ。
■人の意識は変わらない…
かつては、“日本型雇用慣行”の代名詞的に言われていた“終身雇用”。現実は前述した通りだが、人のもつ“イメージ”が“事実”として認識されるには、多くの時間を要するとも思っている。
1991年にバブル経済が崩壊し企業のリストラが進む中(この頃、“日本型雇用慣行”は崩壊したと言われていた)、ボクは再就職支援の事業に携わっていた。リストラされた中高年の人たちが、「こんなハズじゃなかった…」と言って肩を落とす姿を見て、自分の子供たちの世代の若者には、「同じ想いをさせたくない」と考え2002年に人材コンサルティングの会社をはじめた。
けれども、20年経っても、多くの日本人(老若男女)の意識が大きく変わったとは思えない。学生の就職相談でも「親からは、大きな会社・福利厚生が整った会社に入りなさい」とアドバイスされると聞くと、「ボクが40年前に就活する際に、母親から聞かされたアドバイスと変わってないよな~?!」と思ってしまう。
■労働寿命が企業の寿命を追い越しちゃう時代!?
“終身雇用”の良し悪しは別にして、“一つの会社で一生勤めあげるモデル”が一般的ではなくなってきつつあることを知っておく必要はあるだろう。
米国の調査会社の調べによるとS&Pの株価指数を構成する米国大企業の平均寿命は1960年の60年超から20年程度に短縮化し、今後は更に一段と短くなるとのこと。日本でも帝国データバンクによると現時点の企業の平均寿命は37.16年で、今後、米国と同様に短縮化が進んでいきそうだ。
一方、みなさんが22歳で大学を卒業して70歳まで働くとすれば、仕事に従事するのは48年間。人の労働寿命が企業の寿命を追い越してしまうことになる。
■『チーズはどこへ消えた?』、知っている…?
「“環境変化”を認識するには、多くの時間を要する!」って書いたけど、より重要なのは時間よりもキッカケの方かもしれない…。そんなことを考えていたら、2000年に発売されたビジネス書『チーズはどこへ消えた?』(スペンサー・ジョンソン 著)のことを想い出した。
迷路にあった大切なもの(チーズ)がなくなるという突然の「変化」に、ある者は状況を変えようと迷路を飛び出し、ある者はそのまま迷路に残って現状を維持しようとする。バブル経済崩壊後、大手企業が次々と社員教育のテキストに採用したことも話題となって、ミリオンセラーになった。
「20年も前の本だから、既に絶版になっているだろうな〜!?」とアマゾンで検索してみたら、「今でも売ってるんだ~?!」とビックリ、“環境変化”への対応はボクたちの永遠の課題なんだろうね。
『チーズはどこへ消えた?』、寓話形式で変化への対応の重要性をやさしく説いた100ページ足らずの本なので、「環境変化への対応に躊躇しちゃいそう…!?」ってヒトは、是非、読んでみて欲しい。
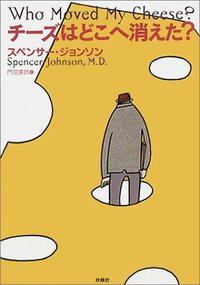
※Pic:紹介した『チーズはどこへ消えた?』。ステマじゃありません。
*********************
【学生さんの感想:Thanks!!】
・仕事を意味のあるものにするのは自分次第なのだと考えました。また、雇用制度というのは時代によって変わっていくので固定観念に縛られず、柔軟な考えでその都度対応していかないといけないのだということもわかりました。
・今回の講義を聞いて思ったことはコロナによる影響で被害が及ぶのは今年の就活生だけではないということ。その現状を理解しすべきことは、自分のキャリアを考え、行動に移す準備をすることだと想いました。
・転職せずに仕事を続けている男性が思った以上に少なかったことにとても驚きました。また企業の寿命が30年以下というのは本当に短く、もし自分が何年も続けている会社に就職することになったら数年経ったら潰れてしまうのか…、という不安も持ちました。長く続けることが出来ている会社にはどんな共通点があるのかと疑問に思いました。
【学生さんからのQuestion & ボクのAnswer】
Q1.コロナウイルスの影響は就職活動にどれほど出るのか知りたいです。
A1.程度はわからないけれど、少なからず影響はあるのだと思う。ただ、いくつかの視点から分析する必要はあるんだと思う。まず第一は、影響があるのは自分だけじゃなくライバル(?)とも言える他の学生も同じだということ。第二に、採用したい企業への影響も大だ。どこの企業も、どうすれば学生と接触出来るかを模索してる。第三は、経済の停滞による企業の採用意欲の減退かな…。いずれにしても“自分が変えられること”と“自分を変え無くちゃならないこと”を整理して考える必要があると思う。
Q2.現在、コロナウイルスの影響で自宅で仕事をする会社が増えています。この体制が終息した後も行うことができれば、女性や障がいを抱えた方など様々な人が働きやすくなると思うのですか、どう思いますか?
A2.ボクは今回、ウチの会社でも急遽、リモートワークをやってみた。やる前までは「出来るのかな〜?」と疑心暗鬼だったんだけど、今はリモートワークに大きな可能性を感じている。特にウチの場合は、子育て中の社員も多いし、そもそも仕事が出来さえすれば、何処で仕事をするのかは大きな問題じゃないわけだから…。ただ、導入の際は「個々のメンバーの自律心が必要条件になるよな〜!」とも思ってます。
ということで、今日はここまで。
注)このブログは、2020年4月22日(水)静岡県立大学 キャリア概論を聴講してくれた学生を対象に書いています。聴いていない方には解りにくい部分もあるかもしれないことをご承知おきください。
■トヨタ自動車社長のコメントが物議をかもしている
昨年5月、日本自動車工業会の豊田章男 会長(トヨタ自動車 代表取締役社長)は会見で、「日本の“終身雇用”を守っていくのが難しい局面に入ってきた」と話した。
“終身雇用”を巡っては、経団連 中西宏明会長(日立製作所 会長)の「企業からみると、従業員を一生雇い続ける保証書を持っているわけではない」、経済同友会 桜田謙悟代表幹事(SOMPOホールディングス 代表取締役社長兼CEO)の「“終身雇用”という制度は、『制度疲労』を起こしている可能性がある」等、経済界の重鎮が終身雇用見直し論ともとれる発言をしている。
マスメディアやSNS上では、「“終身雇用”の崩壊で若手社員の給与はアップする」vs「長期雇用は“雇用制度”ではなく“経営家哲学”だ!」他…、賛否両論が渦巻いている。
■“事実”で語ろう!?
ここでは、“終身雇用”の賛否は置いといて、事実を共有しておきたい。平成30年1月発表の内閣府の資料(日本経済2017-2018)によると、男性の場合、初職(学校卒業後はじめて就いた仕事)が正社員である割合は79%。そのうち一度も退職することなく“終身雇用”パスを歩んでいる(退職回数0回)のは、30代で48%、40代で38%、50代で34%。わかりやすく言うと、50代で初職の会社に勤め続けている人は、79%×34%≒26.9%、同年代の男性の4人に一人ということになる。
女性の場合、初職が正社員である割合は76%と男性と大きな違いは無いが、“終身雇用”パスを歩んでいるのは50代で7%程度(76%×7%≒5.3%)。つまり“終身雇用”パスを歩んでいるのは、同年代の女性の20人に一人ということになる。女性の場合は、仕事を辞めちゃう人の割合も高そうだ。
ボクは政治家でもないし、学校の先生でも無いので、“日本型雇用慣行”や“終身雇用”について、自身の考えを語るつもりはないけれど、事実を知っとくことは大切だ。
■人の意識は変わらない…
かつては、“日本型雇用慣行”の代名詞的に言われていた“終身雇用”。現実は前述した通りだが、人のもつ“イメージ”が“事実”として認識されるには、多くの時間を要するとも思っている。
1991年にバブル経済が崩壊し企業のリストラが進む中(この頃、“日本型雇用慣行”は崩壊したと言われていた)、ボクは再就職支援の事業に携わっていた。リストラされた中高年の人たちが、「こんなハズじゃなかった…」と言って肩を落とす姿を見て、自分の子供たちの世代の若者には、「同じ想いをさせたくない」と考え2002年に人材コンサルティングの会社をはじめた。
けれども、20年経っても、多くの日本人(老若男女)の意識が大きく変わったとは思えない。学生の就職相談でも「親からは、大きな会社・福利厚生が整った会社に入りなさい」とアドバイスされると聞くと、「ボクが40年前に就活する際に、母親から聞かされたアドバイスと変わってないよな~?!」と思ってしまう。
■労働寿命が企業の寿命を追い越しちゃう時代!?
“終身雇用”の良し悪しは別にして、“一つの会社で一生勤めあげるモデル”が一般的ではなくなってきつつあることを知っておく必要はあるだろう。
米国の調査会社の調べによるとS&Pの株価指数を構成する米国大企業の平均寿命は1960年の60年超から20年程度に短縮化し、今後は更に一段と短くなるとのこと。日本でも帝国データバンクによると現時点の企業の平均寿命は37.16年で、今後、米国と同様に短縮化が進んでいきそうだ。
一方、みなさんが22歳で大学を卒業して70歳まで働くとすれば、仕事に従事するのは48年間。人の労働寿命が企業の寿命を追い越してしまうことになる。
■『チーズはどこへ消えた?』、知っている…?
「“環境変化”を認識するには、多くの時間を要する!」って書いたけど、より重要なのは時間よりもキッカケの方かもしれない…。そんなことを考えていたら、2000年に発売されたビジネス書『チーズはどこへ消えた?』(スペンサー・ジョンソン 著)のことを想い出した。
迷路にあった大切なもの(チーズ)がなくなるという突然の「変化」に、ある者は状況を変えようと迷路を飛び出し、ある者はそのまま迷路に残って現状を維持しようとする。バブル経済崩壊後、大手企業が次々と社員教育のテキストに採用したことも話題となって、ミリオンセラーになった。
「20年も前の本だから、既に絶版になっているだろうな〜!?」とアマゾンで検索してみたら、「今でも売ってるんだ~?!」とビックリ、“環境変化”への対応はボクたちの永遠の課題なんだろうね。
『チーズはどこへ消えた?』、寓話形式で変化への対応の重要性をやさしく説いた100ページ足らずの本なので、「環境変化への対応に躊躇しちゃいそう…!?」ってヒトは、是非、読んでみて欲しい。
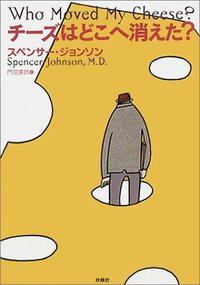
※Pic:紹介した『チーズはどこへ消えた?』。ステマじゃありません。
*********************
【学生さんの感想:Thanks!!】
・仕事を意味のあるものにするのは自分次第なのだと考えました。また、雇用制度というのは時代によって変わっていくので固定観念に縛られず、柔軟な考えでその都度対応していかないといけないのだということもわかりました。
・今回の講義を聞いて思ったことはコロナによる影響で被害が及ぶのは今年の就活生だけではないということ。その現状を理解しすべきことは、自分のキャリアを考え、行動に移す準備をすることだと想いました。
・転職せずに仕事を続けている男性が思った以上に少なかったことにとても驚きました。また企業の寿命が30年以下というのは本当に短く、もし自分が何年も続けている会社に就職することになったら数年経ったら潰れてしまうのか…、という不安も持ちました。長く続けることが出来ている会社にはどんな共通点があるのかと疑問に思いました。
【学生さんからのQuestion & ボクのAnswer】
Q1.コロナウイルスの影響は就職活動にどれほど出るのか知りたいです。
A1.程度はわからないけれど、少なからず影響はあるのだと思う。ただ、いくつかの視点から分析する必要はあるんだと思う。まず第一は、影響があるのは自分だけじゃなくライバル(?)とも言える他の学生も同じだということ。第二に、採用したい企業への影響も大だ。どこの企業も、どうすれば学生と接触出来るかを模索してる。第三は、経済の停滞による企業の採用意欲の減退かな…。いずれにしても“自分が変えられること”と“自分を変え無くちゃならないこと”を整理して考える必要があると思う。
Q2.現在、コロナウイルスの影響で自宅で仕事をする会社が増えています。この体制が終息した後も行うことができれば、女性や障がいを抱えた方など様々な人が働きやすくなると思うのですか、どう思いますか?
A2.ボクは今回、ウチの会社でも急遽、リモートワークをやってみた。やる前までは「出来るのかな〜?」と疑心暗鬼だったんだけど、今はリモートワークに大きな可能性を感じている。特にウチの場合は、子育て中の社員も多いし、そもそも仕事が出来さえすれば、何処で仕事をするのかは大きな問題じゃないわけだから…。ただ、導入の際は「個々のメンバーの自律心が必要条件になるよな〜!」とも思ってます。
ということで、今日はここまで。
注)このブログは、2020年4月22日(水)静岡県立大学 キャリア概論を聴講してくれた学生を対象に書いています。聴いていない方には解りにくい部分もあるかもしれないことをご承知おきください。
2020年05月16日
キャリアについて考える意味 Vol.3
〜ウチ(取締役を務める会社)の社員の実際〜
■成長したい人が増えている?
会社では、管理事業推進部の担当取締役を務めさせていただいている。部署名に“事業推進”って付いているのは、単に管理するだけでなく事業推進の役割を担っていることを社内に示したいから(うまくやれているかどうかは別の話…(苦笑 )。
それはさておき、ウチのメンバーに限らず、学生も社員も「成長したい!」って言う人が本当に多い!!で、それを聴いたボクは「どうなったら成長したって言えるの…、30歳になった時にどうなっていたい?」なんて質問してしまうのだけど…。
ほとんどの人は、具体的なイメージを持たないまま、呪文の様に「成長!!成長!?」と唱えているだけの様に感じる。学生のみなさんは、意地悪な人事担当者にこんな質問をされた際にドギマギしない様に準備しておくといい。
■成長したいメンバーと育成したい上司
一方で、「メンバーを育成したい!」という管理職も多い。ボクも昔は、同じ様なことを言っていたかもしれないので、偉そうなことは言えないが、何十年か社会人をやっていて思うことは、「人を育成するなんて、おこがましいよな〜」ってこと。
社会人としての基本である“報・連・相”がキチッと出来たり、“営業のコツ”を教えたり等、業務が円滑に進むための指導するコトは出来るかもしれないけれど、それは単なる技術指導で、ボクのイメージする育成とは違う。
そんな中、先日、人事考課のヒアリングで入社5年目のメンバーから、「上司は、何でも知っていると思っていたけれど、杉山さんは知らないコトが多いですよね?!」というコメントをもらった。それを聴いてボクはなんか嬉しかった。どんな背景での話なのかをご存じないみなさんが、嬉しい理由を推察するのは難しいと思うけど、ボクは『1年後の彼がどうなっているのか?!』が、とっても楽しみだ。
■想い出したこと
昨今、七五三転職(※注)が社会問題だと言われているが、ボクは大学卒業して、3年しないうちに3つ(企業・公務員)の団体を経験した。転職の主な理由は「休みが少ない」「仕事にやりがいを感じられない」だ。
3つ目の会社は、創業から10年ほどのアルバイトタイムス(求人情報誌のDOMOを発行している)という会社で、社員数は10名程だった。入社の決め手は、当時珍しかった『完全週休2日制!』と『求人情報の会社だから、次に転職する際の情報も多そう?!』という超安易な理由だ。結果的に、この会社では、営業、企画、編集・制作、流通事業、人材関連事業etc…、様々な仕事を経験した。経験しなかったのは、今ウチでやっている管理部門のシゴトくらいだろう。
いろいろやらせてもらったけど、上司である創業社長(満井義政さん)から指導を受けた覚えがない。とはいえ、満井さんには“感謝”の気持ちしかない。技術指導をしてもらったことは一切ないが、多くの機会を与えてくれたことが、その後のボクの人生のとても大きな財産になったと感じている。
結果、アルバイトタイムスのグループには、JASDAQに上場する直前までの17年間お世話になった。そして、入社時に思っていた『次の条件のいい会社』を見つけることなく、自身で起業する道を選んだ。
■離職は悪いこと?
ウチは大学生の就活では、比較的人気のある企業だと思うけど、ご多分にもれず退職者は少なくない。『期待して入社してくれたメンバーが辞めてしまうこと』が寂しくないと言えば、嘘になるけど、辞めないことが良いことだとも思っていない。
あくまで私見だが、『メンバーには自分のために自分を磨き続けて欲しいし、プロの職業人としてどこででも戦える実力をつけて欲しい』と思っている。ボクたち経営の役割は、メンバーが“踊り甲斐を感じられるステージを用意すること”であり、“ウチのステージで踊り続けたいと思ってくれる様なステージを用意すること”だと思っている。
だから、新進気鋭のベンチャー企業に転職したり、地域課題解決のための会社を起こしたりするメンバーの退職は、「次のステージでの活躍への期待や興味」と「ステージが用意できない自身の力不足を嘆く気持ち」が入り交じる。会社としては、大きな損失だから…。
■成長の先にあるもの
授業でもお話したとおり、キャリアの語源は、ラテン語の「carrus(荷馬車)」。キャリアとは、車輪の通った轍を意味する。
学生のみなさんには、「自身の成長の先に何があるのか?将来どうなっていたいのか?」を想像して欲しい。重要なのは、『思った通りになること』ではなく、『“想像した未来”に向かって歩み始めること自体』なんだと思う。
先週、ウチの新卒採用面接(今年はWeb面接)で、学生さんから「若い頃、苦労した経験があったら教えてください」という質問があった。会社の取締役やっている人は苦労の先に取締役というポジションが与えられたと思ったのだろう。面接官であるもうひとりの取締役が「毎日が苦労の連続だよ!若い頃も苦労したコトはたくさんあるけど、今の方がもっと苦労している」と答えた。ボクにとって“もわが意を得たり”の回答だった。
“想像した未来”に向かって歩み続けたとしても、『思った通りになる可能性』は高くない。けれども、人生は想像していなかった自分になれるから面白いんじゃない?
※注)七五三転職:正社員で入社した会社を、中学卒業者で7割、高校卒業者で5割、大学卒業者で3割が3年以内に退職してしまう現象。
***********************************************
【学生さんの感想:Thanks!!】
・何かを始める時に「成長したい」と言ってしまいがちだけど、何をもって成長したとするかの自分の中にはっきりした基準があるわけでもないし、様々な経験をした結果あとから振り返った時に成長したと言えるようになるのかなと思いました。
・“私は人を育成できないから”という発言が面白かった。長くキャリアを積んできて、それが出た結論なんだと深く感じました。確かにいい営業マンにさせることはたくさんの人が出来ると思いますが、そうでは無いんですよね。
・成長とは多少なりとも他人の影響はあるかもしれないが、一番は自分自身によることであることを気づかされた。
・夢を見つけ、そのために今の仕事をやめて一から、また新しいことを始めていく方がいると聴いて、かっこいいなと思いました。たとえお金が稼げない職業だとしても自分がやりたいことならばそれも良い、周りの目を気にして仕事を選ぶのではなく自分がやりたいと思えるようなことをできたらと考えるようになりました。
【学生さんからのQuestion & ボクのAnswer】
Q1.将来、フリーランスで働きたいと思っています。スキルを磨くための踏み台として会社に就職するのは良いことだと思いますか?
A1.“踏み台”というコトバには抵抗があるけど、「“就職=就社”ではない!?」って考えれば、“自分のために仕事に就く”コトは大いにアリだと思う。ただ、ボクはスキルUPを単なる技術や知識の向上と考えるのではなく、もう少し広義に捉えて欲しいとも思う。スキルは、『会社で果たすべき役割』をしっかり担ってこそ、身につくものだと思う。
Q2.なぜ、貴社では若いうちから上司をさせたりするのですか?
A2.う〜ん、これは「なぜ、上司は若くちゃダメなんですか?」って逆質問したくなっちゃう質問かも…。「任せれば、頑張って成果を出してくれそうだ?!」って思えれば、年齢に関わらず任せるのはむしろ必然だと思う。マネジメントの本読むだけじゃ、マネジメントが出来る様にはならないでしょ。
ということで、今日はここまで。

※Pic:アルバイトタイムの企画担当の頃、レーサーのスポンサーをしていた時のもの。上司からシゴトを教えてもらった記憶は無いが、機会を与えてもらえた。感謝の気持ちしかない。
注)このブログは、2020年4月22日(水)静岡県立大学 キャリア概論を聴講してくれた学生を対象に書いています。聴いていない方には解りにくい部分もあるかもしれないことをご承知おきください。
■成長したい人が増えている?
会社では、管理事業推進部の担当取締役を務めさせていただいている。部署名に“事業推進”って付いているのは、単に管理するだけでなく事業推進の役割を担っていることを社内に示したいから(うまくやれているかどうかは別の話…(苦笑 )。
それはさておき、ウチのメンバーに限らず、学生も社員も「成長したい!」って言う人が本当に多い!!で、それを聴いたボクは「どうなったら成長したって言えるの…、30歳になった時にどうなっていたい?」なんて質問してしまうのだけど…。
ほとんどの人は、具体的なイメージを持たないまま、呪文の様に「成長!!成長!?」と唱えているだけの様に感じる。学生のみなさんは、意地悪な人事担当者にこんな質問をされた際にドギマギしない様に準備しておくといい。
■成長したいメンバーと育成したい上司
一方で、「メンバーを育成したい!」という管理職も多い。ボクも昔は、同じ様なことを言っていたかもしれないので、偉そうなことは言えないが、何十年か社会人をやっていて思うことは、「人を育成するなんて、おこがましいよな〜」ってこと。
社会人としての基本である“報・連・相”がキチッと出来たり、“営業のコツ”を教えたり等、業務が円滑に進むための指導するコトは出来るかもしれないけれど、それは単なる技術指導で、ボクのイメージする育成とは違う。
そんな中、先日、人事考課のヒアリングで入社5年目のメンバーから、「上司は、何でも知っていると思っていたけれど、杉山さんは知らないコトが多いですよね?!」というコメントをもらった。それを聴いてボクはなんか嬉しかった。どんな背景での話なのかをご存じないみなさんが、嬉しい理由を推察するのは難しいと思うけど、ボクは『1年後の彼がどうなっているのか?!』が、とっても楽しみだ。
■想い出したこと
昨今、七五三転職(※注)が社会問題だと言われているが、ボクは大学卒業して、3年しないうちに3つ(企業・公務員)の団体を経験した。転職の主な理由は「休みが少ない」「仕事にやりがいを感じられない」だ。
3つ目の会社は、創業から10年ほどのアルバイトタイムス(求人情報誌のDOMOを発行している)という会社で、社員数は10名程だった。入社の決め手は、当時珍しかった『完全週休2日制!』と『求人情報の会社だから、次に転職する際の情報も多そう?!』という超安易な理由だ。結果的に、この会社では、営業、企画、編集・制作、流通事業、人材関連事業etc…、様々な仕事を経験した。経験しなかったのは、今ウチでやっている管理部門のシゴトくらいだろう。
いろいろやらせてもらったけど、上司である創業社長(満井義政さん)から指導を受けた覚えがない。とはいえ、満井さんには“感謝”の気持ちしかない。技術指導をしてもらったことは一切ないが、多くの機会を与えてくれたことが、その後のボクの人生のとても大きな財産になったと感じている。
結果、アルバイトタイムスのグループには、JASDAQに上場する直前までの17年間お世話になった。そして、入社時に思っていた『次の条件のいい会社』を見つけることなく、自身で起業する道を選んだ。
■離職は悪いこと?
ウチは大学生の就活では、比較的人気のある企業だと思うけど、ご多分にもれず退職者は少なくない。『期待して入社してくれたメンバーが辞めてしまうこと』が寂しくないと言えば、嘘になるけど、辞めないことが良いことだとも思っていない。
あくまで私見だが、『メンバーには自分のために自分を磨き続けて欲しいし、プロの職業人としてどこででも戦える実力をつけて欲しい』と思っている。ボクたち経営の役割は、メンバーが“踊り甲斐を感じられるステージを用意すること”であり、“ウチのステージで踊り続けたいと思ってくれる様なステージを用意すること”だと思っている。
だから、新進気鋭のベンチャー企業に転職したり、地域課題解決のための会社を起こしたりするメンバーの退職は、「次のステージでの活躍への期待や興味」と「ステージが用意できない自身の力不足を嘆く気持ち」が入り交じる。会社としては、大きな損失だから…。
■成長の先にあるもの
授業でもお話したとおり、キャリアの語源は、ラテン語の「carrus(荷馬車)」。キャリアとは、車輪の通った轍を意味する。
学生のみなさんには、「自身の成長の先に何があるのか?将来どうなっていたいのか?」を想像して欲しい。重要なのは、『思った通りになること』ではなく、『“想像した未来”に向かって歩み始めること自体』なんだと思う。
先週、ウチの新卒採用面接(今年はWeb面接)で、学生さんから「若い頃、苦労した経験があったら教えてください」という質問があった。会社の取締役やっている人は苦労の先に取締役というポジションが与えられたと思ったのだろう。面接官であるもうひとりの取締役が「毎日が苦労の連続だよ!若い頃も苦労したコトはたくさんあるけど、今の方がもっと苦労している」と答えた。ボクにとって“もわが意を得たり”の回答だった。
“想像した未来”に向かって歩み続けたとしても、『思った通りになる可能性』は高くない。けれども、人生は想像していなかった自分になれるから面白いんじゃない?
※注)七五三転職:正社員で入社した会社を、中学卒業者で7割、高校卒業者で5割、大学卒業者で3割が3年以内に退職してしまう現象。
***********************************************
【学生さんの感想:Thanks!!】
・何かを始める時に「成長したい」と言ってしまいがちだけど、何をもって成長したとするかの自分の中にはっきりした基準があるわけでもないし、様々な経験をした結果あとから振り返った時に成長したと言えるようになるのかなと思いました。
・“私は人を育成できないから”という発言が面白かった。長くキャリアを積んできて、それが出た結論なんだと深く感じました。確かにいい営業マンにさせることはたくさんの人が出来ると思いますが、そうでは無いんですよね。
・成長とは多少なりとも他人の影響はあるかもしれないが、一番は自分自身によることであることを気づかされた。
・夢を見つけ、そのために今の仕事をやめて一から、また新しいことを始めていく方がいると聴いて、かっこいいなと思いました。たとえお金が稼げない職業だとしても自分がやりたいことならばそれも良い、周りの目を気にして仕事を選ぶのではなく自分がやりたいと思えるようなことをできたらと考えるようになりました。
【学生さんからのQuestion & ボクのAnswer】
Q1.将来、フリーランスで働きたいと思っています。スキルを磨くための踏み台として会社に就職するのは良いことだと思いますか?
A1.“踏み台”というコトバには抵抗があるけど、「“就職=就社”ではない!?」って考えれば、“自分のために仕事に就く”コトは大いにアリだと思う。ただ、ボクはスキルUPを単なる技術や知識の向上と考えるのではなく、もう少し広義に捉えて欲しいとも思う。スキルは、『会社で果たすべき役割』をしっかり担ってこそ、身につくものだと思う。
Q2.なぜ、貴社では若いうちから上司をさせたりするのですか?
A2.う〜ん、これは「なぜ、上司は若くちゃダメなんですか?」って逆質問したくなっちゃう質問かも…。「任せれば、頑張って成果を出してくれそうだ?!」って思えれば、年齢に関わらず任せるのはむしろ必然だと思う。マネジメントの本読むだけじゃ、マネジメントが出来る様にはならないでしょ。
ということで、今日はここまで。

※Pic:アルバイトタイムの企画担当の頃、レーサーのスポンサーをしていた時のもの。上司からシゴトを教えてもらった記憶は無いが、機会を与えてもらえた。感謝の気持ちしかない。
注)このブログは、2020年4月22日(水)静岡県立大学 キャリア概論を聴講してくれた学生を対象に書いています。聴いていない方には解りにくい部分もあるかもしれないことをご承知おきください。
2020年05月06日
キャリアについて考える意味 Vol.2
〜ボクが学生と接する中、感じること〜
■よくある就職相談
学生の就職相談で多いのが、就活の三大鬼門?(自己分析、ES、面接)の一つでもある「エントリーシート(以下、ES)の添削依頼。ESは、何かの意図を持って書いているハズ(?)だから、「このES、面接官に何を伝えたくて書いたの?」などと質問するのだが…。質問(例:学生時代頑張ったことは?)に対する答えは丁寧に書かれているけれど、それを通して採用担当者に何を伝えたいという意図が無いまま書いているコトが多い様に感じる。
そんなコトもあって、最近は添削の依頼があると「添削はしないけど、このES読んで聴いてみたいと思ったことを質問するよ!?」などと前置きしてから相談業務に入ることも少なくない。
■意図を持った発言が出来ているか?
就職相談では、他にも似たような場面に出くわす。例えば、「面接の時に〇〇聴かれたら、なんて答えれば良いですか?」という質問。質問に対する答えは“人それぞれ”だし“採用側の質問の意図”が解らないのに、「なんて答えればよいのか?」って言われても困ってしまう。逆に、「就活マニュアルに『この質問にはこう答えろ!』と書いてあるんだが、違和感がある」なんていう学生の言葉には、ホッとする。
あと、(採用担当の)「何か質問ありますか?」の問に対して、「残りの学生生活、何をすればいいですか?」って質問にも困ってしまう。ボクは、本番(ウチの会社)の面接では「あなたは何をやればいいと思う?」と逆質問し、「あなたがやりたいと思ったコトをやればいいよ!」と返している。意地悪だね…(笑
■答えはひとつ?
今回の講義では、「学校の試験以外に答えが一つに決まっているものを教えて!?」という問いかけをさせていただいた。ボクには、陸上競技の様なイコールコンディション(コレとて道具の進歩で全くのイコールとは言えなくなってきている…)で行われる競技以外は、一つしか答えがないケースを思い浮かべることが出来ない。更に、チームには、技術的に優れている人だけじゃなく、リーダーシップに秀でた人、ムードメーカー等、いろんなメンバーが必要で、誰か一人だけで成り立つモノじゃない。ボクがF-1や自転車のロードレースが好きな理由は、“不公平で、スーパースター一人の力だけじゃ勝てないコト”なのかもしれない。
答えはひとつじゃない。“人それぞれの答えがある”ハズだし、“置かれた状況によって答えは変わっていくモノ”という当たり前が共有できていない様な気がする。
■自分の基準を持つことの大切さ
ボクたちは、学校教育の中で、“正解は一つ”と刷り込まれ続けてきた様な気がする。現在、小・中・高校で推し進められているキャリア教育でよく聴く「なりたい自分を見つけよう!」っていうコトバも、視野を狭める一つの要因になっていないだろうか。「どんな職業に就きたい?」と言われても「なりたい自分が見つからない?」と悩み立ち止ってしまう学生は少なくない。
更に、社会経験の浅い学生に、「なりたい自分は明確です!」って断言されちゃうのはもっと心配だ。そういう学生によくよく話を聴くと、単に“知名度が高かったり福利厚生の整った会社”に入ることだけが目的になってしまっているケースが少なくない。そんな会社選びをして、入社2〜3年でウチに転職してくる学生もいるからな〜?!
誰かに与えられた目標とか基準じゃなく、自分のモノサシを持つことが大切なんだと思う。
*********************************
【学生さんの感想:Thanks!!】
・面接の質疑応答での「(学生が)やっておいた方がいいことは?」のお話を聴いて、自分のやりたいことに挑戦しようと思えるようになりました。
・学校の試験以外、答えは一つではないということにとても納得しました。大学生のうちにやりたいことをやり、机上の勉強では学べないことを様々な分野で挑戦して、自分の視野を広げたいなと思いました。
・「なりたい自分なんてあとから見つかる」「就活で焦ることなんてない」という言葉がとても心に残りました。
・私は高校まで、周りからの評価ばかり気にしていました。そして、誰かが持っている答えにたどり着くことを目的に行動していました。まずは、自分がやりたいことを考えてみることからはじめてみようと思いました。
・私は成績がいいわけではありませんが他人からの評価を気にしすぎているのかもしれないと思いました。しかし、自分が死ぬ時に後悔しないためにも、自分と向き合って、自分が幸せで充実していると思える人生なら、それが一番だと思いました。
・自分は、良い会社に入って、業務をこなせるようになり、昇進していくことが「成長」であったり、「キャリア」を積んでいくことだと思っていたので、正直ギクッとしました。
・この授業は、“いい企業”に就くためには何をしたらいいかの答えを見つけるために受講した。いわゆる“いい企業”に入るコトを目的にしていた自分は、耳が痛くなるような思いでした。
・何事に関しても自分の基準を設けようと思いました。会社の基準に合わせることも必要な場面は多々あると思うが、会社の基準の一歩先に行った基準を設け、ほかと違う質の良い働きをすることでキャリアを育てたい。
・授業を聴いたことによって、“自分で考えて自分で決める”のが重要なのではないかと思いました。
・私は、将来の夢がなく、大卒という学歴のために大学進学を選択したようなものですが、今回の授業を受けて、今の生活がただの学歴として終わってしまうことは非常に残念なことだと感じました。
【学生さんからのQuestion】
・何かを始めるときどこから勇気や自信が湧いてくるのですか?
・何か行動を起こす時に、周りの反応や評価を考えて、積極的に行動できないです。これは、自意識過剰でしょうか?
【ボクのAnswer】
“勇気や自信”“自意識過剰”に対する答えになるかはわからないけれど、『勇気を持たないと始められない』場合と『とりあえず始めてみる』場合の2つがある様に思う。で、ボクの場合、多いのは『とりあえず始めてみる』ですね。趣味なんかは、圧倒的にコレ!!
『勇気を持たないと始められない』場合…。う〜ん、今まででの一番は、18年前の起業かな?当時、前職では取締役だったし、家族もいたから…。で、なんで踏み切れたかというと、将来を俯瞰するに足り得る情報を持っていたからだと思う。簡単に言うと、大手企業も雇用の保証をしなくなる中、今いる会社が未来永劫まで面倒見てくれるわけではない、“自分の足で立つ術”を習得することが、結果的にリスク回避につながると考えたからかな。
ちょうど、父親が亡くなった頃だったので、「人間、いつかは死ぬんだ!だったら好きなようにやろう!!」と実感できたのも大きいかもしれない。
ということで、今日はここまで。

※Pic:20代前半、流行りはじめたWSFにハマってた時期があります。
注)このブログは、2020年4月22日(水)静岡県立大学 キャリア概論を聴講してくれた学生を対象に書いています。聴いていない方には解りにくい部分もあるかもしれないことをご承知おきください。
■よくある就職相談
学生の就職相談で多いのが、就活の三大鬼門?(自己分析、ES、面接)の一つでもある「エントリーシート(以下、ES)の添削依頼。ESは、何かの意図を持って書いているハズ(?)だから、「このES、面接官に何を伝えたくて書いたの?」などと質問するのだが…。質問(例:学生時代頑張ったことは?)に対する答えは丁寧に書かれているけれど、それを通して採用担当者に何を伝えたいという意図が無いまま書いているコトが多い様に感じる。
そんなコトもあって、最近は添削の依頼があると「添削はしないけど、このES読んで聴いてみたいと思ったことを質問するよ!?」などと前置きしてから相談業務に入ることも少なくない。
■意図を持った発言が出来ているか?
就職相談では、他にも似たような場面に出くわす。例えば、「面接の時に〇〇聴かれたら、なんて答えれば良いですか?」という質問。質問に対する答えは“人それぞれ”だし“採用側の質問の意図”が解らないのに、「なんて答えればよいのか?」って言われても困ってしまう。逆に、「就活マニュアルに『この質問にはこう答えろ!』と書いてあるんだが、違和感がある」なんていう学生の言葉には、ホッとする。
あと、(採用担当の)「何か質問ありますか?」の問に対して、「残りの学生生活、何をすればいいですか?」って質問にも困ってしまう。ボクは、本番(ウチの会社)の面接では「あなたは何をやればいいと思う?」と逆質問し、「あなたがやりたいと思ったコトをやればいいよ!」と返している。意地悪だね…(笑
■答えはひとつ?
今回の講義では、「学校の試験以外に答えが一つに決まっているものを教えて!?」という問いかけをさせていただいた。ボクには、陸上競技の様なイコールコンディション(コレとて道具の進歩で全くのイコールとは言えなくなってきている…)で行われる競技以外は、一つしか答えがないケースを思い浮かべることが出来ない。更に、チームには、技術的に優れている人だけじゃなく、リーダーシップに秀でた人、ムードメーカー等、いろんなメンバーが必要で、誰か一人だけで成り立つモノじゃない。ボクがF-1や自転車のロードレースが好きな理由は、“不公平で、スーパースター一人の力だけじゃ勝てないコト”なのかもしれない。
答えはひとつじゃない。“人それぞれの答えがある”ハズだし、“置かれた状況によって答えは変わっていくモノ”という当たり前が共有できていない様な気がする。
■自分の基準を持つことの大切さ
ボクたちは、学校教育の中で、“正解は一つ”と刷り込まれ続けてきた様な気がする。現在、小・中・高校で推し進められているキャリア教育でよく聴く「なりたい自分を見つけよう!」っていうコトバも、視野を狭める一つの要因になっていないだろうか。「どんな職業に就きたい?」と言われても「なりたい自分が見つからない?」と悩み立ち止ってしまう学生は少なくない。
更に、社会経験の浅い学生に、「なりたい自分は明確です!」って断言されちゃうのはもっと心配だ。そういう学生によくよく話を聴くと、単に“知名度が高かったり福利厚生の整った会社”に入ることだけが目的になってしまっているケースが少なくない。そんな会社選びをして、入社2〜3年でウチに転職してくる学生もいるからな〜?!
誰かに与えられた目標とか基準じゃなく、自分のモノサシを持つことが大切なんだと思う。
*********************************
【学生さんの感想:Thanks!!】
・面接の質疑応答での「(学生が)やっておいた方がいいことは?」のお話を聴いて、自分のやりたいことに挑戦しようと思えるようになりました。
・学校の試験以外、答えは一つではないということにとても納得しました。大学生のうちにやりたいことをやり、机上の勉強では学べないことを様々な分野で挑戦して、自分の視野を広げたいなと思いました。
・「なりたい自分なんてあとから見つかる」「就活で焦ることなんてない」という言葉がとても心に残りました。
・私は高校まで、周りからの評価ばかり気にしていました。そして、誰かが持っている答えにたどり着くことを目的に行動していました。まずは、自分がやりたいことを考えてみることからはじめてみようと思いました。
・私は成績がいいわけではありませんが他人からの評価を気にしすぎているのかもしれないと思いました。しかし、自分が死ぬ時に後悔しないためにも、自分と向き合って、自分が幸せで充実していると思える人生なら、それが一番だと思いました。
・自分は、良い会社に入って、業務をこなせるようになり、昇進していくことが「成長」であったり、「キャリア」を積んでいくことだと思っていたので、正直ギクッとしました。
・この授業は、“いい企業”に就くためには何をしたらいいかの答えを見つけるために受講した。いわゆる“いい企業”に入るコトを目的にしていた自分は、耳が痛くなるような思いでした。
・何事に関しても自分の基準を設けようと思いました。会社の基準に合わせることも必要な場面は多々あると思うが、会社の基準の一歩先に行った基準を設け、ほかと違う質の良い働きをすることでキャリアを育てたい。
・授業を聴いたことによって、“自分で考えて自分で決める”のが重要なのではないかと思いました。
・私は、将来の夢がなく、大卒という学歴のために大学進学を選択したようなものですが、今回の授業を受けて、今の生活がただの学歴として終わってしまうことは非常に残念なことだと感じました。
【学生さんからのQuestion】
・何かを始めるときどこから勇気や自信が湧いてくるのですか?
・何か行動を起こす時に、周りの反応や評価を考えて、積極的に行動できないです。これは、自意識過剰でしょうか?
【ボクのAnswer】
“勇気や自信”“自意識過剰”に対する答えになるかはわからないけれど、『勇気を持たないと始められない』場合と『とりあえず始めてみる』場合の2つがある様に思う。で、ボクの場合、多いのは『とりあえず始めてみる』ですね。趣味なんかは、圧倒的にコレ!!
『勇気を持たないと始められない』場合…。う〜ん、今まででの一番は、18年前の起業かな?当時、前職では取締役だったし、家族もいたから…。で、なんで踏み切れたかというと、将来を俯瞰するに足り得る情報を持っていたからだと思う。簡単に言うと、大手企業も雇用の保証をしなくなる中、今いる会社が未来永劫まで面倒見てくれるわけではない、“自分の足で立つ術”を習得することが、結果的にリスク回避につながると考えたからかな。
ちょうど、父親が亡くなった頃だったので、「人間、いつかは死ぬんだ!だったら好きなようにやろう!!」と実感できたのも大きいかもしれない。
ということで、今日はここまで。

※Pic:20代前半、流行りはじめたWSFにハマってた時期があります。
注)このブログは、2020年4月22日(水)静岡県立大学 キャリア概論を聴講してくれた学生を対象に書いています。聴いていない方には解りにくい部分もあるかもしれないことをご承知おきください。
2020年05月04日
キャリアについて考える意味 Vol.1
〜新型コロナウイルス感染拡大の最中、キャリアについてお話をする機会をいただきました!〜
例年登壇の機会をいただいている静岡県立大学のキャリア概論Ⅰ(津富宏 教授)で、今年もお話をする機会をいただきました。例年と大きく違うのは、コロナ禍の影響で主な受講対象である1年生は入学式も無く、未だ同級生と1度も顔を合わせることも無い中でのWebでの授業であるということ。こんな状況だからこそ、「キャリアとは何か?」「キャリアについてなぜ考える必要があるのか?」という問いかけをしたいと思い、授業の構成を考えてみた。
大きな流れは、パラレルワーカー(人材コンサルタント、企業経営者、大学講師)という働き方を選んだボクの自己紹介から始まって、『1.ボクが学生と接する中、感じること』『2. ウチ(取締役を務める会社)の社員の実際』『3. 社会環境変化について』『4. みなさんへの質問』という4つのフェーズで整理してみた。また、資料は「スマホで参加する学生も少なくないだろうから、文字を大きくポイントだけを載せよう!」とか「ワンウェイになる可能性大だから、後半は質問も織り交ぜよう!」とか、無い知恵絞って作成した。
ボクにとっては初のWeb授業。今回は、当該科目の1回目であり、概ね70名の学生も(たぶん)Web授業は初体験ということで、「果たして90分(ボクの持ち時間は概ね60分強)持つのだろか…?」という不安いっぱいでスタートした。確かにリアルな反応を感じ取ることは難しいのだけれど、学生の顔がモニターに映っていることもあり、喋り手としては比較的安心して話が出来る。
また当初は『4. みなさんへの質問』についても、質問を投げかけた後、しばらく時間を置いてから調査結果の開示をしようと考えていたのだが…。zoomのチャットボタンを見つけ「何番の答えを選んだか?チャットで教えて!」と投げかけることにより、ボクが参加学生の考えを把握出来るだけじゃなく、他の学生にも解答の全体像が共有され気づきを与えられるトコロも悪くない。実際、学生の感想にも「いろんな考え方の学生がいることに驚いた」「対面では言い辛いことでもネットを通じてだったら言えるので続けて欲しい」等の感想も少なくなかった。直に学生と接するのに越したことはないとは思うけど、マスプロ授業で双方向のコミュニケーションに悩んでいるボクには、Web授業もツールのひとつとしては“アリ”と思える経験となった。
とここまで、“Web授業体験記”みたいになってしまったけど、超ひさしぶりにBlogを書こうと思った理由は実はソコじゃない。授業終了後の学生のコメント(考えたこと、質問等)を読ませてもらい、「こりゃ、ボクの感想やボクなりの回答を返すのが礼儀だろう!?」と思ったから…。ということで、数回に分けて一部、学生のコメントも引用しつつ、ボクなりのコメントを綴ってみようと思う。
ということで、今日はここまで。

※Pic:大学卒業後、1社目を9ヶ月で退職。最初の冬の伊勢神宮。
例年登壇の機会をいただいている静岡県立大学のキャリア概論Ⅰ(津富宏 教授)で、今年もお話をする機会をいただきました。例年と大きく違うのは、コロナ禍の影響で主な受講対象である1年生は入学式も無く、未だ同級生と1度も顔を合わせることも無い中でのWebでの授業であるということ。こんな状況だからこそ、「キャリアとは何か?」「キャリアについてなぜ考える必要があるのか?」という問いかけをしたいと思い、授業の構成を考えてみた。
大きな流れは、パラレルワーカー(人材コンサルタント、企業経営者、大学講師)という働き方を選んだボクの自己紹介から始まって、『1.ボクが学生と接する中、感じること』『2. ウチ(取締役を務める会社)の社員の実際』『3. 社会環境変化について』『4. みなさんへの質問』という4つのフェーズで整理してみた。また、資料は「スマホで参加する学生も少なくないだろうから、文字を大きくポイントだけを載せよう!」とか「ワンウェイになる可能性大だから、後半は質問も織り交ぜよう!」とか、無い知恵絞って作成した。
ボクにとっては初のWeb授業。今回は、当該科目の1回目であり、概ね70名の学生も(たぶん)Web授業は初体験ということで、「果たして90分(ボクの持ち時間は概ね60分強)持つのだろか…?」という不安いっぱいでスタートした。確かにリアルな反応を感じ取ることは難しいのだけれど、学生の顔がモニターに映っていることもあり、喋り手としては比較的安心して話が出来る。
また当初は『4. みなさんへの質問』についても、質問を投げかけた後、しばらく時間を置いてから調査結果の開示をしようと考えていたのだが…。zoomのチャットボタンを見つけ「何番の答えを選んだか?チャットで教えて!」と投げかけることにより、ボクが参加学生の考えを把握出来るだけじゃなく、他の学生にも解答の全体像が共有され気づきを与えられるトコロも悪くない。実際、学生の感想にも「いろんな考え方の学生がいることに驚いた」「対面では言い辛いことでもネットを通じてだったら言えるので続けて欲しい」等の感想も少なくなかった。直に学生と接するのに越したことはないとは思うけど、マスプロ授業で双方向のコミュニケーションに悩んでいるボクには、Web授業もツールのひとつとしては“アリ”と思える経験となった。
とここまで、“Web授業体験記”みたいになってしまったけど、超ひさしぶりにBlogを書こうと思った理由は実はソコじゃない。授業終了後の学生のコメント(考えたこと、質問等)を読ませてもらい、「こりゃ、ボクの感想やボクなりの回答を返すのが礼儀だろう!?」と思ったから…。ということで、数回に分けて一部、学生のコメントも引用しつつ、ボクなりのコメントを綴ってみようと思う。
ということで、今日はここまで。

※Pic:大学卒業後、1社目を9ヶ月で退職。最初の冬の伊勢神宮。




