2020年06月07日
キャリアについて考える意味 Vol.5
~ みなさんへの質問 ~
キャリアについて考える意味Vol.5、最終回。講座のフェイズ4は『みなさんへの質問』。「お金があったら働くか?」「自身のキャリアプランに反する仕事を強いられたら?」「理想のライフ・キャリアプランは?」等の質問を投げかけてみた。
■お金があったら働く?
先ずは、「お金があったら働く?」と質問を投げかけてみた。仕事に就いたことの無い学生の多くは「仕事はお金を稼ぐためにあるんだから、就くわけない!」「やりたい仕事だったら就くかも…!?」「世間体もあるから就くかな…?」等々、働くことに消極的な反応を示すことが多いし、今回のチャットでも同じ様な印象を受けた。ボクは機会あるたびに、様々な年齢や立場の人にこの質問しているので、今までに聴いたいろんな人の話(ex.困っている人のためにボランティアしたい。自身のアイデアを試すために起業したい、etc…)を紹介した。
学生からの講義終了後の感想には、『普段アルバイトをしていると、もう働きたくないなぁと思ってしまうけど、コロナの影響でバイトが0になった時、初めて“働きたい”と思いました。人との関わりが欲しいと思ったし、自分の力を必要として欲しいと思いました(2年生)』とか、『授業終了後、実際に働いている人の意見も聴いてみたくなり、両親に質問したら、両親の答えはそろって“働く”でした。「仕事場は自分の居場所でもあるから」「人と関わらないとしんどい」「何かを作り上げる面白さはかけがえのないものだから」というのが理由でした(1年生)』等のコメントが記されていました。
■「自分のキャリアプランに反する仕事」を続けることは無意味か?
コレ、日本生産性本部で実施している「新入社員 春の意識調査」での質問で、2010年には「無意味だと思わない:83.5%、無意味だ:16.5%」だったのが、2018年には「無意味だと思わない:62.0%、無意味だ:38.0%」と無意味だと思う新入社員の増加が目立っている。今回の学生の反応からも同じ様な印象を受けた。
学生のチャットを読んだ後、「若い頃、そもそもボクにはキャリアプランなんて無かったし、こんな職業人生を歩むなんて想像すらしていなかった」「ボクに限らず、社会経験も無い中で“不変のキャリアプラン”なんて立てられるんだろうか?」等の話をした。確かに素晴らしいキャリアプランを描くことが出来、それを実現できるのは素晴らしいことかもしれないけれど、そもそもキャリアの語源はラテン語の「carrus(荷馬車)」。荷馬車の轍は通った後に残るモノなわけで…。
■貴女の理想のライフ・キャリアプランは?
ウチの会社の採用面接で、「結婚・出産後に仕事を続ける?」と質問すると、女子学生の十中八九は「続けます!」と答える。「面接だから…」というのもあるだろうし、「金銭的に働かないと無理かな…?」なんて思っている学生も少なくないんだろう。
ただ、ボクが聴きたいのは『仕事とどう付き合っていきたいか?』なので、“バリキャリ(総合職として男女の区別なく働く)で働きたい”のか“ゆるキャリ(事務職で補助的に働く)で働きたい”のか、はたまた“専業主婦志向”なのかを聴いてみた。
以下、女子学生からの講義終了後の感想抜粋。『私も専業主婦になりたいけど、せっかく大学に入って様々なことを学んでいるのだから、学んだ知識を少しでも活かせる様、専業主婦になるまでは“バリキャリ”で働きたい』『結婚して子育てするのが夢だけど、仕事をせずに専業主婦をやる気は無いので、両方実現出来る“ゆるキャリライフ”を希望』『結婚し、子供が出来ても仕事は続けたい。もちろん家事はしっかりこなすけど、同時に仕事にも専念することで、子供に「今の時代は女性も男性と同じ様に働くんだよ、守られるだけの立場じゃないんだよ!」ということを教えてあげたい』『“バリキャリ”で働かないことを選んだ際、万一配偶者からDVを受ければ、身の危険に直結すると感じた』等々…。
■貴方が配偶者(妻)に期待するライフ・キャリアプランは?
一方、男子学生には、『配偶者にはどんなキャリアを望むか?』を知りたくて、「1.バリキャリで働いて欲しい」「2.ゆるキャリで働いて欲しい」「3.専業主婦でいて欲しい」「4.本人の意志に任せたい」の四択で聴いてみた。チャットでの感覚値だけど、想定どおり(?)「4.本人の意志に任せたい」が多かった。“本人の意志に任せる”っていうのは、“男性が外で働き女性が家を守る”という考え方がベースにあるんだろうなぁ…。
女子学生の講義終了後の感想に、『女性の“キャリア”について考えた時、まだまだ社会の中で女性の働きやすい環境は不十分であると感じた』『奥さんに専業主婦になる事を望む男性が多いのは、日本の男女の差を示していると思った。確かに専業主婦になりたいと思っている女性もいるが、周りの人や環境によって専業主婦を強いられる女性もいると思う。それは、昔から言われ続けている「女だから」「女らしく」という考え方によるものだと思う。その様な男女差を減らすには、自分の価値観を持つことが大切なのだと感じた』とのコメントもあった。
キャリアについての考え方は、十人十色だったけど、今回もらった感想のボク的『いいね!』は、『女性に対して「“バリキャリ”で働くか?」という質問自体が出ない世の中になって欲しいと思いました』かな!!
■たくさんの感想、ありがとう
以下に、学生からの感想の一部を記載しました。全部は紹介できないけれど、たくさんの感想をありがとう!!
・キャリア概論ということで、なんだか小難しい話をする授業だろうと思っていましたが、全くそんなことはありませんでした。思っていたより、身近なお話で、考えさせられることが多くありました。
・杉山さんが学校にあまり行かなかったというお話を聞いて、とても驚きました。いわゆる、学校で言う優等生タイプではなかった人が、今、社会で活躍・活動されているということ自体が新鮮でした。
・今回の講義で杉山さんが、「キャリアとは、広義の意味では“生き方”です」とおっしゃっていたことに納得しました。
・私のキャリアに対するイメージはプラン先行でしたが、「過ぎてみないとわからない」と聞き、いつもと違った考え方を得ることが出来ました。
・「学生生活は、自分がどんな人生を歩むのかを考える機会なんだ」という言葉がとても印象に残りました。
・お話の中で最も心に残ったメッセージは、「学生時代に、やりたいと思ったことは、余すことなく何でもやっておけ」というものです。
・例えば、「就活がうまくいかず希望の職種に就けなくても“就いた職でしか出会えない人に出会えるかもしれないし、自分が気づかなかった一面にも気付けるかもしれない”そうやって思考を変換していければいい」というお話だと受け止めました。それってざっくり言うと、「どうにかなる」ってコトだと思います。うまくいかなかった時でも、どうにかなるからその時を全力でやるという考え方に切り替えるのは大事です。でもわたし個人の意見としては、「“これでも良かったんだけど、学生時代に○○していたら、その後の道が広がったのかな”の○○を大学生のうちに探してやっておきたい」と思います。
・「他人の評価を気にするのではなく、自分の評価軸を創ることが大切」というお話が心に残りました。絶対的な答えが無い問いに対し、「正解はなんだろう?」と考えるのではなく、「これが自分の意見・答え!」としっかりいえる人間になりたいと思います。
ということで、無事(?)終了です。

※Pic:5月のとある日の静岡県立大学
注)このブログは、2020年4月22日(水)静岡県立大学 キャリア概論を聴講してくれた学生を対象に書いています。聴いていない方には解りにくい部分もあるかもしれないことをご承知おきください。
キャリアについて考える意味Vol.5、最終回。講座のフェイズ4は『みなさんへの質問』。「お金があったら働くか?」「自身のキャリアプランに反する仕事を強いられたら?」「理想のライフ・キャリアプランは?」等の質問を投げかけてみた。
■お金があったら働く?
先ずは、「お金があったら働く?」と質問を投げかけてみた。仕事に就いたことの無い学生の多くは「仕事はお金を稼ぐためにあるんだから、就くわけない!」「やりたい仕事だったら就くかも…!?」「世間体もあるから就くかな…?」等々、働くことに消極的な反応を示すことが多いし、今回のチャットでも同じ様な印象を受けた。ボクは機会あるたびに、様々な年齢や立場の人にこの質問しているので、今までに聴いたいろんな人の話(ex.困っている人のためにボランティアしたい。自身のアイデアを試すために起業したい、etc…)を紹介した。
学生からの講義終了後の感想には、『普段アルバイトをしていると、もう働きたくないなぁと思ってしまうけど、コロナの影響でバイトが0になった時、初めて“働きたい”と思いました。人との関わりが欲しいと思ったし、自分の力を必要として欲しいと思いました(2年生)』とか、『授業終了後、実際に働いている人の意見も聴いてみたくなり、両親に質問したら、両親の答えはそろって“働く”でした。「仕事場は自分の居場所でもあるから」「人と関わらないとしんどい」「何かを作り上げる面白さはかけがえのないものだから」というのが理由でした(1年生)』等のコメントが記されていました。
■「自分のキャリアプランに反する仕事」を続けることは無意味か?
コレ、日本生産性本部で実施している「新入社員 春の意識調査」での質問で、2010年には「無意味だと思わない:83.5%、無意味だ:16.5%」だったのが、2018年には「無意味だと思わない:62.0%、無意味だ:38.0%」と無意味だと思う新入社員の増加が目立っている。今回の学生の反応からも同じ様な印象を受けた。
学生のチャットを読んだ後、「若い頃、そもそもボクにはキャリアプランなんて無かったし、こんな職業人生を歩むなんて想像すらしていなかった」「ボクに限らず、社会経験も無い中で“不変のキャリアプラン”なんて立てられるんだろうか?」等の話をした。確かに素晴らしいキャリアプランを描くことが出来、それを実現できるのは素晴らしいことかもしれないけれど、そもそもキャリアの語源はラテン語の「carrus(荷馬車)」。荷馬車の轍は通った後に残るモノなわけで…。
■貴女の理想のライフ・キャリアプランは?
ウチの会社の採用面接で、「結婚・出産後に仕事を続ける?」と質問すると、女子学生の十中八九は「続けます!」と答える。「面接だから…」というのもあるだろうし、「金銭的に働かないと無理かな…?」なんて思っている学生も少なくないんだろう。
ただ、ボクが聴きたいのは『仕事とどう付き合っていきたいか?』なので、“バリキャリ(総合職として男女の区別なく働く)で働きたい”のか“ゆるキャリ(事務職で補助的に働く)で働きたい”のか、はたまた“専業主婦志向”なのかを聴いてみた。
以下、女子学生からの講義終了後の感想抜粋。『私も専業主婦になりたいけど、せっかく大学に入って様々なことを学んでいるのだから、学んだ知識を少しでも活かせる様、専業主婦になるまでは“バリキャリ”で働きたい』『結婚して子育てするのが夢だけど、仕事をせずに専業主婦をやる気は無いので、両方実現出来る“ゆるキャリライフ”を希望』『結婚し、子供が出来ても仕事は続けたい。もちろん家事はしっかりこなすけど、同時に仕事にも専念することで、子供に「今の時代は女性も男性と同じ様に働くんだよ、守られるだけの立場じゃないんだよ!」ということを教えてあげたい』『“バリキャリ”で働かないことを選んだ際、万一配偶者からDVを受ければ、身の危険に直結すると感じた』等々…。
■貴方が配偶者(妻)に期待するライフ・キャリアプランは?
一方、男子学生には、『配偶者にはどんなキャリアを望むか?』を知りたくて、「1.バリキャリで働いて欲しい」「2.ゆるキャリで働いて欲しい」「3.専業主婦でいて欲しい」「4.本人の意志に任せたい」の四択で聴いてみた。チャットでの感覚値だけど、想定どおり(?)「4.本人の意志に任せたい」が多かった。“本人の意志に任せる”っていうのは、“男性が外で働き女性が家を守る”という考え方がベースにあるんだろうなぁ…。
女子学生の講義終了後の感想に、『女性の“キャリア”について考えた時、まだまだ社会の中で女性の働きやすい環境は不十分であると感じた』『奥さんに専業主婦になる事を望む男性が多いのは、日本の男女の差を示していると思った。確かに専業主婦になりたいと思っている女性もいるが、周りの人や環境によって専業主婦を強いられる女性もいると思う。それは、昔から言われ続けている「女だから」「女らしく」という考え方によるものだと思う。その様な男女差を減らすには、自分の価値観を持つことが大切なのだと感じた』とのコメントもあった。
キャリアについての考え方は、十人十色だったけど、今回もらった感想のボク的『いいね!』は、『女性に対して「“バリキャリ”で働くか?」という質問自体が出ない世の中になって欲しいと思いました』かな!!
■たくさんの感想、ありがとう
以下に、学生からの感想の一部を記載しました。全部は紹介できないけれど、たくさんの感想をありがとう!!
・キャリア概論ということで、なんだか小難しい話をする授業だろうと思っていましたが、全くそんなことはありませんでした。思っていたより、身近なお話で、考えさせられることが多くありました。
・杉山さんが学校にあまり行かなかったというお話を聞いて、とても驚きました。いわゆる、学校で言う優等生タイプではなかった人が、今、社会で活躍・活動されているということ自体が新鮮でした。
・今回の講義で杉山さんが、「キャリアとは、広義の意味では“生き方”です」とおっしゃっていたことに納得しました。
・私のキャリアに対するイメージはプラン先行でしたが、「過ぎてみないとわからない」と聞き、いつもと違った考え方を得ることが出来ました。
・「学生生活は、自分がどんな人生を歩むのかを考える機会なんだ」という言葉がとても印象に残りました。
・お話の中で最も心に残ったメッセージは、「学生時代に、やりたいと思ったことは、余すことなく何でもやっておけ」というものです。
・例えば、「就活がうまくいかず希望の職種に就けなくても“就いた職でしか出会えない人に出会えるかもしれないし、自分が気づかなかった一面にも気付けるかもしれない”そうやって思考を変換していければいい」というお話だと受け止めました。それってざっくり言うと、「どうにかなる」ってコトだと思います。うまくいかなかった時でも、どうにかなるからその時を全力でやるという考え方に切り替えるのは大事です。でもわたし個人の意見としては、「“これでも良かったんだけど、学生時代に○○していたら、その後の道が広がったのかな”の○○を大学生のうちに探してやっておきたい」と思います。
・「他人の評価を気にするのではなく、自分の評価軸を創ることが大切」というお話が心に残りました。絶対的な答えが無い問いに対し、「正解はなんだろう?」と考えるのではなく、「これが自分の意見・答え!」としっかりいえる人間になりたいと思います。
ということで、無事(?)終了です。

※Pic:5月のとある日の静岡県立大学
注)このブログは、2020年4月22日(水)静岡県立大学 キャリア概論を聴講してくれた学生を対象に書いています。聴いていない方には解りにくい部分もあるかもしれないことをご承知おきください。
2020年05月22日
キャリアについて考える意味 Vol.4
~ 社会環境変化について ~
■トヨタ自動車社長のコメントが物議をかもしている
昨年5月、日本自動車工業会の豊田章男 会長(トヨタ自動車 代表取締役社長)は会見で、「日本の“終身雇用”を守っていくのが難しい局面に入ってきた」と話した。
“終身雇用”を巡っては、経団連 中西宏明会長(日立製作所 会長)の「企業からみると、従業員を一生雇い続ける保証書を持っているわけではない」、経済同友会 桜田謙悟代表幹事(SOMPOホールディングス 代表取締役社長兼CEO)の「“終身雇用”という制度は、『制度疲労』を起こしている可能性がある」等、経済界の重鎮が終身雇用見直し論ともとれる発言をしている。
マスメディアやSNS上では、「“終身雇用”の崩壊で若手社員の給与はアップする」vs「長期雇用は“雇用制度”ではなく“経営家哲学”だ!」他…、賛否両論が渦巻いている。
■“事実”で語ろう!?
ここでは、“終身雇用”の賛否は置いといて、事実を共有しておきたい。平成30年1月発表の内閣府の資料(日本経済2017-2018)によると、男性の場合、初職(学校卒業後はじめて就いた仕事)が正社員である割合は79%。そのうち一度も退職することなく“終身雇用”パスを歩んでいる(退職回数0回)のは、30代で48%、40代で38%、50代で34%。わかりやすく言うと、50代で初職の会社に勤め続けている人は、79%×34%≒26.9%、同年代の男性の4人に一人ということになる。
女性の場合、初職が正社員である割合は76%と男性と大きな違いは無いが、“終身雇用”パスを歩んでいるのは50代で7%程度(76%×7%≒5.3%)。つまり“終身雇用”パスを歩んでいるのは、同年代の女性の20人に一人ということになる。女性の場合は、仕事を辞めちゃう人の割合も高そうだ。
ボクは政治家でもないし、学校の先生でも無いので、“日本型雇用慣行”や“終身雇用”について、自身の考えを語るつもりはないけれど、事実を知っとくことは大切だ。
■人の意識は変わらない…
かつては、“日本型雇用慣行”の代名詞的に言われていた“終身雇用”。現実は前述した通りだが、人のもつ“イメージ”が“事実”として認識されるには、多くの時間を要するとも思っている。
1991年にバブル経済が崩壊し企業のリストラが進む中(この頃、“日本型雇用慣行”は崩壊したと言われていた)、ボクは再就職支援の事業に携わっていた。リストラされた中高年の人たちが、「こんなハズじゃなかった…」と言って肩を落とす姿を見て、自分の子供たちの世代の若者には、「同じ想いをさせたくない」と考え2002年に人材コンサルティングの会社をはじめた。
けれども、20年経っても、多くの日本人(老若男女)の意識が大きく変わったとは思えない。学生の就職相談でも「親からは、大きな会社・福利厚生が整った会社に入りなさい」とアドバイスされると聞くと、「ボクが40年前に就活する際に、母親から聞かされたアドバイスと変わってないよな~?!」と思ってしまう。
■労働寿命が企業の寿命を追い越しちゃう時代!?
“終身雇用”の良し悪しは別にして、“一つの会社で一生勤めあげるモデル”が一般的ではなくなってきつつあることを知っておく必要はあるだろう。
米国の調査会社の調べによるとS&Pの株価指数を構成する米国大企業の平均寿命は1960年の60年超から20年程度に短縮化し、今後は更に一段と短くなるとのこと。日本でも帝国データバンクによると現時点の企業の平均寿命は37.16年で、今後、米国と同様に短縮化が進んでいきそうだ。
一方、みなさんが22歳で大学を卒業して70歳まで働くとすれば、仕事に従事するのは48年間。人の労働寿命が企業の寿命を追い越してしまうことになる。
■『チーズはどこへ消えた?』、知っている…?
「“環境変化”を認識するには、多くの時間を要する!」って書いたけど、より重要なのは時間よりもキッカケの方かもしれない…。そんなことを考えていたら、2000年に発売されたビジネス書『チーズはどこへ消えた?』(スペンサー・ジョンソン 著)のことを想い出した。
迷路にあった大切なもの(チーズ)がなくなるという突然の「変化」に、ある者は状況を変えようと迷路を飛び出し、ある者はそのまま迷路に残って現状を維持しようとする。バブル経済崩壊後、大手企業が次々と社員教育のテキストに採用したことも話題となって、ミリオンセラーになった。
「20年も前の本だから、既に絶版になっているだろうな〜!?」とアマゾンで検索してみたら、「今でも売ってるんだ~?!」とビックリ、“環境変化”への対応はボクたちの永遠の課題なんだろうね。
『チーズはどこへ消えた?』、寓話形式で変化への対応の重要性をやさしく説いた100ページ足らずの本なので、「環境変化への対応に躊躇しちゃいそう…!?」ってヒトは、是非、読んでみて欲しい。
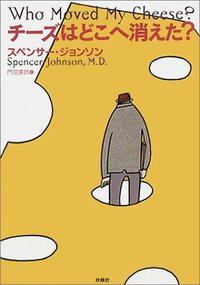
※Pic:紹介した『チーズはどこへ消えた?』。ステマじゃありません。
*********************
【学生さんの感想:Thanks!!】
・仕事を意味のあるものにするのは自分次第なのだと考えました。また、雇用制度というのは時代によって変わっていくので固定観念に縛られず、柔軟な考えでその都度対応していかないといけないのだということもわかりました。
・今回の講義を聞いて思ったことはコロナによる影響で被害が及ぶのは今年の就活生だけではないということ。その現状を理解しすべきことは、自分のキャリアを考え、行動に移す準備をすることだと想いました。
・転職せずに仕事を続けている男性が思った以上に少なかったことにとても驚きました。また企業の寿命が30年以下というのは本当に短く、もし自分が何年も続けている会社に就職することになったら数年経ったら潰れてしまうのか…、という不安も持ちました。長く続けることが出来ている会社にはどんな共通点があるのかと疑問に思いました。
【学生さんからのQuestion & ボクのAnswer】
Q1.コロナウイルスの影響は就職活動にどれほど出るのか知りたいです。
A1.程度はわからないけれど、少なからず影響はあるのだと思う。ただ、いくつかの視点から分析する必要はあるんだと思う。まず第一は、影響があるのは自分だけじゃなくライバル(?)とも言える他の学生も同じだということ。第二に、採用したい企業への影響も大だ。どこの企業も、どうすれば学生と接触出来るかを模索してる。第三は、経済の停滞による企業の採用意欲の減退かな…。いずれにしても“自分が変えられること”と“自分を変え無くちゃならないこと”を整理して考える必要があると思う。
Q2.現在、コロナウイルスの影響で自宅で仕事をする会社が増えています。この体制が終息した後も行うことができれば、女性や障がいを抱えた方など様々な人が働きやすくなると思うのですか、どう思いますか?
A2.ボクは今回、ウチの会社でも急遽、リモートワークをやってみた。やる前までは「出来るのかな〜?」と疑心暗鬼だったんだけど、今はリモートワークに大きな可能性を感じている。特にウチの場合は、子育て中の社員も多いし、そもそも仕事が出来さえすれば、何処で仕事をするのかは大きな問題じゃないわけだから…。ただ、導入の際は「個々のメンバーの自律心が必要条件になるよな〜!」とも思ってます。
ということで、今日はここまで。
注)このブログは、2020年4月22日(水)静岡県立大学 キャリア概論を聴講してくれた学生を対象に書いています。聴いていない方には解りにくい部分もあるかもしれないことをご承知おきください。
■トヨタ自動車社長のコメントが物議をかもしている
昨年5月、日本自動車工業会の豊田章男 会長(トヨタ自動車 代表取締役社長)は会見で、「日本の“終身雇用”を守っていくのが難しい局面に入ってきた」と話した。
“終身雇用”を巡っては、経団連 中西宏明会長(日立製作所 会長)の「企業からみると、従業員を一生雇い続ける保証書を持っているわけではない」、経済同友会 桜田謙悟代表幹事(SOMPOホールディングス 代表取締役社長兼CEO)の「“終身雇用”という制度は、『制度疲労』を起こしている可能性がある」等、経済界の重鎮が終身雇用見直し論ともとれる発言をしている。
マスメディアやSNS上では、「“終身雇用”の崩壊で若手社員の給与はアップする」vs「長期雇用は“雇用制度”ではなく“経営家哲学”だ!」他…、賛否両論が渦巻いている。
■“事実”で語ろう!?
ここでは、“終身雇用”の賛否は置いといて、事実を共有しておきたい。平成30年1月発表の内閣府の資料(日本経済2017-2018)によると、男性の場合、初職(学校卒業後はじめて就いた仕事)が正社員である割合は79%。そのうち一度も退職することなく“終身雇用”パスを歩んでいる(退職回数0回)のは、30代で48%、40代で38%、50代で34%。わかりやすく言うと、50代で初職の会社に勤め続けている人は、79%×34%≒26.9%、同年代の男性の4人に一人ということになる。
女性の場合、初職が正社員である割合は76%と男性と大きな違いは無いが、“終身雇用”パスを歩んでいるのは50代で7%程度(76%×7%≒5.3%)。つまり“終身雇用”パスを歩んでいるのは、同年代の女性の20人に一人ということになる。女性の場合は、仕事を辞めちゃう人の割合も高そうだ。
ボクは政治家でもないし、学校の先生でも無いので、“日本型雇用慣行”や“終身雇用”について、自身の考えを語るつもりはないけれど、事実を知っとくことは大切だ。
■人の意識は変わらない…
かつては、“日本型雇用慣行”の代名詞的に言われていた“終身雇用”。現実は前述した通りだが、人のもつ“イメージ”が“事実”として認識されるには、多くの時間を要するとも思っている。
1991年にバブル経済が崩壊し企業のリストラが進む中(この頃、“日本型雇用慣行”は崩壊したと言われていた)、ボクは再就職支援の事業に携わっていた。リストラされた中高年の人たちが、「こんなハズじゃなかった…」と言って肩を落とす姿を見て、自分の子供たちの世代の若者には、「同じ想いをさせたくない」と考え2002年に人材コンサルティングの会社をはじめた。
けれども、20年経っても、多くの日本人(老若男女)の意識が大きく変わったとは思えない。学生の就職相談でも「親からは、大きな会社・福利厚生が整った会社に入りなさい」とアドバイスされると聞くと、「ボクが40年前に就活する際に、母親から聞かされたアドバイスと変わってないよな~?!」と思ってしまう。
■労働寿命が企業の寿命を追い越しちゃう時代!?
“終身雇用”の良し悪しは別にして、“一つの会社で一生勤めあげるモデル”が一般的ではなくなってきつつあることを知っておく必要はあるだろう。
米国の調査会社の調べによるとS&Pの株価指数を構成する米国大企業の平均寿命は1960年の60年超から20年程度に短縮化し、今後は更に一段と短くなるとのこと。日本でも帝国データバンクによると現時点の企業の平均寿命は37.16年で、今後、米国と同様に短縮化が進んでいきそうだ。
一方、みなさんが22歳で大学を卒業して70歳まで働くとすれば、仕事に従事するのは48年間。人の労働寿命が企業の寿命を追い越してしまうことになる。
■『チーズはどこへ消えた?』、知っている…?
「“環境変化”を認識するには、多くの時間を要する!」って書いたけど、より重要なのは時間よりもキッカケの方かもしれない…。そんなことを考えていたら、2000年に発売されたビジネス書『チーズはどこへ消えた?』(スペンサー・ジョンソン 著)のことを想い出した。
迷路にあった大切なもの(チーズ)がなくなるという突然の「変化」に、ある者は状況を変えようと迷路を飛び出し、ある者はそのまま迷路に残って現状を維持しようとする。バブル経済崩壊後、大手企業が次々と社員教育のテキストに採用したことも話題となって、ミリオンセラーになった。
「20年も前の本だから、既に絶版になっているだろうな〜!?」とアマゾンで検索してみたら、「今でも売ってるんだ~?!」とビックリ、“環境変化”への対応はボクたちの永遠の課題なんだろうね。
『チーズはどこへ消えた?』、寓話形式で変化への対応の重要性をやさしく説いた100ページ足らずの本なので、「環境変化への対応に躊躇しちゃいそう…!?」ってヒトは、是非、読んでみて欲しい。
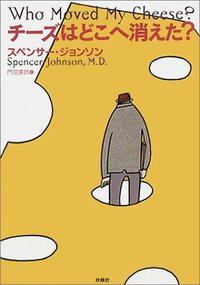
※Pic:紹介した『チーズはどこへ消えた?』。ステマじゃありません。
*********************
【学生さんの感想:Thanks!!】
・仕事を意味のあるものにするのは自分次第なのだと考えました。また、雇用制度というのは時代によって変わっていくので固定観念に縛られず、柔軟な考えでその都度対応していかないといけないのだということもわかりました。
・今回の講義を聞いて思ったことはコロナによる影響で被害が及ぶのは今年の就活生だけではないということ。その現状を理解しすべきことは、自分のキャリアを考え、行動に移す準備をすることだと想いました。
・転職せずに仕事を続けている男性が思った以上に少なかったことにとても驚きました。また企業の寿命が30年以下というのは本当に短く、もし自分が何年も続けている会社に就職することになったら数年経ったら潰れてしまうのか…、という不安も持ちました。長く続けることが出来ている会社にはどんな共通点があるのかと疑問に思いました。
【学生さんからのQuestion & ボクのAnswer】
Q1.コロナウイルスの影響は就職活動にどれほど出るのか知りたいです。
A1.程度はわからないけれど、少なからず影響はあるのだと思う。ただ、いくつかの視点から分析する必要はあるんだと思う。まず第一は、影響があるのは自分だけじゃなくライバル(?)とも言える他の学生も同じだということ。第二に、採用したい企業への影響も大だ。どこの企業も、どうすれば学生と接触出来るかを模索してる。第三は、経済の停滞による企業の採用意欲の減退かな…。いずれにしても“自分が変えられること”と“自分を変え無くちゃならないこと”を整理して考える必要があると思う。
Q2.現在、コロナウイルスの影響で自宅で仕事をする会社が増えています。この体制が終息した後も行うことができれば、女性や障がいを抱えた方など様々な人が働きやすくなると思うのですか、どう思いますか?
A2.ボクは今回、ウチの会社でも急遽、リモートワークをやってみた。やる前までは「出来るのかな〜?」と疑心暗鬼だったんだけど、今はリモートワークに大きな可能性を感じている。特にウチの場合は、子育て中の社員も多いし、そもそも仕事が出来さえすれば、何処で仕事をするのかは大きな問題じゃないわけだから…。ただ、導入の際は「個々のメンバーの自律心が必要条件になるよな〜!」とも思ってます。
ということで、今日はここまで。
注)このブログは、2020年4月22日(水)静岡県立大学 キャリア概論を聴講してくれた学生を対象に書いています。聴いていない方には解りにくい部分もあるかもしれないことをご承知おきください。
2020年05月16日
キャリアについて考える意味 Vol.3
〜ウチ(取締役を務める会社)の社員の実際〜
■成長したい人が増えている?
会社では、管理事業推進部の担当取締役を務めさせていただいている。部署名に“事業推進”って付いているのは、単に管理するだけでなく事業推進の役割を担っていることを社内に示したいから(うまくやれているかどうかは別の話…(苦笑 )。
それはさておき、ウチのメンバーに限らず、学生も社員も「成長したい!」って言う人が本当に多い!!で、それを聴いたボクは「どうなったら成長したって言えるの…、30歳になった時にどうなっていたい?」なんて質問してしまうのだけど…。
ほとんどの人は、具体的なイメージを持たないまま、呪文の様に「成長!!成長!?」と唱えているだけの様に感じる。学生のみなさんは、意地悪な人事担当者にこんな質問をされた際にドギマギしない様に準備しておくといい。
■成長したいメンバーと育成したい上司
一方で、「メンバーを育成したい!」という管理職も多い。ボクも昔は、同じ様なことを言っていたかもしれないので、偉そうなことは言えないが、何十年か社会人をやっていて思うことは、「人を育成するなんて、おこがましいよな〜」ってこと。
社会人としての基本である“報・連・相”がキチッと出来たり、“営業のコツ”を教えたり等、業務が円滑に進むための指導するコトは出来るかもしれないけれど、それは単なる技術指導で、ボクのイメージする育成とは違う。
そんな中、先日、人事考課のヒアリングで入社5年目のメンバーから、「上司は、何でも知っていると思っていたけれど、杉山さんは知らないコトが多いですよね?!」というコメントをもらった。それを聴いてボクはなんか嬉しかった。どんな背景での話なのかをご存じないみなさんが、嬉しい理由を推察するのは難しいと思うけど、ボクは『1年後の彼がどうなっているのか?!』が、とっても楽しみだ。
■想い出したこと
昨今、七五三転職(※注)が社会問題だと言われているが、ボクは大学卒業して、3年しないうちに3つ(企業・公務員)の団体を経験した。転職の主な理由は「休みが少ない」「仕事にやりがいを感じられない」だ。
3つ目の会社は、創業から10年ほどのアルバイトタイムス(求人情報誌のDOMOを発行している)という会社で、社員数は10名程だった。入社の決め手は、当時珍しかった『完全週休2日制!』と『求人情報の会社だから、次に転職する際の情報も多そう?!』という超安易な理由だ。結果的に、この会社では、営業、企画、編集・制作、流通事業、人材関連事業etc…、様々な仕事を経験した。経験しなかったのは、今ウチでやっている管理部門のシゴトくらいだろう。
いろいろやらせてもらったけど、上司である創業社長(満井義政さん)から指導を受けた覚えがない。とはいえ、満井さんには“感謝”の気持ちしかない。技術指導をしてもらったことは一切ないが、多くの機会を与えてくれたことが、その後のボクの人生のとても大きな財産になったと感じている。
結果、アルバイトタイムスのグループには、JASDAQに上場する直前までの17年間お世話になった。そして、入社時に思っていた『次の条件のいい会社』を見つけることなく、自身で起業する道を選んだ。
■離職は悪いこと?
ウチは大学生の就活では、比較的人気のある企業だと思うけど、ご多分にもれず退職者は少なくない。『期待して入社してくれたメンバーが辞めてしまうこと』が寂しくないと言えば、嘘になるけど、辞めないことが良いことだとも思っていない。
あくまで私見だが、『メンバーには自分のために自分を磨き続けて欲しいし、プロの職業人としてどこででも戦える実力をつけて欲しい』と思っている。ボクたち経営の役割は、メンバーが“踊り甲斐を感じられるステージを用意すること”であり、“ウチのステージで踊り続けたいと思ってくれる様なステージを用意すること”だと思っている。
だから、新進気鋭のベンチャー企業に転職したり、地域課題解決のための会社を起こしたりするメンバーの退職は、「次のステージでの活躍への期待や興味」と「ステージが用意できない自身の力不足を嘆く気持ち」が入り交じる。会社としては、大きな損失だから…。
■成長の先にあるもの
授業でもお話したとおり、キャリアの語源は、ラテン語の「carrus(荷馬車)」。キャリアとは、車輪の通った轍を意味する。
学生のみなさんには、「自身の成長の先に何があるのか?将来どうなっていたいのか?」を想像して欲しい。重要なのは、『思った通りになること』ではなく、『“想像した未来”に向かって歩み始めること自体』なんだと思う。
先週、ウチの新卒採用面接(今年はWeb面接)で、学生さんから「若い頃、苦労した経験があったら教えてください」という質問があった。会社の取締役やっている人は苦労の先に取締役というポジションが与えられたと思ったのだろう。面接官であるもうひとりの取締役が「毎日が苦労の連続だよ!若い頃も苦労したコトはたくさんあるけど、今の方がもっと苦労している」と答えた。ボクにとって“もわが意を得たり”の回答だった。
“想像した未来”に向かって歩み続けたとしても、『思った通りになる可能性』は高くない。けれども、人生は想像していなかった自分になれるから面白いんじゃない?
※注)七五三転職:正社員で入社した会社を、中学卒業者で7割、高校卒業者で5割、大学卒業者で3割が3年以内に退職してしまう現象。
***********************************************
【学生さんの感想:Thanks!!】
・何かを始める時に「成長したい」と言ってしまいがちだけど、何をもって成長したとするかの自分の中にはっきりした基準があるわけでもないし、様々な経験をした結果あとから振り返った時に成長したと言えるようになるのかなと思いました。
・“私は人を育成できないから”という発言が面白かった。長くキャリアを積んできて、それが出た結論なんだと深く感じました。確かにいい営業マンにさせることはたくさんの人が出来ると思いますが、そうでは無いんですよね。
・成長とは多少なりとも他人の影響はあるかもしれないが、一番は自分自身によることであることを気づかされた。
・夢を見つけ、そのために今の仕事をやめて一から、また新しいことを始めていく方がいると聴いて、かっこいいなと思いました。たとえお金が稼げない職業だとしても自分がやりたいことならばそれも良い、周りの目を気にして仕事を選ぶのではなく自分がやりたいと思えるようなことをできたらと考えるようになりました。
【学生さんからのQuestion & ボクのAnswer】
Q1.将来、フリーランスで働きたいと思っています。スキルを磨くための踏み台として会社に就職するのは良いことだと思いますか?
A1.“踏み台”というコトバには抵抗があるけど、「“就職=就社”ではない!?」って考えれば、“自分のために仕事に就く”コトは大いにアリだと思う。ただ、ボクはスキルUPを単なる技術や知識の向上と考えるのではなく、もう少し広義に捉えて欲しいとも思う。スキルは、『会社で果たすべき役割』をしっかり担ってこそ、身につくものだと思う。
Q2.なぜ、貴社では若いうちから上司をさせたりするのですか?
A2.う〜ん、これは「なぜ、上司は若くちゃダメなんですか?」って逆質問したくなっちゃう質問かも…。「任せれば、頑張って成果を出してくれそうだ?!」って思えれば、年齢に関わらず任せるのはむしろ必然だと思う。マネジメントの本読むだけじゃ、マネジメントが出来る様にはならないでしょ。
ということで、今日はここまで。

※Pic:アルバイトタイムの企画担当の頃、レーサーのスポンサーをしていた時のもの。上司からシゴトを教えてもらった記憶は無いが、機会を与えてもらえた。感謝の気持ちしかない。
注)このブログは、2020年4月22日(水)静岡県立大学 キャリア概論を聴講してくれた学生を対象に書いています。聴いていない方には解りにくい部分もあるかもしれないことをご承知おきください。
■成長したい人が増えている?
会社では、管理事業推進部の担当取締役を務めさせていただいている。部署名に“事業推進”って付いているのは、単に管理するだけでなく事業推進の役割を担っていることを社内に示したいから(うまくやれているかどうかは別の話…(苦笑 )。
それはさておき、ウチのメンバーに限らず、学生も社員も「成長したい!」って言う人が本当に多い!!で、それを聴いたボクは「どうなったら成長したって言えるの…、30歳になった時にどうなっていたい?」なんて質問してしまうのだけど…。
ほとんどの人は、具体的なイメージを持たないまま、呪文の様に「成長!!成長!?」と唱えているだけの様に感じる。学生のみなさんは、意地悪な人事担当者にこんな質問をされた際にドギマギしない様に準備しておくといい。
■成長したいメンバーと育成したい上司
一方で、「メンバーを育成したい!」という管理職も多い。ボクも昔は、同じ様なことを言っていたかもしれないので、偉そうなことは言えないが、何十年か社会人をやっていて思うことは、「人を育成するなんて、おこがましいよな〜」ってこと。
社会人としての基本である“報・連・相”がキチッと出来たり、“営業のコツ”を教えたり等、業務が円滑に進むための指導するコトは出来るかもしれないけれど、それは単なる技術指導で、ボクのイメージする育成とは違う。
そんな中、先日、人事考課のヒアリングで入社5年目のメンバーから、「上司は、何でも知っていると思っていたけれど、杉山さんは知らないコトが多いですよね?!」というコメントをもらった。それを聴いてボクはなんか嬉しかった。どんな背景での話なのかをご存じないみなさんが、嬉しい理由を推察するのは難しいと思うけど、ボクは『1年後の彼がどうなっているのか?!』が、とっても楽しみだ。
■想い出したこと
昨今、七五三転職(※注)が社会問題だと言われているが、ボクは大学卒業して、3年しないうちに3つ(企業・公務員)の団体を経験した。転職の主な理由は「休みが少ない」「仕事にやりがいを感じられない」だ。
3つ目の会社は、創業から10年ほどのアルバイトタイムス(求人情報誌のDOMOを発行している)という会社で、社員数は10名程だった。入社の決め手は、当時珍しかった『完全週休2日制!』と『求人情報の会社だから、次に転職する際の情報も多そう?!』という超安易な理由だ。結果的に、この会社では、営業、企画、編集・制作、流通事業、人材関連事業etc…、様々な仕事を経験した。経験しなかったのは、今ウチでやっている管理部門のシゴトくらいだろう。
いろいろやらせてもらったけど、上司である創業社長(満井義政さん)から指導を受けた覚えがない。とはいえ、満井さんには“感謝”の気持ちしかない。技術指導をしてもらったことは一切ないが、多くの機会を与えてくれたことが、その後のボクの人生のとても大きな財産になったと感じている。
結果、アルバイトタイムスのグループには、JASDAQに上場する直前までの17年間お世話になった。そして、入社時に思っていた『次の条件のいい会社』を見つけることなく、自身で起業する道を選んだ。
■離職は悪いこと?
ウチは大学生の就活では、比較的人気のある企業だと思うけど、ご多分にもれず退職者は少なくない。『期待して入社してくれたメンバーが辞めてしまうこと』が寂しくないと言えば、嘘になるけど、辞めないことが良いことだとも思っていない。
あくまで私見だが、『メンバーには自分のために自分を磨き続けて欲しいし、プロの職業人としてどこででも戦える実力をつけて欲しい』と思っている。ボクたち経営の役割は、メンバーが“踊り甲斐を感じられるステージを用意すること”であり、“ウチのステージで踊り続けたいと思ってくれる様なステージを用意すること”だと思っている。
だから、新進気鋭のベンチャー企業に転職したり、地域課題解決のための会社を起こしたりするメンバーの退職は、「次のステージでの活躍への期待や興味」と「ステージが用意できない自身の力不足を嘆く気持ち」が入り交じる。会社としては、大きな損失だから…。
■成長の先にあるもの
授業でもお話したとおり、キャリアの語源は、ラテン語の「carrus(荷馬車)」。キャリアとは、車輪の通った轍を意味する。
学生のみなさんには、「自身の成長の先に何があるのか?将来どうなっていたいのか?」を想像して欲しい。重要なのは、『思った通りになること』ではなく、『“想像した未来”に向かって歩み始めること自体』なんだと思う。
先週、ウチの新卒採用面接(今年はWeb面接)で、学生さんから「若い頃、苦労した経験があったら教えてください」という質問があった。会社の取締役やっている人は苦労の先に取締役というポジションが与えられたと思ったのだろう。面接官であるもうひとりの取締役が「毎日が苦労の連続だよ!若い頃も苦労したコトはたくさんあるけど、今の方がもっと苦労している」と答えた。ボクにとって“もわが意を得たり”の回答だった。
“想像した未来”に向かって歩み続けたとしても、『思った通りになる可能性』は高くない。けれども、人生は想像していなかった自分になれるから面白いんじゃない?
※注)七五三転職:正社員で入社した会社を、中学卒業者で7割、高校卒業者で5割、大学卒業者で3割が3年以内に退職してしまう現象。
***********************************************
【学生さんの感想:Thanks!!】
・何かを始める時に「成長したい」と言ってしまいがちだけど、何をもって成長したとするかの自分の中にはっきりした基準があるわけでもないし、様々な経験をした結果あとから振り返った時に成長したと言えるようになるのかなと思いました。
・“私は人を育成できないから”という発言が面白かった。長くキャリアを積んできて、それが出た結論なんだと深く感じました。確かにいい営業マンにさせることはたくさんの人が出来ると思いますが、そうでは無いんですよね。
・成長とは多少なりとも他人の影響はあるかもしれないが、一番は自分自身によることであることを気づかされた。
・夢を見つけ、そのために今の仕事をやめて一から、また新しいことを始めていく方がいると聴いて、かっこいいなと思いました。たとえお金が稼げない職業だとしても自分がやりたいことならばそれも良い、周りの目を気にして仕事を選ぶのではなく自分がやりたいと思えるようなことをできたらと考えるようになりました。
【学生さんからのQuestion & ボクのAnswer】
Q1.将来、フリーランスで働きたいと思っています。スキルを磨くための踏み台として会社に就職するのは良いことだと思いますか?
A1.“踏み台”というコトバには抵抗があるけど、「“就職=就社”ではない!?」って考えれば、“自分のために仕事に就く”コトは大いにアリだと思う。ただ、ボクはスキルUPを単なる技術や知識の向上と考えるのではなく、もう少し広義に捉えて欲しいとも思う。スキルは、『会社で果たすべき役割』をしっかり担ってこそ、身につくものだと思う。
Q2.なぜ、貴社では若いうちから上司をさせたりするのですか?
A2.う〜ん、これは「なぜ、上司は若くちゃダメなんですか?」って逆質問したくなっちゃう質問かも…。「任せれば、頑張って成果を出してくれそうだ?!」って思えれば、年齢に関わらず任せるのはむしろ必然だと思う。マネジメントの本読むだけじゃ、マネジメントが出来る様にはならないでしょ。
ということで、今日はここまで。

※Pic:アルバイトタイムの企画担当の頃、レーサーのスポンサーをしていた時のもの。上司からシゴトを教えてもらった記憶は無いが、機会を与えてもらえた。感謝の気持ちしかない。
注)このブログは、2020年4月22日(水)静岡県立大学 キャリア概論を聴講してくれた学生を対象に書いています。聴いていない方には解りにくい部分もあるかもしれないことをご承知おきください。
2020年05月06日
キャリアについて考える意味 Vol.2
〜ボクが学生と接する中、感じること〜
■よくある就職相談
学生の就職相談で多いのが、就活の三大鬼門?(自己分析、ES、面接)の一つでもある「エントリーシート(以下、ES)の添削依頼。ESは、何かの意図を持って書いているハズ(?)だから、「このES、面接官に何を伝えたくて書いたの?」などと質問するのだが…。質問(例:学生時代頑張ったことは?)に対する答えは丁寧に書かれているけれど、それを通して採用担当者に何を伝えたいという意図が無いまま書いているコトが多い様に感じる。
そんなコトもあって、最近は添削の依頼があると「添削はしないけど、このES読んで聴いてみたいと思ったことを質問するよ!?」などと前置きしてから相談業務に入ることも少なくない。
■意図を持った発言が出来ているか?
就職相談では、他にも似たような場面に出くわす。例えば、「面接の時に〇〇聴かれたら、なんて答えれば良いですか?」という質問。質問に対する答えは“人それぞれ”だし“採用側の質問の意図”が解らないのに、「なんて答えればよいのか?」って言われても困ってしまう。逆に、「就活マニュアルに『この質問にはこう答えろ!』と書いてあるんだが、違和感がある」なんていう学生の言葉には、ホッとする。
あと、(採用担当の)「何か質問ありますか?」の問に対して、「残りの学生生活、何をすればいいですか?」って質問にも困ってしまう。ボクは、本番(ウチの会社)の面接では「あなたは何をやればいいと思う?」と逆質問し、「あなたがやりたいと思ったコトをやればいいよ!」と返している。意地悪だね…(笑
■答えはひとつ?
今回の講義では、「学校の試験以外に答えが一つに決まっているものを教えて!?」という問いかけをさせていただいた。ボクには、陸上競技の様なイコールコンディション(コレとて道具の進歩で全くのイコールとは言えなくなってきている…)で行われる競技以外は、一つしか答えがないケースを思い浮かべることが出来ない。更に、チームには、技術的に優れている人だけじゃなく、リーダーシップに秀でた人、ムードメーカー等、いろんなメンバーが必要で、誰か一人だけで成り立つモノじゃない。ボクがF-1や自転車のロードレースが好きな理由は、“不公平で、スーパースター一人の力だけじゃ勝てないコト”なのかもしれない。
答えはひとつじゃない。“人それぞれの答えがある”ハズだし、“置かれた状況によって答えは変わっていくモノ”という当たり前が共有できていない様な気がする。
■自分の基準を持つことの大切さ
ボクたちは、学校教育の中で、“正解は一つ”と刷り込まれ続けてきた様な気がする。現在、小・中・高校で推し進められているキャリア教育でよく聴く「なりたい自分を見つけよう!」っていうコトバも、視野を狭める一つの要因になっていないだろうか。「どんな職業に就きたい?」と言われても「なりたい自分が見つからない?」と悩み立ち止ってしまう学生は少なくない。
更に、社会経験の浅い学生に、「なりたい自分は明確です!」って断言されちゃうのはもっと心配だ。そういう学生によくよく話を聴くと、単に“知名度が高かったり福利厚生の整った会社”に入ることだけが目的になってしまっているケースが少なくない。そんな会社選びをして、入社2〜3年でウチに転職してくる学生もいるからな〜?!
誰かに与えられた目標とか基準じゃなく、自分のモノサシを持つことが大切なんだと思う。
*********************************
【学生さんの感想:Thanks!!】
・面接の質疑応答での「(学生が)やっておいた方がいいことは?」のお話を聴いて、自分のやりたいことに挑戦しようと思えるようになりました。
・学校の試験以外、答えは一つではないということにとても納得しました。大学生のうちにやりたいことをやり、机上の勉強では学べないことを様々な分野で挑戦して、自分の視野を広げたいなと思いました。
・「なりたい自分なんてあとから見つかる」「就活で焦ることなんてない」という言葉がとても心に残りました。
・私は高校まで、周りからの評価ばかり気にしていました。そして、誰かが持っている答えにたどり着くことを目的に行動していました。まずは、自分がやりたいことを考えてみることからはじめてみようと思いました。
・私は成績がいいわけではありませんが他人からの評価を気にしすぎているのかもしれないと思いました。しかし、自分が死ぬ時に後悔しないためにも、自分と向き合って、自分が幸せで充実していると思える人生なら、それが一番だと思いました。
・自分は、良い会社に入って、業務をこなせるようになり、昇進していくことが「成長」であったり、「キャリア」を積んでいくことだと思っていたので、正直ギクッとしました。
・この授業は、“いい企業”に就くためには何をしたらいいかの答えを見つけるために受講した。いわゆる“いい企業”に入るコトを目的にしていた自分は、耳が痛くなるような思いでした。
・何事に関しても自分の基準を設けようと思いました。会社の基準に合わせることも必要な場面は多々あると思うが、会社の基準の一歩先に行った基準を設け、ほかと違う質の良い働きをすることでキャリアを育てたい。
・授業を聴いたことによって、“自分で考えて自分で決める”のが重要なのではないかと思いました。
・私は、将来の夢がなく、大卒という学歴のために大学進学を選択したようなものですが、今回の授業を受けて、今の生活がただの学歴として終わってしまうことは非常に残念なことだと感じました。
【学生さんからのQuestion】
・何かを始めるときどこから勇気や自信が湧いてくるのですか?
・何か行動を起こす時に、周りの反応や評価を考えて、積極的に行動できないです。これは、自意識過剰でしょうか?
【ボクのAnswer】
“勇気や自信”“自意識過剰”に対する答えになるかはわからないけれど、『勇気を持たないと始められない』場合と『とりあえず始めてみる』場合の2つがある様に思う。で、ボクの場合、多いのは『とりあえず始めてみる』ですね。趣味なんかは、圧倒的にコレ!!
『勇気を持たないと始められない』場合…。う〜ん、今まででの一番は、18年前の起業かな?当時、前職では取締役だったし、家族もいたから…。で、なんで踏み切れたかというと、将来を俯瞰するに足り得る情報を持っていたからだと思う。簡単に言うと、大手企業も雇用の保証をしなくなる中、今いる会社が未来永劫まで面倒見てくれるわけではない、“自分の足で立つ術”を習得することが、結果的にリスク回避につながると考えたからかな。
ちょうど、父親が亡くなった頃だったので、「人間、いつかは死ぬんだ!だったら好きなようにやろう!!」と実感できたのも大きいかもしれない。
ということで、今日はここまで。

※Pic:20代前半、流行りはじめたWSFにハマってた時期があります。
注)このブログは、2020年4月22日(水)静岡県立大学 キャリア概論を聴講してくれた学生を対象に書いています。聴いていない方には解りにくい部分もあるかもしれないことをご承知おきください。
■よくある就職相談
学生の就職相談で多いのが、就活の三大鬼門?(自己分析、ES、面接)の一つでもある「エントリーシート(以下、ES)の添削依頼。ESは、何かの意図を持って書いているハズ(?)だから、「このES、面接官に何を伝えたくて書いたの?」などと質問するのだが…。質問(例:学生時代頑張ったことは?)に対する答えは丁寧に書かれているけれど、それを通して採用担当者に何を伝えたいという意図が無いまま書いているコトが多い様に感じる。
そんなコトもあって、最近は添削の依頼があると「添削はしないけど、このES読んで聴いてみたいと思ったことを質問するよ!?」などと前置きしてから相談業務に入ることも少なくない。
■意図を持った発言が出来ているか?
就職相談では、他にも似たような場面に出くわす。例えば、「面接の時に〇〇聴かれたら、なんて答えれば良いですか?」という質問。質問に対する答えは“人それぞれ”だし“採用側の質問の意図”が解らないのに、「なんて答えればよいのか?」って言われても困ってしまう。逆に、「就活マニュアルに『この質問にはこう答えろ!』と書いてあるんだが、違和感がある」なんていう学生の言葉には、ホッとする。
あと、(採用担当の)「何か質問ありますか?」の問に対して、「残りの学生生活、何をすればいいですか?」って質問にも困ってしまう。ボクは、本番(ウチの会社)の面接では「あなたは何をやればいいと思う?」と逆質問し、「あなたがやりたいと思ったコトをやればいいよ!」と返している。意地悪だね…(笑
■答えはひとつ?
今回の講義では、「学校の試験以外に答えが一つに決まっているものを教えて!?」という問いかけをさせていただいた。ボクには、陸上競技の様なイコールコンディション(コレとて道具の進歩で全くのイコールとは言えなくなってきている…)で行われる競技以外は、一つしか答えがないケースを思い浮かべることが出来ない。更に、チームには、技術的に優れている人だけじゃなく、リーダーシップに秀でた人、ムードメーカー等、いろんなメンバーが必要で、誰か一人だけで成り立つモノじゃない。ボクがF-1や自転車のロードレースが好きな理由は、“不公平で、スーパースター一人の力だけじゃ勝てないコト”なのかもしれない。
答えはひとつじゃない。“人それぞれの答えがある”ハズだし、“置かれた状況によって答えは変わっていくモノ”という当たり前が共有できていない様な気がする。
■自分の基準を持つことの大切さ
ボクたちは、学校教育の中で、“正解は一つ”と刷り込まれ続けてきた様な気がする。現在、小・中・高校で推し進められているキャリア教育でよく聴く「なりたい自分を見つけよう!」っていうコトバも、視野を狭める一つの要因になっていないだろうか。「どんな職業に就きたい?」と言われても「なりたい自分が見つからない?」と悩み立ち止ってしまう学生は少なくない。
更に、社会経験の浅い学生に、「なりたい自分は明確です!」って断言されちゃうのはもっと心配だ。そういう学生によくよく話を聴くと、単に“知名度が高かったり福利厚生の整った会社”に入ることだけが目的になってしまっているケースが少なくない。そんな会社選びをして、入社2〜3年でウチに転職してくる学生もいるからな〜?!
誰かに与えられた目標とか基準じゃなく、自分のモノサシを持つことが大切なんだと思う。
*********************************
【学生さんの感想:Thanks!!】
・面接の質疑応答での「(学生が)やっておいた方がいいことは?」のお話を聴いて、自分のやりたいことに挑戦しようと思えるようになりました。
・学校の試験以外、答えは一つではないということにとても納得しました。大学生のうちにやりたいことをやり、机上の勉強では学べないことを様々な分野で挑戦して、自分の視野を広げたいなと思いました。
・「なりたい自分なんてあとから見つかる」「就活で焦ることなんてない」という言葉がとても心に残りました。
・私は高校まで、周りからの評価ばかり気にしていました。そして、誰かが持っている答えにたどり着くことを目的に行動していました。まずは、自分がやりたいことを考えてみることからはじめてみようと思いました。
・私は成績がいいわけではありませんが他人からの評価を気にしすぎているのかもしれないと思いました。しかし、自分が死ぬ時に後悔しないためにも、自分と向き合って、自分が幸せで充実していると思える人生なら、それが一番だと思いました。
・自分は、良い会社に入って、業務をこなせるようになり、昇進していくことが「成長」であったり、「キャリア」を積んでいくことだと思っていたので、正直ギクッとしました。
・この授業は、“いい企業”に就くためには何をしたらいいかの答えを見つけるために受講した。いわゆる“いい企業”に入るコトを目的にしていた自分は、耳が痛くなるような思いでした。
・何事に関しても自分の基準を設けようと思いました。会社の基準に合わせることも必要な場面は多々あると思うが、会社の基準の一歩先に行った基準を設け、ほかと違う質の良い働きをすることでキャリアを育てたい。
・授業を聴いたことによって、“自分で考えて自分で決める”のが重要なのではないかと思いました。
・私は、将来の夢がなく、大卒という学歴のために大学進学を選択したようなものですが、今回の授業を受けて、今の生活がただの学歴として終わってしまうことは非常に残念なことだと感じました。
【学生さんからのQuestion】
・何かを始めるときどこから勇気や自信が湧いてくるのですか?
・何か行動を起こす時に、周りの反応や評価を考えて、積極的に行動できないです。これは、自意識過剰でしょうか?
【ボクのAnswer】
“勇気や自信”“自意識過剰”に対する答えになるかはわからないけれど、『勇気を持たないと始められない』場合と『とりあえず始めてみる』場合の2つがある様に思う。で、ボクの場合、多いのは『とりあえず始めてみる』ですね。趣味なんかは、圧倒的にコレ!!
『勇気を持たないと始められない』場合…。う〜ん、今まででの一番は、18年前の起業かな?当時、前職では取締役だったし、家族もいたから…。で、なんで踏み切れたかというと、将来を俯瞰するに足り得る情報を持っていたからだと思う。簡単に言うと、大手企業も雇用の保証をしなくなる中、今いる会社が未来永劫まで面倒見てくれるわけではない、“自分の足で立つ術”を習得することが、結果的にリスク回避につながると考えたからかな。
ちょうど、父親が亡くなった頃だったので、「人間、いつかは死ぬんだ!だったら好きなようにやろう!!」と実感できたのも大きいかもしれない。
ということで、今日はここまで。

※Pic:20代前半、流行りはじめたWSFにハマってた時期があります。
注)このブログは、2020年4月22日(水)静岡県立大学 キャリア概論を聴講してくれた学生を対象に書いています。聴いていない方には解りにくい部分もあるかもしれないことをご承知おきください。
2020年05月04日
キャリアについて考える意味 Vol.1
〜新型コロナウイルス感染拡大の最中、キャリアについてお話をする機会をいただきました!〜
例年登壇の機会をいただいている静岡県立大学のキャリア概論Ⅰ(津富宏 教授)で、今年もお話をする機会をいただきました。例年と大きく違うのは、コロナ禍の影響で主な受講対象である1年生は入学式も無く、未だ同級生と1度も顔を合わせることも無い中でのWebでの授業であるということ。こんな状況だからこそ、「キャリアとは何か?」「キャリアについてなぜ考える必要があるのか?」という問いかけをしたいと思い、授業の構成を考えてみた。
大きな流れは、パラレルワーカー(人材コンサルタント、企業経営者、大学講師)という働き方を選んだボクの自己紹介から始まって、『1.ボクが学生と接する中、感じること』『2. ウチ(取締役を務める会社)の社員の実際』『3. 社会環境変化について』『4. みなさんへの質問』という4つのフェーズで整理してみた。また、資料は「スマホで参加する学生も少なくないだろうから、文字を大きくポイントだけを載せよう!」とか「ワンウェイになる可能性大だから、後半は質問も織り交ぜよう!」とか、無い知恵絞って作成した。
ボクにとっては初のWeb授業。今回は、当該科目の1回目であり、概ね70名の学生も(たぶん)Web授業は初体験ということで、「果たして90分(ボクの持ち時間は概ね60分強)持つのだろか…?」という不安いっぱいでスタートした。確かにリアルな反応を感じ取ることは難しいのだけれど、学生の顔がモニターに映っていることもあり、喋り手としては比較的安心して話が出来る。
また当初は『4. みなさんへの質問』についても、質問を投げかけた後、しばらく時間を置いてから調査結果の開示をしようと考えていたのだが…。zoomのチャットボタンを見つけ「何番の答えを選んだか?チャットで教えて!」と投げかけることにより、ボクが参加学生の考えを把握出来るだけじゃなく、他の学生にも解答の全体像が共有され気づきを与えられるトコロも悪くない。実際、学生の感想にも「いろんな考え方の学生がいることに驚いた」「対面では言い辛いことでもネットを通じてだったら言えるので続けて欲しい」等の感想も少なくなかった。直に学生と接するのに越したことはないとは思うけど、マスプロ授業で双方向のコミュニケーションに悩んでいるボクには、Web授業もツールのひとつとしては“アリ”と思える経験となった。
とここまで、“Web授業体験記”みたいになってしまったけど、超ひさしぶりにBlogを書こうと思った理由は実はソコじゃない。授業終了後の学生のコメント(考えたこと、質問等)を読ませてもらい、「こりゃ、ボクの感想やボクなりの回答を返すのが礼儀だろう!?」と思ったから…。ということで、数回に分けて一部、学生のコメントも引用しつつ、ボクなりのコメントを綴ってみようと思う。
ということで、今日はここまで。

※Pic:大学卒業後、1社目を9ヶ月で退職。最初の冬の伊勢神宮。
例年登壇の機会をいただいている静岡県立大学のキャリア概論Ⅰ(津富宏 教授)で、今年もお話をする機会をいただきました。例年と大きく違うのは、コロナ禍の影響で主な受講対象である1年生は入学式も無く、未だ同級生と1度も顔を合わせることも無い中でのWebでの授業であるということ。こんな状況だからこそ、「キャリアとは何か?」「キャリアについてなぜ考える必要があるのか?」という問いかけをしたいと思い、授業の構成を考えてみた。
大きな流れは、パラレルワーカー(人材コンサルタント、企業経営者、大学講師)という働き方を選んだボクの自己紹介から始まって、『1.ボクが学生と接する中、感じること』『2. ウチ(取締役を務める会社)の社員の実際』『3. 社会環境変化について』『4. みなさんへの質問』という4つのフェーズで整理してみた。また、資料は「スマホで参加する学生も少なくないだろうから、文字を大きくポイントだけを載せよう!」とか「ワンウェイになる可能性大だから、後半は質問も織り交ぜよう!」とか、無い知恵絞って作成した。
ボクにとっては初のWeb授業。今回は、当該科目の1回目であり、概ね70名の学生も(たぶん)Web授業は初体験ということで、「果たして90分(ボクの持ち時間は概ね60分強)持つのだろか…?」という不安いっぱいでスタートした。確かにリアルな反応を感じ取ることは難しいのだけれど、学生の顔がモニターに映っていることもあり、喋り手としては比較的安心して話が出来る。
また当初は『4. みなさんへの質問』についても、質問を投げかけた後、しばらく時間を置いてから調査結果の開示をしようと考えていたのだが…。zoomのチャットボタンを見つけ「何番の答えを選んだか?チャットで教えて!」と投げかけることにより、ボクが参加学生の考えを把握出来るだけじゃなく、他の学生にも解答の全体像が共有され気づきを与えられるトコロも悪くない。実際、学生の感想にも「いろんな考え方の学生がいることに驚いた」「対面では言い辛いことでもネットを通じてだったら言えるので続けて欲しい」等の感想も少なくなかった。直に学生と接するのに越したことはないとは思うけど、マスプロ授業で双方向のコミュニケーションに悩んでいるボクには、Web授業もツールのひとつとしては“アリ”と思える経験となった。
とここまで、“Web授業体験記”みたいになってしまったけど、超ひさしぶりにBlogを書こうと思った理由は実はソコじゃない。授業終了後の学生のコメント(考えたこと、質問等)を読ませてもらい、「こりゃ、ボクの感想やボクなりの回答を返すのが礼儀だろう!?」と思ったから…。ということで、数回に分けて一部、学生のコメントも引用しつつ、ボクなりのコメントを綴ってみようと思う。
ということで、今日はここまで。

※Pic:大学卒業後、1社目を9ヶ月で退職。最初の冬の伊勢神宮。
2018年02月12日
江副浩正
〜馬場マコト・土屋洋 著〜
リクルート出身者でもある、馬場マコト・土屋洋 両氏が、多くの証言や膨大な資料を基に、江副浩正氏の実像をあぶり出した本。
江副氏は、多くの日本人にとって昭和のバブル期に政・財界を巻き込んで起こった贈収賄事件であるリクルート事件の主人公かもしれないが…。30余年にわたり情報ビジネス・人材ビジネスに携わってきた私にとって、江副氏は優秀な経営者という域を超えた“日本の産業構造変革を成し遂げたヒーロー”でありスペシャルな存在だ。1983年にリクルートが日軽金ビルを購入したことで、世間は大騒ぎになった。TVのニュース番組が「製造業の代表的企業である日軽金が、得体の知れない新興企業に飲み込まれた…!?」というニュアンスで報じていたことが強く印象に残っている。496頁というボリュームにもかかわらず、迫力と熱量に引き込まれて一気に読破した。
全21章のうち、前半の第11章あたりまでは、江副氏の生い立ち・東大新聞の営業をしていた学生時代から、起業・事業の多角化により成功の階段を駆け上がっていく様子が…。後半は、店頭登録に絡む疑惑報道・裁判の様子が、江副氏の心の変化を織り交ぜながら描かれている。
すべてが読みどころなので、ご興味を持たれた方には読まれることを強くお勧めしますが、以下は、私の備忘録。
前半部分で特に印象深かったのは、リクルートコスモスが快進撃を続ける中での、不動産業界のパーティーでの業界大手経営陣のやりとり。
業界のパーティーで顔を合わせた住友不動産の安藤太郎会長は、ばったり顔を合わせた三井不動産の江戸英雄相談役に思わずこう言った。
「うちでは上司の鞄持ち程度しかしていない年齢の人たちが、土地情報を入手して2,3日後に購入の結論を出している。信じられないことだ」
江戸も頷きながら返した。
「江副君という人は、旧財閥系の組織で育ったわれわれには、とうてい及びもつかない発想をする人ですね。あの時代への斬りこみ方は、大企業に身を置いた者にはとてもまねができませんよ」
江副氏の “自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ”“社員皆経営主義”の具現化を周囲の経営者が、どう視ていたかがよく解る。
後半部分で印象深かったのは、疑惑の中にあろうとも信頼できる友人の存在。その一、検察やメディアに対して、「還流株」にかかわったとの疑惑をかけられた友人のやりとり。
「初めから株の譲渡は江副の好意だ。代償など一つもない」
「だろう、俺も同じだ。江副から頼むよと言われた。だから回した。友だちの好だ」
新倉の言う通りだ。別に打算はない。菅原は日ごろ感じていることをしみじみと語った。
「彼ら(メディア)は、世間には損得とは無関係に動く人間がいるとは考えもしないんだ。人はみな、自分と同じくカネのためにしか動かないと思っている。江副の不幸は、そんなやつらににらまれたことだ」
その二、リクルートの社章・ビルのデザインから始まり、社外取締役となる亀倉雄策の存在。
亀倉は「経営とデザインの一体化」を願い、戦後の日本経済の成長とともに歩んできた。リクルートの成長もまた、亀倉のデザインとともにあった。江副は、その恩義を忘れず、ビルデザインや総合レジャー開発という新しい領域に自分の才能を導いてくれた。
そのうえに、社外取締役として経営にまで参画させてくれた。その江副が、世間からあらゆる罵詈雑言を浴び、苦しんでいる。潮が引くように、多くの人が江副と疎遠となっていくなか、立っていられないほどに消耗し自死の誘惑に耐えている。
それを放っておけるか。この男の傍らに寄り添い、最後のひとりになっても良いから彼と同じ道を歩もう。
亀倉デザイン研究所をリクルート本社ビル内に移すことに決め、江副に電話をかけた。
「大変ありがたいお申し出ですが、先生の晩年を汚すことになりかねません。お気持ちだけいただき、先生のお引っ越しはご遠慮させていただきます」
「いや、もう私は決めたんです。いまの事務所は年内で解約します」
電話を置くと、亀倉はすぐに、事務所引っ越しの案内状づくりに取り掛かった。
お互いが尊敬・信頼しあえる人に出会えることは、最高の幸せであり、何よりの財産だとつくづく感じさせる。
最後に、常に心に留めておきたいと思った一文。
江副が師と仰ぐドラッカーもまた言う。
「凡人に非凡なことをさせるのが組織の目的である」
ならば、優秀な人材がその能力をフルに発揮すれば、かなりのことができる。では、社員をそうし向けるにはどうすればいいか。組織のために働くのではなく、自分のために働く。これが個人を成長させる近道だ。そして、成長し続ける個人が集まる組織は強い。それなら、その制約は少ないほうがいい。社員が可能な限り自由に働ける制度と風土づくりをめざした。
まったく書評の体を成していませんが、とにかく良い本でした。

リクルート出身者でもある、馬場マコト・土屋洋 両氏が、多くの証言や膨大な資料を基に、江副浩正氏の実像をあぶり出した本。
江副氏は、多くの日本人にとって昭和のバブル期に政・財界を巻き込んで起こった贈収賄事件であるリクルート事件の主人公かもしれないが…。30余年にわたり情報ビジネス・人材ビジネスに携わってきた私にとって、江副氏は優秀な経営者という域を超えた“日本の産業構造変革を成し遂げたヒーロー”でありスペシャルな存在だ。1983年にリクルートが日軽金ビルを購入したことで、世間は大騒ぎになった。TVのニュース番組が「製造業の代表的企業である日軽金が、得体の知れない新興企業に飲み込まれた…!?」というニュアンスで報じていたことが強く印象に残っている。496頁というボリュームにもかかわらず、迫力と熱量に引き込まれて一気に読破した。
全21章のうち、前半の第11章あたりまでは、江副氏の生い立ち・東大新聞の営業をしていた学生時代から、起業・事業の多角化により成功の階段を駆け上がっていく様子が…。後半は、店頭登録に絡む疑惑報道・裁判の様子が、江副氏の心の変化を織り交ぜながら描かれている。
すべてが読みどころなので、ご興味を持たれた方には読まれることを強くお勧めしますが、以下は、私の備忘録。
前半部分で特に印象深かったのは、リクルートコスモスが快進撃を続ける中での、不動産業界のパーティーでの業界大手経営陣のやりとり。
業界のパーティーで顔を合わせた住友不動産の安藤太郎会長は、ばったり顔を合わせた三井不動産の江戸英雄相談役に思わずこう言った。
「うちでは上司の鞄持ち程度しかしていない年齢の人たちが、土地情報を入手して2,3日後に購入の結論を出している。信じられないことだ」
江戸も頷きながら返した。
「江副君という人は、旧財閥系の組織で育ったわれわれには、とうてい及びもつかない発想をする人ですね。あの時代への斬りこみ方は、大企業に身を置いた者にはとてもまねができませんよ」
江副氏の “自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ”“社員皆経営主義”の具現化を周囲の経営者が、どう視ていたかがよく解る。
後半部分で印象深かったのは、疑惑の中にあろうとも信頼できる友人の存在。その一、検察やメディアに対して、「還流株」にかかわったとの疑惑をかけられた友人のやりとり。
「初めから株の譲渡は江副の好意だ。代償など一つもない」
「だろう、俺も同じだ。江副から頼むよと言われた。だから回した。友だちの好だ」
新倉の言う通りだ。別に打算はない。菅原は日ごろ感じていることをしみじみと語った。
「彼ら(メディア)は、世間には損得とは無関係に動く人間がいるとは考えもしないんだ。人はみな、自分と同じくカネのためにしか動かないと思っている。江副の不幸は、そんなやつらににらまれたことだ」
その二、リクルートの社章・ビルのデザインから始まり、社外取締役となる亀倉雄策の存在。
亀倉は「経営とデザインの一体化」を願い、戦後の日本経済の成長とともに歩んできた。リクルートの成長もまた、亀倉のデザインとともにあった。江副は、その恩義を忘れず、ビルデザインや総合レジャー開発という新しい領域に自分の才能を導いてくれた。
そのうえに、社外取締役として経営にまで参画させてくれた。その江副が、世間からあらゆる罵詈雑言を浴び、苦しんでいる。潮が引くように、多くの人が江副と疎遠となっていくなか、立っていられないほどに消耗し自死の誘惑に耐えている。
それを放っておけるか。この男の傍らに寄り添い、最後のひとりになっても良いから彼と同じ道を歩もう。
亀倉デザイン研究所をリクルート本社ビル内に移すことに決め、江副に電話をかけた。
「大変ありがたいお申し出ですが、先生の晩年を汚すことになりかねません。お気持ちだけいただき、先生のお引っ越しはご遠慮させていただきます」
「いや、もう私は決めたんです。いまの事務所は年内で解約します」
電話を置くと、亀倉はすぐに、事務所引っ越しの案内状づくりに取り掛かった。
お互いが尊敬・信頼しあえる人に出会えることは、最高の幸せであり、何よりの財産だとつくづく感じさせる。
最後に、常に心に留めておきたいと思った一文。
江副が師と仰ぐドラッカーもまた言う。
「凡人に非凡なことをさせるのが組織の目的である」
ならば、優秀な人材がその能力をフルに発揮すれば、かなりのことができる。では、社員をそうし向けるにはどうすればいいか。組織のために働くのではなく、自分のために働く。これが個人を成長させる近道だ。そして、成長し続ける個人が集まる組織は強い。それなら、その制約は少ないほうがいい。社員が可能な限り自由に働ける制度と風土づくりをめざした。
まったく書評の体を成していませんが、とにかく良い本でした。

2016年12月17日
レーザーポインター新調!!
〜ふと想い出した父のこと〜
商売道具のレーザーポインター(写真、右から2番目)。「パワーポイントでのプレゼンテーションには欠かせない」ということで、10数年前に買ったものなのですが、ここのところ調子が悪くって…。
とはいえ、当時数万円した記憶があり、騙し騙し使っていたのですが、ついに限界ということで、アマゾン検索。「キヤノン製が、なんと5,715円!」ということで、即発注、中一日で本日届きました(通販って、ほんとに便利)。
せっかくなので、時代の変遷を確認しようと歴代のポインターを並べてみました。いちばん右が今回購入したキヤノンPR500-RC、早々試してみたけれど軽量コンパクトで使いやすい。で、右から2番目が長年愛用していたコクヨ製、10年前はコレを使うと結構注目された記憶があります(当時は、話し手以外に、PC操作要員がいる場合が多かった)。右から3番目はコクヨ製のレーザーポインター、ポインター機能のみなので、パワーポイントでのプレゼンテーションが主流になってからは、ほとんど使っていません(新品同様?)。
で、左端が、指示棒。クルマのアンテナみたくスライドさせるとグーッと伸びるやつです。先っぽのキャップを外すとボールペンとして使えたり、胴体に10㎝のスケールが刻んであったり、小技が効いています。今も、レーザーポインターの電池が無くなった時の緊急用に、常に鞄の中に忍ばせています。
ただ、これは僕が購入したものではなく、父の持ち物。父は技術者で、僕が10代の頃、単身赴任で“日本電信電話公社 鈴鹿電気通信学園”の教官をやっていたことがあります(たぶん、当時、使っていたモノ…)。父が何を教えていたのかは知る由もありませんが、週末、家に帰って設計図の様な書類を見ながら勉強するのを見て、「わざわざ鈴鹿から帰ってきてまで勉強することないのに?!」などと思ったことをうっすら覚えています。
せっかくなのでと、今回、この学園のことをWeb検索してみると「技術系中堅育成の総本山。日本全国、時にはアジア・アフリカからも研修に来ていた。民営化、後に3社分割されて役目が終った」との記述がありました。僕は、父親のことを何もわかっていなかったのかもしれません。
こんなことを想い出すのは、「年の瀬だから…?」「僕が歳を取ったからかな〜?」なんて考えていたら、大切なコトを想い出しました。忙しさにかまけてすっかり忘れていましたが、17年前の12月13日(今週の火曜日…汗)は、父の命日でした。「ここまでなんとかやってこられたのも、鞄の中に忍ばせていた父の指示棒のおかげだったのかも…」などとチョッピリ感傷的になってしまった年の瀬の午後でした。
年末までに、実家に線香あげに行かなくては…。

商売道具のレーザーポインター(写真、右から2番目)。「パワーポイントでのプレゼンテーションには欠かせない」ということで、10数年前に買ったものなのですが、ここのところ調子が悪くって…。
とはいえ、当時数万円した記憶があり、騙し騙し使っていたのですが、ついに限界ということで、アマゾン検索。「キヤノン製が、なんと5,715円!」ということで、即発注、中一日で本日届きました(通販って、ほんとに便利)。
せっかくなので、時代の変遷を確認しようと歴代のポインターを並べてみました。いちばん右が今回購入したキヤノンPR500-RC、早々試してみたけれど軽量コンパクトで使いやすい。で、右から2番目が長年愛用していたコクヨ製、10年前はコレを使うと結構注目された記憶があります(当時は、話し手以外に、PC操作要員がいる場合が多かった)。右から3番目はコクヨ製のレーザーポインター、ポインター機能のみなので、パワーポイントでのプレゼンテーションが主流になってからは、ほとんど使っていません(新品同様?)。
で、左端が、指示棒。クルマのアンテナみたくスライドさせるとグーッと伸びるやつです。先っぽのキャップを外すとボールペンとして使えたり、胴体に10㎝のスケールが刻んであったり、小技が効いています。今も、レーザーポインターの電池が無くなった時の緊急用に、常に鞄の中に忍ばせています。
ただ、これは僕が購入したものではなく、父の持ち物。父は技術者で、僕が10代の頃、単身赴任で“日本電信電話公社 鈴鹿電気通信学園”の教官をやっていたことがあります(たぶん、当時、使っていたモノ…)。父が何を教えていたのかは知る由もありませんが、週末、家に帰って設計図の様な書類を見ながら勉強するのを見て、「わざわざ鈴鹿から帰ってきてまで勉強することないのに?!」などと思ったことをうっすら覚えています。
せっかくなのでと、今回、この学園のことをWeb検索してみると「技術系中堅育成の総本山。日本全国、時にはアジア・アフリカからも研修に来ていた。民営化、後に3社分割されて役目が終った」との記述がありました。僕は、父親のことを何もわかっていなかったのかもしれません。
こんなことを想い出すのは、「年の瀬だから…?」「僕が歳を取ったからかな〜?」なんて考えていたら、大切なコトを想い出しました。忙しさにかまけてすっかり忘れていましたが、17年前の12月13日(今週の火曜日…汗)は、父の命日でした。「ここまでなんとかやってこられたのも、鞄の中に忍ばせていた父の指示棒のおかげだったのかも…」などとチョッピリ感傷的になってしまった年の瀬の午後でした。
年末までに、実家に線香あげに行かなくては…。
2016年08月11日
ひさびさのブログは、趣味のお話し…?!
日本人の健康志向の高まりか、はたまた自転車アニメの影響か、自転車が人気だ。かくいう私も、ロードバイクをはじめて10年ほどになる。
現在の愛車は50歳の誕生日に自分自身に贈ったイタリア製のクロモリ(鉄)バイク。組んで1年くらいはホイールやサドルを替えたりしていたのだが、その後は自分の好みに仕上がったこともあって、ここ何年かは、消耗品の交換程度しかしてこなかった。
特別、走りを意識しているわけでもないし、思い立った時に気の向くままにふらりと走りにいくことができるのが自転車の魅力だと思っている私にとっては、それで十分だったから…。
そんな中、今回「もっと楽に坂道を登りたい」と思い、8年ぶりにスプロケット(後輪のギア)を交換した。一番軽いギアの歯数が25枚から27枚になったので、計算上で言えば、いままでよりも楽に登坂ができるハズだ。
私がそんな気持ちになったのは、最近、仲良くさせていただいている自転車仲間の影響が大きい…?!体力に自信のない私が「自転車って、みんなでも楽しめるものだ!」と再認識した際に、仲間についていくためには、道具に頼るしかないので…(笑
50代も後半を迎え、仕事も年齢もさまざまな仲間と知り合えたことが貴重だと思うし、これからも“Strength of Weak Ties(弱い結びつきの強さ)”を大切にしていきたいと思う。
何はともあれ、「スプロケット交換の効果がどの程度のモノなのか?!」早く試してみたいな〜!!

現在の愛車は50歳の誕生日に自分自身に贈ったイタリア製のクロモリ(鉄)バイク。組んで1年くらいはホイールやサドルを替えたりしていたのだが、その後は自分の好みに仕上がったこともあって、ここ何年かは、消耗品の交換程度しかしてこなかった。
特別、走りを意識しているわけでもないし、思い立った時に気の向くままにふらりと走りにいくことができるのが自転車の魅力だと思っている私にとっては、それで十分だったから…。
そんな中、今回「もっと楽に坂道を登りたい」と思い、8年ぶりにスプロケット(後輪のギア)を交換した。一番軽いギアの歯数が25枚から27枚になったので、計算上で言えば、いままでよりも楽に登坂ができるハズだ。
私がそんな気持ちになったのは、最近、仲良くさせていただいている自転車仲間の影響が大きい…?!体力に自信のない私が「自転車って、みんなでも楽しめるものだ!」と再認識した際に、仲間についていくためには、道具に頼るしかないので…(笑
50代も後半を迎え、仕事も年齢もさまざまな仲間と知り合えたことが貴重だと思うし、これからも“Strength of Weak Ties(弱い結びつきの強さ)”を大切にしていきたいと思う。
何はともあれ、「スプロケット交換の効果がどの程度のモノなのか?!」早く試してみたいな〜!!
2015年12月25日
専業主婦になりたい女たち
〜白河 桃子 著〜
ちょっと古い話になるけれど、2009年の内閣府発表の“家庭観”調査によれば「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」と答えた女性は、年代別で60代がトップ(40.2%)、次いで20代が第2位(36.3%)だったことは、私にとって衝撃だった。
そんなこともあり、学生と話をする際は、意識して学生たちの“家庭観”を聴く様にしてきた。実際に話を聴く中、「専業主婦志向の強い女子学生って多いかも…」「パートナーには、家にいて欲しいと思っている男子学生も少なくない…」と感じていたこともあり、本書を手にとってみたというわけ。
で、本書の内容だが、『専業主婦という安定ほど危険なものはない-!?』という帯に記された挑発的なコピーの根拠を、若い女性や専業主婦・独身男性等、様々な人へのインタビューや座談会の内容をモチーフに説明している。
セレブ妻(?)のインタビューでは、人も羨む様な専業主婦生活を送るには、「夫の所得が高ければOK」というのではなく、「夫のやさしさと理解が必要条件となること」が説明されている。
また、20代独身男性の座談会では、参加者の多くが配偶者の専業主婦生活を望んでいるにも関わらず、「それに必要な所得を明示されるや、自身の考えに現実味が無い」と気づかされる場面などが記されている。
さらには、離婚や夫のリストラ、給与カットといった結婚後のリスクに直面した際“専業主婦である女性が復職すること”が非常に難しいことを具体的な事例を示して説明し、「専業主婦は貧困女性を量産するシステムである」と結論付けている。
労働市場の現場で、具体的な事例に接してきた私としては、「確かにそうだよな~」と頷きつつ、「若い学生等に気付きを与えるには良い本だよな~」という評価を下させていただいた。
そんな中、最近、趣味化している他の読者のレビューを見ると…。
「兼業主婦や兼業家庭のリスクもある。どちらのリスクが大きいと考えるかは各個人次第」「統計データが足りず、リスクの定量評価がされていない」等、著者に対しての批判的なコメントが少なくないことも興味深い。
この話をややこしくしてしまう理由は、「母は専業主婦で、私を愛情いっぱいに育ててくれた。私たちも子供には同じようにしてあげたい」等、自分の両親や祖父母世代の「良妻賢母」像を家族のロールモデルとしている人たちが少なくないことにあるんじゃなかろうか。
産業構造や社会環境の変化などにより、好むと好まざるに関わらず“専業主婦は間違いなく減っていく”はず。世の中の変化を認識しつつ、将来を俯瞰する力をつけることが大切だと感じさせてくれた一冊だった。

ちょっと古い話になるけれど、2009年の内閣府発表の“家庭観”調査によれば「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」と答えた女性は、年代別で60代がトップ(40.2%)、次いで20代が第2位(36.3%)だったことは、私にとって衝撃だった。
そんなこともあり、学生と話をする際は、意識して学生たちの“家庭観”を聴く様にしてきた。実際に話を聴く中、「専業主婦志向の強い女子学生って多いかも…」「パートナーには、家にいて欲しいと思っている男子学生も少なくない…」と感じていたこともあり、本書を手にとってみたというわけ。
で、本書の内容だが、『専業主婦という安定ほど危険なものはない-!?』という帯に記された挑発的なコピーの根拠を、若い女性や専業主婦・独身男性等、様々な人へのインタビューや座談会の内容をモチーフに説明している。
セレブ妻(?)のインタビューでは、人も羨む様な専業主婦生活を送るには、「夫の所得が高ければOK」というのではなく、「夫のやさしさと理解が必要条件となること」が説明されている。
また、20代独身男性の座談会では、参加者の多くが配偶者の専業主婦生活を望んでいるにも関わらず、「それに必要な所得を明示されるや、自身の考えに現実味が無い」と気づかされる場面などが記されている。
さらには、離婚や夫のリストラ、給与カットといった結婚後のリスクに直面した際“専業主婦である女性が復職すること”が非常に難しいことを具体的な事例を示して説明し、「専業主婦は貧困女性を量産するシステムである」と結論付けている。
労働市場の現場で、具体的な事例に接してきた私としては、「確かにそうだよな~」と頷きつつ、「若い学生等に気付きを与えるには良い本だよな~」という評価を下させていただいた。
そんな中、最近、趣味化している他の読者のレビューを見ると…。
「兼業主婦や兼業家庭のリスクもある。どちらのリスクが大きいと考えるかは各個人次第」「統計データが足りず、リスクの定量評価がされていない」等、著者に対しての批判的なコメントが少なくないことも興味深い。
この話をややこしくしてしまう理由は、「母は専業主婦で、私を愛情いっぱいに育ててくれた。私たちも子供には同じようにしてあげたい」等、自分の両親や祖父母世代の「良妻賢母」像を家族のロールモデルとしている人たちが少なくないことにあるんじゃなかろうか。
産業構造や社会環境の変化などにより、好むと好まざるに関わらず“専業主婦は間違いなく減っていく”はず。世の中の変化を認識しつつ、将来を俯瞰する力をつけることが大切だと感じさせてくれた一冊だった。

2015年12月06日
Your time is limited
本日、父親の十七回忌、祖母の十三回忌の法要を行いました。
法要の前に、住職から「今日一日が満足できる一日だったかを振り返り、悔いの無い人生を送ることが大切」というお話しがあり、お経をあげていただいている間、父が亡くなった当時のことを思い起こしていました。
父は、私が中学にあがった頃から社会人になるまで、単身赴任のサラリーマン生活を続けました。その後、私は結婚して所帯を持ったこともあり、父との会話の機会が少なかったことを、今でもとても残念に思っています。
とはいえ、父の死が私のその後の人生を大きく変えたのも事実です。
父は私が41歳の時に、68歳で肝硬変を患って亡くなりました。当時、私はとある人材ビジネス会社の取締役として、再就職支援事業のコンサルティングと離職者に対するカウンセリングに従事していました。上場企業のリストラのコンサルティングをする中、『ひとつの会社に入ったら一生安泰という時代ではない』ということを肌で感じ、次世代(娘や息子の世代)の若者たちに「こんなはずじゃなかった」と言わせてはいけないと考えていました。
そんな時期の父の死でした。実は、父の父(祖父)も同じ肝硬変を患って亡くなっています。同じ血を継いでいる私は、「68歳—41歳=27年、あと27年か…」と計算したのを覚えています。私にとって、死がグッと身近になった瞬間でした。
“人生は一度きりであること、人間には寿命があること”を前提にこれからどう生きていこうかを考えた上で、2年程の準備の後、はじめたのがキャリア・クリエイトです。起業した際に創ったMissionは、『わたしたちは“経営へのコンサルティング”と“社員のキャリア開発支援”を両輪に、“企業と個人のWin-Win”をサポートします』で、現在も名刺の裏にはその言葉を綴っています。
私の人生に於いて仕事は重要な位置を占めていますし、今後もそれは変わらないとは思いますが、最も大切にすべきは“人生のタイムマネジメント”だとも思っています。そんな中、周囲を見渡してみると、「日々の忙しさにかまけて、自分のキャリアビジョンを考えることを蔑ろにしていないか?」と感じさせる人は少なくありません。
ということで、受け売りで恐縮ですが、英語の苦手な私にも解かるスティーブ・ジョブズの名言を…
Your time is limited,so don’t waste it living someone else’s life.
(あなたの時間は限られています。だから、本意でない人生を生きて時間を無駄にしないでください)
うわっ、今、気づいてしまいました。計算上では、あと11年じゃないですか…(汗

法要の前に、住職から「今日一日が満足できる一日だったかを振り返り、悔いの無い人生を送ることが大切」というお話しがあり、お経をあげていただいている間、父が亡くなった当時のことを思い起こしていました。
父は、私が中学にあがった頃から社会人になるまで、単身赴任のサラリーマン生活を続けました。その後、私は結婚して所帯を持ったこともあり、父との会話の機会が少なかったことを、今でもとても残念に思っています。
とはいえ、父の死が私のその後の人生を大きく変えたのも事実です。
父は私が41歳の時に、68歳で肝硬変を患って亡くなりました。当時、私はとある人材ビジネス会社の取締役として、再就職支援事業のコンサルティングと離職者に対するカウンセリングに従事していました。上場企業のリストラのコンサルティングをする中、『ひとつの会社に入ったら一生安泰という時代ではない』ということを肌で感じ、次世代(娘や息子の世代)の若者たちに「こんなはずじゃなかった」と言わせてはいけないと考えていました。
そんな時期の父の死でした。実は、父の父(祖父)も同じ肝硬変を患って亡くなっています。同じ血を継いでいる私は、「68歳—41歳=27年、あと27年か…」と計算したのを覚えています。私にとって、死がグッと身近になった瞬間でした。
“人生は一度きりであること、人間には寿命があること”を前提にこれからどう生きていこうかを考えた上で、2年程の準備の後、はじめたのがキャリア・クリエイトです。起業した際に創ったMissionは、『わたしたちは“経営へのコンサルティング”と“社員のキャリア開発支援”を両輪に、“企業と個人のWin-Win”をサポートします』で、現在も名刺の裏にはその言葉を綴っています。
私の人生に於いて仕事は重要な位置を占めていますし、今後もそれは変わらないとは思いますが、最も大切にすべきは“人生のタイムマネジメント”だとも思っています。そんな中、周囲を見渡してみると、「日々の忙しさにかまけて、自分のキャリアビジョンを考えることを蔑ろにしていないか?」と感じさせる人は少なくありません。
ということで、受け売りで恐縮ですが、英語の苦手な私にも解かるスティーブ・ジョブズの名言を…
Your time is limited,so don’t waste it living someone else’s life.
(あなたの時間は限られています。だから、本意でない人生を生きて時間を無駄にしないでください)
うわっ、今、気づいてしまいました。計算上では、あと11年じゃないですか…(汗

2015年07月28日
若手社員 職場定着セミナー 終了
~自身のキャリアビジョンを描いてみよう!~
7月下旬に沼津・浜松・静岡で実施した若年者向け『職場定着セミナー』が終了したので、備忘録を…。
このセミナー、若者の早期離職が社会問題化している中、とある経済団体のご依頼を受け、会員企業の入社3年以内の若手社員の職場定着を目的に実施しました。内容は、毎年少しずつ更新しているけれど、最初にご依頼いただいてから、かれこれ7年くらいになるでしょうか…。
タイトルに『職場定着』と銘打っているし、実際に会員各社にとって社員の早期離職は、労働力不足につながる痛手なわけだけど、私自身はあくまで参加者サイドに立ち「辞めなきゃいいってわけじゃないでしょう?!意欲を持って仕事に取り組むのが大事!!」というスタンスでメニューを創っとります。
セミナーは2部構成。第1部は「どんな職業人生を送りたい?」と称し、自身の会社しか知らない若手社員に「他社の同期はどんな仕事をしていて、日々、どんなことを思っているのか?」「昨今の日本の労働市場はどうなっているのか?」等を認識してもらうことに時間を割きました。
第2部は「自身のキャリアビジョンを描いてみよう!」と称し、第1部で知った環境変化を認識した上で、キャリアビジョンを描くことの意味とビジョン作成時の考え方を知ってもらうことに時間を割きました。時間の関係もあるのだけれど、“ビジョンを描く方法”よりも、“ビジョンを描くこと”の大切さを認識してもらうことが重要だと考えたメニュー運営を意識しました。
グループワーク中心のセミナーを心がけていたこともあり、参加者からは「“居酒屋で同期が愚痴、言い合う”みたいになっちゃってるんですが、いいんですか?」などという質問も出ましたが、それこそ「我が意を得たり!」で、「いい~んです!」。多くの若者は、自分の会社しか知らないので、「自分ばかりが辛い目に合っているんじゃないか?」「もっと自分にあった会社があるんじゃないか?」と悶々としていることが多い…。他社で若い社員がどんな仕事をどんな気持ちで続けているかを知るのは、とっても重要なことなのです。でないと、結果的に先の見通しも立てないまま早期離職してしまう。
冒頭、早期離職が会社の痛手であることはコメントしたけれど、私はそれ以上に“早期離職した若者のその後”が心配です。人材派遣や職業紹介等の人材ビジネスに携わる中、離職後に苦労する若者たちを見てきた私にとって、離職ばかりをクローズアップするマスメディアの情報発信には、少なからず違和感があるのです。
ということで、3時間半のセミナー終了後の参加者のアンケート内容を見ると…。「今の会社、すぐにでも辞めたいと思っていたけど、もう少し続けてみようと思った」「仕事のことで悩んでいたけれど、ちょっと違う角度から考えてみようと思った」「辞めさせないためのセミナーだと思っていたけど、そうじゃなかったみたい。楽しかった」「自分のキャリアを自分で創っていくって大切なんだと感じた」等々、「私の伝えたかったコト、伝わったかな!?」と手ごたえを感じられるアンケート結果となりました。

7月下旬に沼津・浜松・静岡で実施した若年者向け『職場定着セミナー』が終了したので、備忘録を…。
このセミナー、若者の早期離職が社会問題化している中、とある経済団体のご依頼を受け、会員企業の入社3年以内の若手社員の職場定着を目的に実施しました。内容は、毎年少しずつ更新しているけれど、最初にご依頼いただいてから、かれこれ7年くらいになるでしょうか…。
タイトルに『職場定着』と銘打っているし、実際に会員各社にとって社員の早期離職は、労働力不足につながる痛手なわけだけど、私自身はあくまで参加者サイドに立ち「辞めなきゃいいってわけじゃないでしょう?!意欲を持って仕事に取り組むのが大事!!」というスタンスでメニューを創っとります。
セミナーは2部構成。第1部は「どんな職業人生を送りたい?」と称し、自身の会社しか知らない若手社員に「他社の同期はどんな仕事をしていて、日々、どんなことを思っているのか?」「昨今の日本の労働市場はどうなっているのか?」等を認識してもらうことに時間を割きました。
第2部は「自身のキャリアビジョンを描いてみよう!」と称し、第1部で知った環境変化を認識した上で、キャリアビジョンを描くことの意味とビジョン作成時の考え方を知ってもらうことに時間を割きました。時間の関係もあるのだけれど、“ビジョンを描く方法”よりも、“ビジョンを描くこと”の大切さを認識してもらうことが重要だと考えたメニュー運営を意識しました。
グループワーク中心のセミナーを心がけていたこともあり、参加者からは「“居酒屋で同期が愚痴、言い合う”みたいになっちゃってるんですが、いいんですか?」などという質問も出ましたが、それこそ「我が意を得たり!」で、「いい~んです!」。多くの若者は、自分の会社しか知らないので、「自分ばかりが辛い目に合っているんじゃないか?」「もっと自分にあった会社があるんじゃないか?」と悶々としていることが多い…。他社で若い社員がどんな仕事をどんな気持ちで続けているかを知るのは、とっても重要なことなのです。でないと、結果的に先の見通しも立てないまま早期離職してしまう。
冒頭、早期離職が会社の痛手であることはコメントしたけれど、私はそれ以上に“早期離職した若者のその後”が心配です。人材派遣や職業紹介等の人材ビジネスに携わる中、離職後に苦労する若者たちを見てきた私にとって、離職ばかりをクローズアップするマスメディアの情報発信には、少なからず違和感があるのです。
ということで、3時間半のセミナー終了後の参加者のアンケート内容を見ると…。「今の会社、すぐにでも辞めたいと思っていたけど、もう少し続けてみようと思った」「仕事のことで悩んでいたけれど、ちょっと違う角度から考えてみようと思った」「辞めさせないためのセミナーだと思っていたけど、そうじゃなかったみたい。楽しかった」「自分のキャリアを自分で創っていくって大切なんだと感じた」等々、「私の伝えたかったコト、伝わったかな!?」と手ごたえを感じられるアンケート結果となりました。
2015年06月18日
今秋、就活をはじめる高校生とお話ししました
~就職に対する心構え~
先日、某女子高校の先生より、秋口から就職活動を始める高校生に「“就職に対する心構え”について話をして欲しい」旨のご依頼を受けました。
こちらの高校からは、毎年この時期に同様のご依頼を受け、社会に出ることの不安を取り除くべくメニューを考えお話しさせていただいているのですが…。今年は、例年に加え「学生と社会人の違いを考えてもらうためのワークを入れたい!」とメニューを考えました。
「なんでそんなことを考えたのか?」と言いますと…。とある大学のグループ討論の講座で「学生と社会人の違いをあげよ!」というテーマで討論をしてもらったところ、大学生たちが出した答えに衝撃を受けたからです。
大学生たちがあげた違いは、「1.社会人は失敗が許されない」「2.社会人は縦社会をわきまえている」「3.社会人は主体的に行動する」等々…。私は「違いをあげて…」と言っているのに、出てきた答えは「全て主語が社会人で、且つ社会人ってすごいじゃん?!」というもの。
私自身、「失敗しない社員は、チャレンジしない社員だ!」と思っているし、「縦社会をわきまえた行動しかしないんだったら、中途で経験者を採った方がいいじゃん!」「私は、主体性のない社会人をたくさん知っているよ!」等々、突っ込みどころ満載の答えに、唖然としちゃったわけであります。
で、講習当日。女子高校生たちに同じテーマで社会人になることをイメージしてもらったところ、「年齢や性別、様々な人たちと出会える」「お酒が飲める(←「お酒は20歳になんなきゃ飲めないよ!」とツッコミを入れましたが…)」等々、社会に出ることに前向きなコメントが多く、ウキウキしてしまった次第です。
同じ現象でも、とらえ方により行動の中身も結果も大きく変わります。「前向きな気持ちを持つことって大切だよな~」と高校生から教えられました。

先日、某女子高校の先生より、秋口から就職活動を始める高校生に「“就職に対する心構え”について話をして欲しい」旨のご依頼を受けました。
こちらの高校からは、毎年この時期に同様のご依頼を受け、社会に出ることの不安を取り除くべくメニューを考えお話しさせていただいているのですが…。今年は、例年に加え「学生と社会人の違いを考えてもらうためのワークを入れたい!」とメニューを考えました。
「なんでそんなことを考えたのか?」と言いますと…。とある大学のグループ討論の講座で「学生と社会人の違いをあげよ!」というテーマで討論をしてもらったところ、大学生たちが出した答えに衝撃を受けたからです。
大学生たちがあげた違いは、「1.社会人は失敗が許されない」「2.社会人は縦社会をわきまえている」「3.社会人は主体的に行動する」等々…。私は「違いをあげて…」と言っているのに、出てきた答えは「全て主語が社会人で、且つ社会人ってすごいじゃん?!」というもの。
私自身、「失敗しない社員は、チャレンジしない社員だ!」と思っているし、「縦社会をわきまえた行動しかしないんだったら、中途で経験者を採った方がいいじゃん!」「私は、主体性のない社会人をたくさん知っているよ!」等々、突っ込みどころ満載の答えに、唖然としちゃったわけであります。
で、講習当日。女子高校生たちに同じテーマで社会人になることをイメージしてもらったところ、「年齢や性別、様々な人たちと出会える」「お酒が飲める(←「お酒は20歳になんなきゃ飲めないよ!」とツッコミを入れましたが…)」等々、社会に出ることに前向きなコメントが多く、ウキウキしてしまった次第です。
同じ現象でも、とらえ方により行動の中身も結果も大きく変わります。「前向きな気持ちを持つことって大切だよな~」と高校生から教えられました。

2015年06月16日
「こんなハズじゃなかった!?」とならないための仕事研究
~OB・OGの話に耳を傾けてみよう~
学生の就職相談や、企業の人事担当として学生のエントリーシートを読んだり面接したりする中、「この学生、会社(←しかも知名度や世間体が基準)に入ることが目的になっていないか?」「安心して定年まで働ける会社や組織を探しているんだろうな〜?」等々、「そもそもそもそもスタート時点でボタンの掛け違いがあるんじゃないの?」と感じることは少なくありません。
※ここまでは、前回のブログと同じ…(笑
そんな中、お世話になっている大学の先生から「大学のOB・OGに、現在の仕事内容に触れながら学生時代を振り返り、自身の職業選択について語ってもらうってどうだろう?!」とご相談をいただきました。“目標とした会社に入ったにも関わらず「こんなハズじゃなかった?!」と離職してしまったり、仕事のグチばかり言っている人”“なんとなく入った会社だったけれど充実した職業人生を送っている人”等、いろんな人を見ている私は「それ、やりましょうよ…!」。ということで、コーディネーターを務めさせていただくことになりました。
OB・OGについては、「入社後5~10年程度が経過し、会社の全体像が見えてきている人」「業種・職種は様々に…」「出身学部や性別は出来るだけ様々に…」等の条件で人選していただきました。
で、後輩のために一肌脱いでくれたのは、“研究や開発の仕事に就く友人が多い中、鉄道関係の会社に入った理系学部出身のM君”“本当は、ファッション雑誌を創りたかったのに広告営業を経て人材コンサルタントをしているAさん”“就活時は大手志向が強かったのに大手の内定が取れず、先輩の誘いに運命を感じメディア開発の会社に入ったN君”の3名のOB・OGとなりました。
M君は愛知県出身。都市と田舎のバランスがよく、雰囲気や気候も気に入った静岡県での就活を優先したとのこと。また、当初は学部の友人と同様に食品メーカーの開発職等をターゲットに活動していたものの途中から路線変更。業種の枠を決めない就活に切り替え、現在の会社に入社しました。当初は漠然と「グループ内の介護事業を希望していたが、現在までに4つの部署異動を経験するも、未だ介護事業への配属にはなっていないとのことですが、どの部署もオモシロかったとのことでした。静岡が好きという割に静岡のことを知らない学生は多い「掘り下げていくとオモシロいよ!」とのアドバイスが印象的でした。
Aさんが会社を決めた理由は、「ここで働きたいと思える会社かどうか?」の一点。自身の直感を信じた会社選びだったようです。「営業は大変だと覚悟していたけれど、ここまで大変だとは…!?」とのコメントがあったので、「そんなに大変だったのに何故、辞めなかったの?」と質問すると、間髪入れずに「いい仲間、いい上司に恵まれたから…!」と答えてくれました。現在は、異動になった職業紹介の部署で人材コンサルタントの仕事をしていらっしゃいます。
先輩の誘いに運命を感じ現在の会社に入ったN君の配属先は住宅関連メディアの営業職。営業では、「お客様に喜んでいただきたい!」と好成績を上げるための努力を続けてきたとのこと。昨年、社内のFA制度を利用して管理部門への異動を宣言、念願かなって希望部署への異動を果たしました。「現在は、次なる目標(←将来は経営者になりたいって仰ってました)に向けて張り切って仕事をしてます!」とキッパリ語ってくれました。
その後、3人のOB・OGを囲んでの質問タイム。少し歳は離れているものの、母校の先輩ということもあってか、学生たちからは“就活での苦労話”や“社会人になることの意味”等々、様々な質問が出ていました。
「就活は学生にとって、人生初とも言える大きな転機!!」、なはずなのに多くの学生は入学試験の延長線上で「どの会社に入るのか?」ばかりに目が行ってしまう。選択のポイントは、“周囲に自慢できる”“知名度が高い”“地元を離れなくていい”等々、首を傾げてしまう理由も…。“生き方を選択する機会”と捉える学生にはめったに出会えません。
今回お手伝いいただいたOB・OGだって、就活時には“生き方を選択する機会”なんて考えて現在の仕事を決めたんじゃなく、縁だったり、成り行きだったりで就職先を決めたのも事実だけど…。
「後から振り返ってみると、人生の大きな転機だったんだ!?」と気づくんですよね。ということで、今回の講座が学生たちの“気づき”のきっかけになったのであれば幸いです。

学生の就職相談や、企業の人事担当として学生のエントリーシートを読んだり面接したりする中、「この学生、会社(←しかも知名度や世間体が基準)に入ることが目的になっていないか?」「安心して定年まで働ける会社や組織を探しているんだろうな〜?」等々、「そもそもそもそもスタート時点でボタンの掛け違いがあるんじゃないの?」と感じることは少なくありません。
※ここまでは、前回のブログと同じ…(笑
そんな中、お世話になっている大学の先生から「大学のOB・OGに、現在の仕事内容に触れながら学生時代を振り返り、自身の職業選択について語ってもらうってどうだろう?!」とご相談をいただきました。“目標とした会社に入ったにも関わらず「こんなハズじゃなかった?!」と離職してしまったり、仕事のグチばかり言っている人”“なんとなく入った会社だったけれど充実した職業人生を送っている人”等、いろんな人を見ている私は「それ、やりましょうよ…!」。ということで、コーディネーターを務めさせていただくことになりました。
OB・OGについては、「入社後5~10年程度が経過し、会社の全体像が見えてきている人」「業種・職種は様々に…」「出身学部や性別は出来るだけ様々に…」等の条件で人選していただきました。
で、後輩のために一肌脱いでくれたのは、“研究や開発の仕事に就く友人が多い中、鉄道関係の会社に入った理系学部出身のM君”“本当は、ファッション雑誌を創りたかったのに広告営業を経て人材コンサルタントをしているAさん”“就活時は大手志向が強かったのに大手の内定が取れず、先輩の誘いに運命を感じメディア開発の会社に入ったN君”の3名のOB・OGとなりました。
M君は愛知県出身。都市と田舎のバランスがよく、雰囲気や気候も気に入った静岡県での就活を優先したとのこと。また、当初は学部の友人と同様に食品メーカーの開発職等をターゲットに活動していたものの途中から路線変更。業種の枠を決めない就活に切り替え、現在の会社に入社しました。当初は漠然と「グループ内の介護事業を希望していたが、現在までに4つの部署異動を経験するも、未だ介護事業への配属にはなっていないとのことですが、どの部署もオモシロかったとのことでした。静岡が好きという割に静岡のことを知らない学生は多い「掘り下げていくとオモシロいよ!」とのアドバイスが印象的でした。
Aさんが会社を決めた理由は、「ここで働きたいと思える会社かどうか?」の一点。自身の直感を信じた会社選びだったようです。「営業は大変だと覚悟していたけれど、ここまで大変だとは…!?」とのコメントがあったので、「そんなに大変だったのに何故、辞めなかったの?」と質問すると、間髪入れずに「いい仲間、いい上司に恵まれたから…!」と答えてくれました。現在は、異動になった職業紹介の部署で人材コンサルタントの仕事をしていらっしゃいます。
先輩の誘いに運命を感じ現在の会社に入ったN君の配属先は住宅関連メディアの営業職。営業では、「お客様に喜んでいただきたい!」と好成績を上げるための努力を続けてきたとのこと。昨年、社内のFA制度を利用して管理部門への異動を宣言、念願かなって希望部署への異動を果たしました。「現在は、次なる目標(←将来は経営者になりたいって仰ってました)に向けて張り切って仕事をしてます!」とキッパリ語ってくれました。
その後、3人のOB・OGを囲んでの質問タイム。少し歳は離れているものの、母校の先輩ということもあってか、学生たちからは“就活での苦労話”や“社会人になることの意味”等々、様々な質問が出ていました。
「就活は学生にとって、人生初とも言える大きな転機!!」、なはずなのに多くの学生は入学試験の延長線上で「どの会社に入るのか?」ばかりに目が行ってしまう。選択のポイントは、“周囲に自慢できる”“知名度が高い”“地元を離れなくていい”等々、首を傾げてしまう理由も…。“生き方を選択する機会”と捉える学生にはめったに出会えません。
今回お手伝いいただいたOB・OGだって、就活時には“生き方を選択する機会”なんて考えて現在の仕事を決めたんじゃなく、縁だったり、成り行きだったりで就職先を決めたのも事実だけど…。
「後から振り返ってみると、人生の大きな転機だったんだ!?」と気づくんですよね。ということで、今回の講座が学生たちの“気づき”のきっかけになったのであれば幸いです。

2015年06月14日
就活をじっくり考えるセミナー
~就活本番前にやるべきコトは?~
学生の就職相談や、企業の人事担当として学生のエントリーシートを読んだり面接したりする中、「この学生、会社(←しかも知名度や世間体が基準)に入ることが目的になっていないか?」「安心して定年まで働ける会社や組織を探しているんだろうな〜?」等々、「そもそもスタート時点でボタンの掛け違いがあるんじゃないの?」と感じることは少なくありません。
そんな中、とある大学のキャリア支援室から、「就活前の3年生・M1生に対し、就活のコトをちゃんと考えさせるセミナーをお願いしたい」とのご依頼を受けました。セミナーのタイトルも「“就活をじっくり考えるセミナー”でどうでしょう?」との提案を受け、張り切ってメニューを作成し、セミナーの当日を迎えた次第です。
セミナーは、“働く目的”や“会社とのつきあい方”について考えてもらう『心構え編』と“業界や会社に対する知識”や“企業の採用時にどこを見ているか”等の『知識・情報編』の2つのフェイズに分けて実施。講師が一方的に教えるというのではなく、「いろいろな問いかけを通して、これから社会に出て働くことを考えてもらうこと」を意識したメニューをつくり、実施しました。
終了後のアンケートでは、「就活について勘違いしていた様だ」「焦って大切なモノを見失っていたような気がする」等々、自由記載欄にうれしいコメントをたくさんもらえました(←こういうの、素直にうれしいですネ…笑)。
学生達には、メディアや親や学校や先輩たちから多くの情報や雑音(?)が入って来るわけで…。その中から、「何が正しい情報なのかを自分の頭で考え判断する術を見つけて欲しい!」と、私自身があらためて感じさせられる“就活をじっくり考えるセミナー”でした。

学生の就職相談や、企業の人事担当として学生のエントリーシートを読んだり面接したりする中、「この学生、会社(←しかも知名度や世間体が基準)に入ることが目的になっていないか?」「安心して定年まで働ける会社や組織を探しているんだろうな〜?」等々、「そもそもスタート時点でボタンの掛け違いがあるんじゃないの?」と感じることは少なくありません。
そんな中、とある大学のキャリア支援室から、「就活前の3年生・M1生に対し、就活のコトをちゃんと考えさせるセミナーをお願いしたい」とのご依頼を受けました。セミナーのタイトルも「“就活をじっくり考えるセミナー”でどうでしょう?」との提案を受け、張り切ってメニューを作成し、セミナーの当日を迎えた次第です。
セミナーは、“働く目的”や“会社とのつきあい方”について考えてもらう『心構え編』と“業界や会社に対する知識”や“企業の採用時にどこを見ているか”等の『知識・情報編』の2つのフェイズに分けて実施。講師が一方的に教えるというのではなく、「いろいろな問いかけを通して、これから社会に出て働くことを考えてもらうこと」を意識したメニューをつくり、実施しました。
終了後のアンケートでは、「就活について勘違いしていた様だ」「焦って大切なモノを見失っていたような気がする」等々、自由記載欄にうれしいコメントをたくさんもらえました(←こういうの、素直にうれしいですネ…笑)。
学生達には、メディアや親や学校や先輩たちから多くの情報や雑音(?)が入って来るわけで…。その中から、「何が正しい情報なのかを自分の頭で考え判断する術を見つけて欲しい!」と、私自身があらためて感じさせられる“就活をじっくり考えるセミナー”でした。

2015年03月07日
ファミマ、ユニー統合交渉
~コンビニ2位に、セブン追う 年内の合意めざす~
国内コンビニエンスストア3位のファミリーマートと、同4位のサークルKサンクスを傘下に持つユニーグループ・ホールディングス(GHD)は経営統合に向けて交渉に入る。実現すればコンビニ事業の売上高は首位のセブン―イレブン・ジャパンに次ぐ2位に、店舗数では肩を並べる。両社のコンビニ事業は不振が続いており、規模の拡大によって競争力の確保を目指す。(中略)
ファミマとサークルKサンクスの13年度の全加盟店ベースの売上高は合計で2兆8100億円と、1兆9400億円のローソンを抜き、セブンイレブン(3兆7800億円)に次ぐ規模になる。
ファミマとサークルKサンクスの合計の店舗数は14年11月時点で計1万7400店程度と、セブンイレブンの1万7100店を上回る。国内最大規模のコンビニ店舗網を持てば、資材や商品の調達量が増えて仕入れコストが減らせる。その分、共通商品の開発や販売促進などに投資できる。(中略)
国内のコンビニの店舗数は5万店を超え、顧客の奪い合いが激しさを増している。セブンイレブンは独自開発したプライベートブランド(PB=自主企画)の食品などが消費者の支持を得て既存店売上高のプラスが続くが、ローソン以下はマイナス基調だ。(後略)
出所:2015年3月6日 日本経済新聞 朝刊
-----------------------------------------------
私もほぼ毎日お世話になっているコンビニエンスストアにも、大きな変化が起こっているという記事ですね。
私は20年ほど前に、前職のグループ会社で雑誌の取次会社を立ち上げ、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルKの(バイヤーとの)営業窓口を担当していた。そんなこともあり、大手コンビニエンスストアの動向は、興味深く観察している。
当時から、大手コンビニエンスストアの中でもセブンイレブンの競争力は図抜けていて、私は新しい商品が出ると「先ずはセブンイレブンのマネージャーへの商談」を鉄則にしていた。
理由は2つ。1つ目は『セブンイレブンの販売チャンネルが強力だったこと』。2つ目は、他のコンビニチェーンに商談に行くと『セブンイレブンは何部納入するの?』と聞かれるから…。要は、販売チャンネルが強力なのは、単に店舗数が多いとかいうことではなく、商品に対する戦術・目利きが図抜けていたということだ。
今回のファミリーマートとサークルKサンクスの統合は、消費者目線で見ると、セブンイレブンの一強他弱状況から“健全な競争状態を創る”ということで、好ましいことなのだが…。
セブンイレブンコーヒーを愛飲し、nanacoのチャージをしている自分(←完全にセブンイレブンの抱え込み戦略に取り込まれている…汗)を振り返りつつ、規模拡大だけでは、「一強の牙城を切り崩すことは簡単じゃないだろうな~」とも思ってしまう。
ということで、今後のファミリーマートとサークルKサンクスの統合から目が離せません!!

国内コンビニエンスストア3位のファミリーマートと、同4位のサークルKサンクスを傘下に持つユニーグループ・ホールディングス(GHD)は経営統合に向けて交渉に入る。実現すればコンビニ事業の売上高は首位のセブン―イレブン・ジャパンに次ぐ2位に、店舗数では肩を並べる。両社のコンビニ事業は不振が続いており、規模の拡大によって競争力の確保を目指す。(中略)
ファミマとサークルKサンクスの13年度の全加盟店ベースの売上高は合計で2兆8100億円と、1兆9400億円のローソンを抜き、セブンイレブン(3兆7800億円)に次ぐ規模になる。
ファミマとサークルKサンクスの合計の店舗数は14年11月時点で計1万7400店程度と、セブンイレブンの1万7100店を上回る。国内最大規模のコンビニ店舗網を持てば、資材や商品の調達量が増えて仕入れコストが減らせる。その分、共通商品の開発や販売促進などに投資できる。(中略)
国内のコンビニの店舗数は5万店を超え、顧客の奪い合いが激しさを増している。セブンイレブンは独自開発したプライベートブランド(PB=自主企画)の食品などが消費者の支持を得て既存店売上高のプラスが続くが、ローソン以下はマイナス基調だ。(後略)
出所:2015年3月6日 日本経済新聞 朝刊
-----------------------------------------------
私もほぼ毎日お世話になっているコンビニエンスストアにも、大きな変化が起こっているという記事ですね。
私は20年ほど前に、前職のグループ会社で雑誌の取次会社を立ち上げ、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サークルKの(バイヤーとの)営業窓口を担当していた。そんなこともあり、大手コンビニエンスストアの動向は、興味深く観察している。
当時から、大手コンビニエンスストアの中でもセブンイレブンの競争力は図抜けていて、私は新しい商品が出ると「先ずはセブンイレブンのマネージャーへの商談」を鉄則にしていた。
理由は2つ。1つ目は『セブンイレブンの販売チャンネルが強力だったこと』。2つ目は、他のコンビニチェーンに商談に行くと『セブンイレブンは何部納入するの?』と聞かれるから…。要は、販売チャンネルが強力なのは、単に店舗数が多いとかいうことではなく、商品に対する戦術・目利きが図抜けていたということだ。
今回のファミリーマートとサークルKサンクスの統合は、消費者目線で見ると、セブンイレブンの一強他弱状況から“健全な競争状態を創る”ということで、好ましいことなのだが…。
セブンイレブンコーヒーを愛飲し、nanacoのチャージをしている自分(←完全にセブンイレブンの抱え込み戦略に取り込まれている…汗)を振り返りつつ、規模拡大だけでは、「一強の牙城を切り崩すことは簡単じゃないだろうな~」とも思ってしまう。
ということで、今後のファミリーマートとサークルKサンクスの統合から目が離せません!!

2015年03月06日
損保ジャパン日本興亜、仏再保険に1100億円出資
~海外収益を拡大~
損害保険ジャパン日本興亜は再保険世界大手の仏スコールに出資する方針を固めた。2015年度中に1100億円超を投じて同社株15%程度を取得し、持ち分法適用会社にする。損保ジャパン日本興亜としては過去最大の海外出資となる。スコールが強みを持つ生命保険の再保険市場に参入して海外での収益力を高め、人口減で頭打ちが見込まれる国内の損保事業を補う考えだ。(中略)
昨年9月に損害保険ジャパンと日本興亜損害保険が合併して誕生した損保ジャパン日本興亜は、単体では保険料収入で国内最大手になった。ただ、グループでは欧米での積極的なM&A(合併・買収)で海外事業を伸ばした東京海上ホールディングスが上回る。
損保ジャパン日本興亜も海外事業の強化に向け、14年に英中堅損保のキャノピアスを1000億円弱で買収した。今回の大型出資と合わせて、保険市場の規模が大きい欧米で存在感を高める考え。少子高齢化で国内の損保市場の高成長が見込みにくいなか、大手損保による海外M&Aの動きは今後も続きそうだ。
出所:2015年3月6日 日本経済新聞 朝刊
---------------------------------------------------------
損害保険ジャパン日本興亜が、仏スコールに出資だって…。
損保ジャパン日本興亜の前身、損保ジャパンは2002年に安田火災海上保険と日産火災海上保険の合併で出来た会社。私は合併に伴いお仕事をさせていただいたこともあり、かなり気になる記事だ。
昨年9月の合併により保険料収入で損害保険ジャパン日本興亜は国内最大手になったとはいえ、今後の国内市場の成長イメージが持てない中、次なる戦略は必然的に海外事業強化になるんだろう。
昨今、私の知る中小企業でも、海外進出する企業は少なくない。大手企業に限らず、“国内市場だけでは成長イメージが持てない”ということなんだろう。であれば、この記事を他人事として捉えるのではなく自分に置き換えてみることが大切だ。
「仮に、自分の会社が海外進出をするのだとしたら…」「閉塞感があるのに現状のまま何も対策を講じなかったとしたら…」等々をイメージし、自分たちはどう振る舞うのがいいのかを考え、行動に移すことが大切なんじゃないだろうか?
学生のみなさんであれば、『大手金融系だから「安定」「高収入」』(ちなみに2014年2月の日経新聞 就職人気企業ランキングで、損害保険ジャパン・日本興亜は第6位でした)なんて考えるんじゃなく「縁あって損害保険ジャパン・日本興亜に入社したとしたら、その後は…」とか「日本企業の海外進出は、今後、自分にどんな影響があるのか?」等をイメージして、将来を俯瞰することが大切なんだろう。
周囲で起こっている環境変化を自分事と捉えて観察・行動することが大切だ!!

損害保険ジャパン日本興亜は再保険世界大手の仏スコールに出資する方針を固めた。2015年度中に1100億円超を投じて同社株15%程度を取得し、持ち分法適用会社にする。損保ジャパン日本興亜としては過去最大の海外出資となる。スコールが強みを持つ生命保険の再保険市場に参入して海外での収益力を高め、人口減で頭打ちが見込まれる国内の損保事業を補う考えだ。(中略)
昨年9月に損害保険ジャパンと日本興亜損害保険が合併して誕生した損保ジャパン日本興亜は、単体では保険料収入で国内最大手になった。ただ、グループでは欧米での積極的なM&A(合併・買収)で海外事業を伸ばした東京海上ホールディングスが上回る。
損保ジャパン日本興亜も海外事業の強化に向け、14年に英中堅損保のキャノピアスを1000億円弱で買収した。今回の大型出資と合わせて、保険市場の規模が大きい欧米で存在感を高める考え。少子高齢化で国内の損保市場の高成長が見込みにくいなか、大手損保による海外M&Aの動きは今後も続きそうだ。
出所:2015年3月6日 日本経済新聞 朝刊
---------------------------------------------------------
損害保険ジャパン日本興亜が、仏スコールに出資だって…。
損保ジャパン日本興亜の前身、損保ジャパンは2002年に安田火災海上保険と日産火災海上保険の合併で出来た会社。私は合併に伴いお仕事をさせていただいたこともあり、かなり気になる記事だ。
昨年9月の合併により保険料収入で損害保険ジャパン日本興亜は国内最大手になったとはいえ、今後の国内市場の成長イメージが持てない中、次なる戦略は必然的に海外事業強化になるんだろう。
昨今、私の知る中小企業でも、海外進出する企業は少なくない。大手企業に限らず、“国内市場だけでは成長イメージが持てない”ということなんだろう。であれば、この記事を他人事として捉えるのではなく自分に置き換えてみることが大切だ。
「仮に、自分の会社が海外進出をするのだとしたら…」「閉塞感があるのに現状のまま何も対策を講じなかったとしたら…」等々をイメージし、自分たちはどう振る舞うのがいいのかを考え、行動に移すことが大切なんじゃないだろうか?
学生のみなさんであれば、『大手金融系だから「安定」「高収入」』(ちなみに2014年2月の日経新聞 就職人気企業ランキングで、損害保険ジャパン・日本興亜は第6位でした)なんて考えるんじゃなく「縁あって損害保険ジャパン・日本興亜に入社したとしたら、その後は…」とか「日本企業の海外進出は、今後、自分にどんな影響があるのか?」等をイメージして、将来を俯瞰することが大切なんだろう。
周囲で起こっている環境変化を自分事と捉えて観察・行動することが大切だ!!

2015年02月22日
キャリア・クリエイト14年目がスタートしました!
2015年2月22日、本日はキャリア・クリエイト14年目スタートの日となります。「“企業と個人のWin-Win”をサポートする」をコンセプトにはじめた事業を継続することが出来る『ご縁』と『運』に恵まれたことに心より感謝です。
そんな中、昨日は、某大学キャリア支援サークルの就活支援イベントのお手伝いをしておりました。学生たちと一日一緒にいる中、起業に至った原体験を反芻しておりました。
1990年代、バブル経済の崩壊後、企業のリストラクチャリングがすすむ中、私はアウトプレイスメント(再就職支援)のコンサルタントをしておりました。終身雇用・年功序列等の雇用慣行の崩壊を目の当たりにする中、退職を余儀なくされたみなさんが、「こんなハズじゃ無かった!自分の職業人生は何だったんだ?」と肩を落とす姿を見て、次世代の職業人に「同じ思いをして欲しくない」との想いから起業を決めたことを再確認した次第です。
この13年間、活動の裾野も広がり、当社での活動以外にも大学講師、しずおかオンライン取締役(←設立日が同じで、本日22年目のスタート)等を通してコンセプトの実践に携わることが出来ることを嬉しく感じています。
私の理想とする“企業と個人のWin-Win”実現までの道のりは遠く、これからも暗中模索を繰り返すことになるのだろうと思いますが、「初心を忘れずにやっていこう!」と思う14年目の朝でした。

そんな中、昨日は、某大学キャリア支援サークルの就活支援イベントのお手伝いをしておりました。学生たちと一日一緒にいる中、起業に至った原体験を反芻しておりました。
1990年代、バブル経済の崩壊後、企業のリストラクチャリングがすすむ中、私はアウトプレイスメント(再就職支援)のコンサルタントをしておりました。終身雇用・年功序列等の雇用慣行の崩壊を目の当たりにする中、退職を余儀なくされたみなさんが、「こんなハズじゃ無かった!自分の職業人生は何だったんだ?」と肩を落とす姿を見て、次世代の職業人に「同じ思いをして欲しくない」との想いから起業を決めたことを再確認した次第です。
この13年間、活動の裾野も広がり、当社での活動以外にも大学講師、しずおかオンライン取締役(←設立日が同じで、本日22年目のスタート)等を通してコンセプトの実践に携わることが出来ることを嬉しく感じています。
私の理想とする“企業と個人のWin-Win”実現までの道のりは遠く、これからも暗中模索を繰り返すことになるのだろうと思いますが、「初心を忘れずにやっていこう!」と思う14年目の朝でした。

2014年09月20日
長~いタイトルの申し合わせ?!
~企業等の協力を得て取り組むキャリア教育としての学内行事実施に関する申合せ~
去る9月16日、国公私立の大学、短期大学及び高等専門学校で構成する就職問題懇談会(座長:濵口道成 国立大学協会教育・研究委員会委員長(名古屋大学長))が、「企業等の協力を得て取り組むキャリア教育としての学内行事実施に関する申合せ」を取りまとめ、文部科学省のHPにて発表された。
要約すると、2016年卒の新卒より、広報活動の開始時期は卒業・修了前年度の12月だったものが3月に、採用選考活動の開始時期は卒業・修了年度の4月だったものが8月に後ろ倒しされることが決定している。
その決定を受けて、(一社)日本経済団体連合会(以下、経団連)は、広報活動開始前(3月以前)においては、「大学が行う学内セミナー等への参加を自粛する」ということだったが、学校として「大学等のキャリア教育において、学生の産業や職業に関する理解を深める取組の実効性を高めるためには、学内セミナー等への企業の参加は必要で協力いただきたい」旨を話したところ、経団連も趣旨に賛同し、採用選考に関する指針の手引きの改定を行ったとのこと。
尚、ここでいう学内セミナー等とは、あくまでキャリア教育の一環なので、企業の採用を目的とした「企業説明会」でないことは共有しましょうという内容だ。
う~ん、わかりにくい…。で、私なりに更に要約(解釈)すると「学校としては、採用活動の後ろ倒しにより、学生の企業情報収集に遅れが出ることが心配だ(抜け駆けする企業や学校もあるだろうし…)。学生の就活モチベーションを維持・UPさせるためにも、企業には是非とも学内セミナー等に協力して欲しい。但し、あくまで採用目的はNGですよ!?」ということを就職問題懇談会で申し合わせ、経団連も賛同してくれたということだ。
申し合わせの内容はわかったけど、結果的に当初の“就活後ろ倒し”の目的だった「大学生等の学修時間の確保、留学等の促進」は実行できるんだろうか?
この手の話、悩ましいのは、善し悪しとは別に「流れに乗らないと損をしちゃう!?」というジレンマに陥る可能性大であるということ。民間の就職支援会社が学内セミナー他、いろんな部分で知恵(?)を出して“際の部分の新サービス”を編み出しそうな気もするし…。
老婆心ながら「就職活動の早期化と長期化を助長するコトにならなきゃいいんだけど…」などと考え込んでしまった。

去る9月16日、国公私立の大学、短期大学及び高等専門学校で構成する就職問題懇談会(座長:濵口道成 国立大学協会教育・研究委員会委員長(名古屋大学長))が、「企業等の協力を得て取り組むキャリア教育としての学内行事実施に関する申合せ」を取りまとめ、文部科学省のHPにて発表された。
要約すると、2016年卒の新卒より、広報活動の開始時期は卒業・修了前年度の12月だったものが3月に、採用選考活動の開始時期は卒業・修了年度の4月だったものが8月に後ろ倒しされることが決定している。
その決定を受けて、(一社)日本経済団体連合会(以下、経団連)は、広報活動開始前(3月以前)においては、「大学が行う学内セミナー等への参加を自粛する」ということだったが、学校として「大学等のキャリア教育において、学生の産業や職業に関する理解を深める取組の実効性を高めるためには、学内セミナー等への企業の参加は必要で協力いただきたい」旨を話したところ、経団連も趣旨に賛同し、採用選考に関する指針の手引きの改定を行ったとのこと。
尚、ここでいう学内セミナー等とは、あくまでキャリア教育の一環なので、企業の採用を目的とした「企業説明会」でないことは共有しましょうという内容だ。
う~ん、わかりにくい…。で、私なりに更に要約(解釈)すると「学校としては、採用活動の後ろ倒しにより、学生の企業情報収集に遅れが出ることが心配だ(抜け駆けする企業や学校もあるだろうし…)。学生の就活モチベーションを維持・UPさせるためにも、企業には是非とも学内セミナー等に協力して欲しい。但し、あくまで採用目的はNGですよ!?」ということを就職問題懇談会で申し合わせ、経団連も賛同してくれたということだ。
申し合わせの内容はわかったけど、結果的に当初の“就活後ろ倒し”の目的だった「大学生等の学修時間の確保、留学等の促進」は実行できるんだろうか?
この手の話、悩ましいのは、善し悪しとは別に「流れに乗らないと損をしちゃう!?」というジレンマに陥る可能性大であるということ。民間の就職支援会社が学内セミナー他、いろんな部分で知恵(?)を出して“際の部分の新サービス”を編み出しそうな気もするし…。
老婆心ながら「就職活動の早期化と長期化を助長するコトにならなきゃいいんだけど…」などと考え込んでしまった。

2014年08月19日
「転職検討」20代男性51%
〜男性、給与水準に不満 女性、人間関係で悩み 本社など調査〜
20代男性の半数以上が転職を検討していることが、日本経済新聞社とNTTコム オンライン・マーケティング・ソリューションの「NTTコムリサーチ」が共同で実施した転職意識調査でわかった。20~50代のビジネスパーソンを対象とした調査で、全体では転職希望者は38%だった。転職の理由は男性に「給与水準」が多いのに対し、女性は「職場の人間関係」をあげる人が多かった。
20代男性で「転職を検討している」と回答したのは47.1%。「すでに転職の準備を進めている」(4.3%)と合わせて51.4%と半数を超えた。30、40代は約4割で、50代は27.5%だった。企業が応募する際に年齢制限を設けていることが多いためか、年齢が高くなると転職希望者の割合は低くなる傾向が見られた。(中略)
転職結果に不満があるとの回答者にその理由を3つまで選んでもらったところ、「給与水準」が78.9%を占めた。給与水準の引き上げを目指して転職しても、満足な結果を得られないケースが多くあるようだ。
転職活動について感じることを自由回答してもらったところ、転職前の情報と入社後とのギャップに対して不満の声が多かった。「入ってみないとわからないのがいつも不満」(30代男性)、「募集要項だけでは細かい待遇や条件がわからず、検討しにくい」(20代女性)などの声が上がった。人手不足のなか、中途採用者を貴重な人材確保の戦略と位置づける企業では、より職場の実態にのっとった情報提供が優秀な人材確保のカギになりそうだ。
一部の回答者は「働きながらの転職活動は(理解を得られず)面接日の調整が難しい」(20代男性)、「転職に伴う手続きなどで、日本は終身雇用を前提とした仕組みが残っていると痛感」(40代男性)、「転職=悪という意識が世間にまだ残っている」(40代男性)などの声も目立った。
転職者を戦力ととらえる企業が増えており、転職に対する理解度は高まっているものの、なお一部の理解の薄さに戸惑いを感じるケースは根強く残っているようだ。
出所:2014年8月19日 日本経済新聞 朝刊
----------------------------------------------------------
なんと、「20代男性の半数以上が転職を検討している!?」という記事だ。採用現場の実感としても若手求職者の応募書類が増えているのは実感しているけれど、「20代男性の半数以上が、現状の仕事に全力投球できていない可能性大?」とも言い換えられそうで、少なからず驚きだ。
景気の低迷が続く中、転職しようにも魅力的な求人案件が見当たらない?という時期が続いた反動もあるのかもしれないが…
まっ、私自身、転職自体については、否定も肯定もしないけど、役員を務めさせていただいている会社の面接では、「何故、転職するのか?」について、いろんな角度から根掘り葉掘り(?)聴くことを心がけている。(私の質問の仕方がいいのか…笑)「給与が不満」「労働条件が不満」「人間関係が不満」等、いろんな「不満」が聴き出せるし、話を聴けば「それじゃ、辞めたくなるのも無理ね〜や!?」って思える内容が多いのも事実。
ただ、採用する側は、「応募者の前職への不満」を聴きたい訳じゃないってことを理解することも大切だ。だって、不満ばかりの求職者は「うちに入社しても、また不満ばっかり言うんだろうな〜?!」などと否が応でも想像しちゃうでしょ。
「辞めたい理由」じゃなく、「貴社に入社したらこんなコトしたい、将来はこんな風になりたい!」って自分の言葉で語れることが大切だ。そのためには、自分の今の力量がどの程度なのかを客観視しなくちゃならないし、応募企業はどんな会社でどんな人材を求めているのかをちゃんと研究する必要がある(不明点は、面接で質問すればいい)ということだ。まぁ、記事にもある様に、「募集要項だけではわからない…」というのはもっともなので、企業はより一層の工夫が必要だけど…
企業は「自社への理解を深めてもらう努力をすること」、応募者は「相手(採用企業)の立場に立ってものを考えることが出来ること」が、双方が納得のいく採用・求職活動の必要条件なんでしょうね!?

20代男性の半数以上が転職を検討していることが、日本経済新聞社とNTTコム オンライン・マーケティング・ソリューションの「NTTコムリサーチ」が共同で実施した転職意識調査でわかった。20~50代のビジネスパーソンを対象とした調査で、全体では転職希望者は38%だった。転職の理由は男性に「給与水準」が多いのに対し、女性は「職場の人間関係」をあげる人が多かった。
20代男性で「転職を検討している」と回答したのは47.1%。「すでに転職の準備を進めている」(4.3%)と合わせて51.4%と半数を超えた。30、40代は約4割で、50代は27.5%だった。企業が応募する際に年齢制限を設けていることが多いためか、年齢が高くなると転職希望者の割合は低くなる傾向が見られた。(中略)
転職結果に不満があるとの回答者にその理由を3つまで選んでもらったところ、「給与水準」が78.9%を占めた。給与水準の引き上げを目指して転職しても、満足な結果を得られないケースが多くあるようだ。
転職活動について感じることを自由回答してもらったところ、転職前の情報と入社後とのギャップに対して不満の声が多かった。「入ってみないとわからないのがいつも不満」(30代男性)、「募集要項だけでは細かい待遇や条件がわからず、検討しにくい」(20代女性)などの声が上がった。人手不足のなか、中途採用者を貴重な人材確保の戦略と位置づける企業では、より職場の実態にのっとった情報提供が優秀な人材確保のカギになりそうだ。
一部の回答者は「働きながらの転職活動は(理解を得られず)面接日の調整が難しい」(20代男性)、「転職に伴う手続きなどで、日本は終身雇用を前提とした仕組みが残っていると痛感」(40代男性)、「転職=悪という意識が世間にまだ残っている」(40代男性)などの声も目立った。
転職者を戦力ととらえる企業が増えており、転職に対する理解度は高まっているものの、なお一部の理解の薄さに戸惑いを感じるケースは根強く残っているようだ。
出所:2014年8月19日 日本経済新聞 朝刊
----------------------------------------------------------
なんと、「20代男性の半数以上が転職を検討している!?」という記事だ。採用現場の実感としても若手求職者の応募書類が増えているのは実感しているけれど、「20代男性の半数以上が、現状の仕事に全力投球できていない可能性大?」とも言い換えられそうで、少なからず驚きだ。
景気の低迷が続く中、転職しようにも魅力的な求人案件が見当たらない?という時期が続いた反動もあるのかもしれないが…
まっ、私自身、転職自体については、否定も肯定もしないけど、役員を務めさせていただいている会社の面接では、「何故、転職するのか?」について、いろんな角度から根掘り葉掘り(?)聴くことを心がけている。(私の質問の仕方がいいのか…笑)「給与が不満」「労働条件が不満」「人間関係が不満」等、いろんな「不満」が聴き出せるし、話を聴けば「それじゃ、辞めたくなるのも無理ね〜や!?」って思える内容が多いのも事実。
ただ、採用する側は、「応募者の前職への不満」を聴きたい訳じゃないってことを理解することも大切だ。だって、不満ばかりの求職者は「うちに入社しても、また不満ばっかり言うんだろうな〜?!」などと否が応でも想像しちゃうでしょ。
「辞めたい理由」じゃなく、「貴社に入社したらこんなコトしたい、将来はこんな風になりたい!」って自分の言葉で語れることが大切だ。そのためには、自分の今の力量がどの程度なのかを客観視しなくちゃならないし、応募企業はどんな会社でどんな人材を求めているのかをちゃんと研究する必要がある(不明点は、面接で質問すればいい)ということだ。まぁ、記事にもある様に、「募集要項だけではわからない…」というのはもっともなので、企業はより一層の工夫が必要だけど…
企業は「自社への理解を深めてもらう努力をすること」、応募者は「相手(採用企業)の立場に立ってものを考えることが出来ること」が、双方が納得のいく採用・求職活動の必要条件なんでしょうね!?

2014年07月16日
「妻は専業主婦」希望4割
〜20〜40代男女意識調査〜
明治安田生命福祉研究所が発表した20代〜40代の結婚などに関する意識調査によると、「夫が外で働き、妻は専業主婦がよい」との考え方を支持する人の割合が、男性で39.3%、女性で43.0%に上った。政府は「女性の活躍」を成長戦略の目玉に掲げて社会進出を促しているが、男女とも約4割が「妻は専業主婦」を望んでいる実態が浮き彫りとなった。
調査によると「夫が外で働き、妻は専業主婦がよい」との考え方に、「そう思う」「どちらかというとそう思う」と回答した割合は、未婚男性では34.2%、未婚女性では37.9%。既婚男性は42.5%、既婚女性は46.1%で、男女とも既婚者の方が回答が多かった。
調査担当者は「意外な多さだったが、女性が産後も働き続けられる環境が十分でないとの考えが根強いためではないか」と話している。「こどもが小さいうちは、妻は育児に専念すべきだ」との考え方を支持する割合も、男性64.4%、女性70.9%に上った。
調査は全国の20歳以上49歳以下の男女を対象に、3月下旬、インターネット上で行った。回収数は3616人。
出所:2014年7月13日 静岡新聞 朝刊
----------------------------------------------------
男女とも約4割が「妻は専業主婦」を望んでいるって…。政府の成長戦略の目玉である『女性の社会進出』に水を差すような調査結果だ。
特に、男女問わず、未婚者よりも既婚者の方が「夫が外で働き、妻は専業主婦がよい」という回答が多いのが、少なからずショックかも…
結婚すると、男性は「俺が帰ったら『お帰りなさい』と迎えて欲しい」と思ったり、女性は「旦那さんの稼ぎだけで生活出来たら幸せ…」なんて考えての結果なんだろうか?
とはいえ、調査担当者は「意外な多さ…」とコメントしているけど、この調査結果に驚かない自分がいるのも事実。学生たちと働くことについて議論すると、この調査結果と似たような話に遭遇することは珍しくない。
『仕事にやりがいを感じている両親』のもとで育った学生は「早く社会に出て働きたい」と言い、『仕事の愚痴ばっかり言っている両親』のもとで育った学生は「出来れば仕事をしたくない」と言うケースが多い様に感じるし、実は後者のパターンは少なくない…。
『女性の社会進出』の促進に『女性が産後も働き続けられる環境整備』は、必要条件ではあるけれど、先ずは「『出来れば働きたくない』と思っている人は少なくないかも…」というところから、仮説を立ててみることも必要なのかもしれない。

明治安田生命福祉研究所が発表した20代〜40代の結婚などに関する意識調査によると、「夫が外で働き、妻は専業主婦がよい」との考え方を支持する人の割合が、男性で39.3%、女性で43.0%に上った。政府は「女性の活躍」を成長戦略の目玉に掲げて社会進出を促しているが、男女とも約4割が「妻は専業主婦」を望んでいる実態が浮き彫りとなった。
調査によると「夫が外で働き、妻は専業主婦がよい」との考え方に、「そう思う」「どちらかというとそう思う」と回答した割合は、未婚男性では34.2%、未婚女性では37.9%。既婚男性は42.5%、既婚女性は46.1%で、男女とも既婚者の方が回答が多かった。
調査担当者は「意外な多さだったが、女性が産後も働き続けられる環境が十分でないとの考えが根強いためではないか」と話している。「こどもが小さいうちは、妻は育児に専念すべきだ」との考え方を支持する割合も、男性64.4%、女性70.9%に上った。
調査は全国の20歳以上49歳以下の男女を対象に、3月下旬、インターネット上で行った。回収数は3616人。
出所:2014年7月13日 静岡新聞 朝刊
----------------------------------------------------
男女とも約4割が「妻は専業主婦」を望んでいるって…。政府の成長戦略の目玉である『女性の社会進出』に水を差すような調査結果だ。
特に、男女問わず、未婚者よりも既婚者の方が「夫が外で働き、妻は専業主婦がよい」という回答が多いのが、少なからずショックかも…
結婚すると、男性は「俺が帰ったら『お帰りなさい』と迎えて欲しい」と思ったり、女性は「旦那さんの稼ぎだけで生活出来たら幸せ…」なんて考えての結果なんだろうか?
とはいえ、調査担当者は「意外な多さ…」とコメントしているけど、この調査結果に驚かない自分がいるのも事実。学生たちと働くことについて議論すると、この調査結果と似たような話に遭遇することは珍しくない。
『仕事にやりがいを感じている両親』のもとで育った学生は「早く社会に出て働きたい」と言い、『仕事の愚痴ばっかり言っている両親』のもとで育った学生は「出来れば仕事をしたくない」と言うケースが多い様に感じるし、実は後者のパターンは少なくない…。
『女性の社会進出』の促進に『女性が産後も働き続けられる環境整備』は、必要条件ではあるけれど、先ずは「『出来れば働きたくない』と思っている人は少なくないかも…」というところから、仮説を立ててみることも必要なのかもしれない。






