2018年08月16日
働くということ
〜 黒井千次 著 〜
「衣食住が満たされていたら、あなたは働きますか?」。私がキャリア支援セミナーやカウンセリングでよく聴く質問だが、あなただったら何と答えるだろう。
「えっ、お金があるのになぜ働くの?」という“働かない派”も少なくないけれど、同じ“働く派”でも「社会に貢献したい」「成長したい」という人から「暇になると人間堕落するし…」「世間体もあるしなぁ…」等々、働く目的は様々だ。
ということで、説得力のある答えを求め続ける中で出会った一つがこの本。黒井千次氏の著書『働くということ』。
黒岩氏は1932年生まれ。1955年に富士重工(現SUBARU)入社、1970年に同社を退社するまでの15年の会社員としての体験を振り返り、氏の考える『働くということ』の意味と意義をまとめた書籍だ。実社会を目前にした大学生に向けて書かれた様だけど、正直、1982年3月の初版から36年も経っているので、「あまり参考にはならないんじゃないか?」と疑心暗鬼で読みはじめたのだが…。
入社前は、イメージする小説家となるため、実社会で生きる最初の数年を会社員として過ごそうという、ある種不純な動機でスタートした会社員生活。それが、実際に働き出してみると、次第に“会社の仕事が自分の内部に入り込んできて、与えられた仕事が単に与えられたものにとどまらず、我を忘れている瞬間があることに気づいてく”という実体験に基づく心の変遷が、読む人を惹きつける。
「社会・経済環境が変わっても、働くことの本質が大きく変わる訳じゃないのかもな~!?」などと感じつつ、一気に読破した。
目次を見ると、“仕事が自分の中に入るまで”“人は金のみのために働くのか”“会社員は職業か”“企業意識と職業意識”“働くことと遊ぶこと”なんて文書が並んでる。「どんなことが書いてあるんだろう?」とちょっとでも興味を持ってくれたのであれば、是非、手に取って読んでみて欲しい。
お奨めです!!

「衣食住が満たされていたら、あなたは働きますか?」。私がキャリア支援セミナーやカウンセリングでよく聴く質問だが、あなただったら何と答えるだろう。
「えっ、お金があるのになぜ働くの?」という“働かない派”も少なくないけれど、同じ“働く派”でも「社会に貢献したい」「成長したい」という人から「暇になると人間堕落するし…」「世間体もあるしなぁ…」等々、働く目的は様々だ。
ということで、説得力のある答えを求め続ける中で出会った一つがこの本。黒井千次氏の著書『働くということ』。
黒岩氏は1932年生まれ。1955年に富士重工(現SUBARU)入社、1970年に同社を退社するまでの15年の会社員としての体験を振り返り、氏の考える『働くということ』の意味と意義をまとめた書籍だ。実社会を目前にした大学生に向けて書かれた様だけど、正直、1982年3月の初版から36年も経っているので、「あまり参考にはならないんじゃないか?」と疑心暗鬼で読みはじめたのだが…。
入社前は、イメージする小説家となるため、実社会で生きる最初の数年を会社員として過ごそうという、ある種不純な動機でスタートした会社員生活。それが、実際に働き出してみると、次第に“会社の仕事が自分の内部に入り込んできて、与えられた仕事が単に与えられたものにとどまらず、我を忘れている瞬間があることに気づいてく”という実体験に基づく心の変遷が、読む人を惹きつける。
「社会・経済環境が変わっても、働くことの本質が大きく変わる訳じゃないのかもな~!?」などと感じつつ、一気に読破した。
目次を見ると、“仕事が自分の中に入るまで”“人は金のみのために働くのか”“会社員は職業か”“企業意識と職業意識”“働くことと遊ぶこと”なんて文書が並んでる。「どんなことが書いてあるんだろう?」とちょっとでも興味を持ってくれたのであれば、是非、手に取って読んでみて欲しい。
お奨めです!!

2018年07月04日
未来をつくるキャリアの授業
~ 最短距離で希望の人生を手に入れる! 渡辺 秀和 著~
「本の帯」にある“東京大学が使用する「キャリアデザイン」の教科書”のコピーにつられて読んでみた。
この本を端的に説明するのであれば、“経営企画、営業、経理・財務、人事等々の文系エグゼクティブ向けの転職指南書”かな…。著者の渡辺秀和氏は、コンコードエグゼクティブグループという人材紹介会社のCEOだという事もあってか、労働市場の変化とそれに伴う内・外資企業の採用に関するスタンス、および人材紹介、ヘッドハンティング、就活関連メディアの特性・利用方法等々がポイントを押さえて的確に書かれている。
転職を考えるみなさんには、「読んでみたら…!!」とお勧めしたいし、アマゾンンのレビューで「キャリアはこういう事が知りたかった」「希望の人生を手に入れたいすべての学生にお薦め」等の好意的なコメントが並ぶのも頷ける。
とはいえ、勉強は出来るかもしれないけれど社会人経験の無い東大生がキャリアデザインの授業を受講した際、「この本(教科書)から何を学ぶのだろう?」という興味(疑問)も湧いてくる。
本書では、「“キャリアデザイン”とは、単に年収アップや有名企業に転職することではない」と謳ってはいるけれど…。読み間違えて「この本に書かれた定石のレールに乗せられていることに気づかぬまま、単にリスク回避の術を習得しただけ!?」なんてコトにならなきゃいいけど等、いらん心配をしてしまう。
特に、第5章の起業についてのくだり…。 “手堅く、安全に「起業」する”方法として、「(コンサルティングファームやベンチャーキャピタルをはじめとするプロフェッショナルファームで)戦略コンサルティング経験を積んで起業するコトがリスク回避に役立つ」等の記述を読む中、「確かにリスクは減るかもしれないけれど、起業する上で“もっと大切なコト”があるんじゃないの?」などと思えてしまう。
中身も濃くてとってもいい本だけど、「“キャリアデザイン”の教科書じゃなく、参考資料としての利用だったらアリかな?!」と思った一冊でした。

「本の帯」にある“東京大学が使用する「キャリアデザイン」の教科書”のコピーにつられて読んでみた。
この本を端的に説明するのであれば、“経営企画、営業、経理・財務、人事等々の文系エグゼクティブ向けの転職指南書”かな…。著者の渡辺秀和氏は、コンコードエグゼクティブグループという人材紹介会社のCEOだという事もあってか、労働市場の変化とそれに伴う内・外資企業の採用に関するスタンス、および人材紹介、ヘッドハンティング、就活関連メディアの特性・利用方法等々がポイントを押さえて的確に書かれている。
転職を考えるみなさんには、「読んでみたら…!!」とお勧めしたいし、アマゾンンのレビューで「キャリアはこういう事が知りたかった」「希望の人生を手に入れたいすべての学生にお薦め」等の好意的なコメントが並ぶのも頷ける。
とはいえ、勉強は出来るかもしれないけれど社会人経験の無い東大生がキャリアデザインの授業を受講した際、「この本(教科書)から何を学ぶのだろう?」という興味(疑問)も湧いてくる。
本書では、「“キャリアデザイン”とは、単に年収アップや有名企業に転職することではない」と謳ってはいるけれど…。読み間違えて「この本に書かれた定石のレールに乗せられていることに気づかぬまま、単にリスク回避の術を習得しただけ!?」なんてコトにならなきゃいいけど等、いらん心配をしてしまう。
特に、第5章の起業についてのくだり…。 “手堅く、安全に「起業」する”方法として、「(コンサルティングファームやベンチャーキャピタルをはじめとするプロフェッショナルファームで)戦略コンサルティング経験を積んで起業するコトがリスク回避に役立つ」等の記述を読む中、「確かにリスクは減るかもしれないけれど、起業する上で“もっと大切なコト”があるんじゃないの?」などと思えてしまう。
中身も濃くてとってもいい本だけど、「“キャリアデザイン”の教科書じゃなく、参考資料としての利用だったらアリかな?!」と思った一冊でした。

2018年05月06日
女性に伝えたい 未来が変わる働き方
〜 野村浩子 著 〜
元“日経WOMAN”編集長でもある著者の野村氏が、男女雇用機会均等法施行(1986年)後の30年を振り返りつつ、新しい時代の「働き方」「生き方」を探るという本。
日頃から、「“女性の働き方”を一括りになんか出来ないよ〜!?」と思っている私ではありますが、雇均法施行とほぼ同時期の1984年に職業人生のスタートを切った野村氏が、この30年をどの様に見ているのか、興味津々で読んでみました。
結論から言ってしまうと、「とっても良い本!」でした。働き方は十人十色ではありますが、仕事との付き合い方を解りやすく分類・分析しているので、とても読みやすいし腹落ちする内容でした。章立てを見ると、「女性をどんな風に分類しているか?」「全体がどんな構成になっているか?」が推察出来ると思うので、備忘録代わりに以下に目次を記載しておきます。
第1章 仕事と子育て両立編:“残業できる人、できない人”“家事・育児を手放せない人、任せられる人”
第2章 ライフコース編:“専業主婦か、キャリア女性か”“扶養枠を超える人、超えない人”“子どものいる人、いない人”
第3章 働く女性の30年(A面・正社員):“総合職か、一般職か”“雇均法施行から30年、どう変わったか?”
第4章 働く女性の30年(B面・非正規女子):“非正規で働く女性”“シングルマザー”
第5章 キャリア編:“管理職になりたい人、なりたくない人”“女性起業家”
第6章 これからの働き方、生き方を探る:“2極化の時代に、どう働くか”
タイトルには、“女性に伝えたい”とありますが、女性だけで仕事をする訳じゃ無いんだし…。仕事仲間や配偶者としての役割を担う立場でもある“男性”、従業員と雇用契約を結ぶ立場にある“経営者”、働き方改革の旗振り役である“政治家やお役人”のみなさんにも、読んでもらいたいと思った本でした。
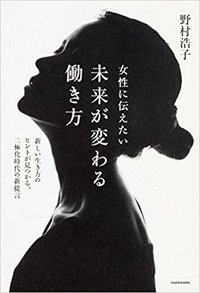
元“日経WOMAN”編集長でもある著者の野村氏が、男女雇用機会均等法施行(1986年)後の30年を振り返りつつ、新しい時代の「働き方」「生き方」を探るという本。
日頃から、「“女性の働き方”を一括りになんか出来ないよ〜!?」と思っている私ではありますが、雇均法施行とほぼ同時期の1984年に職業人生のスタートを切った野村氏が、この30年をどの様に見ているのか、興味津々で読んでみました。
結論から言ってしまうと、「とっても良い本!」でした。働き方は十人十色ではありますが、仕事との付き合い方を解りやすく分類・分析しているので、とても読みやすいし腹落ちする内容でした。章立てを見ると、「女性をどんな風に分類しているか?」「全体がどんな構成になっているか?」が推察出来ると思うので、備忘録代わりに以下に目次を記載しておきます。
第1章 仕事と子育て両立編:“残業できる人、できない人”“家事・育児を手放せない人、任せられる人”
第2章 ライフコース編:“専業主婦か、キャリア女性か”“扶養枠を超える人、超えない人”“子どものいる人、いない人”
第3章 働く女性の30年(A面・正社員):“総合職か、一般職か”“雇均法施行から30年、どう変わったか?”
第4章 働く女性の30年(B面・非正規女子):“非正規で働く女性”“シングルマザー”
第5章 キャリア編:“管理職になりたい人、なりたくない人”“女性起業家”
第6章 これからの働き方、生き方を探る:“2極化の時代に、どう働くか”
タイトルには、“女性に伝えたい”とありますが、女性だけで仕事をする訳じゃ無いんだし…。仕事仲間や配偶者としての役割を担う立場でもある“男性”、従業員と雇用契約を結ぶ立場にある“経営者”、働き方改革の旗振り役である“政治家やお役人”のみなさんにも、読んでもらいたいと思った本でした。
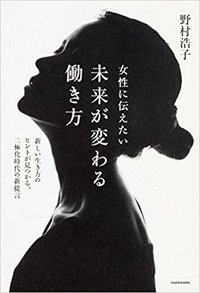
2018年03月31日
キャリアを手放す勇気
〜石井てる美 著〜
仕事柄、『キャリアを手放す勇気』というタイトルに惹かれて手に取ってみた。
著者は、東大大学院卒・マッキンゼーを経てお笑い芸人に転身した石井てる美氏。とはいえ、私は石井氏がどんな芸人なのか(ヒラリー・クリントンのモノマネをやっていること位は知っていた)も知らないし、実はそれほど内容に期待していたわけではなかったのだが…。
就活時、他の多くの東大生と同じ様に一流企業を受験。結果、「目指すべきはそのトップ集団」という価値観のもとマッキンゼーというステータスの権化の様な超一流企業の内定を得、職業人生のスタートを切る。
受験、進学、就職、いろんなことがたまたまうまくいき、どんなことも「頑張ればどうにかなる」と思い込んでいたものの、マッキンゼーでの仕事で初めて超えられない壁にぶつかり、「車がひいてくれたらいいのに…」と思うまでに追い詰められる。
その後、マッキンゼーを辞める決断をし、お笑い芸人を目指すことになるわけだが…。マッキンゼーを辞めて6・7年くらいは、後悔こそしないものの、悩みもがきながら生きてきた石井氏。お笑い芸人になって「心からよかった」「決断は正しかった」と思える様になったのはここ1・2年だとのこと。
そんな今だって、翻訳のアルバイトをしながらの芸人生活をしている石井氏を見て「もったいない」という人もいるのかもしれないが、私には石井氏がとっても輝いて見える。
ということで、予想を裏切り「キャリアのコトを真面目に語る、とっても良い本」でした。
※注:2013年7月に発行された「マッキンゼーを辞めた理由」を加筆・修正し文庫化した本。

仕事柄、『キャリアを手放す勇気』というタイトルに惹かれて手に取ってみた。
著者は、東大大学院卒・マッキンゼーを経てお笑い芸人に転身した石井てる美氏。とはいえ、私は石井氏がどんな芸人なのか(ヒラリー・クリントンのモノマネをやっていること位は知っていた)も知らないし、実はそれほど内容に期待していたわけではなかったのだが…。
就活時、他の多くの東大生と同じ様に一流企業を受験。結果、「目指すべきはそのトップ集団」という価値観のもとマッキンゼーというステータスの権化の様な超一流企業の内定を得、職業人生のスタートを切る。
受験、進学、就職、いろんなことがたまたまうまくいき、どんなことも「頑張ればどうにかなる」と思い込んでいたものの、マッキンゼーでの仕事で初めて超えられない壁にぶつかり、「車がひいてくれたらいいのに…」と思うまでに追い詰められる。
その後、マッキンゼーを辞める決断をし、お笑い芸人を目指すことになるわけだが…。マッキンゼーを辞めて6・7年くらいは、後悔こそしないものの、悩みもがきながら生きてきた石井氏。お笑い芸人になって「心からよかった」「決断は正しかった」と思える様になったのはここ1・2年だとのこと。
そんな今だって、翻訳のアルバイトをしながらの芸人生活をしている石井氏を見て「もったいない」という人もいるのかもしれないが、私には石井氏がとっても輝いて見える。
ということで、予想を裏切り「キャリアのコトを真面目に語る、とっても良い本」でした。
※注:2013年7月に発行された「マッキンゼーを辞めた理由」を加筆・修正し文庫化した本。

2018年03月16日
社員ゼロ!会社は「1人」で経営しなさい
〜山本憲明 著〜
『社員ゼロ!会社は「1人」で経営しなさい』というタイトルに惹かれて読んでみた。
日本の総人口・生産年齢人口共に減少を続けていく中、経済規模が縮小していくことは避けられない。また、周囲を見渡せば、「安定している!!」と思われていた大企業が合併したり、外資の傘下に入ったり、はたまた倒産したりと、大企業にしがみつく働き方が現実的ではなくなってきている。
そんな中、この本は、税理士・経営コンサルタントでもある著者が、自身の経験に基づき、「緩やかな衰退を前向きに生きるには“一人親方がおすすめ!”」と提唱している。時代を俯瞰的に見ての内容だし、何より著者自身が実践していることをベースに書いているので、説得力がある。
ちょっとだけ気になったのは、「会社経営のポイントは“維持”することであり“成長”することを考えるな」という趣旨の著述。“維持”が重要だということに異論は無いけれど、自分にちょうどいいボリュームでの“維持”は決して楽じゃない。というか、そんなに都合よくコトは進みません(私の実感…汗)。
タイトルに惹かれて読んだけど、内容的には『フリーランスの心得!!』ですね。とはいえ、内容も想像どおりの良書でした…。
現在、どこかの会社で働いているけれど、「このままでいいんだろうか?!」などと悶々としている方にお勧めです。

『社員ゼロ!会社は「1人」で経営しなさい』というタイトルに惹かれて読んでみた。
日本の総人口・生産年齢人口共に減少を続けていく中、経済規模が縮小していくことは避けられない。また、周囲を見渡せば、「安定している!!」と思われていた大企業が合併したり、外資の傘下に入ったり、はたまた倒産したりと、大企業にしがみつく働き方が現実的ではなくなってきている。
そんな中、この本は、税理士・経営コンサルタントでもある著者が、自身の経験に基づき、「緩やかな衰退を前向きに生きるには“一人親方がおすすめ!”」と提唱している。時代を俯瞰的に見ての内容だし、何より著者自身が実践していることをベースに書いているので、説得力がある。
ちょっとだけ気になったのは、「会社経営のポイントは“維持”することであり“成長”することを考えるな」という趣旨の著述。“維持”が重要だということに異論は無いけれど、自分にちょうどいいボリュームでの“維持”は決して楽じゃない。というか、そんなに都合よくコトは進みません(私の実感…汗)。
タイトルに惹かれて読んだけど、内容的には『フリーランスの心得!!』ですね。とはいえ、内容も想像どおりの良書でした…。
現在、どこかの会社で働いているけれど、「このままでいいんだろうか?!」などと悶々としている方にお勧めです。

2018年02月12日
江副浩正
〜馬場マコト・土屋洋 著〜
リクルート出身者でもある、馬場マコト・土屋洋 両氏が、多くの証言や膨大な資料を基に、江副浩正氏の実像をあぶり出した本。
江副氏は、多くの日本人にとって昭和のバブル期に政・財界を巻き込んで起こった贈収賄事件であるリクルート事件の主人公かもしれないが…。30余年にわたり情報ビジネス・人材ビジネスに携わってきた私にとって、江副氏は優秀な経営者という域を超えた“日本の産業構造変革を成し遂げたヒーロー”でありスペシャルな存在だ。1983年にリクルートが日軽金ビルを購入したことで、世間は大騒ぎになった。TVのニュース番組が「製造業の代表的企業である日軽金が、得体の知れない新興企業に飲み込まれた…!?」というニュアンスで報じていたことが強く印象に残っている。496頁というボリュームにもかかわらず、迫力と熱量に引き込まれて一気に読破した。
全21章のうち、前半の第11章あたりまでは、江副氏の生い立ち・東大新聞の営業をしていた学生時代から、起業・事業の多角化により成功の階段を駆け上がっていく様子が…。後半は、店頭登録に絡む疑惑報道・裁判の様子が、江副氏の心の変化を織り交ぜながら描かれている。
すべてが読みどころなので、ご興味を持たれた方には読まれることを強くお勧めしますが、以下は、私の備忘録。
前半部分で特に印象深かったのは、リクルートコスモスが快進撃を続ける中での、不動産業界のパーティーでの業界大手経営陣のやりとり。
業界のパーティーで顔を合わせた住友不動産の安藤太郎会長は、ばったり顔を合わせた三井不動産の江戸英雄相談役に思わずこう言った。
「うちでは上司の鞄持ち程度しかしていない年齢の人たちが、土地情報を入手して2,3日後に購入の結論を出している。信じられないことだ」
江戸も頷きながら返した。
「江副君という人は、旧財閥系の組織で育ったわれわれには、とうてい及びもつかない発想をする人ですね。あの時代への斬りこみ方は、大企業に身を置いた者にはとてもまねができませんよ」
江副氏の “自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ”“社員皆経営主義”の具現化を周囲の経営者が、どう視ていたかがよく解る。
後半部分で印象深かったのは、疑惑の中にあろうとも信頼できる友人の存在。その一、検察やメディアに対して、「還流株」にかかわったとの疑惑をかけられた友人のやりとり。
「初めから株の譲渡は江副の好意だ。代償など一つもない」
「だろう、俺も同じだ。江副から頼むよと言われた。だから回した。友だちの好だ」
新倉の言う通りだ。別に打算はない。菅原は日ごろ感じていることをしみじみと語った。
「彼ら(メディア)は、世間には損得とは無関係に動く人間がいるとは考えもしないんだ。人はみな、自分と同じくカネのためにしか動かないと思っている。江副の不幸は、そんなやつらににらまれたことだ」
その二、リクルートの社章・ビルのデザインから始まり、社外取締役となる亀倉雄策の存在。
亀倉は「経営とデザインの一体化」を願い、戦後の日本経済の成長とともに歩んできた。リクルートの成長もまた、亀倉のデザインとともにあった。江副は、その恩義を忘れず、ビルデザインや総合レジャー開発という新しい領域に自分の才能を導いてくれた。
そのうえに、社外取締役として経営にまで参画させてくれた。その江副が、世間からあらゆる罵詈雑言を浴び、苦しんでいる。潮が引くように、多くの人が江副と疎遠となっていくなか、立っていられないほどに消耗し自死の誘惑に耐えている。
それを放っておけるか。この男の傍らに寄り添い、最後のひとりになっても良いから彼と同じ道を歩もう。
亀倉デザイン研究所をリクルート本社ビル内に移すことに決め、江副に電話をかけた。
「大変ありがたいお申し出ですが、先生の晩年を汚すことになりかねません。お気持ちだけいただき、先生のお引っ越しはご遠慮させていただきます」
「いや、もう私は決めたんです。いまの事務所は年内で解約します」
電話を置くと、亀倉はすぐに、事務所引っ越しの案内状づくりに取り掛かった。
お互いが尊敬・信頼しあえる人に出会えることは、最高の幸せであり、何よりの財産だとつくづく感じさせる。
最後に、常に心に留めておきたいと思った一文。
江副が師と仰ぐドラッカーもまた言う。
「凡人に非凡なことをさせるのが組織の目的である」
ならば、優秀な人材がその能力をフルに発揮すれば、かなりのことができる。では、社員をそうし向けるにはどうすればいいか。組織のために働くのではなく、自分のために働く。これが個人を成長させる近道だ。そして、成長し続ける個人が集まる組織は強い。それなら、その制約は少ないほうがいい。社員が可能な限り自由に働ける制度と風土づくりをめざした。
まったく書評の体を成していませんが、とにかく良い本でした。

リクルート出身者でもある、馬場マコト・土屋洋 両氏が、多くの証言や膨大な資料を基に、江副浩正氏の実像をあぶり出した本。
江副氏は、多くの日本人にとって昭和のバブル期に政・財界を巻き込んで起こった贈収賄事件であるリクルート事件の主人公かもしれないが…。30余年にわたり情報ビジネス・人材ビジネスに携わってきた私にとって、江副氏は優秀な経営者という域を超えた“日本の産業構造変革を成し遂げたヒーロー”でありスペシャルな存在だ。1983年にリクルートが日軽金ビルを購入したことで、世間は大騒ぎになった。TVのニュース番組が「製造業の代表的企業である日軽金が、得体の知れない新興企業に飲み込まれた…!?」というニュアンスで報じていたことが強く印象に残っている。496頁というボリュームにもかかわらず、迫力と熱量に引き込まれて一気に読破した。
全21章のうち、前半の第11章あたりまでは、江副氏の生い立ち・東大新聞の営業をしていた学生時代から、起業・事業の多角化により成功の階段を駆け上がっていく様子が…。後半は、店頭登録に絡む疑惑報道・裁判の様子が、江副氏の心の変化を織り交ぜながら描かれている。
すべてが読みどころなので、ご興味を持たれた方には読まれることを強くお勧めしますが、以下は、私の備忘録。
前半部分で特に印象深かったのは、リクルートコスモスが快進撃を続ける中での、不動産業界のパーティーでの業界大手経営陣のやりとり。
業界のパーティーで顔を合わせた住友不動産の安藤太郎会長は、ばったり顔を合わせた三井不動産の江戸英雄相談役に思わずこう言った。
「うちでは上司の鞄持ち程度しかしていない年齢の人たちが、土地情報を入手して2,3日後に購入の結論を出している。信じられないことだ」
江戸も頷きながら返した。
「江副君という人は、旧財閥系の組織で育ったわれわれには、とうてい及びもつかない発想をする人ですね。あの時代への斬りこみ方は、大企業に身を置いた者にはとてもまねができませんよ」
江副氏の “自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ”“社員皆経営主義”の具現化を周囲の経営者が、どう視ていたかがよく解る。
後半部分で印象深かったのは、疑惑の中にあろうとも信頼できる友人の存在。その一、検察やメディアに対して、「還流株」にかかわったとの疑惑をかけられた友人のやりとり。
「初めから株の譲渡は江副の好意だ。代償など一つもない」
「だろう、俺も同じだ。江副から頼むよと言われた。だから回した。友だちの好だ」
新倉の言う通りだ。別に打算はない。菅原は日ごろ感じていることをしみじみと語った。
「彼ら(メディア)は、世間には損得とは無関係に動く人間がいるとは考えもしないんだ。人はみな、自分と同じくカネのためにしか動かないと思っている。江副の不幸は、そんなやつらににらまれたことだ」
その二、リクルートの社章・ビルのデザインから始まり、社外取締役となる亀倉雄策の存在。
亀倉は「経営とデザインの一体化」を願い、戦後の日本経済の成長とともに歩んできた。リクルートの成長もまた、亀倉のデザインとともにあった。江副は、その恩義を忘れず、ビルデザインや総合レジャー開発という新しい領域に自分の才能を導いてくれた。
そのうえに、社外取締役として経営にまで参画させてくれた。その江副が、世間からあらゆる罵詈雑言を浴び、苦しんでいる。潮が引くように、多くの人が江副と疎遠となっていくなか、立っていられないほどに消耗し自死の誘惑に耐えている。
それを放っておけるか。この男の傍らに寄り添い、最後のひとりになっても良いから彼と同じ道を歩もう。
亀倉デザイン研究所をリクルート本社ビル内に移すことに決め、江副に電話をかけた。
「大変ありがたいお申し出ですが、先生の晩年を汚すことになりかねません。お気持ちだけいただき、先生のお引っ越しはご遠慮させていただきます」
「いや、もう私は決めたんです。いまの事務所は年内で解約します」
電話を置くと、亀倉はすぐに、事務所引っ越しの案内状づくりに取り掛かった。
お互いが尊敬・信頼しあえる人に出会えることは、最高の幸せであり、何よりの財産だとつくづく感じさせる。
最後に、常に心に留めておきたいと思った一文。
江副が師と仰ぐドラッカーもまた言う。
「凡人に非凡なことをさせるのが組織の目的である」
ならば、優秀な人材がその能力をフルに発揮すれば、かなりのことができる。では、社員をそうし向けるにはどうすればいいか。組織のために働くのではなく、自分のために働く。これが個人を成長させる近道だ。そして、成長し続ける個人が集まる組織は強い。それなら、その制約は少ないほうがいい。社員が可能な限り自由に働ける制度と風土づくりをめざした。
まったく書評の体を成していませんが、とにかく良い本でした。

2017年09月12日
日本企業の社員は、なぜこんなにもモチベーションが低いのか?
~ ロッシェル・カップ 著 ~
“日本企業の社員は、なぜこんなにもモチベーションが低いのか?”う~ん、おもいっきり憂鬱な気分にさせられるタイトルだなぁ!?
著者は、職場における異文化コミュニケーションと人事管理を専門とするコンサルタント。大手金融機関の東京本社勤務を経て、現在は多くの日本企業のコンサルティング活動を行っているということもあり、日本の職場の実態を認識した上での考察であるのが特徴だ。
かつては、「会社人間」と揶揄された私たち日本人だが、いろんなところで「日本人のやる気の無さ?!」が言われている。昨今、社員にやる気を起こさせるためにエンゲージメント(社員の企業に対する関与の度合いと、仕事に対する感情的つながり)が重要だと言われているが、いろんな調査から日本企業のエンゲージメントレベルが他国と比較してかなり低いという傾向が出ている様だ。
日本の労働生産性が低い(2015年国民ひとりあたりのGDPは、OECD加盟国35カ国中20位)のは、周知の事実だと思うけど「モチベーションが低い社員ばかりの集団だったら、労働生産性が低いのは当たり前だよな~」と思いつつ、モチベーションが低い理由を知りたくって読んでみた。
社員のモチベーション低下の背景には、日本の雇用制度が以下の3つの環境変化に対応しきれなくなってきたことが挙げられている。第1の変化は、60年代~70年代の高度成長期からの急激な成長の衰え。第2の変化は、経済のグローバル化により、諸外国から日本市場の開放を求められたこと。第3の変化は、バブル経済崩壊とそれに続く長期不況。この様な環境変化に対し、早期退職制度や一時解雇の実施、非正規社員の雇用増加策を行ってきたものの、うまく機能させることが出来ない。そして何より、成長を前提とした人事管理が出来ないためにすべての社員(厳密には、すべての男性正社員という方が当たっているかも…)が出世することが難しくなってきたという見立てだ。
そんな背景の中、氏は「仕事の定義の明確化」「各社員のスキルと能力の判断」「社員の将来の計画を立てるキャリアパスの構築」etc…を通し、「日本の人事管理を完全に考え直す必要がある」と説いている。わかりやすく言えば、「個人の目標を明確に定義したり業績に基づいた賃金制度を取り入れるなど、“アメリカ式”の勤務評価システムへの移行が必要だ」ということだ。
まぁ、個々の対応策については理解も納得もする一方で、「“アメリカ式”の勤務評価システムが機能しているのは、アメリカのどんな企業なんだろう?」「旧来型の製造業などでもうまく機能してるんだろうか?」という疑問も湧いてくる。
ひとつの会社内だけで完結する課題であれば、日本でも出来る企業はあると思うけれど、コトはもっと複雑なんだと思う。今の日本にとって必要なのは、個々の会社の人事管理制度改革ではなく、“企業と社員のもたれあいの構図(空気感)”を打破することなんじゃないかと思えてきた。
ということで、唐突ですが第8章(最終章)からの抜粋を…。
「自分の人生に対する展望を持たない者は、他人の人生の展望の一部になってしまう」。新しい環境の下、企業が自分に魅力的なキャリアパスを用意してくれることを当てにすることは、もはやできなくなっている。自分がどんな仕事をして何を達成したいのか、自分で考える時がきている。(中略)
これは、企業に忠実であるのをやめることではない。また、仕事に力を入れないということでもない。それは、自分と自分の興味・関心を企業と企業の興味・関心から分離して考えることを指している。
政府も企業も“雇用に関する空気感打破のための努力”をするのはもちろんだけど、私たちひとりひとりが「自分の人生なんだから、ちゃんと自分で考えなくっちゃネ!!」と考えさせられる一冊でした。

“日本企業の社員は、なぜこんなにもモチベーションが低いのか?”う~ん、おもいっきり憂鬱な気分にさせられるタイトルだなぁ!?
著者は、職場における異文化コミュニケーションと人事管理を専門とするコンサルタント。大手金融機関の東京本社勤務を経て、現在は多くの日本企業のコンサルティング活動を行っているということもあり、日本の職場の実態を認識した上での考察であるのが特徴だ。
かつては、「会社人間」と揶揄された私たち日本人だが、いろんなところで「日本人のやる気の無さ?!」が言われている。昨今、社員にやる気を起こさせるためにエンゲージメント(社員の企業に対する関与の度合いと、仕事に対する感情的つながり)が重要だと言われているが、いろんな調査から日本企業のエンゲージメントレベルが他国と比較してかなり低いという傾向が出ている様だ。
日本の労働生産性が低い(2015年国民ひとりあたりのGDPは、OECD加盟国35カ国中20位)のは、周知の事実だと思うけど「モチベーションが低い社員ばかりの集団だったら、労働生産性が低いのは当たり前だよな~」と思いつつ、モチベーションが低い理由を知りたくって読んでみた。
社員のモチベーション低下の背景には、日本の雇用制度が以下の3つの環境変化に対応しきれなくなってきたことが挙げられている。第1の変化は、60年代~70年代の高度成長期からの急激な成長の衰え。第2の変化は、経済のグローバル化により、諸外国から日本市場の開放を求められたこと。第3の変化は、バブル経済崩壊とそれに続く長期不況。この様な環境変化に対し、早期退職制度や一時解雇の実施、非正規社員の雇用増加策を行ってきたものの、うまく機能させることが出来ない。そして何より、成長を前提とした人事管理が出来ないためにすべての社員(厳密には、すべての男性正社員という方が当たっているかも…)が出世することが難しくなってきたという見立てだ。
そんな背景の中、氏は「仕事の定義の明確化」「各社員のスキルと能力の判断」「社員の将来の計画を立てるキャリアパスの構築」etc…を通し、「日本の人事管理を完全に考え直す必要がある」と説いている。わかりやすく言えば、「個人の目標を明確に定義したり業績に基づいた賃金制度を取り入れるなど、“アメリカ式”の勤務評価システムへの移行が必要だ」ということだ。
まぁ、個々の対応策については理解も納得もする一方で、「“アメリカ式”の勤務評価システムが機能しているのは、アメリカのどんな企業なんだろう?」「旧来型の製造業などでもうまく機能してるんだろうか?」という疑問も湧いてくる。
ひとつの会社内だけで完結する課題であれば、日本でも出来る企業はあると思うけれど、コトはもっと複雑なんだと思う。今の日本にとって必要なのは、個々の会社の人事管理制度改革ではなく、“企業と社員のもたれあいの構図(空気感)”を打破することなんじゃないかと思えてきた。
ということで、唐突ですが第8章(最終章)からの抜粋を…。
「自分の人生に対する展望を持たない者は、他人の人生の展望の一部になってしまう」。新しい環境の下、企業が自分に魅力的なキャリアパスを用意してくれることを当てにすることは、もはやできなくなっている。自分がどんな仕事をして何を達成したいのか、自分で考える時がきている。(中略)
これは、企業に忠実であるのをやめることではない。また、仕事に力を入れないということでもない。それは、自分と自分の興味・関心を企業と企業の興味・関心から分離して考えることを指している。
政府も企業も“雇用に関する空気感打破のための努力”をするのはもちろんだけど、私たちひとりひとりが「自分の人生なんだから、ちゃんと自分で考えなくっちゃネ!!」と考えさせられる一冊でした。

2016年04月26日
ハーバードでいちばん人気の国・日本
〜佐藤 智恵 著〜
新聞の書籍広告に載っていた「テレビ番組で紹介、お茶の間でも大反響!」「書籍ランキング1位」のキャッチコピーに、「“ニッポンすごい系番組”の書籍版かな…?」と興味をそそられて読んでみた。
ちなみに私は、「“ニッポンすごい系番組”最近チョッピリ多すぎかも…?」と感じはするものの、それに対する批判のコメントを目にして、「目くじら立てて批判する…?」とちょっぴり引いちゃう様な輩です。
書籍の内容はタイトルの通り、ハーバードの授業で教材として扱われる日本や日本企業の事例の紹介を通して、日本や日本企業の人気の理由が丁寧、且つわかりやすく書かれている。事例自体は、私たち日本人が知っているものが多いけれど、それをハーバードの教授陣が「どんな視点でどう評価しているのか?」という観点で書かれているのが読みやすい。
ちなみに、学生たちが卒業までの2年間で学ぶ約500本の事例のうち、必修科目(2014年)で学ぶ日本の事例は、トヨタ自動車(テクノロジーとオペレーションマネジメント)、楽天(リーダーシップと組織行動)、全日本空輸(マーケティング)、本田技研工業(経営戦略)、日本航空(ファイナンス)、アベノミクス(ビジネス・政府・国際政治)の6本ということなので、数よりも質で勝負ということの様…。
そんな中、印象に残ったのは、同大学で何十年も教えられている、トヨタ自動車と本田技研工業のケース。
トヨタ自動車の事例で言えば、『謙虚なリーダー像』。1980年代、日本の製造業が飛躍を遂げた際、当時の米国では「日本のメーカーが強いのは、日本人と米国人の労働者の能力の差だ」というのが一般的常識だった。ところが、日本企業を研究するにつれ、「米国人労働者の生産性が低いのは、米国企業の経営者、役員、管理職のリーダーシップにも問題があるからだ」とわかってきた。
そこで注目されたのが、日本人経営者の「謙虚さ」。グローバル企業では、経営者が決めたことを部下はそのとおりに実施するのが当たり前だったが、日本のメーカーの経営者は、下からの意見を聞いて一緒に考える。それが“学習する組織”を形成し、強さの源泉となったという分析だ。
本田技研工業の事例で言えば、ホンダの米国進出に『論理的な戦略』はなかったということ。1959年に米国進出後、15年で米国のオートバイ市場の43%を占めるまでに成長したホンダについて、ボストンコンサルティングは「いかに素晴らしい競争戦略で米国市場を制したか」を論理的に分析したが、それは結果論。ホンダは欧米流の合理的な戦略を描いて米国に進出したわけではないことがわかったとのこと。
そもそもホンダは、「資本主義の牙城、世界経済の中心である米国での成功なくして国際商品にはなりえない」という理由だけで米国進出を決めたのであって、米国の潜在市場がどの程度で、どのようなニーズがあるかなどを事前に把握していたわけではない。ホンダの成功は、机上で論理的に考えた戦略が功を奏したのではなく、“偶然や現場学習の積み重ね”によって達成されたものだったという分析だ。ただ、1981年にボストンコンサルティングが日本進出した際、欧米流の意図的戦略も必要だと考え、最初の顧客になったのもホンダだったというのも見逃してはいけない。
ということで、「書籍ランキング1位の理由」も「アマゾンのレビューが高評価」なのも納得の内容だったけど、多くの事例は、過去の日本が高く評価されているということ。ハーバードの学生たちが学んでいるのと同じように、私たちも「しっかり事例から学ばなくっちゃ!!」と考えさせられた一冊でした。

新聞の書籍広告に載っていた「テレビ番組で紹介、お茶の間でも大反響!」「書籍ランキング1位」のキャッチコピーに、「“ニッポンすごい系番組”の書籍版かな…?」と興味をそそられて読んでみた。
ちなみに私は、「“ニッポンすごい系番組”最近チョッピリ多すぎかも…?」と感じはするものの、それに対する批判のコメントを目にして、「目くじら立てて批判する…?」とちょっぴり引いちゃう様な輩です。
書籍の内容はタイトルの通り、ハーバードの授業で教材として扱われる日本や日本企業の事例の紹介を通して、日本や日本企業の人気の理由が丁寧、且つわかりやすく書かれている。事例自体は、私たち日本人が知っているものが多いけれど、それをハーバードの教授陣が「どんな視点でどう評価しているのか?」という観点で書かれているのが読みやすい。
ちなみに、学生たちが卒業までの2年間で学ぶ約500本の事例のうち、必修科目(2014年)で学ぶ日本の事例は、トヨタ自動車(テクノロジーとオペレーションマネジメント)、楽天(リーダーシップと組織行動)、全日本空輸(マーケティング)、本田技研工業(経営戦略)、日本航空(ファイナンス)、アベノミクス(ビジネス・政府・国際政治)の6本ということなので、数よりも質で勝負ということの様…。
そんな中、印象に残ったのは、同大学で何十年も教えられている、トヨタ自動車と本田技研工業のケース。
トヨタ自動車の事例で言えば、『謙虚なリーダー像』。1980年代、日本の製造業が飛躍を遂げた際、当時の米国では「日本のメーカーが強いのは、日本人と米国人の労働者の能力の差だ」というのが一般的常識だった。ところが、日本企業を研究するにつれ、「米国人労働者の生産性が低いのは、米国企業の経営者、役員、管理職のリーダーシップにも問題があるからだ」とわかってきた。
そこで注目されたのが、日本人経営者の「謙虚さ」。グローバル企業では、経営者が決めたことを部下はそのとおりに実施するのが当たり前だったが、日本のメーカーの経営者は、下からの意見を聞いて一緒に考える。それが“学習する組織”を形成し、強さの源泉となったという分析だ。
本田技研工業の事例で言えば、ホンダの米国進出に『論理的な戦略』はなかったということ。1959年に米国進出後、15年で米国のオートバイ市場の43%を占めるまでに成長したホンダについて、ボストンコンサルティングは「いかに素晴らしい競争戦略で米国市場を制したか」を論理的に分析したが、それは結果論。ホンダは欧米流の合理的な戦略を描いて米国に進出したわけではないことがわかったとのこと。
そもそもホンダは、「資本主義の牙城、世界経済の中心である米国での成功なくして国際商品にはなりえない」という理由だけで米国進出を決めたのであって、米国の潜在市場がどの程度で、どのようなニーズがあるかなどを事前に把握していたわけではない。ホンダの成功は、机上で論理的に考えた戦略が功を奏したのではなく、“偶然や現場学習の積み重ね”によって達成されたものだったという分析だ。ただ、1981年にボストンコンサルティングが日本進出した際、欧米流の意図的戦略も必要だと考え、最初の顧客になったのもホンダだったというのも見逃してはいけない。
ということで、「書籍ランキング1位の理由」も「アマゾンのレビューが高評価」なのも納得の内容だったけど、多くの事例は、過去の日本が高く評価されているということ。ハーバードの学生たちが学んでいるのと同じように、私たちも「しっかり事例から学ばなくっちゃ!!」と考えさせられた一冊でした。

2015年12月25日
専業主婦になりたい女たち
〜白河 桃子 著〜
ちょっと古い話になるけれど、2009年の内閣府発表の“家庭観”調査によれば「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」と答えた女性は、年代別で60代がトップ(40.2%)、次いで20代が第2位(36.3%)だったことは、私にとって衝撃だった。
そんなこともあり、学生と話をする際は、意識して学生たちの“家庭観”を聴く様にしてきた。実際に話を聴く中、「専業主婦志向の強い女子学生って多いかも…」「パートナーには、家にいて欲しいと思っている男子学生も少なくない…」と感じていたこともあり、本書を手にとってみたというわけ。
で、本書の内容だが、『専業主婦という安定ほど危険なものはない-!?』という帯に記された挑発的なコピーの根拠を、若い女性や専業主婦・独身男性等、様々な人へのインタビューや座談会の内容をモチーフに説明している。
セレブ妻(?)のインタビューでは、人も羨む様な専業主婦生活を送るには、「夫の所得が高ければOK」というのではなく、「夫のやさしさと理解が必要条件となること」が説明されている。
また、20代独身男性の座談会では、参加者の多くが配偶者の専業主婦生活を望んでいるにも関わらず、「それに必要な所得を明示されるや、自身の考えに現実味が無い」と気づかされる場面などが記されている。
さらには、離婚や夫のリストラ、給与カットといった結婚後のリスクに直面した際“専業主婦である女性が復職すること”が非常に難しいことを具体的な事例を示して説明し、「専業主婦は貧困女性を量産するシステムである」と結論付けている。
労働市場の現場で、具体的な事例に接してきた私としては、「確かにそうだよな~」と頷きつつ、「若い学生等に気付きを与えるには良い本だよな~」という評価を下させていただいた。
そんな中、最近、趣味化している他の読者のレビューを見ると…。
「兼業主婦や兼業家庭のリスクもある。どちらのリスクが大きいと考えるかは各個人次第」「統計データが足りず、リスクの定量評価がされていない」等、著者に対しての批判的なコメントが少なくないことも興味深い。
この話をややこしくしてしまう理由は、「母は専業主婦で、私を愛情いっぱいに育ててくれた。私たちも子供には同じようにしてあげたい」等、自分の両親や祖父母世代の「良妻賢母」像を家族のロールモデルとしている人たちが少なくないことにあるんじゃなかろうか。
産業構造や社会環境の変化などにより、好むと好まざるに関わらず“専業主婦は間違いなく減っていく”はず。世の中の変化を認識しつつ、将来を俯瞰する力をつけることが大切だと感じさせてくれた一冊だった。

ちょっと古い話になるけれど、2009年の内閣府発表の“家庭観”調査によれば「夫は外で働き、妻は家庭を守るべき」と答えた女性は、年代別で60代がトップ(40.2%)、次いで20代が第2位(36.3%)だったことは、私にとって衝撃だった。
そんなこともあり、学生と話をする際は、意識して学生たちの“家庭観”を聴く様にしてきた。実際に話を聴く中、「専業主婦志向の強い女子学生って多いかも…」「パートナーには、家にいて欲しいと思っている男子学生も少なくない…」と感じていたこともあり、本書を手にとってみたというわけ。
で、本書の内容だが、『専業主婦という安定ほど危険なものはない-!?』という帯に記された挑発的なコピーの根拠を、若い女性や専業主婦・独身男性等、様々な人へのインタビューや座談会の内容をモチーフに説明している。
セレブ妻(?)のインタビューでは、人も羨む様な専業主婦生活を送るには、「夫の所得が高ければOK」というのではなく、「夫のやさしさと理解が必要条件となること」が説明されている。
また、20代独身男性の座談会では、参加者の多くが配偶者の専業主婦生活を望んでいるにも関わらず、「それに必要な所得を明示されるや、自身の考えに現実味が無い」と気づかされる場面などが記されている。
さらには、離婚や夫のリストラ、給与カットといった結婚後のリスクに直面した際“専業主婦である女性が復職すること”が非常に難しいことを具体的な事例を示して説明し、「専業主婦は貧困女性を量産するシステムである」と結論付けている。
労働市場の現場で、具体的な事例に接してきた私としては、「確かにそうだよな~」と頷きつつ、「若い学生等に気付きを与えるには良い本だよな~」という評価を下させていただいた。
そんな中、最近、趣味化している他の読者のレビューを見ると…。
「兼業主婦や兼業家庭のリスクもある。どちらのリスクが大きいと考えるかは各個人次第」「統計データが足りず、リスクの定量評価がされていない」等、著者に対しての批判的なコメントが少なくないことも興味深い。
この話をややこしくしてしまう理由は、「母は専業主婦で、私を愛情いっぱいに育ててくれた。私たちも子供には同じようにしてあげたい」等、自分の両親や祖父母世代の「良妻賢母」像を家族のロールモデルとしている人たちが少なくないことにあるんじゃなかろうか。
産業構造や社会環境の変化などにより、好むと好まざるに関わらず“専業主婦は間違いなく減っていく”はず。世の中の変化を認識しつつ、将来を俯瞰する力をつけることが大切だと感じさせてくれた一冊だった。

2015年11月17日
僕が18年勤めた会社を辞めた時、後悔した12のこと
~和田 一郎 著~
タイトルに惹かれて手に取ったこの本は、こんな書き出しで始まる。
大学を卒業後、僕はひとつの会社に18年勤めた。
残念ながら、僕の会社人としての人生は失敗だった。
40歳くらいの時、高い壁にぶち当った。あろうことか四方をその高い壁に取り囲まれ、にっちもさっちもいかなくなった。
そして、42歳の時に、僕は会社を辞めた。
もちろん、周囲には前向きな退社であることを強調したけれど、本当のところは、どうしても会社に自分の居場所が見つからず、負けて、傷ついて、ボロボロになって、逃げるようにして辞めたのだった。
著者のプロフィールを読むと、「1959年3月生まれ。京都大学農学部卒、大手百貨店18年勤務、42歳で退職し、アンティーク・リサイクル着物の販売を始める」との記述が…。
おぉ、同級生(私は京大とは縁なしですが…)。且つ18年勤めた会社を辞め40代前半に起業したのも、周囲の人は前向き退職だと思っていたが、本人は会社に居場所が見つけられずに辞めたというのも私と同じだ。同世代で共通点が多そうな和田氏が、「会社を辞めた時にどんなことを後悔したのか?」に俄然興味が湧いた。
で、実際の12の後悔だが“入社初日から社長を目指して全力疾走すればよかった”“会社のカラーに染まりたくないなんて思わなければよかった”“ゴルフを始めてワインをたしなめればよかった”“信念なんてゴミ箱に捨てればよかった”等々…。“旧来型の大企業での処世術が身につけられなかったこと”の後悔が綴られており、読み進めていく中で、私の興味は少しずつ薄れていった。
アマゾンのレビューに“驚くほど同じ後悔”“重みのあるウンチク本”等々、高評価のコメントが多いのを見ると、まだまだ“旧来型の大企業”が生き残っているんだな〜と感じると共に、「果たして共感している人たちの会社が今後も人員削減することなく、社員を守り続けてくれるだろうか?」などといらん心配をしてしまった。
この本に共感できる人は、将来、会社が人員削減しないことを祈りつつ“在籍中の会社にしがみつく術”を体得する必要があると感じた。
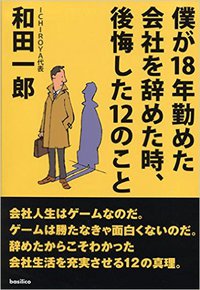
タイトルに惹かれて手に取ったこの本は、こんな書き出しで始まる。
大学を卒業後、僕はひとつの会社に18年勤めた。
残念ながら、僕の会社人としての人生は失敗だった。
40歳くらいの時、高い壁にぶち当った。あろうことか四方をその高い壁に取り囲まれ、にっちもさっちもいかなくなった。
そして、42歳の時に、僕は会社を辞めた。
もちろん、周囲には前向きな退社であることを強調したけれど、本当のところは、どうしても会社に自分の居場所が見つからず、負けて、傷ついて、ボロボロになって、逃げるようにして辞めたのだった。
著者のプロフィールを読むと、「1959年3月生まれ。京都大学農学部卒、大手百貨店18年勤務、42歳で退職し、アンティーク・リサイクル着物の販売を始める」との記述が…。
おぉ、同級生(私は京大とは縁なしですが…)。且つ18年勤めた会社を辞め40代前半に起業したのも、周囲の人は前向き退職だと思っていたが、本人は会社に居場所が見つけられずに辞めたというのも私と同じだ。同世代で共通点が多そうな和田氏が、「会社を辞めた時にどんなことを後悔したのか?」に俄然興味が湧いた。
で、実際の12の後悔だが“入社初日から社長を目指して全力疾走すればよかった”“会社のカラーに染まりたくないなんて思わなければよかった”“ゴルフを始めてワインをたしなめればよかった”“信念なんてゴミ箱に捨てればよかった”等々…。“旧来型の大企業での処世術が身につけられなかったこと”の後悔が綴られており、読み進めていく中で、私の興味は少しずつ薄れていった。
アマゾンのレビューに“驚くほど同じ後悔”“重みのあるウンチク本”等々、高評価のコメントが多いのを見ると、まだまだ“旧来型の大企業”が生き残っているんだな〜と感じると共に、「果たして共感している人たちの会社が今後も人員削減することなく、社員を守り続けてくれるだろうか?」などといらん心配をしてしまった。
この本に共感できる人は、将来、会社が人員削減しないことを祈りつつ“在籍中の会社にしがみつく術”を体得する必要があると感じた。
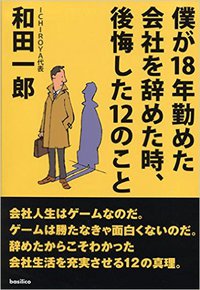
2015年09月19日
アドラーに学ぶ部下育成の心理学
〜 小倉 広 著〜
ここ数年、「自己啓発の源流」と言われブームの様相を呈しているアドラー心理学。遅ればせながら、最近、興味を持って情報収集しております。ということで、『アドラーに学ぶ部下育成の心理学』の備忘録を…。
アドラー心理学を一言で語るのであれば、『課題の分離』。例えば、アドラー心理学では、母親が子どもに「勉強しなさい」と強制するのは、人間関係のトラブルに繋がると考えます。何故なら「勉強をするか?否か?」は、母親の課題ではなく、子どもの課題だから…。人の課題に土足で踏み込むことが、人間関係トラブルの原因になるということです。
また、会社組織において、多くの上司は自身の部下が難易度の高い目標を達成した場合、「ほめる」という行動に出ますが、アドラー心理学では「ほめる」ことを否定します。「ほめる」ことは、上から目線であり、「相手の自律心を阻害し、依存型人間を作る」と考えるからです。
上司と部下の間柄であるにせよ、上下関係はあくまでも役割上のもの。いくら職位に上下があったとしても人としての尊厳は対等です。上司のほめ言葉には、仕事だけでなく、人間としての存在に関わる要素も含まれており、それを感じた部下はカチンと反応してしまう場合もあると考えるわけです。
ということで、この様なケースでは、上から目線で「ほめる」のではなく、「横から目線」の「勇気づけ」が重要だと説いています。
『自律と共生』を標榜する(?)私にとって、部下育成に際し「ほめない」「叱らない」「教えない」というアドラー心理学のスタンスは、す〜っと腹に落ちました。
まぁ、考え方と実践の差を埋めることは容易ではないのでしょうが…(苦笑

ここ数年、「自己啓発の源流」と言われブームの様相を呈しているアドラー心理学。遅ればせながら、最近、興味を持って情報収集しております。ということで、『アドラーに学ぶ部下育成の心理学』の備忘録を…。
アドラー心理学を一言で語るのであれば、『課題の分離』。例えば、アドラー心理学では、母親が子どもに「勉強しなさい」と強制するのは、人間関係のトラブルに繋がると考えます。何故なら「勉強をするか?否か?」は、母親の課題ではなく、子どもの課題だから…。人の課題に土足で踏み込むことが、人間関係トラブルの原因になるということです。
また、会社組織において、多くの上司は自身の部下が難易度の高い目標を達成した場合、「ほめる」という行動に出ますが、アドラー心理学では「ほめる」ことを否定します。「ほめる」ことは、上から目線であり、「相手の自律心を阻害し、依存型人間を作る」と考えるからです。
上司と部下の間柄であるにせよ、上下関係はあくまでも役割上のもの。いくら職位に上下があったとしても人としての尊厳は対等です。上司のほめ言葉には、仕事だけでなく、人間としての存在に関わる要素も含まれており、それを感じた部下はカチンと反応してしまう場合もあると考えるわけです。
ということで、この様なケースでは、上から目線で「ほめる」のではなく、「横から目線」の「勇気づけ」が重要だと説いています。
『自律と共生』を標榜する(?)私にとって、部下育成に際し「ほめない」「叱らない」「教えない」というアドラー心理学のスタンスは、す〜っと腹に落ちました。
まぁ、考え方と実践の差を埋めることは容易ではないのでしょうが…(苦笑

2015年04月29日
How Google Works
〜エリック・シュミット、ジョナサン・ローゼンバーグ 著〜
Googleの現会長エリック・シュミットと CEO 兼共同創業者ラリー・ペイジのアドバイザーのジョナサン・ローゼンバーグの共著で、Google の経営ポリシーが書かれた本。21世紀に、成長・進化し続ける組織づくりのヒントが、文化、戦略、人材、意思決定、コミュニケーション、イノベーションという章立てで書かれている。
Googleの成長と成功を支える核心は、「スマート・クリエイティブ」と呼ばれる新種の知識労働者であり、彼らを惹きつけ、力を発揮できる環境をつくることが、唯一の道であると結論づけている。
ここで言う「スマート・クリエイティブ」とは…。自分の“商売道具“を使いこなすための高度な専門知識を持ち、経験値も高い。分析力に優れている。ビジネス感覚に優れている等々…。要約すると、「ビジネスセンス、専門知識、クリエイティブなエネルギー、自分で手を動かして業務を遂行しようとする姿勢」が基本的要件にある人材と定義される。
そもそも「そんな人材をどんな風に集めてくればいいのか?」「採用できたとしても、どうすれば惹きつけ続けることが出来るのか?」等々、疑問満載ではあるが、以下に疑問解決のためのヒントとなる部分を備忘録という視点で残しておこうと思う。
“ワークライフ・バランス”について…
ワークライフ・バランス。先進的経営の尺度とされるが、優秀でやる気のある従業員は屈辱的に感じることもある要素だ。このフレーズ自体に問題がある。多くの人にとって、ワーク(仕事)はライフ(生活)の重要な一部であり、切り離せるものではない。最高の文化とは、おもしろい仕事がありすぎるので、職場でも自宅でも良い意味で働きすぎになるような、そしてそれを可能にするものだ。だからあなたがマネージャーなら「ワーク」の部分をいきいきと、充実したものにする責任がある。従業員が週40時間労働を守っているか、目を光らせるのが一番重要な仕事ではない。
最近、大学生の集団討論Workで“ワークライフ・バランス”についての考えを聴く機会が多い。学生達が、「仕事は苦痛なモノ」「仕事と生活(多くの場合、家庭)のバランスが必須」等のオンパレードに辟易している私としては、「我が意を得たり!」の内容だ。
会社を経営する人間として、従業員の労務管理を蔑ろにするつもりは全くないし、仕事人間になって欲しいとも思わないが、昨今の「仕事も生活もそこそこでいいよね」的なワークライフ・バランス論には首をかしげてしまう。
個々人がどんなバランスで仕事をするのかを考えることは大切だと思うし、マネージャーは、部下の意志を尊重しなくてはならないとも思っているが、そもそも仕事は楽しいもの(←私はそう思っている)だし、それを伝えることがマネージャーの重要な役割だと思う。
採用について…
経営者の場合、「あなたの仕事のうち一番重要なものは?」という問いへの正解は「採用」だ。あの日、ジョナサンを面接していたセルゲイは、真剣そのものだった。ジョナサンは当初、それは自分が幹部候補で、入社したらセルゲイと仕事をする機会が多くなるためかと思っていた。だが入社して、グーグルの経営者はすべての候補者を同じくらい真剣に面接することを知った。相手が駆け出しのソフトウェアエンジニアであろうが、幹部候補であろうが、グーグラーは最高の人材を確実に採用するために最大限の時間と労力をかける。
「う〜ん、全く異論なし!」。加えて、本書には…。
最も優秀な人材を採用し続けるには、産業界ではなく学術界のモデルを見習う必要があることを理解していた。大学は通常、教授に採用した人間を解雇しないので、専門委員会を立ち上げ、教員の採用や昇進の検討に膨大な時間を費やす。私たちが採用はヒエラルキー型ではなく、委員会によるピア型が好ましいと考えるのはこのためで、候補者の経歴が空きポストと合致するか否かにかかわらず、とにかく優秀な人材を採用することに集中する。
「大学教授級の人材を採用するわけじゃないんだから、通常の会社だったら、ヒエラルキー型の採用でいいんじゃない?」などという声が聞こえてきそうだが、採用した従業員には、中長期にわたって仕事のやりがいを感じられる環境を用意すべきだし、厳しい解雇規制がある現実を考えると、通常の採用の場面でも、大学教授を採用するのと同じくらいの労力をかけてもいいのではないかと思う。
また、情熱と知性、誠実さと独自の視点を持った理想の候補者を見つけ出し、獲得するかについて、発掘、面接、採用、報酬の4つのプロセスについても書かれている。グーグルでは、発掘時の作業を「絞りを広げる」と表現している。
絞りを変えることで、カメラの画像センサーに入る光量が変わる。採用担当者の多くは絞りを狭くする。いま求められている仕事をきちんとこなせそうな、特定の分野で特定の仕事に就いている特定の人の中から候補者を探そうとする。だが優秀な採用担当者は絞りを広げて、当たり前の候補者以外から適任者を探そうとする。
絞りを広げる方法の一つは、候補者の「軌道」を見ることだ。グーグルの元社員、ジャレド・スミスは最高の人材はキャリアの軌道が上向いていることが多い、と指摘する。その軌道を延長すると、大幅な成長が見込める。優秀で経験豊富でも、キャリアが頭打ちになった人はたくさんいる。こうした候補者については、どんな成果を期待できるかがはっきりしている(これはプラスだ)が、予想外ののびしろがない(これはマイナスだ)。年齢と軌道に相関はないことも指摘しておくべきだろう。また、自分で事業を経営している人、あるいは型にはまらないキャリアパスを歩んでいる人には、軌道という指針は当てはまらないこともある。
確かに採用の際、絞りを狭くしてしまうことはあるかもしれない。候補者の伸びしろを見る目が重要であることに気づかされる。併せて「自分自身のキャリアが頭打ちになっていないか?」と考え、反省!?次に面接について…。
ビジネスパーソンが磨くべき最も重要なスキルは面接スキルだ。
質の高い面接をするには、準備が必要だ。それはあなたが平社員であろうと、経営幹部であろうと変わらない。きちんとした面接をするには、自分の役割を理解し、候補者の履歴書を読み、そして一番重要なこと−何を聞くか−を考えなければならない。
面接の目的は、応募者とあたりさわりのない会話をすることではなく、相手の限界を確かめることだ。とはいえ、過剰なストレスをかけるのは避けよう。最高の面接は、友人同士の知的な会話のようなものだ。質問は間口の広い、複雑なものにしよう。正解が一つではないので、相手のモノの考え方や議論の組み立て方を見られる。
確かに。面接では、面接をする側も候補者に評価されていることを知っておく必要があるだろう。次に採用について…。
質を重視するからといって、採用プロセスに必ずしも時間がかかるわけではない。むしろ、これまで説明してきたグーグルの仕組みは、採用を迅速にするためのものだ。面接時間は30分。ひとりの候補者につき最大5回まで。面接官には、面接が終わったらすぐに採用担当者に合格か不合格かを知らせるように義務づけている。
採用には、絶対に侵してはならない黄金律がある。「採用の質を犠牲にしてまで埋めるべきポストはない」だ。速さか質か、という二者択一を迫られる場面は必ず出てくるが、必ず質を選ばなければならない。
現場のマネージャーから、「このままでは、仕事が回らない!」と懇願されると、「質を犠牲にしてでも…」という誘惑にかられることは少なくないが…。一緒に働く仲間を見つけるのだから、採用の質を犠牲にしてまで埋めるべきポストは無いことを再確認。最後に報酬について…。
首尾よくスマート・クリエイティブを獲得したら、今度は報酬を払わなければならない。ケタはずれの人材には、ケタ外れの報酬で報いるべきだ。
一方マネージャーは、破格の報酬を支払う対象を破格の働きをした人材に限定するよう心掛けるべきだ。相手はプロフェッショナルであり、リトルリーグのコーチをするのとはわけが違う。すべての人間には基本的人権があり、生まれながらにして平等だ。しかし言うまでもなく、それは全員が仕事において同じような能力があるという意味ではない。だから、あたかもそうであるかのように報酬を払ったり、昇進させたりするのはやめよう。
職位や入社年次にかかわらず、その人の成果に見合った報酬を支払うことが重要。この当たり前を適正に運用することが、経営に求められることをあらためて認識させられた。
ということで、従業員を惹きつけ、力を発揮できる環境をつくることの重要性を再認識させてくれた“How Google Works”でした。推敲ベタなため、長文の備忘録となってしまった…(苦笑

Googleの現会長エリック・シュミットと CEO 兼共同創業者ラリー・ペイジのアドバイザーのジョナサン・ローゼンバーグの共著で、Google の経営ポリシーが書かれた本。21世紀に、成長・進化し続ける組織づくりのヒントが、文化、戦略、人材、意思決定、コミュニケーション、イノベーションという章立てで書かれている。
Googleの成長と成功を支える核心は、「スマート・クリエイティブ」と呼ばれる新種の知識労働者であり、彼らを惹きつけ、力を発揮できる環境をつくることが、唯一の道であると結論づけている。
ここで言う「スマート・クリエイティブ」とは…。自分の“商売道具“を使いこなすための高度な専門知識を持ち、経験値も高い。分析力に優れている。ビジネス感覚に優れている等々…。要約すると、「ビジネスセンス、専門知識、クリエイティブなエネルギー、自分で手を動かして業務を遂行しようとする姿勢」が基本的要件にある人材と定義される。
そもそも「そんな人材をどんな風に集めてくればいいのか?」「採用できたとしても、どうすれば惹きつけ続けることが出来るのか?」等々、疑問満載ではあるが、以下に疑問解決のためのヒントとなる部分を備忘録という視点で残しておこうと思う。
“ワークライフ・バランス”について…
ワークライフ・バランス。先進的経営の尺度とされるが、優秀でやる気のある従業員は屈辱的に感じることもある要素だ。このフレーズ自体に問題がある。多くの人にとって、ワーク(仕事)はライフ(生活)の重要な一部であり、切り離せるものではない。最高の文化とは、おもしろい仕事がありすぎるので、職場でも自宅でも良い意味で働きすぎになるような、そしてそれを可能にするものだ。だからあなたがマネージャーなら「ワーク」の部分をいきいきと、充実したものにする責任がある。従業員が週40時間労働を守っているか、目を光らせるのが一番重要な仕事ではない。
最近、大学生の集団討論Workで“ワークライフ・バランス”についての考えを聴く機会が多い。学生達が、「仕事は苦痛なモノ」「仕事と生活(多くの場合、家庭)のバランスが必須」等のオンパレードに辟易している私としては、「我が意を得たり!」の内容だ。
会社を経営する人間として、従業員の労務管理を蔑ろにするつもりは全くないし、仕事人間になって欲しいとも思わないが、昨今の「仕事も生活もそこそこでいいよね」的なワークライフ・バランス論には首をかしげてしまう。
個々人がどんなバランスで仕事をするのかを考えることは大切だと思うし、マネージャーは、部下の意志を尊重しなくてはならないとも思っているが、そもそも仕事は楽しいもの(←私はそう思っている)だし、それを伝えることがマネージャーの重要な役割だと思う。
採用について…
経営者の場合、「あなたの仕事のうち一番重要なものは?」という問いへの正解は「採用」だ。あの日、ジョナサンを面接していたセルゲイは、真剣そのものだった。ジョナサンは当初、それは自分が幹部候補で、入社したらセルゲイと仕事をする機会が多くなるためかと思っていた。だが入社して、グーグルの経営者はすべての候補者を同じくらい真剣に面接することを知った。相手が駆け出しのソフトウェアエンジニアであろうが、幹部候補であろうが、グーグラーは最高の人材を確実に採用するために最大限の時間と労力をかける。
「う〜ん、全く異論なし!」。加えて、本書には…。
最も優秀な人材を採用し続けるには、産業界ではなく学術界のモデルを見習う必要があることを理解していた。大学は通常、教授に採用した人間を解雇しないので、専門委員会を立ち上げ、教員の採用や昇進の検討に膨大な時間を費やす。私たちが採用はヒエラルキー型ではなく、委員会によるピア型が好ましいと考えるのはこのためで、候補者の経歴が空きポストと合致するか否かにかかわらず、とにかく優秀な人材を採用することに集中する。
「大学教授級の人材を採用するわけじゃないんだから、通常の会社だったら、ヒエラルキー型の採用でいいんじゃない?」などという声が聞こえてきそうだが、採用した従業員には、中長期にわたって仕事のやりがいを感じられる環境を用意すべきだし、厳しい解雇規制がある現実を考えると、通常の採用の場面でも、大学教授を採用するのと同じくらいの労力をかけてもいいのではないかと思う。
また、情熱と知性、誠実さと独自の視点を持った理想の候補者を見つけ出し、獲得するかについて、発掘、面接、採用、報酬の4つのプロセスについても書かれている。グーグルでは、発掘時の作業を「絞りを広げる」と表現している。
絞りを変えることで、カメラの画像センサーに入る光量が変わる。採用担当者の多くは絞りを狭くする。いま求められている仕事をきちんとこなせそうな、特定の分野で特定の仕事に就いている特定の人の中から候補者を探そうとする。だが優秀な採用担当者は絞りを広げて、当たり前の候補者以外から適任者を探そうとする。
絞りを広げる方法の一つは、候補者の「軌道」を見ることだ。グーグルの元社員、ジャレド・スミスは最高の人材はキャリアの軌道が上向いていることが多い、と指摘する。その軌道を延長すると、大幅な成長が見込める。優秀で経験豊富でも、キャリアが頭打ちになった人はたくさんいる。こうした候補者については、どんな成果を期待できるかがはっきりしている(これはプラスだ)が、予想外ののびしろがない(これはマイナスだ)。年齢と軌道に相関はないことも指摘しておくべきだろう。また、自分で事業を経営している人、あるいは型にはまらないキャリアパスを歩んでいる人には、軌道という指針は当てはまらないこともある。
確かに採用の際、絞りを狭くしてしまうことはあるかもしれない。候補者の伸びしろを見る目が重要であることに気づかされる。併せて「自分自身のキャリアが頭打ちになっていないか?」と考え、反省!?次に面接について…。
ビジネスパーソンが磨くべき最も重要なスキルは面接スキルだ。
質の高い面接をするには、準備が必要だ。それはあなたが平社員であろうと、経営幹部であろうと変わらない。きちんとした面接をするには、自分の役割を理解し、候補者の履歴書を読み、そして一番重要なこと−何を聞くか−を考えなければならない。
面接の目的は、応募者とあたりさわりのない会話をすることではなく、相手の限界を確かめることだ。とはいえ、過剰なストレスをかけるのは避けよう。最高の面接は、友人同士の知的な会話のようなものだ。質問は間口の広い、複雑なものにしよう。正解が一つではないので、相手のモノの考え方や議論の組み立て方を見られる。
確かに。面接では、面接をする側も候補者に評価されていることを知っておく必要があるだろう。次に採用について…。
質を重視するからといって、採用プロセスに必ずしも時間がかかるわけではない。むしろ、これまで説明してきたグーグルの仕組みは、採用を迅速にするためのものだ。面接時間は30分。ひとりの候補者につき最大5回まで。面接官には、面接が終わったらすぐに採用担当者に合格か不合格かを知らせるように義務づけている。
採用には、絶対に侵してはならない黄金律がある。「採用の質を犠牲にしてまで埋めるべきポストはない」だ。速さか質か、という二者択一を迫られる場面は必ず出てくるが、必ず質を選ばなければならない。
現場のマネージャーから、「このままでは、仕事が回らない!」と懇願されると、「質を犠牲にしてでも…」という誘惑にかられることは少なくないが…。一緒に働く仲間を見つけるのだから、採用の質を犠牲にしてまで埋めるべきポストは無いことを再確認。最後に報酬について…。
首尾よくスマート・クリエイティブを獲得したら、今度は報酬を払わなければならない。ケタはずれの人材には、ケタ外れの報酬で報いるべきだ。
一方マネージャーは、破格の報酬を支払う対象を破格の働きをした人材に限定するよう心掛けるべきだ。相手はプロフェッショナルであり、リトルリーグのコーチをするのとはわけが違う。すべての人間には基本的人権があり、生まれながらにして平等だ。しかし言うまでもなく、それは全員が仕事において同じような能力があるという意味ではない。だから、あたかもそうであるかのように報酬を払ったり、昇進させたりするのはやめよう。
職位や入社年次にかかわらず、その人の成果に見合った報酬を支払うことが重要。この当たり前を適正に運用することが、経営に求められることをあらためて認識させられた。
ということで、従業員を惹きつけ、力を発揮できる環境をつくることの重要性を再認識させてくれた“How Google Works”でした。推敲ベタなため、長文の備忘録となってしまった…(苦笑

2014年12月22日
正社員消滅時代の人事改革
〜今野浩一郎 著〜
戦後40年以上にわたり世界の注目を集めてきた日本的雇用慣行(終身雇用制・年功制・企業内組合…)が崩壊しつつある(崩壊した?)と言われて久しいが、次なる人事管理のモデルは見えてこない。
そんな状況の中、『正社員消滅時代の人事改革』というタイトルと帯に記載のあった『「制約社員」を活かす会社になる』という言葉に誘われて読んでみた。
全体は、8章で構成されており、大まかには『現状の人事管理』~『今後の予測』~『新たな人事管理の仕組み』の3つのフェーズに分けて以下の様なことが書かれている。
先ずは、『現状の人事管理』について。高度経済成長期には、「作れば売れる」市場環境を前提に、組織メンバーの管理は、明確な数値目標とプロセス管理をすればよかったが、市場の不確実性が増す中、最終成果に関わる目標に変化させる必要性が生まれてきた。結果として、昨今は自営業に似て裁量的になる仕事の進め方が要求される様になってきており、「任せるから責任を取りなさい」に変化してきている。
また、『今後の予測』につては、「制約社員」が多数派になり、企業は「制約社員」の増加を前提とした人事管理が必要になってくる。ここで言う「制約社員」とは、「無制約社員(イメージは、かつて総合職と呼ばれてきた男性中心の基幹的社員)」が会社の指示や業務上の都合に合わせて場所・時間・仕事を柔軟に変えることが出来るのに比べ、何らかの制約を持つ社員のことを指す。
正規・非正規社員の別に関わらず、多くの女性は家事や出産・育児等の時間制約があるし、男性だって親の介護の時間や場所の制約がある、定年後に再雇用された高齢社員は時間や場所の制約・障害者は労働機能面での制約がある等々、「制約の無い社員の方が少ないんじゃないの?」ということだ…。
とここまでは、すべて納得なのだが…。一番肝心な『新たな人事管理の仕組み』については、いろいろな角度からいろいろな案が提示されてはいるものの、「なるほど~!」と納得できるような新たな仕組の提案はなかった。
そんな中、筆者は著書の最後で「人事管理の新しいモデル、それも世界に発信できるようなモデルを作り上げたいと意気込んでみたが、本書を書き終えてみると、それには到底及ばないものになってしまったようだ」と正直な感想で結んでいるのが良心的?
そもそも万能な人事管理の処方など存在するはずもないワケで…。「現在の日本の人事管理の課題についてはわかりやすく整理されている良書かな?」というのが読了後の感想かな…?!

戦後40年以上にわたり世界の注目を集めてきた日本的雇用慣行(終身雇用制・年功制・企業内組合…)が崩壊しつつある(崩壊した?)と言われて久しいが、次なる人事管理のモデルは見えてこない。
そんな状況の中、『正社員消滅時代の人事改革』というタイトルと帯に記載のあった『「制約社員」を活かす会社になる』という言葉に誘われて読んでみた。
全体は、8章で構成されており、大まかには『現状の人事管理』~『今後の予測』~『新たな人事管理の仕組み』の3つのフェーズに分けて以下の様なことが書かれている。
先ずは、『現状の人事管理』について。高度経済成長期には、「作れば売れる」市場環境を前提に、組織メンバーの管理は、明確な数値目標とプロセス管理をすればよかったが、市場の不確実性が増す中、最終成果に関わる目標に変化させる必要性が生まれてきた。結果として、昨今は自営業に似て裁量的になる仕事の進め方が要求される様になってきており、「任せるから責任を取りなさい」に変化してきている。
また、『今後の予測』につては、「制約社員」が多数派になり、企業は「制約社員」の増加を前提とした人事管理が必要になってくる。ここで言う「制約社員」とは、「無制約社員(イメージは、かつて総合職と呼ばれてきた男性中心の基幹的社員)」が会社の指示や業務上の都合に合わせて場所・時間・仕事を柔軟に変えることが出来るのに比べ、何らかの制約を持つ社員のことを指す。
正規・非正規社員の別に関わらず、多くの女性は家事や出産・育児等の時間制約があるし、男性だって親の介護の時間や場所の制約がある、定年後に再雇用された高齢社員は時間や場所の制約・障害者は労働機能面での制約がある等々、「制約の無い社員の方が少ないんじゃないの?」ということだ…。
とここまでは、すべて納得なのだが…。一番肝心な『新たな人事管理の仕組み』については、いろいろな角度からいろいろな案が提示されてはいるものの、「なるほど~!」と納得できるような新たな仕組の提案はなかった。
そんな中、筆者は著書の最後で「人事管理の新しいモデル、それも世界に発信できるようなモデルを作り上げたいと意気込んでみたが、本書を書き終えてみると、それには到底及ばないものになってしまったようだ」と正直な感想で結んでいるのが良心的?
そもそも万能な人事管理の処方など存在するはずもないワケで…。「現在の日本の人事管理の課題についてはわかりやすく整理されている良書かな?」というのが読了後の感想かな…?!

2014年07月09日
トヨタ対VW 2020年の覇者を目指す最強企業
~中西孝樹 著~
トヨタとVW。クルマ好きの私としては、大量生産のメーカーのイメージが強いこの2社は、興味の対象になる存在ではなかったのだが…。そんな私ですら「自動車業界、何かが変わりはじめている?!」と感じる中、タイトルに惹かれて読んでみた。
トヨタとVW、創業家支配の自動車メーカーという共通点はあるものの、経営に対するスタンスが全く違うことに驚かされる。
トヨタの経営思想はじっくりと同じ価値観を共有できる文化や仕組みを育てるという信念にあり、まさに日本のモノづくり、人づくりのビジネスモデルとなる会社。
一方のVWは、戦略的に企業買収を進め、マーケティング、デザイン、ブランドを含むソフト面のマネジメント能力を駆使することにより、製品の平準化や同一化のリスク管理を行い差別化の維持が出来る会社であり、私の概念にある自動車会社の枠をはるかに超えている。
読んでいるうちに、「この本、単に『トヨタ対VW』というんじゃなく、2020年に日本の製造業のビジネスモデルは生き残れるのかを占う本なんじゃない?」なんて考えてしまった。
まっ、僕は日本人なので、「2020年には、トヨタが自動車業界の覇権を握ってくれてるコト」を期待しております…!?
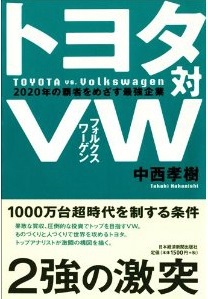
トヨタとVW。クルマ好きの私としては、大量生産のメーカーのイメージが強いこの2社は、興味の対象になる存在ではなかったのだが…。そんな私ですら「自動車業界、何かが変わりはじめている?!」と感じる中、タイトルに惹かれて読んでみた。
トヨタとVW、創業家支配の自動車メーカーという共通点はあるものの、経営に対するスタンスが全く違うことに驚かされる。
トヨタの経営思想はじっくりと同じ価値観を共有できる文化や仕組みを育てるという信念にあり、まさに日本のモノづくり、人づくりのビジネスモデルとなる会社。
一方のVWは、戦略的に企業買収を進め、マーケティング、デザイン、ブランドを含むソフト面のマネジメント能力を駆使することにより、製品の平準化や同一化のリスク管理を行い差別化の維持が出来る会社であり、私の概念にある自動車会社の枠をはるかに超えている。
読んでいるうちに、「この本、単に『トヨタ対VW』というんじゃなく、2020年に日本の製造業のビジネスモデルは生き残れるのかを占う本なんじゃない?」なんて考えてしまった。
まっ、僕は日本人なので、「2020年には、トヨタが自動車業界の覇権を握ってくれてるコト」を期待しております…!?
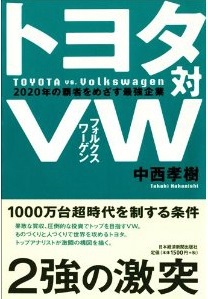
2014年06月18日
社長は少しバカがいい
~エステー株式会社 会長 鈴木喬 著~
著者は、消臭力等で有名なエステー会長の鈴木喬氏。1年程前に買って積み重ねておいた本のうちの1冊。テレビ出演でべらんめー調で受け答えする氏に興味を持って読んでみた。
書かれている内容は、いたってまともというよりも、経営指南書として参考になることがてんこ盛り。トップは何を考え、どう振る舞えばいいのかを考えさせられる。
特に、東日本大震災時の判断についての件(くだり)なんかを読ませていただくと、「この人、すげ~! 会社が公器であることが体に染みついているんだ~?!」などと感服してしまう。「創業家出身の社長だから、こんな風に出来るんだ!?」なんて、陰口をたたく人もいるかもしれないけれど、僕はこんな経営トップを支持しちゃう!!
内容は濃いけれど、2~3時間あれば読めるし、とっても読みやすい。居酒屋でたまたまとなりに座ったおじさんから、「すっごくいい話、聴けた~!!」と満足しながら帰路につく時に似た読後感…。
「タイトルに、偽り大あり!?」の本でした…(笑

著者は、消臭力等で有名なエステー会長の鈴木喬氏。1年程前に買って積み重ねておいた本のうちの1冊。テレビ出演でべらんめー調で受け答えする氏に興味を持って読んでみた。
書かれている内容は、いたってまともというよりも、経営指南書として参考になることがてんこ盛り。トップは何を考え、どう振る舞えばいいのかを考えさせられる。
特に、東日本大震災時の判断についての件(くだり)なんかを読ませていただくと、「この人、すげ~! 会社が公器であることが体に染みついているんだ~?!」などと感服してしまう。「創業家出身の社長だから、こんな風に出来るんだ!?」なんて、陰口をたたく人もいるかもしれないけれど、僕はこんな経営トップを支持しちゃう!!
内容は濃いけれど、2~3時間あれば読めるし、とっても読みやすい。居酒屋でたまたまとなりに座ったおじさんから、「すっごくいい話、聴けた~!!」と満足しながら帰路につく時に似た読後感…。
「タイトルに、偽り大あり!?」の本でした…(笑

2014年06月13日
年収は「住むところ」で決まる
~エンリコ・モレッティ 著~
「イノベーション都市」の高卒者は、「旧来型製造業都市」の大卒者より、稼いでいる!?の帯に釣られて読んでみた。
現代の製造業がそうであるように、多くの産業では、グローバル化と技術の進歩によって雇用の大半は低賃金の国に出ていってしまうと考えるのが一般的。少なくとも私はそう思っていた。
にも関わらず、アメリカ経済の新たな成長エンジンであるイノベーション産業では、グローバル化と技術の進歩が雇用を増やす原動力になっており、結果的に成長する都市の高卒者の給料は衰退する都市の大卒者の給料よりも高くなるという現象が起きている。
イノベーションに取り組む企業にとっては、人件費やオフィス賃料等のビジネスをおこなうためのコストが格段に高くても、『生産性の高い働き手』が集まっている土地に拠点を置き続けるのが合理的であるというのがその理由だ。
では、『生産性の高い働き手』が集まる要因は…?
著者は、超一流の交響楽団や美術館などの文化施設を擁するクリーブランドやライフスタイルの面では魅力的なイタリアが新しい経済基盤を築くことが出来ていないことを例に出し、『魅力的な町というだけでは地域経済を支えられないことを示している。ものごとの原因と結果を混同しては、本質的な課題は見えてこない。大切なのは、どうすれば結果(雇用創出)を導き出すための効果的な対策が立てられるかだ。
雇用創出というと、行政の産業政策や補助金による企業誘致等が真っ先に思い浮かぶが…。
著者は、『地方政府は、その土地の強みと専門性を活用することを考えなくてはならない。その際、雇用創出のために税金を投入するのは、市場の失敗が放置しがたく、しかも自律的な産業集積地を築ける可能性が十分にあると判断できる場合に限るべき。』と警鐘を鳴らしている。また、『どの産業が勝者になるかを前もって予測することは、政策決定者にとって容易ではない。』とも…。
『私たちの仕事の環境と社会の基本的骨格は、グローバル化とローカル化という、21世紀の2つの潮流によって根本から様変わりしようとしている』という言葉で結ばれているこの本、示唆に富む良書だった。

「イノベーション都市」の高卒者は、「旧来型製造業都市」の大卒者より、稼いでいる!?の帯に釣られて読んでみた。
現代の製造業がそうであるように、多くの産業では、グローバル化と技術の進歩によって雇用の大半は低賃金の国に出ていってしまうと考えるのが一般的。少なくとも私はそう思っていた。
にも関わらず、アメリカ経済の新たな成長エンジンであるイノベーション産業では、グローバル化と技術の進歩が雇用を増やす原動力になっており、結果的に成長する都市の高卒者の給料は衰退する都市の大卒者の給料よりも高くなるという現象が起きている。
イノベーションに取り組む企業にとっては、人件費やオフィス賃料等のビジネスをおこなうためのコストが格段に高くても、『生産性の高い働き手』が集まっている土地に拠点を置き続けるのが合理的であるというのがその理由だ。
では、『生産性の高い働き手』が集まる要因は…?
著者は、超一流の交響楽団や美術館などの文化施設を擁するクリーブランドやライフスタイルの面では魅力的なイタリアが新しい経済基盤を築くことが出来ていないことを例に出し、『魅力的な町というだけでは地域経済を支えられないことを示している。ものごとの原因と結果を混同しては、本質的な課題は見えてこない。大切なのは、どうすれば結果(雇用創出)を導き出すための効果的な対策が立てられるかだ。
雇用創出というと、行政の産業政策や補助金による企業誘致等が真っ先に思い浮かぶが…。
著者は、『地方政府は、その土地の強みと専門性を活用することを考えなくてはならない。その際、雇用創出のために税金を投入するのは、市場の失敗が放置しがたく、しかも自律的な産業集積地を築ける可能性が十分にあると判断できる場合に限るべき。』と警鐘を鳴らしている。また、『どの産業が勝者になるかを前もって予測することは、政策決定者にとって容易ではない。』とも…。
『私たちの仕事の環境と社会の基本的骨格は、グローバル化とローカル化という、21世紀の2つの潮流によって根本から様変わりしようとしている』という言葉で結ばれているこの本、示唆に富む良書だった。

2014年05月21日
ワーク・シフト
〜孤独と貧困から自由になる働き方の未来図<2025> リンダ・グラットン著〜
「ビジネス書大賞2013大賞受賞、全世代必読!「働き方」の決定版」という帯に惹かれて読んでみた。
大雑把に言えば、「テクノロジーの発展」「グローバル化」「人口構成の変化と長寿化」「個人、家族、社会の変化」「エネルギーと環境問題」という5つの変化によって、2025年の職業人は、地球規模で「下流民」と「自由民」に二極分化する。「自由民」になるためには、ワーク・シフトが必要ですよ!という本。
で、どんな風にシフトするかというと…
1. ゼネラリスト→連続スペシャリスト
2. 孤独な競争→みんなでイノベーション
3. 金儲けと消費→価値ある経験
へのシフトが必要だとのこと。
う〜ん、リンダ・グラットン氏の予測どおりになるかは分からないが、好むと好まざるとにかかわらず、10年後の働き方が現状と大きく変わり、二極分化する方向に進んでいることは間違いなさそうだ。
競争社会自体は否定しないけれど、「自由民」になれる人がほんの一握りになってしまうかもしれない世の中が、果たしていいのだろうか?という疑問も沸いてくる。まぁ、グラットン氏は、そういう未来の是非を論じているんではなく「その中でどう生きるのかを考えましょう!」と言っているのだが…。
そんな中、備忘録がわりに琴線に触れた箇所を抜粋しておこう。
私にとって重要なことがあなたにとって重要だとは限らないし、私が望む働き方があなたの望む働き方と同じだとも限らない。私たちは、一人ひとりが自分なりの働き方の未来を築いていかなくてはならない。
私たち一人ひとりにとっての課題は、明確な意図をもって職業生活を送ることだ。自分がどういう人間なのか、人生でなにを大切にしたいのかをはっきり意識し、自分の前にある選択肢と、それぞれの道を選んだ場合に待っている結果について、深く理解しなくてはならない。
「普通」でありたいと思うのではなく、ほかの人とは違う一人の個人として自分の生き方に責任をもち、自分を確立していく覚悟が必要だ。
うん、私たちの働き方が変化していく中、“自分の人生に責任を持つ覚悟”が必要なことだけは、間違いなさそうだ。

「ビジネス書大賞2013大賞受賞、全世代必読!「働き方」の決定版」という帯に惹かれて読んでみた。
大雑把に言えば、「テクノロジーの発展」「グローバル化」「人口構成の変化と長寿化」「個人、家族、社会の変化」「エネルギーと環境問題」という5つの変化によって、2025年の職業人は、地球規模で「下流民」と「自由民」に二極分化する。「自由民」になるためには、ワーク・シフトが必要ですよ!という本。
で、どんな風にシフトするかというと…
1. ゼネラリスト→連続スペシャリスト
2. 孤独な競争→みんなでイノベーション
3. 金儲けと消費→価値ある経験
へのシフトが必要だとのこと。
う〜ん、リンダ・グラットン氏の予測どおりになるかは分からないが、好むと好まざるとにかかわらず、10年後の働き方が現状と大きく変わり、二極分化する方向に進んでいることは間違いなさそうだ。
競争社会自体は否定しないけれど、「自由民」になれる人がほんの一握りになってしまうかもしれない世の中が、果たしていいのだろうか?という疑問も沸いてくる。まぁ、グラットン氏は、そういう未来の是非を論じているんではなく「その中でどう生きるのかを考えましょう!」と言っているのだが…。
そんな中、備忘録がわりに琴線に触れた箇所を抜粋しておこう。
私にとって重要なことがあなたにとって重要だとは限らないし、私が望む働き方があなたの望む働き方と同じだとも限らない。私たちは、一人ひとりが自分なりの働き方の未来を築いていかなくてはならない。
私たち一人ひとりにとっての課題は、明確な意図をもって職業生活を送ることだ。自分がどういう人間なのか、人生でなにを大切にしたいのかをはっきり意識し、自分の前にある選択肢と、それぞれの道を選んだ場合に待っている結果について、深く理解しなくてはならない。
「普通」でありたいと思うのではなく、ほかの人とは違う一人の個人として自分の生き方に責任をもち、自分を確立していく覚悟が必要だ。
うん、私たちの働き方が変化していく中、“自分の人生に責任を持つ覚悟”が必要なことだけは、間違いなさそうだ。

2014年05月07日
20歳のときに知っておきたかったこと
〜スタンフォード大学 集中講義 ティナ・シーリグ著〜
著者のティナ・シーリグ氏は、マイケル・サンデル教授で有名なNHK「白熱教室」海外版の第2弾の特別講義をしていたので、ご存じの方も多いのでは…。
この本、著者の息子ジョシュが16歳の誕生日を迎えた際、「大学進学まであと2年しかない。自分自身が実家を出たとき、社会に出たときに知っていればよかったと思うことを伝えておきたい」と思ったことをリスト化した内容をベースに書いたとのこと。
著書についての大雑把な印象は、ジョン・D・クランボルツ博士の計画的偶発性理論(Planned Happenstance Theory)の著者の実体験版という感じかな〜。自身の体験に則り、自身の言葉で語ってくれているので、決してクランボルツ博士の二番煎じなんて感じはしないけれど…。
そんな中、特に記憶に留めておきたいのは、第10章:新しい目で世界を見つめてみよう。
種明かしをすると、これまでの章のタイトルはすべて、「あなた自身に許可を与える」としてもよかったのです。わたしが伝えたかったのは、常識を疑う許可、世の中を新鮮な目で見る許可、実験する許可、失敗する許可、自分自身で進路を描く許可、そして自分自身の限界を試す許可を、あなた自身に与えてください、ということなのですから。じつは、これこそ、わたしが20歳のとき、あるいは30、40のときに知っておきたかったことであり、50歳のいまも、たえず思い出さなくてはいけないことなのです。
多くの人は、(もちろん、私も…)意識しないままに他者のつくったルールを破らないことを第一義に物事の判断をしてしまう傾向がある様に思う。
自分の人生の主人公は自分自身。この本を読んで、『自分自身に許可を与える』といういたってシンプルで当たり前のコトが、如何に大切かということを再認識させられた。
スティーブ・ジョブズの2005年のスタンフォード大学卒業式でのスピーチ(伝説のスピーチ)なんかが事例として取り上げられているのも、ちょっぴりうれしい本でした。

著者のティナ・シーリグ氏は、マイケル・サンデル教授で有名なNHK「白熱教室」海外版の第2弾の特別講義をしていたので、ご存じの方も多いのでは…。
この本、著者の息子ジョシュが16歳の誕生日を迎えた際、「大学進学まであと2年しかない。自分自身が実家を出たとき、社会に出たときに知っていればよかったと思うことを伝えておきたい」と思ったことをリスト化した内容をベースに書いたとのこと。
著書についての大雑把な印象は、ジョン・D・クランボルツ博士の計画的偶発性理論(Planned Happenstance Theory)の著者の実体験版という感じかな〜。自身の体験に則り、自身の言葉で語ってくれているので、決してクランボルツ博士の二番煎じなんて感じはしないけれど…。
そんな中、特に記憶に留めておきたいのは、第10章:新しい目で世界を見つめてみよう。
種明かしをすると、これまでの章のタイトルはすべて、「あなた自身に許可を与える」としてもよかったのです。わたしが伝えたかったのは、常識を疑う許可、世の中を新鮮な目で見る許可、実験する許可、失敗する許可、自分自身で進路を描く許可、そして自分自身の限界を試す許可を、あなた自身に与えてください、ということなのですから。じつは、これこそ、わたしが20歳のとき、あるいは30、40のときに知っておきたかったことであり、50歳のいまも、たえず思い出さなくてはいけないことなのです。
多くの人は、(もちろん、私も…)意識しないままに他者のつくったルールを破らないことを第一義に物事の判断をしてしまう傾向がある様に思う。
自分の人生の主人公は自分自身。この本を読んで、『自分自身に許可を与える』といういたってシンプルで当たり前のコトが、如何に大切かということを再認識させられた。
スティーブ・ジョブズの2005年のスタンフォード大学卒業式でのスピーチ(伝説のスピーチ)なんかが事例として取り上げられているのも、ちょっぴりうれしい本でした。

2013年10月12日
LEAN IN(リーン・イン)
~シェリル・サンドバーグ 著~
FaceBookの最高執行責任者 シェリル・サンドバーグ氏の著書。サブタイトルの「女性、仕事、リーダーへの意欲」等の記述を見ると、ジェンダー論なんかが綴られているんじゃないかと思う人もいるかもしれないけれど…。
氏の主張は、女性が社会で力を発揮しようとする際に『社会に築かれた女性の外の障壁』があることは認識しつつも、もっと大切なことは「『自分の内なる障壁』を打破することだ!」というものだ。
ここで言う『内なる障壁』とは、自信のなさから、一歩踏み出すべき時に引いてしまうこと。家事や育児や夫の世話のために多くの時間を確保しようとして、自分に対する期待を低めに設定してしまう傾向のことを指している。
多くの女性が、思い切って二歩も三歩も踏み出すことによって、現在の慣習も変化し、多くの人に道が拓けるだろうと言っている。
私自身は、性別に限らず「リスクをとること、成長に賭けること、チャレンジすることは素晴らしい!」と考えているし、私の知人には、そんな女性が沢山いるので、氏の主張はすっごく腑に落ちてしまう。
とはいえ、どのへんが腑に落ちたのかを上手く伝えられる自信は無いし、たぶん「上手く伝わっていないだろうな~」と思う。
ということで、「こんな書評じゃ、どんな本なのか全くわからないじゃないか?!」と思う人にこそ、読んでもらいたい一冊でした。

FaceBookの最高執行責任者 シェリル・サンドバーグ氏の著書。サブタイトルの「女性、仕事、リーダーへの意欲」等の記述を見ると、ジェンダー論なんかが綴られているんじゃないかと思う人もいるかもしれないけれど…。
氏の主張は、女性が社会で力を発揮しようとする際に『社会に築かれた女性の外の障壁』があることは認識しつつも、もっと大切なことは「『自分の内なる障壁』を打破することだ!」というものだ。
ここで言う『内なる障壁』とは、自信のなさから、一歩踏み出すべき時に引いてしまうこと。家事や育児や夫の世話のために多くの時間を確保しようとして、自分に対する期待を低めに設定してしまう傾向のことを指している。
多くの女性が、思い切って二歩も三歩も踏み出すことによって、現在の慣習も変化し、多くの人に道が拓けるだろうと言っている。
私自身は、性別に限らず「リスクをとること、成長に賭けること、チャレンジすることは素晴らしい!」と考えているし、私の知人には、そんな女性が沢山いるので、氏の主張はすっごく腑に落ちてしまう。
とはいえ、どのへんが腑に落ちたのかを上手く伝えられる自信は無いし、たぶん「上手く伝わっていないだろうな~」と思う。
ということで、「こんな書評じゃ、どんな本なのか全くわからないじゃないか?!」と思う人にこそ、読んでもらいたい一冊でした。
2013年09月10日
創造するミドル
~金井 壽宏 米倉誠一郎 沼上幹 編 ~
本書は、第1部「創造的なミドルのインタビュー」と第2部「3名の著者それぞれの提言」で構成されている。
第1部は、企業に所属しながらも、自分らしく生き生きと仕事を創造している11人のミドルへのインタビューとなっており、それなりに魅力は感じるのだけれど…。1994年初版ということで、「事例が少々古いかな~」というのが素直な感想。
第2部の3名の著者のミドル論は、各々の個性が出ており、すっごく楽しめる。米倉先生は、大企業では独立心や企業者精神は発揮できないと思い込んでいる人に、「そんなこと無いよ!」との直接的なメッセージが綴られているし、金井先生は、キャリアアンカーとキャリアエンジンが自身のキャリアを醸成する際の両輪であることをクルマにたとえて、わかりやすく説明してくれている。
米倉先生・金井先生だったら、「きっとこんな風に言ってくれるんだろうな~!」という私の期待通りの提言で気持ちいい。
そんな中、特に印象に残ったのは、沼上先生の、以下の2つの提言。
第1は、会社も社会も学校も非決定論的な世界(どこかに<答え>が隠されていたり、誰かが<答え>を持っているわけではない)であるはずなのに、決定論的世界観が蔓延している。自らの眼前に非決定論的な世界を切り拓けるように<答え>をあてにする態度は、さっぱり捨て去り「主体的な世界構築のスキルを身につけよう!」という提言。
第2は、企業の研修に関わる者へのメッセージで、「個の自立性獲得」や「企業の活性化」は、【社員の意識転換】によって行うものではなく、【社員の知識開発】によって行う必要があるという提言。「自立が大切!」と何百回も唱えるよりも、知識開発により足りない部分を客観視する方が、よほど現実的だと、何度も頷いてしまった。
沼上先生の著書を読むのが、はじめてだったこともあるのだろうが、強い感銘を受けた。
『創造するミドル』というタイトルから、ミドルに向けた書籍の様に感じ取られてしまうかも知れないが、ミドルはもちろん、企業で働き始めた若者や就活をはじめる学生にもオススメの一冊だ。

本書は、第1部「創造的なミドルのインタビュー」と第2部「3名の著者それぞれの提言」で構成されている。
第1部は、企業に所属しながらも、自分らしく生き生きと仕事を創造している11人のミドルへのインタビューとなっており、それなりに魅力は感じるのだけれど…。1994年初版ということで、「事例が少々古いかな~」というのが素直な感想。
第2部の3名の著者のミドル論は、各々の個性が出ており、すっごく楽しめる。米倉先生は、大企業では独立心や企業者精神は発揮できないと思い込んでいる人に、「そんなこと無いよ!」との直接的なメッセージが綴られているし、金井先生は、キャリアアンカーとキャリアエンジンが自身のキャリアを醸成する際の両輪であることをクルマにたとえて、わかりやすく説明してくれている。
米倉先生・金井先生だったら、「きっとこんな風に言ってくれるんだろうな~!」という私の期待通りの提言で気持ちいい。
そんな中、特に印象に残ったのは、沼上先生の、以下の2つの提言。
第1は、会社も社会も学校も非決定論的な世界(どこかに<答え>が隠されていたり、誰かが<答え>を持っているわけではない)であるはずなのに、決定論的世界観が蔓延している。自らの眼前に非決定論的な世界を切り拓けるように<答え>をあてにする態度は、さっぱり捨て去り「主体的な世界構築のスキルを身につけよう!」という提言。
第2は、企業の研修に関わる者へのメッセージで、「個の自立性獲得」や「企業の活性化」は、【社員の意識転換】によって行うものではなく、【社員の知識開発】によって行う必要があるという提言。「自立が大切!」と何百回も唱えるよりも、知識開発により足りない部分を客観視する方が、よほど現実的だと、何度も頷いてしまった。
沼上先生の著書を読むのが、はじめてだったこともあるのだろうが、強い感銘を受けた。
『創造するミドル』というタイトルから、ミドルに向けた書籍の様に感じ取られてしまうかも知れないが、ミドルはもちろん、企業で働き始めた若者や就活をはじめる学生にもオススメの一冊だ。





