2013年07月28日
スクールカースト
~鈴木翔 著~
スクールカーストとは、主に中学・高等学校のクラス内で発生するヒエラルキーのことで、いじめや不登校の原因になるとも言われてきた。とはいえ、「社会問題化したこともなく、曖昧でよくわからないので、検証してみよう」という内容。
概要は、こんな感じ…。
サンプル(大学生:10名、教師:4名+α)は少ないものの、生徒・教員への聞き取りからは、生徒・教員共にスクールカーストの存在を認めており、現象についての認識も一致している。
ただ、スクールカーストについての受け取り方については、生徒が「スクールカーストは、『権力』で出来ており、自分の力で変えるコトは難しい」と考えているのに対し、今回の聞き取りに応じた教師は「スクールカーストは、『能力』を軸としたヒエラルキーだ」と考えており、大きな違いがある。
ここで教師の言う『能力』とは、「生きる力」や「コミュニケーション能力」「リーダー性」のこと。教師は、スクールカーストの上層にいる生徒は「悪ガキ」であろうが「ギャル」であろうが、社会に出てもまあまあうまくいくだろうが、スクールカーストの下層にいる人は社会に出てからちゃんと就職できるか不安なのだという。
で、教師は「これから社会に出て行く生徒は、自分の『能力』の足りない部分を「努力」や「やる気」で改善していく必要がある」と考え、足りない部分を客観視できるスクールカーストを肯定的に捉えているというワケ(サンプルの教師数が+αとなっているのは、スクールカーストを問題視し、途中辞退の教員もいたため)。
そんな中、アマゾンのレビュー等を見ると、「サンプルが少なすぎる」「学術的な根拠に欠ける」等のコメントも多いのも事実なのだけど…。
スクールカーストの存在については、多くの人が感じてはいるモノの、今まではっきりした定義もなく学術的に検証しようという動きがなかったのも事実。中学・高等学校での体験は、キャリア形成に大きな影響を与えるワケで、それを「ささいなこと」として片付けるのではなく、「重要なトピック」として課題提案したことには「大きな意義があるんじゃないの…!?」と感じさせてくれる本でした。

スクールカーストとは、主に中学・高等学校のクラス内で発生するヒエラルキーのことで、いじめや不登校の原因になるとも言われてきた。とはいえ、「社会問題化したこともなく、曖昧でよくわからないので、検証してみよう」という内容。
概要は、こんな感じ…。
サンプル(大学生:10名、教師:4名+α)は少ないものの、生徒・教員への聞き取りからは、生徒・教員共にスクールカーストの存在を認めており、現象についての認識も一致している。
ただ、スクールカーストについての受け取り方については、生徒が「スクールカーストは、『権力』で出来ており、自分の力で変えるコトは難しい」と考えているのに対し、今回の聞き取りに応じた教師は「スクールカーストは、『能力』を軸としたヒエラルキーだ」と考えており、大きな違いがある。
ここで教師の言う『能力』とは、「生きる力」や「コミュニケーション能力」「リーダー性」のこと。教師は、スクールカーストの上層にいる生徒は「悪ガキ」であろうが「ギャル」であろうが、社会に出てもまあまあうまくいくだろうが、スクールカーストの下層にいる人は社会に出てからちゃんと就職できるか不安なのだという。
で、教師は「これから社会に出て行く生徒は、自分の『能力』の足りない部分を「努力」や「やる気」で改善していく必要がある」と考え、足りない部分を客観視できるスクールカーストを肯定的に捉えているというワケ(サンプルの教師数が+αとなっているのは、スクールカーストを問題視し、途中辞退の教員もいたため)。
そんな中、アマゾンのレビュー等を見ると、「サンプルが少なすぎる」「学術的な根拠に欠ける」等のコメントも多いのも事実なのだけど…。
スクールカーストの存在については、多くの人が感じてはいるモノの、今まではっきりした定義もなく学術的に検証しようという動きがなかったのも事実。中学・高等学校での体験は、キャリア形成に大きな影響を与えるワケで、それを「ささいなこと」として片付けるのではなく、「重要なトピック」として課題提案したことには「大きな意義があるんじゃないの…!?」と感じさせてくれる本でした。

2013年07月20日
法と経済で読みとく雇用の世界
~大内信哉・川口大司 著~
法学者(労働法)の大内信哉 氏と経済学者の川口大司 氏の共著で、『雇用』を労働法と経済学の両方の視点から抉っている。なんて書くと、学者の書いた小難しい本の様に感じるかもしれないが…
テーマは、採用内定取り消し・解雇規制・最低賃金・非正規社員・サービス残業・男女間格差・障害者雇用・服務規律違反・高齢者雇用・労働組合…等々。各章冒頭の導入部分に、当該テーマをモチーフにしたストーリー(これが、結構おもしろい)が書かれており、「う~ん、こんな話あるある!」とテーマに現実味を持たせ、労働法をより身近なモノに感じさせてくれる。
「労働者の賃金はいくらが妥当か?」「どれだけの労働者が企業に雇われるのか?」といった労働問題は、"労働市場での取引"であることを前提に語られるべきだと思っている私にとっては、「う~ん、なるほど…」と思える内容ばかりだった。
また、法学者と経済学者の共著というのに、どこからどこまでをお二人のうち、どちらが書いているのかがわからないのも驚きだ。「学者ってすごいな~」と感心してしまった。こういうのを『学際的な書籍』とでも言うんだろうな~!?
「エコノミストが選ぶ経済図書ベスト10」第1位(『日本経済新聞』2012年12月30日付)に選ばれたというのも納得の一冊でした。
お勧めです。

法学者(労働法)の大内信哉 氏と経済学者の川口大司 氏の共著で、『雇用』を労働法と経済学の両方の視点から抉っている。なんて書くと、学者の書いた小難しい本の様に感じるかもしれないが…
テーマは、採用内定取り消し・解雇規制・最低賃金・非正規社員・サービス残業・男女間格差・障害者雇用・服務規律違反・高齢者雇用・労働組合…等々。各章冒頭の導入部分に、当該テーマをモチーフにしたストーリー(これが、結構おもしろい)が書かれており、「う~ん、こんな話あるある!」とテーマに現実味を持たせ、労働法をより身近なモノに感じさせてくれる。
「労働者の賃金はいくらが妥当か?」「どれだけの労働者が企業に雇われるのか?」といった労働問題は、"労働市場での取引"であることを前提に語られるべきだと思っている私にとっては、「う~ん、なるほど…」と思える内容ばかりだった。
また、法学者と経済学者の共著というのに、どこからどこまでをお二人のうち、どちらが書いているのかがわからないのも驚きだ。「学者ってすごいな~」と感心してしまった。こういうのを『学際的な書籍』とでも言うんだろうな~!?
「エコノミストが選ぶ経済図書ベスト10」第1位(『日本経済新聞』2012年12月30日付)に選ばれたというのも納得の一冊でした。
お勧めです。
2012年08月19日
これが論点!就職問題
~児美川孝一郎 編~
法政大学の児美川先生が、「シューカツ論壇」の“俯瞰図”を示そうと、『中央公論』『Voice』などの論壇誌、『週刊東洋経済』『エコノミスト』などの経済誌から、重要論文・対談22本を収録・編集した書籍。
論文・対談の切り口は、『若者のシュウカツ』。とはいえ、著者、自らもコメントしているように、『若者のシュウカツ』を突き詰めていくと、結果的に「戦後の日本社会のあり方や労働市場全体の課題を問うことになる」というわけです。
22本の論文・対談は、学生よりの視点・学校側の視点・産業界からの視点・採用システムに関する視点などなど、当然のことながら、立ち位置も方向性も様々…。また、著者自身も、敢えて「どのベクトルが正しい」とか「どの話が妥当だ」とかいった価値的な判断を示していない。
ということで、読者である私たち自身が、自分の考えを整理するには、良い本じゃないでしょうか。
私としては、「いまどきの若者は、けしからん!」なんて言っている輩に読んでもらった上で、「読後感を聞いてみたいな~」と思った本でした。

法政大学の児美川先生が、「シューカツ論壇」の“俯瞰図”を示そうと、『中央公論』『Voice』などの論壇誌、『週刊東洋経済』『エコノミスト』などの経済誌から、重要論文・対談22本を収録・編集した書籍。
論文・対談の切り口は、『若者のシュウカツ』。とはいえ、著者、自らもコメントしているように、『若者のシュウカツ』を突き詰めていくと、結果的に「戦後の日本社会のあり方や労働市場全体の課題を問うことになる」というわけです。
22本の論文・対談は、学生よりの視点・学校側の視点・産業界からの視点・採用システムに関する視点などなど、当然のことながら、立ち位置も方向性も様々…。また、著者自身も、敢えて「どのベクトルが正しい」とか「どの話が妥当だ」とかいった価値的な判断を示していない。
ということで、読者である私たち自身が、自分の考えを整理するには、良い本じゃないでしょうか。
私としては、「いまどきの若者は、けしからん!」なんて言っている輩に読んでもらった上で、「読後感を聞いてみたいな~」と思った本でした。

2012年05月03日
就活難民にならないための 大学生活30のルール
~常見陽平 著~
常見氏の本は、「就活格差」に続いて2冊目。「就活格差」が、昨今の就活の状況を客観的、且つ正確に表現していたことに好感を持てたこともあって読んでみた。
「大学生活が充実していた人は就活が上手くいく」ということを、『30のルール』と『学生の体験談』を交えて表現している。
最近は、メディアや親の影響もあって、低学年時から就活に対する不安で萎縮している学生は少なくない。ということで、私自身も、大学のキャリア関連の授業では「就活の心配なんかするよりも、有意義な学生生活をすることが大切」と言っているので、常見氏の主張には大賛成。
「大学進学を考えている高校生や大学低学年時の学生に読んで欲しいな~」と思った。
敢えて、欠点を探すとしたら、最初から最後まで、正論が山谷なく綴られているので、単調に感じちゃうことだろうか?最近、常見氏がラジオ番組に出てはじけているのを聴いたので、「そんなはじけた感じが出せたら、もっとおもしろいかも…」とも感した。
最近、読了後、SNSの書籍レビューで、同じ本を読んだ若者がどんな感じ方をしているかを知るのを楽しみにしているのだが、今回は、どんな評価が…?
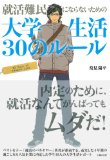
常見氏の本は、「就活格差」に続いて2冊目。「就活格差」が、昨今の就活の状況を客観的、且つ正確に表現していたことに好感を持てたこともあって読んでみた。
「大学生活が充実していた人は就活が上手くいく」ということを、『30のルール』と『学生の体験談』を交えて表現している。
最近は、メディアや親の影響もあって、低学年時から就活に対する不安で萎縮している学生は少なくない。ということで、私自身も、大学のキャリア関連の授業では「就活の心配なんかするよりも、有意義な学生生活をすることが大切」と言っているので、常見氏の主張には大賛成。
「大学進学を考えている高校生や大学低学年時の学生に読んで欲しいな~」と思った。
敢えて、欠点を探すとしたら、最初から最後まで、正論が山谷なく綴られているので、単調に感じちゃうことだろうか?最近、常見氏がラジオ番組に出てはじけているのを聴いたので、「そんなはじけた感じが出せたら、もっとおもしろいかも…」とも感した。
最近、読了後、SNSの書籍レビューで、同じ本を読んだ若者がどんな感じ方をしているかを知るのを楽しみにしているのだが、今回は、どんな評価が…?
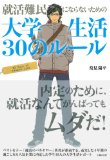
2012年03月31日
若者はなぜ「就職」できなくなったのか?
~生き抜くために知っておくべきこと 児美川孝一郎 著~
法政大学キャリアデザイン学部の先生が書いた本。昨今の労働市場変化(すべての大学生が正社員になれないのは構造的な問題、等)とそれに伴い大学などで流行しているキャリア教育・キャリア支援の問題点が、丁寧且つ客観的に書かれている。
私自身、大学でキャリア関連の授業を担当したり、学生のキャリア相談に応じる中、児美川教授と同じ様な問題を感じていることもあり、当事者である若者や親はもちろんのこと、「キャリア支援やキャリア教育に携わる人たちも是非、読んで欲しい!」と思える内容の本だった。
そんな中、児美川教授の考えに異を唱えるつもりはないが、大学で授業を担当しつつ、企業の経営者として学生たちを見させていただいている立場から、ひとこと…。
<大学講師として感じるコト>
私が、担当するキャリア関連の授業で意識しているのは、「1.労働市場の事実」「2.充実した学生生活が、今後の人生に彩りを添える」の2点を伝えること。その2つをキッチリ受けとめてくれる学生であれば、有意義な人生を送れるだろうと考えて授業に臨んでいる。
とはいえ、上記の2つはキャリア関連授業だけで、効果を発揮するとは思えない(寂しいけれど…)。じゃ~、どうすれば…
私自身は、大学の教・職員が、「今までより少しだけ世の中の変化や目の前の学生の将来に興味を持つこと」によって、救われる学生も増えるのではないかとも思うのだが、どうだろう(労働市場の構造自体は変えられないにしても、児美川教授が感じている課題を解決するのは、コチラの方がずっと有効かも…)。
<経営者として感じるコト>
今年も大学生の選考に携わっているのだが、応募者と接する中、在学時に一般常識として伝えておかなくてはならないこと(一般常識を、キャリア教育と言う人もいるかもしれないが…)も多いのではないかと感じる。
一番感じるのは、現在の学生(日本)を取り巻く環境を客観視出来ていない学生が圧倒的に多いということ。昨今、若者の非正規社員化・年金の世代間格差等を指して若者を『社会的弱者』と位置づける論調が多く聞かれるが、当事者である多くの若者からは、そんな危機感は感じ取れない(危機感を煽るつもりはないけれど、私は、現状に満足し問題意識を持たない人からは新しいモノは生まれないと思っている)。
茹蛙状態の学生を見ていると、10年後の彼らが、『1990年代に大手企業をリストラされた企業戦士たちが「こんなハズじゃなかった」と肩を落としていたこと』の二の舞にならなければいいと願ってしまう自分がいる。
1990年代に日本型雇用慣行は終わったと言われているけれど、日本全体が茹蛙状態に陥っているのかもしれない…。等々、いろんなコトを考えさせてくれる本でした。

法政大学キャリアデザイン学部の先生が書いた本。昨今の労働市場変化(すべての大学生が正社員になれないのは構造的な問題、等)とそれに伴い大学などで流行しているキャリア教育・キャリア支援の問題点が、丁寧且つ客観的に書かれている。
私自身、大学でキャリア関連の授業を担当したり、学生のキャリア相談に応じる中、児美川教授と同じ様な問題を感じていることもあり、当事者である若者や親はもちろんのこと、「キャリア支援やキャリア教育に携わる人たちも是非、読んで欲しい!」と思える内容の本だった。
そんな中、児美川教授の考えに異を唱えるつもりはないが、大学で授業を担当しつつ、企業の経営者として学生たちを見させていただいている立場から、ひとこと…。
<大学講師として感じるコト>
私が、担当するキャリア関連の授業で意識しているのは、「1.労働市場の事実」「2.充実した学生生活が、今後の人生に彩りを添える」の2点を伝えること。その2つをキッチリ受けとめてくれる学生であれば、有意義な人生を送れるだろうと考えて授業に臨んでいる。
とはいえ、上記の2つはキャリア関連授業だけで、効果を発揮するとは思えない(寂しいけれど…)。じゃ~、どうすれば…
私自身は、大学の教・職員が、「今までより少しだけ世の中の変化や目の前の学生の将来に興味を持つこと」によって、救われる学生も増えるのではないかとも思うのだが、どうだろう(労働市場の構造自体は変えられないにしても、児美川教授が感じている課題を解決するのは、コチラの方がずっと有効かも…)。
<経営者として感じるコト>
今年も大学生の選考に携わっているのだが、応募者と接する中、在学時に一般常識として伝えておかなくてはならないこと(一般常識を、キャリア教育と言う人もいるかもしれないが…)も多いのではないかと感じる。
一番感じるのは、現在の学生(日本)を取り巻く環境を客観視出来ていない学生が圧倒的に多いということ。昨今、若者の非正規社員化・年金の世代間格差等を指して若者を『社会的弱者』と位置づける論調が多く聞かれるが、当事者である多くの若者からは、そんな危機感は感じ取れない(危機感を煽るつもりはないけれど、私は、現状に満足し問題意識を持たない人からは新しいモノは生まれないと思っている)。
茹蛙状態の学生を見ていると、10年後の彼らが、『1990年代に大手企業をリストラされた企業戦士たちが「こんなハズじゃなかった」と肩を落としていたこと』の二の舞にならなければいいと願ってしまう自分がいる。
1990年代に日本型雇用慣行は終わったと言われているけれど、日本全体が茹蛙状態に陥っているのかもしれない…。等々、いろんなコトを考えさせてくれる本でした。

2012年03月10日
坂の上の坂
~藤原和博 著~
成熟期を迎えた日本では、坂を登りきっても(60歳定年?)まだ坂は続く。じゃ~、どうするのか?40~50代のみなさんは、55歳までに55のコトをはじめよう!というお話し。
リクルート出身~義務教育初の民間校長で有名な藤原和博流のキャリアデザイン論ですね。で、私自身も「坂の上の坂世代」ということで、藤原氏がどんな提案をしてくれるのかを楽しみに読んでみた。
う~ん、坂の上の坂でどんなことが起こるのか、至極まっとうな状況把握と対策が書かれているので、「仕事中心のサラリーマン生活を送っていて、このままでいいのかな~」と不安に思っている坂の上世代が、今後の生き方を整理するのにはよいのかもしれないが…
藤原氏の書籍を読むのは初めてで、55の提案はどんなものなのか?と期待して読み始めただけに、あまりにも正論すぎて少々拍子抜けしてしまった。
けど、mixiのレビューは意外と高評価。多くの日本人が、坂の上の坂に不安を感じているコトの表れなのだろうか…。

成熟期を迎えた日本では、坂を登りきっても(60歳定年?)まだ坂は続く。じゃ~、どうするのか?40~50代のみなさんは、55歳までに55のコトをはじめよう!というお話し。
リクルート出身~義務教育初の民間校長で有名な藤原和博流のキャリアデザイン論ですね。で、私自身も「坂の上の坂世代」ということで、藤原氏がどんな提案をしてくれるのかを楽しみに読んでみた。
う~ん、坂の上の坂でどんなことが起こるのか、至極まっとうな状況把握と対策が書かれているので、「仕事中心のサラリーマン生活を送っていて、このままでいいのかな~」と不安に思っている坂の上世代が、今後の生き方を整理するのにはよいのかもしれないが…
藤原氏の書籍を読むのは初めてで、55の提案はどんなものなのか?と期待して読み始めただけに、あまりにも正論すぎて少々拍子抜けしてしまった。
けど、mixiのレビューは意外と高評価。多くの日本人が、坂の上の坂に不安を感じているコトの表れなのだろうか…。

2012年03月06日
さよなら!僕らのソニー
~立石泰則 著~
『Sunday Nikkei、現代の「経営者像」を考える』で、『スティーブ・ジョブズⅠ・Ⅱ』との比較で紹介されていたので読んでみました。
何せ、僕たち世代にとって「SONYは特別な企業!」でしたし、ジョブズが目標としていた企業でもありましたから…。
ということで、井深・盛田両氏が掲げた経営方針を今一度確認してみると…
一.不当なる儲け主義を廃し、あくまで内容の充実、実質的な活動に重点を置き、いたずらに規模の拡大を追わず
一.経営規模としては、むしろ小なるを望み、大経営企業の大経営なるがために進み得ざる分野に、技術の進路と経営活動を期する。
一.従業員は厳選されたる、かなり小員数をもって構成し、形式的階級制を避け、一切の秩序を実力本位、人格主義の上に置き個人の技術を最大限に発揮せしむ
と、現代でも十分に通用する素晴らしい経営方針だと感心してしまいます。
その一方で、立石氏の出井氏へのインタビュー…
「創業者は創業者というだけで、求心力を持つ。ソニーでは大賀さんは創業者ではないけれど、井深さんや盛田さんと創業期から仕事をしていたから創業グループという意味では同等の存在だと思う。でも僕は、違う。だから、数字(業績)が大切になる。(創業者ではない)僕は数字を出すことで求心力を持つ。数字がすべてなんだ」
そのとき、「サラリーマン経営者ですからね」と水を向けると、出井氏は「サラリーマン経営者なんておかしな言い方だよ。僕は『プロフェッショナル経営者』だと思っている」と力強く言い放った。
との記載がありました。
う~ん、インタビューの全体像が見えないので、立石氏の話の全部を鵜呑みにするのはフェアーではないと思いますが、仮に立石氏の話が正しいのであれば、出井氏のコメントは、設立時の経営方針とは、大きなギャップがあると言わざるを得ないと思います。
また、僕自身は『数値(業績)は経営者として必要条件』でしかないと思いますし、出井氏が『創業者というだけで求心力が持てる』と考えているのだとしたら、既にスタートの時点からボタンの掛け違いがあった様な気すらしてしまいます。
ストリンガー氏についても、辛辣な記載が並んでいますが、先日、4月にCEO退任との発表がありましたので、ここでは「省略」ということで…
最終章あたりで、「僕らのソニー、復活のシナリオ!」などという記述があることを期待してたのですが、残念ながら、タイトルどおりの終わり方となっていました。
今更ながらですが、ビジョナリーカンパニーであり続けることのたいへんさを、痛感させられた一冊でした。

『Sunday Nikkei、現代の「経営者像」を考える』で、『スティーブ・ジョブズⅠ・Ⅱ』との比較で紹介されていたので読んでみました。
何せ、僕たち世代にとって「SONYは特別な企業!」でしたし、ジョブズが目標としていた企業でもありましたから…。
ということで、井深・盛田両氏が掲げた経営方針を今一度確認してみると…
一.不当なる儲け主義を廃し、あくまで内容の充実、実質的な活動に重点を置き、いたずらに規模の拡大を追わず
一.経営規模としては、むしろ小なるを望み、大経営企業の大経営なるがために進み得ざる分野に、技術の進路と経営活動を期する。
一.従業員は厳選されたる、かなり小員数をもって構成し、形式的階級制を避け、一切の秩序を実力本位、人格主義の上に置き個人の技術を最大限に発揮せしむ
と、現代でも十分に通用する素晴らしい経営方針だと感心してしまいます。
その一方で、立石氏の出井氏へのインタビュー…
「創業者は創業者というだけで、求心力を持つ。ソニーでは大賀さんは創業者ではないけれど、井深さんや盛田さんと創業期から仕事をしていたから創業グループという意味では同等の存在だと思う。でも僕は、違う。だから、数字(業績)が大切になる。(創業者ではない)僕は数字を出すことで求心力を持つ。数字がすべてなんだ」
そのとき、「サラリーマン経営者ですからね」と水を向けると、出井氏は「サラリーマン経営者なんておかしな言い方だよ。僕は『プロフェッショナル経営者』だと思っている」と力強く言い放った。
との記載がありました。
う~ん、インタビューの全体像が見えないので、立石氏の話の全部を鵜呑みにするのはフェアーではないと思いますが、仮に立石氏の話が正しいのであれば、出井氏のコメントは、設立時の経営方針とは、大きなギャップがあると言わざるを得ないと思います。
また、僕自身は『数値(業績)は経営者として必要条件』でしかないと思いますし、出井氏が『創業者というだけで求心力が持てる』と考えているのだとしたら、既にスタートの時点からボタンの掛け違いがあった様な気すらしてしまいます。
ストリンガー氏についても、辛辣な記載が並んでいますが、先日、4月にCEO退任との発表がありましたので、ここでは「省略」ということで…
最終章あたりで、「僕らのソニー、復活のシナリオ!」などという記述があることを期待してたのですが、残念ながら、タイトルどおりの終わり方となっていました。
今更ながらですが、ビジョナリーカンパニーであり続けることのたいへんさを、痛感させられた一冊でした。

2012年03月03日
絶望の国の幸福な若者たち
~古市憲寿 著~
最近、マスメディアでもよく見かける古市憲寿氏の著書。世代間格差が問題となっている現代、当事者である古市氏(26歳)が「どんな思いでいるのか?」を知りたくて、読んでみた。
古市氏の著書だけを読んで、「若者のことが理解できた」と思うこと自体が、ピントはずれであることはわかっているつもりだけど、好き嫌いは別にして、例えば…
経済成長の恩恵を受けられた世代を「自分たちとは違う」と見なし、勝手に自分たちで身の丈にあった幸せを見つけ、仲間たちと村々している。何かを勝ち得て自分を着飾るような時代と見切りをつけて、小さなコミュニティ内のささやかな相互承認とともに生きていく。
等、「僕も彼らと同じ時代を生きていたとすれば、こんな気持ちになるのかも…」と思える事象が盛りだくさんだった。
また…
ツイッターやソーシャルメデイアが「社会を変える」ツールになるとも思えない。それらが個人の承認欲求を満たしやすいメディアであることを考えると、機能はむしろ逆だ。ツイッターで適当に社会派っぽいことをつぶやいて、フォロワーたちに賞賛されて、たくさんツイートされることだけで、多くの人はタダ満足してしまう。
実利実益から離れたコミュニティーで提供されるぬくぬくとした相互承認のおかげで、若者たちは社会の様々な問題を解決せずとも生きていけるようになる。
う~ん、SNSの拡大が若者を内向きにさせるかもしれないというのも、説得力あるな~。
ただ…
一人一人がより幸せに生きられるなら「日本」は守られるべきだが、そうでないならば別に「日本」にこだわる必要はない。
と言い切られてしまうと、かなりの違和感を感じるのも事実!う~ん、じゃ~どうする。
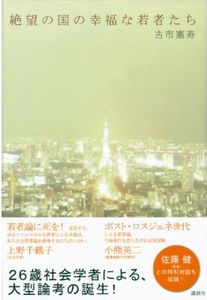
最近、マスメディアでもよく見かける古市憲寿氏の著書。世代間格差が問題となっている現代、当事者である古市氏(26歳)が「どんな思いでいるのか?」を知りたくて、読んでみた。
古市氏の著書だけを読んで、「若者のことが理解できた」と思うこと自体が、ピントはずれであることはわかっているつもりだけど、好き嫌いは別にして、例えば…
経済成長の恩恵を受けられた世代を「自分たちとは違う」と見なし、勝手に自分たちで身の丈にあった幸せを見つけ、仲間たちと村々している。何かを勝ち得て自分を着飾るような時代と見切りをつけて、小さなコミュニティ内のささやかな相互承認とともに生きていく。
等、「僕も彼らと同じ時代を生きていたとすれば、こんな気持ちになるのかも…」と思える事象が盛りだくさんだった。
また…
ツイッターやソーシャルメデイアが「社会を変える」ツールになるとも思えない。それらが個人の承認欲求を満たしやすいメディアであることを考えると、機能はむしろ逆だ。ツイッターで適当に社会派っぽいことをつぶやいて、フォロワーたちに賞賛されて、たくさんツイートされることだけで、多くの人はタダ満足してしまう。
実利実益から離れたコミュニティーで提供されるぬくぬくとした相互承認のおかげで、若者たちは社会の様々な問題を解決せずとも生きていけるようになる。
う~ん、SNSの拡大が若者を内向きにさせるかもしれないというのも、説得力あるな~。
ただ…
一人一人がより幸せに生きられるなら「日本」は守られるべきだが、そうでないならば別に「日本」にこだわる必要はない。
と言い切られてしまうと、かなりの違和感を感じるのも事実!う~ん、じゃ~どうする。
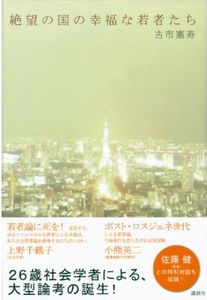
2011年09月19日
われ日本海の橋とならん
~加藤嘉一 著~
現在、日本にとって最も関係の深い国のひとつのハズなのに、もうひとつ内情が見えてこない中国。そんな中国について、内部に踏み込んだものしかわからない中国人とのつきあいかた、中国の政治のしくみ、ビジネスのやりかた、中国人の生活等について明快に解説してくれます。
まぁ、この本一冊で、中国の現状や中国人の考え方が理解できると思っているわけじゃないけれど、私自身、今までメディアから伝えられていた以外の見方が出来る様になったことだけは確か!
そのこと自体も、すごく貴重だけど、それ以上に、まだ20代の加藤氏が『実際に中国で体を張って生きている感じがビンビン伝わってくる』のが心地よく、一気に読破してしまいました。
「今どきの若者にも、こんなヤツがいるんだ~!」と、かなり刺激を受けてしまいました。
今の日本に必要なのは、こんな若者(いや、自身の反省も込めて、老若男女)なんじゃないでしょうか!

現在、日本にとって最も関係の深い国のひとつのハズなのに、もうひとつ内情が見えてこない中国。そんな中国について、内部に踏み込んだものしかわからない中国人とのつきあいかた、中国の政治のしくみ、ビジネスのやりかた、中国人の生活等について明快に解説してくれます。
まぁ、この本一冊で、中国の現状や中国人の考え方が理解できると思っているわけじゃないけれど、私自身、今までメディアから伝えられていた以外の見方が出来る様になったことだけは確か!
そのこと自体も、すごく貴重だけど、それ以上に、まだ20代の加藤氏が『実際に中国で体を張って生きている感じがビンビン伝わってくる』のが心地よく、一気に読破してしまいました。
「今どきの若者にも、こんなヤツがいるんだ~!」と、かなり刺激を受けてしまいました。
今の日本に必要なのは、こんな若者(いや、自身の反省も込めて、老若男女)なんじゃないでしょうか!

2011年08月21日
カンブリア宮殿 就職ガイド
~村上龍×73人の経済人~
本の帯に、『就職を考えるすべての学生、若者、転職者のヒントとして活用してもらうために作られた』と書いてあったので、読んでみた。
本の内容は、村上龍の経済番組『カンブリア宮殿』にゲストとして登場した企業トップのインタビューを業態別に分けて紹介したもの。登場するのは、素晴らしい経営者ばかりなので、確かに読者の心に訴えかける様な名言もたくさん載っているんだけど…。
如何せん、おひとり3P(鏡を含めば4P)の扱いじゃ~なぁ…。登場する経営者の素晴らしさを確認するには、別な情報源で深掘りしていく必要がありそうだ。
『就職ガイド』というよりも、『日本の経営者73人の金言集』って感じかな…
ということで、★2つ(2/5)ってところでしょうか…?

本の帯に、『就職を考えるすべての学生、若者、転職者のヒントとして活用してもらうために作られた』と書いてあったので、読んでみた。
本の内容は、村上龍の経済番組『カンブリア宮殿』にゲストとして登場した企業トップのインタビューを業態別に分けて紹介したもの。登場するのは、素晴らしい経営者ばかりなので、確かに読者の心に訴えかける様な名言もたくさん載っているんだけど…。
如何せん、おひとり3P(鏡を含めば4P)の扱いじゃ~なぁ…。登場する経営者の素晴らしさを確認するには、別な情報源で深掘りしていく必要がありそうだ。
『就職ガイド』というよりも、『日本の経営者73人の金言集』って感じかな…
ということで、★2つ(2/5)ってところでしょうか…?

2011年08月14日
コトラーのマーケティング3.0
~ソーシャル・メディア時代の新法則~
3.0シリーズ第2弾です!な~んてシリーズがあるわけでは無いのですが…。最近、コンピュータのVerみたいなタイトルが流行なのかな?最近読んだ、ダニエルピンクの本のタイトルも『モチベーション3.0』だった。
で、タイトルから想像できるように、マーケティングの進化の歴史を3段階に分け、それぞれの段階の特徴を解説すると共に、「3.0の時代には、企業は何をすべきか!」を提言している。
1.0の時代とは、産業革命後の工業化時代を指し、工場から生み出される製品をすべての潜在的購買者に売り込むことを目的としたマーケティングの時代。
2.0の時代は、情報技術が発達した現代を指す。消費者は類似の製品を比較する十分な情報を持っているため、マーケターは市場をセグメント化し、特定の標的市場に向けて他社より優れた製品を開発・販売しなくてはならない。
そして3.0の時代。顧客を受動的なターゲットとしてとらえる伝統的なマーケティング発想では、機能面での満足を充足できても精神面での満足を充足することが難しくなっており、マーケティングにもイノベーションが求められる段階が訪れていると説いている。
具体的な内容は、「グローバル化した今日の社会において企業が貢献するためには、人間の志や精神面にも目を向ける必要がある」等、所謂、マーケティング論の枠を大きく超え、企業理念や企業の存在意義を問うような提案が書かれてる。
ということで、タイトルだけ見るとマーケティングの専門書っぽく写るけど、マーケティングの専門家ではない私の様な人間にとっても、読みやすい本でした。

3.0シリーズ第2弾です!な~んてシリーズがあるわけでは無いのですが…。最近、コンピュータのVerみたいなタイトルが流行なのかな?最近読んだ、ダニエルピンクの本のタイトルも『モチベーション3.0』だった。
で、タイトルから想像できるように、マーケティングの進化の歴史を3段階に分け、それぞれの段階の特徴を解説すると共に、「3.0の時代には、企業は何をすべきか!」を提言している。
1.0の時代とは、産業革命後の工業化時代を指し、工場から生み出される製品をすべての潜在的購買者に売り込むことを目的としたマーケティングの時代。
2.0の時代は、情報技術が発達した現代を指す。消費者は類似の製品を比較する十分な情報を持っているため、マーケターは市場をセグメント化し、特定の標的市場に向けて他社より優れた製品を開発・販売しなくてはならない。
そして3.0の時代。顧客を受動的なターゲットとしてとらえる伝統的なマーケティング発想では、機能面での満足を充足できても精神面での満足を充足することが難しくなっており、マーケティングにもイノベーションが求められる段階が訪れていると説いている。
具体的な内容は、「グローバル化した今日の社会において企業が貢献するためには、人間の志や精神面にも目を向ける必要がある」等、所謂、マーケティング論の枠を大きく超え、企業理念や企業の存在意義を問うような提案が書かれてる。
ということで、タイトルだけ見るとマーケティングの専門書っぽく写るけど、マーケティングの専門家ではない私の様な人間にとっても、読みやすい本でした。

2011年07月09日
モチベーション3.0
~持続する「やる気!」をいかに引き出すか~
原題は『DRIVE』。邦題の『モチベーション3.0』は、人のやる気を引き出すための基本ソフト(OS)を、コンピュータのOSになぞらえて付けられている。
「モチベーション1.0」は、「生きてくためには、とにかく頑張らなくっちゃ!」という人間の最初のOS。「モチベーション2.0」は、アメとムチによる与えられた動機付けによるOS。「モチベーション2.0」は、20世紀のルーチンワーク中心の時代には有効だったけれど、21世紀を迎え機能不全に陥っているというお話。
で、著者が提唱する「モチベーション3.0」。21世紀のビジネスを円滑に機能させるためには、自分の内面から湧き出る「やる気!」に基づくOSが必要だと説いている。
現代でもルーチンワークは無くなっていないし、「アメとムチが好き(?)な人も少なからずいるよな~」とは思いつつも、筆者の考えには大賛成。
人間は、本質的に人生の意義や目的を探すもの。目先のアメに釣られて頑張るだけじゃ、ちと寂しいんじゃ…
僕も今一度「自分自身の人生の目的を確認してみようかな~」と思いました。
内容的には同意できたけど、後半単調だったので★2つかな…!?

原題は『DRIVE』。邦題の『モチベーション3.0』は、人のやる気を引き出すための基本ソフト(OS)を、コンピュータのOSになぞらえて付けられている。
「モチベーション1.0」は、「生きてくためには、とにかく頑張らなくっちゃ!」という人間の最初のOS。「モチベーション2.0」は、アメとムチによる与えられた動機付けによるOS。「モチベーション2.0」は、20世紀のルーチンワーク中心の時代には有効だったけれど、21世紀を迎え機能不全に陥っているというお話。
で、著者が提唱する「モチベーション3.0」。21世紀のビジネスを円滑に機能させるためには、自分の内面から湧き出る「やる気!」に基づくOSが必要だと説いている。
現代でもルーチンワークは無くなっていないし、「アメとムチが好き(?)な人も少なからずいるよな~」とは思いつつも、筆者の考えには大賛成。
人間は、本質的に人生の意義や目的を探すもの。目先のアメに釣られて頑張るだけじゃ、ちと寂しいんじゃ…
僕も今一度「自分自身の人生の目的を確認してみようかな~」と思いました。
内容的には同意できたけど、後半単調だったので★2つかな…!?

2011年05月17日
不安定社会の中の若者たち
~大学生調査から見るこの20年~
関西大学社会学部の片桐新自教授の著書。サブタイトルにあるように、1987年~2007年までの20年間に著者が実施した大学生の意識調査データを基に、若者の意識変化について書かれている。
著者は、大学の教員でもあるので、日常的に接する学生たちとのつきあいや観察が調査データの分析のベースになっており、単なるデータ分析に終わっていない。
ということで、分析内容は説得力があり「そうだよね~」と頷ける内容が多いかな。まぁ、著者が私と同世代なので「若者に対するモノの見方が近くなる?」ということもあるのだろうけれど…。
バブル経済、失われた10年、就職氷河期、格差社会等々、この20年、本当にいろいろなことがあった。「これらの不安定要素は、若者の意識にどんな影響を与えてきたのか…?」、そんな疑問を持った人は是非とも読んでみて欲しい。

関西大学社会学部の片桐新自教授の著書。サブタイトルにあるように、1987年~2007年までの20年間に著者が実施した大学生の意識調査データを基に、若者の意識変化について書かれている。
著者は、大学の教員でもあるので、日常的に接する学生たちとのつきあいや観察が調査データの分析のベースになっており、単なるデータ分析に終わっていない。
ということで、分析内容は説得力があり「そうだよね~」と頷ける内容が多いかな。まぁ、著者が私と同世代なので「若者に対するモノの見方が近くなる?」ということもあるのだろうけれど…。
バブル経済、失われた10年、就職氷河期、格差社会等々、この20年、本当にいろいろなことがあった。「これらの不安定要素は、若者の意識にどんな影響を与えてきたのか…?」、そんな疑問を持った人は是非とも読んでみて欲しい。

2011年05月08日
巨像も踊る
~ルイス・ガースナー著~
2002年12月初版ということで、ちょっぴり古いけれど、『IBM再生の立役者』と言われるルイス・ガースナーがどんな人物なのかを知りたくて買っておいた本。連休中に1冊くらいは読みたいと、手にとってみた。
第Ⅰ部:掌握から、第Ⅱ部:戦略、第Ⅲ部:企業文化、第Ⅳ部:教訓、第Ⅴ部:個人的な意見と、ガースナーが改革を進めたプロセスが順をおって書かれている。客観的、且つ冷静で、「さすが、元マッキンゼー上級パートナー」ということなのだろうが、言い方を変えれば少々単調かも…
そんな中、少なからず私の琴線に触れたのは、第Ⅲ部の企業文化かな…。
IBMでの約10年間に、わたしは企業文化が経営のひとつの側面ではないことを理解するようになった。ひとつの側面ではなく、経営そのものなのだ。
数十万人の社員の姿勢や行動様式を変えるのは、極端なまでにむずかしい。ビジネス・スクールではその方法を教えていない。心地よい本社にいて社員から隔絶されていては、革命を率いることはできない。
等々…
このあたりには、強く同意しちゃう。個人的には、社員数は、数十人だったとしても、同じ課題を抱えることになると思っているが…。
ということで、全編を通しては若干の退屈さを感じたが、まぁ、古くからのThinkPadユーザー(今は、Lenovo製ですが…)としては、「読んどいてよかった!?」と思える本でした。

2002年12月初版ということで、ちょっぴり古いけれど、『IBM再生の立役者』と言われるルイス・ガースナーがどんな人物なのかを知りたくて買っておいた本。連休中に1冊くらいは読みたいと、手にとってみた。
第Ⅰ部:掌握から、第Ⅱ部:戦略、第Ⅲ部:企業文化、第Ⅳ部:教訓、第Ⅴ部:個人的な意見と、ガースナーが改革を進めたプロセスが順をおって書かれている。客観的、且つ冷静で、「さすが、元マッキンゼー上級パートナー」ということなのだろうが、言い方を変えれば少々単調かも…
そんな中、少なからず私の琴線に触れたのは、第Ⅲ部の企業文化かな…。
IBMでの約10年間に、わたしは企業文化が経営のひとつの側面ではないことを理解するようになった。ひとつの側面ではなく、経営そのものなのだ。
数十万人の社員の姿勢や行動様式を変えるのは、極端なまでにむずかしい。ビジネス・スクールではその方法を教えていない。心地よい本社にいて社員から隔絶されていては、革命を率いることはできない。
等々…
このあたりには、強く同意しちゃう。個人的には、社員数は、数十人だったとしても、同じ課題を抱えることになると思っているが…。
ということで、全編を通しては若干の退屈さを感じたが、まぁ、古くからのThinkPadユーザー(今は、Lenovo製ですが…)としては、「読んどいてよかった!?」と思える本でした。

2011年04月22日
おとなの進路教室。
~山田 ズーニー 著~
本書は、「ほぼ日刊イトイ新聞」の人気コラム「おとなの小論文教室。」を単行本化したモノ。
月10万の国内外の読者から、現場の切実な問題意識、経験、想いが寄せられ、ズーニーさんと読者が鍛えあい、導きあうようにして出来上がった本。
例えば…
Lesson1:意志ある選択が人生をつくる
納得のいく就職先に決まりました。
そこには意志のある選択があったから。
じーんと打たれて、その場を動けなかった。私は、こういう言葉を聞くための、ずっと仕事をしてきているんだと思う。
「考える」ことがその人の人生になる。
選んだ先が、結果的にすごくいいところだったとか、よくなかったとか、自分の選択が、あとあとまちがっていたとか、いなかったとか、そんなことはどうでもいい。
意志ある選択こそが、自分の人生を創っていくんだ。確かにそう思った。
こんな言葉が琴線に触れるようだったら、是非、読んでみるといい。

本書は、「ほぼ日刊イトイ新聞」の人気コラム「おとなの小論文教室。」を単行本化したモノ。
月10万の国内外の読者から、現場の切実な問題意識、経験、想いが寄せられ、ズーニーさんと読者が鍛えあい、導きあうようにして出来上がった本。
例えば…
Lesson1:意志ある選択が人生をつくる
納得のいく就職先に決まりました。
そこには意志のある選択があったから。
じーんと打たれて、その場を動けなかった。私は、こういう言葉を聞くための、ずっと仕事をしてきているんだと思う。
「考える」ことがその人の人生になる。
選んだ先が、結果的にすごくいいところだったとか、よくなかったとか、自分の選択が、あとあとまちがっていたとか、いなかったとか、そんなことはどうでもいい。
意志ある選択こそが、自分の人生を創っていくんだ。確かにそう思った。
こんな言葉が琴線に触れるようだったら、是非、読んでみるといい。

2011年04月11日
希望学1 希望を語る
~社会科学の新たな地平へ~
労働経済学者の玄田有史さんを中心とした東京大学社会科学研究所による「希望学」に関する書。社会科学のさまざまの分野の9人の研究者が、「希望」についての考察をしています。
正直、論文には興味を引くものとそうでないものがあり、「一気に読破…」という感じではなかったですが、「希望学」とは、僕にとって、今、一番興味のあるテーマでもあります。
2002年に調査実施以来最高(当時)の5.4%を記録した完全失業率(実は、私はこの年、起業したのも偶然ではありません)。その後、日本経済は統計上改善してきたものの、依然として漠然とした閉塞感が漂い続けています。
玄田氏は、「根底にあるのは、かつてすべての行動の前提として誰もが持っていたはずの希望が、多くの個人から失われつつある」のがその理由だと考えているようです。
この本には、「そもそも『まだない存在』である『希望』とは、何なのか?」また、「私たちの回りに漂う漠然とした閉塞感」をどうしたらぬぐい去れるかのヒントが書かれているんじゃないかと思います。
「…いるんじゃないかと思います。」というのは、私には一度読んだだけでは、すべてが理解できていないということです…(苦笑

労働経済学者の玄田有史さんを中心とした東京大学社会科学研究所による「希望学」に関する書。社会科学のさまざまの分野の9人の研究者が、「希望」についての考察をしています。
正直、論文には興味を引くものとそうでないものがあり、「一気に読破…」という感じではなかったですが、「希望学」とは、僕にとって、今、一番興味のあるテーマでもあります。
2002年に調査実施以来最高(当時)の5.4%を記録した完全失業率(実は、私はこの年、起業したのも偶然ではありません)。その後、日本経済は統計上改善してきたものの、依然として漠然とした閉塞感が漂い続けています。
玄田氏は、「根底にあるのは、かつてすべての行動の前提として誰もが持っていたはずの希望が、多くの個人から失われつつある」のがその理由だと考えているようです。
この本には、「そもそも『まだない存在』である『希望』とは、何なのか?」また、「私たちの回りに漂う漠然とした閉塞感」をどうしたらぬぐい去れるかのヒントが書かれているんじゃないかと思います。
「…いるんじゃないかと思います。」というのは、私には一度読んだだけでは、すべてが理解できていないということです…(苦笑

2011年02月20日
はたらきたい。
~ほぼ日の就職論~
ウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」に掲載された「ほぼ日の就職論」で連載された5つの対話+過去の「ほぼ日」アーカイブの中から抜き出した言葉で構成されている就職に関する本。
金井壽宏先生や河野晴樹氏などのキャリアの専門家から、漫画家のしりあがり寿氏, 言わずと知れた矢沢永吉氏、果ては板尾創路, ピエール瀧, 天久聖一, 浜野謙太等のフリーランスのみなさんまで、いったいどんなコトを言ってるんだろう?という興味本意で読んでみた。
糸井氏自身がコメントしているように、そもそもこの本は「職を得るためにうまく立ち回るための方法を否定したい…」ということで書かれたモノで、「はたらくコトについて、すぐ効く処方箋」が書かれてるわけじゃない。
とは言え、読み手ひとりひとりが、「はたらくこと」ってどういうことなのか?を考えるためのヒントがいっぱい詰まってる。ジワ~ッと効いてきますヨ!?

ウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」に掲載された「ほぼ日の就職論」で連載された5つの対話+過去の「ほぼ日」アーカイブの中から抜き出した言葉で構成されている就職に関する本。
金井壽宏先生や河野晴樹氏などのキャリアの専門家から、漫画家のしりあがり寿氏, 言わずと知れた矢沢永吉氏、果ては板尾創路, ピエール瀧, 天久聖一, 浜野謙太等のフリーランスのみなさんまで、いったいどんなコトを言ってるんだろう?という興味本意で読んでみた。
糸井氏自身がコメントしているように、そもそもこの本は「職を得るためにうまく立ち回るための方法を否定したい…」ということで書かれたモノで、「はたらくコトについて、すぐ効く処方箋」が書かれてるわけじゃない。
とは言え、読み手ひとりひとりが、「はたらくこと」ってどういうことなのか?を考えるためのヒントがいっぱい詰まってる。ジワ~ッと効いてきますヨ!?

2010年08月29日
遠距離交際と近所づきあい
~成功する組織ネットワーク戦略~
一橋大学イノベーション研究センター教授 西口敏宏氏の著書。思わず、タイトルに惹かれて読んでみました。
以下、僕の備忘録…。
『第1部:遠くに及ぶ近隣社会』では、『六度の隔たり』(何度の隔たりで、ターゲットパーソンに行き着くか?ってヤツです)や中国・温州人の経済繁栄を例に「人的ネットワークにおける遠距離交際と近所づきあいのバランスをとることが成功するネットワーク戦略の秘訣だ」というようなことが書かれています。
『第2部:企業と地域にネットワーク』では、自動車産業のネットワークを例にとり、GMに代表される腕長ぶら下がり型とトヨタの階層クラスター型を比較。ネットワーク全体の問題解決能力の違いの考察がされてます。トヨタの、日常業務とは別次元に設けた特定の選良サプライヤーとの自主研究会が遠距離交際を可能にする好事例だと紹介されてます。
『第3部:政府のリワイヤリング』では、民間企業ばかりではなく政府機関でも「従来の要求プッシュ型ではなく、国民を顧客とみなし、そのニーズを吸い上げるニーズ・プル型に移行する必要がある」ということが、筆者の関わった防衛庁のコスト管理を例に紹介されています。
で、『第4部:総括』では、ネットワーク思考が未来を開くとまとめていらっしゃいます。
専門性が高い部分も多く、私にはちょいと難解な部分もありましたが、興味を持って読むことが出来ました。時間をあけて「もう一度、読んでみたい」と思わせてくれる内容でした。

一橋大学イノベーション研究センター教授 西口敏宏氏の著書。思わず、タイトルに惹かれて読んでみました。
以下、僕の備忘録…。
『第1部:遠くに及ぶ近隣社会』では、『六度の隔たり』(何度の隔たりで、ターゲットパーソンに行き着くか?ってヤツです)や中国・温州人の経済繁栄を例に「人的ネットワークにおける遠距離交際と近所づきあいのバランスをとることが成功するネットワーク戦略の秘訣だ」というようなことが書かれています。
『第2部:企業と地域にネットワーク』では、自動車産業のネットワークを例にとり、GMに代表される腕長ぶら下がり型とトヨタの階層クラスター型を比較。ネットワーク全体の問題解決能力の違いの考察がされてます。トヨタの、日常業務とは別次元に設けた特定の選良サプライヤーとの自主研究会が遠距離交際を可能にする好事例だと紹介されてます。
『第3部:政府のリワイヤリング』では、民間企業ばかりではなく政府機関でも「従来の要求プッシュ型ではなく、国民を顧客とみなし、そのニーズを吸い上げるニーズ・プル型に移行する必要がある」ということが、筆者の関わった防衛庁のコスト管理を例に紹介されています。
で、『第4部:総括』では、ネットワーク思考が未来を開くとまとめていらっしゃいます。
専門性が高い部分も多く、私にはちょいと難解な部分もありましたが、興味を持って読むことが出来ました。時間をあけて「もう一度、読んでみたい」と思わせてくれる内容でした。

2010年08月23日
ビジョナリーカンパニー3
~衰退の5段階~
ご存じ、ジェームズ・C・コリンズ氏の名著、ビジョナリーカンパニーの第3弾!早速読んでみました。
今回のテーマは、衰退への5段階。組織の衰退のプロセスを、緻密な調査・分析によって導き出しています。コリンズ氏のスゴイところは、驚くようなコトが書いてある訳では無いのだけれど、事実より導き出した分析結果を法則の域にまで昇華して目の前に提示してくれること。
ということで、衰退のプロセスは以下の5つのプロセスに分解されるとのことです。
第1段階 成功から生まれる傲慢
第2段階 規律なき拡大路線
第3段階 リスクと問題の否認
第4段階 一発逆転策の追及
第5段階 屈服と凡庸な企業への転落か消滅
中でも、僕が、もっとも感銘を受けた(というか、最近感じている)のが、第5段階の一節。
スタンフォード大学のビル・ラジアー教授が、中小企業経営の授業で「衰退事例の中心問題は何か」と質問を浴びせたところ、大企業やコンサルティング会社、投資銀行に勤務した経験のある受講生が、「戦略の選択です」「価値連鎖を見いだす必要があります」「ブランドを確立すべきです」など、いかにもMBAらしい気のきいた言葉で答える。それに対し教授は、中身のない流行り言葉を使った答えに満足せず「違う、考えろ」と迫る。
で、もちろん、質問に対しての答えはいたってシンプルに語られているのですが…
私自身、「組織にとってのビジョンの共有の大切さ」や「マネジメント能力の醸成」なんてコトを説いたりすることもあるわけですが、その一方で「(特に最近)、当たり前のコトが出来なければ、企業の存続はあり得ない!」と強く感じていることもあり、大きく頷いちゃったわけです。

ご存じ、ジェームズ・C・コリンズ氏の名著、ビジョナリーカンパニーの第3弾!早速読んでみました。
今回のテーマは、衰退への5段階。組織の衰退のプロセスを、緻密な調査・分析によって導き出しています。コリンズ氏のスゴイところは、驚くようなコトが書いてある訳では無いのだけれど、事実より導き出した分析結果を法則の域にまで昇華して目の前に提示してくれること。
ということで、衰退のプロセスは以下の5つのプロセスに分解されるとのことです。
第1段階 成功から生まれる傲慢
第2段階 規律なき拡大路線
第3段階 リスクと問題の否認
第4段階 一発逆転策の追及
第5段階 屈服と凡庸な企業への転落か消滅
中でも、僕が、もっとも感銘を受けた(というか、最近感じている)のが、第5段階の一節。
スタンフォード大学のビル・ラジアー教授が、中小企業経営の授業で「衰退事例の中心問題は何か」と質問を浴びせたところ、大企業やコンサルティング会社、投資銀行に勤務した経験のある受講生が、「戦略の選択です」「価値連鎖を見いだす必要があります」「ブランドを確立すべきです」など、いかにもMBAらしい気のきいた言葉で答える。それに対し教授は、中身のない流行り言葉を使った答えに満足せず「違う、考えろ」と迫る。
で、もちろん、質問に対しての答えはいたってシンプルに語られているのですが…
私自身、「組織にとってのビジョンの共有の大切さ」や「マネジメント能力の醸成」なんてコトを説いたりすることもあるわけですが、その一方で「(特に最近)、当たり前のコトが出来なければ、企業の存続はあり得ない!」と強く感じていることもあり、大きく頷いちゃったわけです。

2010年08月09日
日本経済の真実
~辛坊治郎、辛坊正記 著~
9月末で読売テレビを退社するニュースキャスター&解説委員長の辛坊治郎さんと兄さん(辛坊正記)の著書。『たかじんのそこまで言って委員会』で紹介していたので読んでみました。
戦後の日本経済の推移と仕組みがわかりやすく書かれている。私的には、最近「そうだったのか…」で人気急上昇中の池上彰氏の話よりもコチラの方がわかりやすいかも…。
内容には賛否はあるだろうし、あえて書評はしませんが、日本経済の行く末に不安を感じている人はもちろん、以下の【日本を滅ぼす5つの「悪の呪文」】に違和感を持たない人には是非、読んでもらって、国民的な議論をしてみたいですね。
【日本を滅ぼす5つの「悪の呪文」】
1.経済の豊かさより心の豊かさが大切
2.大企業優遇はやめろ!
3.金持ち待遇は不公正だ!
4.外資に日本が乗っ取られる
5.金をばらまけば、景気が良くなる

9月末で読売テレビを退社するニュースキャスター&解説委員長の辛坊治郎さんと兄さん(辛坊正記)の著書。『たかじんのそこまで言って委員会』で紹介していたので読んでみました。
戦後の日本経済の推移と仕組みがわかりやすく書かれている。私的には、最近「そうだったのか…」で人気急上昇中の池上彰氏の話よりもコチラの方がわかりやすいかも…。
内容には賛否はあるだろうし、あえて書評はしませんが、日本経済の行く末に不安を感じている人はもちろん、以下の【日本を滅ぼす5つの「悪の呪文」】に違和感を持たない人には是非、読んでもらって、国民的な議論をしてみたいですね。
【日本を滅ぼす5つの「悪の呪文」】
1.経済の豊かさより心の豊かさが大切
2.大企業優遇はやめろ!
3.金持ち待遇は不公正だ!
4.外資に日本が乗っ取られる
5.金をばらまけば、景気が良くなる







