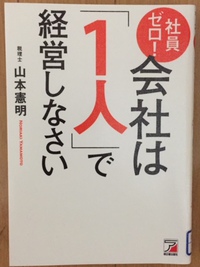2012年03月31日
若者はなぜ「就職」できなくなったのか?
~生き抜くために知っておくべきこと 児美川孝一郎 著~
法政大学キャリアデザイン学部の先生が書いた本。昨今の労働市場変化(すべての大学生が正社員になれないのは構造的な問題、等)とそれに伴い大学などで流行しているキャリア教育・キャリア支援の問題点が、丁寧且つ客観的に書かれている。
私自身、大学でキャリア関連の授業を担当したり、学生のキャリア相談に応じる中、児美川教授と同じ様な問題を感じていることもあり、当事者である若者や親はもちろんのこと、「キャリア支援やキャリア教育に携わる人たちも是非、読んで欲しい!」と思える内容の本だった。
そんな中、児美川教授の考えに異を唱えるつもりはないが、大学で授業を担当しつつ、企業の経営者として学生たちを見させていただいている立場から、ひとこと…。
<大学講師として感じるコト>
私が、担当するキャリア関連の授業で意識しているのは、「1.労働市場の事実」「2.充実した学生生活が、今後の人生に彩りを添える」の2点を伝えること。その2つをキッチリ受けとめてくれる学生であれば、有意義な人生を送れるだろうと考えて授業に臨んでいる。
とはいえ、上記の2つはキャリア関連授業だけで、効果を発揮するとは思えない(寂しいけれど…)。じゃ~、どうすれば…
私自身は、大学の教・職員が、「今までより少しだけ世の中の変化や目の前の学生の将来に興味を持つこと」によって、救われる学生も増えるのではないかとも思うのだが、どうだろう(労働市場の構造自体は変えられないにしても、児美川教授が感じている課題を解決するのは、コチラの方がずっと有効かも…)。
<経営者として感じるコト>
今年も大学生の選考に携わっているのだが、応募者と接する中、在学時に一般常識として伝えておかなくてはならないこと(一般常識を、キャリア教育と言う人もいるかもしれないが…)も多いのではないかと感じる。
一番感じるのは、現在の学生(日本)を取り巻く環境を客観視出来ていない学生が圧倒的に多いということ。昨今、若者の非正規社員化・年金の世代間格差等を指して若者を『社会的弱者』と位置づける論調が多く聞かれるが、当事者である多くの若者からは、そんな危機感は感じ取れない(危機感を煽るつもりはないけれど、私は、現状に満足し問題意識を持たない人からは新しいモノは生まれないと思っている)。
茹蛙状態の学生を見ていると、10年後の彼らが、『1990年代に大手企業をリストラされた企業戦士たちが「こんなハズじゃなかった」と肩を落としていたこと』の二の舞にならなければいいと願ってしまう自分がいる。
1990年代に日本型雇用慣行は終わったと言われているけれど、日本全体が茹蛙状態に陥っているのかもしれない…。等々、いろんなコトを考えさせてくれる本でした。

法政大学キャリアデザイン学部の先生が書いた本。昨今の労働市場変化(すべての大学生が正社員になれないのは構造的な問題、等)とそれに伴い大学などで流行しているキャリア教育・キャリア支援の問題点が、丁寧且つ客観的に書かれている。
私自身、大学でキャリア関連の授業を担当したり、学生のキャリア相談に応じる中、児美川教授と同じ様な問題を感じていることもあり、当事者である若者や親はもちろんのこと、「キャリア支援やキャリア教育に携わる人たちも是非、読んで欲しい!」と思える内容の本だった。
そんな中、児美川教授の考えに異を唱えるつもりはないが、大学で授業を担当しつつ、企業の経営者として学生たちを見させていただいている立場から、ひとこと…。
<大学講師として感じるコト>
私が、担当するキャリア関連の授業で意識しているのは、「1.労働市場の事実」「2.充実した学生生活が、今後の人生に彩りを添える」の2点を伝えること。その2つをキッチリ受けとめてくれる学生であれば、有意義な人生を送れるだろうと考えて授業に臨んでいる。
とはいえ、上記の2つはキャリア関連授業だけで、効果を発揮するとは思えない(寂しいけれど…)。じゃ~、どうすれば…
私自身は、大学の教・職員が、「今までより少しだけ世の中の変化や目の前の学生の将来に興味を持つこと」によって、救われる学生も増えるのではないかとも思うのだが、どうだろう(労働市場の構造自体は変えられないにしても、児美川教授が感じている課題を解決するのは、コチラの方がずっと有効かも…)。
<経営者として感じるコト>
今年も大学生の選考に携わっているのだが、応募者と接する中、在学時に一般常識として伝えておかなくてはならないこと(一般常識を、キャリア教育と言う人もいるかもしれないが…)も多いのではないかと感じる。
一番感じるのは、現在の学生(日本)を取り巻く環境を客観視出来ていない学生が圧倒的に多いということ。昨今、若者の非正規社員化・年金の世代間格差等を指して若者を『社会的弱者』と位置づける論調が多く聞かれるが、当事者である多くの若者からは、そんな危機感は感じ取れない(危機感を煽るつもりはないけれど、私は、現状に満足し問題意識を持たない人からは新しいモノは生まれないと思っている)。
茹蛙状態の学生を見ていると、10年後の彼らが、『1990年代に大手企業をリストラされた企業戦士たちが「こんなハズじゃなかった」と肩を落としていたこと』の二の舞にならなければいいと願ってしまう自分がいる。
1990年代に日本型雇用慣行は終わったと言われているけれど、日本全体が茹蛙状態に陥っているのかもしれない…。等々、いろんなコトを考えさせてくれる本でした。

Posted by オルベア at 22:56│Comments(0)
│書評