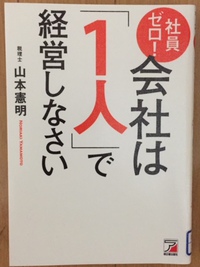2016年04月26日
ハーバードでいちばん人気の国・日本
〜佐藤 智恵 著〜
新聞の書籍広告に載っていた「テレビ番組で紹介、お茶の間でも大反響!」「書籍ランキング1位」のキャッチコピーに、「“ニッポンすごい系番組”の書籍版かな…?」と興味をそそられて読んでみた。
ちなみに私は、「“ニッポンすごい系番組”最近チョッピリ多すぎかも…?」と感じはするものの、それに対する批判のコメントを目にして、「目くじら立てて批判する…?」とちょっぴり引いちゃう様な輩です。
書籍の内容はタイトルの通り、ハーバードの授業で教材として扱われる日本や日本企業の事例の紹介を通して、日本や日本企業の人気の理由が丁寧、且つわかりやすく書かれている。事例自体は、私たち日本人が知っているものが多いけれど、それをハーバードの教授陣が「どんな視点でどう評価しているのか?」という観点で書かれているのが読みやすい。
ちなみに、学生たちが卒業までの2年間で学ぶ約500本の事例のうち、必修科目(2014年)で学ぶ日本の事例は、トヨタ自動車(テクノロジーとオペレーションマネジメント)、楽天(リーダーシップと組織行動)、全日本空輸(マーケティング)、本田技研工業(経営戦略)、日本航空(ファイナンス)、アベノミクス(ビジネス・政府・国際政治)の6本ということなので、数よりも質で勝負ということの様…。
そんな中、印象に残ったのは、同大学で何十年も教えられている、トヨタ自動車と本田技研工業のケース。
トヨタ自動車の事例で言えば、『謙虚なリーダー像』。1980年代、日本の製造業が飛躍を遂げた際、当時の米国では「日本のメーカーが強いのは、日本人と米国人の労働者の能力の差だ」というのが一般的常識だった。ところが、日本企業を研究するにつれ、「米国人労働者の生産性が低いのは、米国企業の経営者、役員、管理職のリーダーシップにも問題があるからだ」とわかってきた。
そこで注目されたのが、日本人経営者の「謙虚さ」。グローバル企業では、経営者が決めたことを部下はそのとおりに実施するのが当たり前だったが、日本のメーカーの経営者は、下からの意見を聞いて一緒に考える。それが“学習する組織”を形成し、強さの源泉となったという分析だ。
本田技研工業の事例で言えば、ホンダの米国進出に『論理的な戦略』はなかったということ。1959年に米国進出後、15年で米国のオートバイ市場の43%を占めるまでに成長したホンダについて、ボストンコンサルティングは「いかに素晴らしい競争戦略で米国市場を制したか」を論理的に分析したが、それは結果論。ホンダは欧米流の合理的な戦略を描いて米国に進出したわけではないことがわかったとのこと。
そもそもホンダは、「資本主義の牙城、世界経済の中心である米国での成功なくして国際商品にはなりえない」という理由だけで米国進出を決めたのであって、米国の潜在市場がどの程度で、どのようなニーズがあるかなどを事前に把握していたわけではない。ホンダの成功は、机上で論理的に考えた戦略が功を奏したのではなく、“偶然や現場学習の積み重ね”によって達成されたものだったという分析だ。ただ、1981年にボストンコンサルティングが日本進出した際、欧米流の意図的戦略も必要だと考え、最初の顧客になったのもホンダだったというのも見逃してはいけない。
ということで、「書籍ランキング1位の理由」も「アマゾンのレビューが高評価」なのも納得の内容だったけど、多くの事例は、過去の日本が高く評価されているということ。ハーバードの学生たちが学んでいるのと同じように、私たちも「しっかり事例から学ばなくっちゃ!!」と考えさせられた一冊でした。

新聞の書籍広告に載っていた「テレビ番組で紹介、お茶の間でも大反響!」「書籍ランキング1位」のキャッチコピーに、「“ニッポンすごい系番組”の書籍版かな…?」と興味をそそられて読んでみた。
ちなみに私は、「“ニッポンすごい系番組”最近チョッピリ多すぎかも…?」と感じはするものの、それに対する批判のコメントを目にして、「目くじら立てて批判する…?」とちょっぴり引いちゃう様な輩です。
書籍の内容はタイトルの通り、ハーバードの授業で教材として扱われる日本や日本企業の事例の紹介を通して、日本や日本企業の人気の理由が丁寧、且つわかりやすく書かれている。事例自体は、私たち日本人が知っているものが多いけれど、それをハーバードの教授陣が「どんな視点でどう評価しているのか?」という観点で書かれているのが読みやすい。
ちなみに、学生たちが卒業までの2年間で学ぶ約500本の事例のうち、必修科目(2014年)で学ぶ日本の事例は、トヨタ自動車(テクノロジーとオペレーションマネジメント)、楽天(リーダーシップと組織行動)、全日本空輸(マーケティング)、本田技研工業(経営戦略)、日本航空(ファイナンス)、アベノミクス(ビジネス・政府・国際政治)の6本ということなので、数よりも質で勝負ということの様…。
そんな中、印象に残ったのは、同大学で何十年も教えられている、トヨタ自動車と本田技研工業のケース。
トヨタ自動車の事例で言えば、『謙虚なリーダー像』。1980年代、日本の製造業が飛躍を遂げた際、当時の米国では「日本のメーカーが強いのは、日本人と米国人の労働者の能力の差だ」というのが一般的常識だった。ところが、日本企業を研究するにつれ、「米国人労働者の生産性が低いのは、米国企業の経営者、役員、管理職のリーダーシップにも問題があるからだ」とわかってきた。
そこで注目されたのが、日本人経営者の「謙虚さ」。グローバル企業では、経営者が決めたことを部下はそのとおりに実施するのが当たり前だったが、日本のメーカーの経営者は、下からの意見を聞いて一緒に考える。それが“学習する組織”を形成し、強さの源泉となったという分析だ。
本田技研工業の事例で言えば、ホンダの米国進出に『論理的な戦略』はなかったということ。1959年に米国進出後、15年で米国のオートバイ市場の43%を占めるまでに成長したホンダについて、ボストンコンサルティングは「いかに素晴らしい競争戦略で米国市場を制したか」を論理的に分析したが、それは結果論。ホンダは欧米流の合理的な戦略を描いて米国に進出したわけではないことがわかったとのこと。
そもそもホンダは、「資本主義の牙城、世界経済の中心である米国での成功なくして国際商品にはなりえない」という理由だけで米国進出を決めたのであって、米国の潜在市場がどの程度で、どのようなニーズがあるかなどを事前に把握していたわけではない。ホンダの成功は、机上で論理的に考えた戦略が功を奏したのではなく、“偶然や現場学習の積み重ね”によって達成されたものだったという分析だ。ただ、1981年にボストンコンサルティングが日本進出した際、欧米流の意図的戦略も必要だと考え、最初の顧客になったのもホンダだったというのも見逃してはいけない。
ということで、「書籍ランキング1位の理由」も「アマゾンのレビューが高評価」なのも納得の内容だったけど、多くの事例は、過去の日本が高く評価されているということ。ハーバードの学生たちが学んでいるのと同じように、私たちも「しっかり事例から学ばなくっちゃ!!」と考えさせられた一冊でした。

Posted by オルベア at 21:47│Comments(0)
│書評