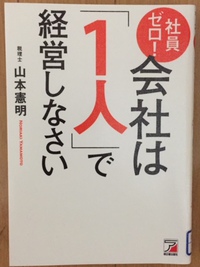2015年04月29日
How Google Works
〜エリック・シュミット、ジョナサン・ローゼンバーグ 著〜
Googleの現会長エリック・シュミットと CEO 兼共同創業者ラリー・ペイジのアドバイザーのジョナサン・ローゼンバーグの共著で、Google の経営ポリシーが書かれた本。21世紀に、成長・進化し続ける組織づくりのヒントが、文化、戦略、人材、意思決定、コミュニケーション、イノベーションという章立てで書かれている。
Googleの成長と成功を支える核心は、「スマート・クリエイティブ」と呼ばれる新種の知識労働者であり、彼らを惹きつけ、力を発揮できる環境をつくることが、唯一の道であると結論づけている。
ここで言う「スマート・クリエイティブ」とは…。自分の“商売道具“を使いこなすための高度な専門知識を持ち、経験値も高い。分析力に優れている。ビジネス感覚に優れている等々…。要約すると、「ビジネスセンス、専門知識、クリエイティブなエネルギー、自分で手を動かして業務を遂行しようとする姿勢」が基本的要件にある人材と定義される。
そもそも「そんな人材をどんな風に集めてくればいいのか?」「採用できたとしても、どうすれば惹きつけ続けることが出来るのか?」等々、疑問満載ではあるが、以下に疑問解決のためのヒントとなる部分を備忘録という視点で残しておこうと思う。
“ワークライフ・バランス”について…
ワークライフ・バランス。先進的経営の尺度とされるが、優秀でやる気のある従業員は屈辱的に感じることもある要素だ。このフレーズ自体に問題がある。多くの人にとって、ワーク(仕事)はライフ(生活)の重要な一部であり、切り離せるものではない。最高の文化とは、おもしろい仕事がありすぎるので、職場でも自宅でも良い意味で働きすぎになるような、そしてそれを可能にするものだ。だからあなたがマネージャーなら「ワーク」の部分をいきいきと、充実したものにする責任がある。従業員が週40時間労働を守っているか、目を光らせるのが一番重要な仕事ではない。
最近、大学生の集団討論Workで“ワークライフ・バランス”についての考えを聴く機会が多い。学生達が、「仕事は苦痛なモノ」「仕事と生活(多くの場合、家庭)のバランスが必須」等のオンパレードに辟易している私としては、「我が意を得たり!」の内容だ。
会社を経営する人間として、従業員の労務管理を蔑ろにするつもりは全くないし、仕事人間になって欲しいとも思わないが、昨今の「仕事も生活もそこそこでいいよね」的なワークライフ・バランス論には首をかしげてしまう。
個々人がどんなバランスで仕事をするのかを考えることは大切だと思うし、マネージャーは、部下の意志を尊重しなくてはならないとも思っているが、そもそも仕事は楽しいもの(←私はそう思っている)だし、それを伝えることがマネージャーの重要な役割だと思う。
採用について…
経営者の場合、「あなたの仕事のうち一番重要なものは?」という問いへの正解は「採用」だ。あの日、ジョナサンを面接していたセルゲイは、真剣そのものだった。ジョナサンは当初、それは自分が幹部候補で、入社したらセルゲイと仕事をする機会が多くなるためかと思っていた。だが入社して、グーグルの経営者はすべての候補者を同じくらい真剣に面接することを知った。相手が駆け出しのソフトウェアエンジニアであろうが、幹部候補であろうが、グーグラーは最高の人材を確実に採用するために最大限の時間と労力をかける。
「う〜ん、全く異論なし!」。加えて、本書には…。
最も優秀な人材を採用し続けるには、産業界ではなく学術界のモデルを見習う必要があることを理解していた。大学は通常、教授に採用した人間を解雇しないので、専門委員会を立ち上げ、教員の採用や昇進の検討に膨大な時間を費やす。私たちが採用はヒエラルキー型ではなく、委員会によるピア型が好ましいと考えるのはこのためで、候補者の経歴が空きポストと合致するか否かにかかわらず、とにかく優秀な人材を採用することに集中する。
「大学教授級の人材を採用するわけじゃないんだから、通常の会社だったら、ヒエラルキー型の採用でいいんじゃない?」などという声が聞こえてきそうだが、採用した従業員には、中長期にわたって仕事のやりがいを感じられる環境を用意すべきだし、厳しい解雇規制がある現実を考えると、通常の採用の場面でも、大学教授を採用するのと同じくらいの労力をかけてもいいのではないかと思う。
また、情熱と知性、誠実さと独自の視点を持った理想の候補者を見つけ出し、獲得するかについて、発掘、面接、採用、報酬の4つのプロセスについても書かれている。グーグルでは、発掘時の作業を「絞りを広げる」と表現している。
絞りを変えることで、カメラの画像センサーに入る光量が変わる。採用担当者の多くは絞りを狭くする。いま求められている仕事をきちんとこなせそうな、特定の分野で特定の仕事に就いている特定の人の中から候補者を探そうとする。だが優秀な採用担当者は絞りを広げて、当たり前の候補者以外から適任者を探そうとする。
絞りを広げる方法の一つは、候補者の「軌道」を見ることだ。グーグルの元社員、ジャレド・スミスは最高の人材はキャリアの軌道が上向いていることが多い、と指摘する。その軌道を延長すると、大幅な成長が見込める。優秀で経験豊富でも、キャリアが頭打ちになった人はたくさんいる。こうした候補者については、どんな成果を期待できるかがはっきりしている(これはプラスだ)が、予想外ののびしろがない(これはマイナスだ)。年齢と軌道に相関はないことも指摘しておくべきだろう。また、自分で事業を経営している人、あるいは型にはまらないキャリアパスを歩んでいる人には、軌道という指針は当てはまらないこともある。
確かに採用の際、絞りを狭くしてしまうことはあるかもしれない。候補者の伸びしろを見る目が重要であることに気づかされる。併せて「自分自身のキャリアが頭打ちになっていないか?」と考え、反省!?次に面接について…。
ビジネスパーソンが磨くべき最も重要なスキルは面接スキルだ。
質の高い面接をするには、準備が必要だ。それはあなたが平社員であろうと、経営幹部であろうと変わらない。きちんとした面接をするには、自分の役割を理解し、候補者の履歴書を読み、そして一番重要なこと−何を聞くか−を考えなければならない。
面接の目的は、応募者とあたりさわりのない会話をすることではなく、相手の限界を確かめることだ。とはいえ、過剰なストレスをかけるのは避けよう。最高の面接は、友人同士の知的な会話のようなものだ。質問は間口の広い、複雑なものにしよう。正解が一つではないので、相手のモノの考え方や議論の組み立て方を見られる。
確かに。面接では、面接をする側も候補者に評価されていることを知っておく必要があるだろう。次に採用について…。
質を重視するからといって、採用プロセスに必ずしも時間がかかるわけではない。むしろ、これまで説明してきたグーグルの仕組みは、採用を迅速にするためのものだ。面接時間は30分。ひとりの候補者につき最大5回まで。面接官には、面接が終わったらすぐに採用担当者に合格か不合格かを知らせるように義務づけている。
採用には、絶対に侵してはならない黄金律がある。「採用の質を犠牲にしてまで埋めるべきポストはない」だ。速さか質か、という二者択一を迫られる場面は必ず出てくるが、必ず質を選ばなければならない。
現場のマネージャーから、「このままでは、仕事が回らない!」と懇願されると、「質を犠牲にしてでも…」という誘惑にかられることは少なくないが…。一緒に働く仲間を見つけるのだから、採用の質を犠牲にしてまで埋めるべきポストは無いことを再確認。最後に報酬について…。
首尾よくスマート・クリエイティブを獲得したら、今度は報酬を払わなければならない。ケタはずれの人材には、ケタ外れの報酬で報いるべきだ。
一方マネージャーは、破格の報酬を支払う対象を破格の働きをした人材に限定するよう心掛けるべきだ。相手はプロフェッショナルであり、リトルリーグのコーチをするのとはわけが違う。すべての人間には基本的人権があり、生まれながらにして平等だ。しかし言うまでもなく、それは全員が仕事において同じような能力があるという意味ではない。だから、あたかもそうであるかのように報酬を払ったり、昇進させたりするのはやめよう。
職位や入社年次にかかわらず、その人の成果に見合った報酬を支払うことが重要。この当たり前を適正に運用することが、経営に求められることをあらためて認識させられた。
ということで、従業員を惹きつけ、力を発揮できる環境をつくることの重要性を再認識させてくれた“How Google Works”でした。推敲ベタなため、長文の備忘録となってしまった…(苦笑

Googleの現会長エリック・シュミットと CEO 兼共同創業者ラリー・ペイジのアドバイザーのジョナサン・ローゼンバーグの共著で、Google の経営ポリシーが書かれた本。21世紀に、成長・進化し続ける組織づくりのヒントが、文化、戦略、人材、意思決定、コミュニケーション、イノベーションという章立てで書かれている。
Googleの成長と成功を支える核心は、「スマート・クリエイティブ」と呼ばれる新種の知識労働者であり、彼らを惹きつけ、力を発揮できる環境をつくることが、唯一の道であると結論づけている。
ここで言う「スマート・クリエイティブ」とは…。自分の“商売道具“を使いこなすための高度な専門知識を持ち、経験値も高い。分析力に優れている。ビジネス感覚に優れている等々…。要約すると、「ビジネスセンス、専門知識、クリエイティブなエネルギー、自分で手を動かして業務を遂行しようとする姿勢」が基本的要件にある人材と定義される。
そもそも「そんな人材をどんな風に集めてくればいいのか?」「採用できたとしても、どうすれば惹きつけ続けることが出来るのか?」等々、疑問満載ではあるが、以下に疑問解決のためのヒントとなる部分を備忘録という視点で残しておこうと思う。
“ワークライフ・バランス”について…
ワークライフ・バランス。先進的経営の尺度とされるが、優秀でやる気のある従業員は屈辱的に感じることもある要素だ。このフレーズ自体に問題がある。多くの人にとって、ワーク(仕事)はライフ(生活)の重要な一部であり、切り離せるものではない。最高の文化とは、おもしろい仕事がありすぎるので、職場でも自宅でも良い意味で働きすぎになるような、そしてそれを可能にするものだ。だからあなたがマネージャーなら「ワーク」の部分をいきいきと、充実したものにする責任がある。従業員が週40時間労働を守っているか、目を光らせるのが一番重要な仕事ではない。
最近、大学生の集団討論Workで“ワークライフ・バランス”についての考えを聴く機会が多い。学生達が、「仕事は苦痛なモノ」「仕事と生活(多くの場合、家庭)のバランスが必須」等のオンパレードに辟易している私としては、「我が意を得たり!」の内容だ。
会社を経営する人間として、従業員の労務管理を蔑ろにするつもりは全くないし、仕事人間になって欲しいとも思わないが、昨今の「仕事も生活もそこそこでいいよね」的なワークライフ・バランス論には首をかしげてしまう。
個々人がどんなバランスで仕事をするのかを考えることは大切だと思うし、マネージャーは、部下の意志を尊重しなくてはならないとも思っているが、そもそも仕事は楽しいもの(←私はそう思っている)だし、それを伝えることがマネージャーの重要な役割だと思う。
採用について…
経営者の場合、「あなたの仕事のうち一番重要なものは?」という問いへの正解は「採用」だ。あの日、ジョナサンを面接していたセルゲイは、真剣そのものだった。ジョナサンは当初、それは自分が幹部候補で、入社したらセルゲイと仕事をする機会が多くなるためかと思っていた。だが入社して、グーグルの経営者はすべての候補者を同じくらい真剣に面接することを知った。相手が駆け出しのソフトウェアエンジニアであろうが、幹部候補であろうが、グーグラーは最高の人材を確実に採用するために最大限の時間と労力をかける。
「う〜ん、全く異論なし!」。加えて、本書には…。
最も優秀な人材を採用し続けるには、産業界ではなく学術界のモデルを見習う必要があることを理解していた。大学は通常、教授に採用した人間を解雇しないので、専門委員会を立ち上げ、教員の採用や昇進の検討に膨大な時間を費やす。私たちが採用はヒエラルキー型ではなく、委員会によるピア型が好ましいと考えるのはこのためで、候補者の経歴が空きポストと合致するか否かにかかわらず、とにかく優秀な人材を採用することに集中する。
「大学教授級の人材を採用するわけじゃないんだから、通常の会社だったら、ヒエラルキー型の採用でいいんじゃない?」などという声が聞こえてきそうだが、採用した従業員には、中長期にわたって仕事のやりがいを感じられる環境を用意すべきだし、厳しい解雇規制がある現実を考えると、通常の採用の場面でも、大学教授を採用するのと同じくらいの労力をかけてもいいのではないかと思う。
また、情熱と知性、誠実さと独自の視点を持った理想の候補者を見つけ出し、獲得するかについて、発掘、面接、採用、報酬の4つのプロセスについても書かれている。グーグルでは、発掘時の作業を「絞りを広げる」と表現している。
絞りを変えることで、カメラの画像センサーに入る光量が変わる。採用担当者の多くは絞りを狭くする。いま求められている仕事をきちんとこなせそうな、特定の分野で特定の仕事に就いている特定の人の中から候補者を探そうとする。だが優秀な採用担当者は絞りを広げて、当たり前の候補者以外から適任者を探そうとする。
絞りを広げる方法の一つは、候補者の「軌道」を見ることだ。グーグルの元社員、ジャレド・スミスは最高の人材はキャリアの軌道が上向いていることが多い、と指摘する。その軌道を延長すると、大幅な成長が見込める。優秀で経験豊富でも、キャリアが頭打ちになった人はたくさんいる。こうした候補者については、どんな成果を期待できるかがはっきりしている(これはプラスだ)が、予想外ののびしろがない(これはマイナスだ)。年齢と軌道に相関はないことも指摘しておくべきだろう。また、自分で事業を経営している人、あるいは型にはまらないキャリアパスを歩んでいる人には、軌道という指針は当てはまらないこともある。
確かに採用の際、絞りを狭くしてしまうことはあるかもしれない。候補者の伸びしろを見る目が重要であることに気づかされる。併せて「自分自身のキャリアが頭打ちになっていないか?」と考え、反省!?次に面接について…。
ビジネスパーソンが磨くべき最も重要なスキルは面接スキルだ。
質の高い面接をするには、準備が必要だ。それはあなたが平社員であろうと、経営幹部であろうと変わらない。きちんとした面接をするには、自分の役割を理解し、候補者の履歴書を読み、そして一番重要なこと−何を聞くか−を考えなければならない。
面接の目的は、応募者とあたりさわりのない会話をすることではなく、相手の限界を確かめることだ。とはいえ、過剰なストレスをかけるのは避けよう。最高の面接は、友人同士の知的な会話のようなものだ。質問は間口の広い、複雑なものにしよう。正解が一つではないので、相手のモノの考え方や議論の組み立て方を見られる。
確かに。面接では、面接をする側も候補者に評価されていることを知っておく必要があるだろう。次に採用について…。
質を重視するからといって、採用プロセスに必ずしも時間がかかるわけではない。むしろ、これまで説明してきたグーグルの仕組みは、採用を迅速にするためのものだ。面接時間は30分。ひとりの候補者につき最大5回まで。面接官には、面接が終わったらすぐに採用担当者に合格か不合格かを知らせるように義務づけている。
採用には、絶対に侵してはならない黄金律がある。「採用の質を犠牲にしてまで埋めるべきポストはない」だ。速さか質か、という二者択一を迫られる場面は必ず出てくるが、必ず質を選ばなければならない。
現場のマネージャーから、「このままでは、仕事が回らない!」と懇願されると、「質を犠牲にしてでも…」という誘惑にかられることは少なくないが…。一緒に働く仲間を見つけるのだから、採用の質を犠牲にしてまで埋めるべきポストは無いことを再確認。最後に報酬について…。
首尾よくスマート・クリエイティブを獲得したら、今度は報酬を払わなければならない。ケタはずれの人材には、ケタ外れの報酬で報いるべきだ。
一方マネージャーは、破格の報酬を支払う対象を破格の働きをした人材に限定するよう心掛けるべきだ。相手はプロフェッショナルであり、リトルリーグのコーチをするのとはわけが違う。すべての人間には基本的人権があり、生まれながらにして平等だ。しかし言うまでもなく、それは全員が仕事において同じような能力があるという意味ではない。だから、あたかもそうであるかのように報酬を払ったり、昇進させたりするのはやめよう。
職位や入社年次にかかわらず、その人の成果に見合った報酬を支払うことが重要。この当たり前を適正に運用することが、経営に求められることをあらためて認識させられた。
ということで、従業員を惹きつけ、力を発揮できる環境をつくることの重要性を再認識させてくれた“How Google Works”でした。推敲ベタなため、長文の備忘録となってしまった…(苦笑

Posted by オルベア at 17:31│Comments(0)
│書評