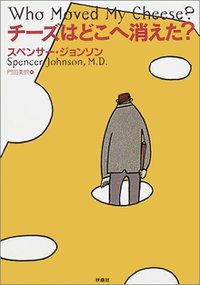2014年12月19日
大学3年生に気づきは与えられたかな…?
~今年の授業、終了しました~
ここのところ、「書かなくっちゃ、書かなくっちゃ…」と思いつつ、ブログの更新をさぼっておりました。ということで今回は、一昨日終了した今年の大学での授業(年明けにあと2回ありますが…)の中で、本年度から担当した「職業・キャリア教育」についての雑感を…。
この授業のテーマは「労働者保護は、どうあるべきか?」。昨今、日本の労働市場では「就職できない若者の増加」「低賃金非正規労働者の増加」他、多くの課題を抱えている。
そんな中、「これから就活に臨む学生たちが、知名度や条件だけで企業や団体を選択して欲しくない!」との思いから、既存の『労働者保護の法律』についての理解を深めると共に、『採用内定取消・解雇規制』『非正規社員』『男女間の賃金・待遇格差』他をテーマに、毎回、討論をしてもらっている。
で、今年最後の授業(第13回)のテーマは、『高齢者雇用』。高年齢者雇用安定法の概要説明をした後、「みんなは、自分には関係ないと思っているかもしれないけれど…(←高齢者雇用を、年金問題・若年者雇用等々と関連があると考える学生は多くないので…)」と前置きし、「定年制があった方がよいと思うか?」を討論してもらった。
各グループの話に聞き耳を立てていると、予想通り(?)「定年が無いと自分は死ぬまで働き続けちゃいそう…」「高齢者の継続雇用で若者の就労機会が減るのは困るけど、ウチの親父60だし、自分が卒業するまでは頑張ってもらわないと…」等、自分たちに直接関わる話題に終始してる。
そこで、昨今の雇用環境や年金制度の情報を提供しつつ、各グループで気になるコメントがあったら他のグループに「あっちでは、あんなこと話してたよ!」等と伝えることを意識した。そんなこともあってか、議論も中盤以降は「そもそも何で定年制が出来たんだろう?」等の話が聞えはじめ、ホッ…。
以下、出席簿代わりに書いてもらっている感想の一部。
「高齢者雇用について、私には殆ど関係ない話だと思っていたけれど、話は全てつながっていることに気付いた。選挙のこと(←私が「選挙行けよ!」と話したので…)もそうだけど、私は制度・政治等に無関心すぎる。もっと、なぜこの制度が出来たのかなどの視点で見ていくことが出来ないと、人生損する気がした。」
「一人ひとりそれぞれの立場によって、モノの見方や考え方は変わるからこそ、自分自身の視野を広げたり、価値観を高めるべきだと思った。そのためには、多くの情報を取り入れ、その中で取捨選択することが大切だと感じた。」
「何が良い悪いということではなく、世の中の制度はもう決まっているのだから…と思ってしまうのではなく、自分にも関係があり、今後生きていく上で損をしないためにも、いろいろな立場の人の様々な意見や考え方を知ることが必要であると感じました。正直、今回もこの話し合いをしなければ、女性である自分に定年制のことはあまり関係ないと感じ、気にもしていませんでした。しかし、今回の授業ではじめて考えることなどもあり、他人事ではないと思いました。」
私は、学者じゃなく人材コンサルタントだということも影響(?)してか、学生のコメントの中に「損をしないためにも…」といったコメントが見られるけれど、コレも大切なこと。
学生たちが、「自分たちの身の回りで起こっているコトやルールはすべて自分にも関係しているということ」「自分も社会の一員であること」を理解し、自分事として捉えはじめてくれていることが嬉しい感想でした。

ここのところ、「書かなくっちゃ、書かなくっちゃ…」と思いつつ、ブログの更新をさぼっておりました。ということで今回は、一昨日終了した今年の大学での授業(年明けにあと2回ありますが…)の中で、本年度から担当した「職業・キャリア教育」についての雑感を…。
この授業のテーマは「労働者保護は、どうあるべきか?」。昨今、日本の労働市場では「就職できない若者の増加」「低賃金非正規労働者の増加」他、多くの課題を抱えている。
そんな中、「これから就活に臨む学生たちが、知名度や条件だけで企業や団体を選択して欲しくない!」との思いから、既存の『労働者保護の法律』についての理解を深めると共に、『採用内定取消・解雇規制』『非正規社員』『男女間の賃金・待遇格差』他をテーマに、毎回、討論をしてもらっている。
で、今年最後の授業(第13回)のテーマは、『高齢者雇用』。高年齢者雇用安定法の概要説明をした後、「みんなは、自分には関係ないと思っているかもしれないけれど…(←高齢者雇用を、年金問題・若年者雇用等々と関連があると考える学生は多くないので…)」と前置きし、「定年制があった方がよいと思うか?」を討論してもらった。
各グループの話に聞き耳を立てていると、予想通り(?)「定年が無いと自分は死ぬまで働き続けちゃいそう…」「高齢者の継続雇用で若者の就労機会が減るのは困るけど、ウチの親父60だし、自分が卒業するまでは頑張ってもらわないと…」等、自分たちに直接関わる話題に終始してる。
そこで、昨今の雇用環境や年金制度の情報を提供しつつ、各グループで気になるコメントがあったら他のグループに「あっちでは、あんなこと話してたよ!」等と伝えることを意識した。そんなこともあってか、議論も中盤以降は「そもそも何で定年制が出来たんだろう?」等の話が聞えはじめ、ホッ…。
以下、出席簿代わりに書いてもらっている感想の一部。
「高齢者雇用について、私には殆ど関係ない話だと思っていたけれど、話は全てつながっていることに気付いた。選挙のこと(←私が「選挙行けよ!」と話したので…)もそうだけど、私は制度・政治等に無関心すぎる。もっと、なぜこの制度が出来たのかなどの視点で見ていくことが出来ないと、人生損する気がした。」
「一人ひとりそれぞれの立場によって、モノの見方や考え方は変わるからこそ、自分自身の視野を広げたり、価値観を高めるべきだと思った。そのためには、多くの情報を取り入れ、その中で取捨選択することが大切だと感じた。」
「何が良い悪いということではなく、世の中の制度はもう決まっているのだから…と思ってしまうのではなく、自分にも関係があり、今後生きていく上で損をしないためにも、いろいろな立場の人の様々な意見や考え方を知ることが必要であると感じました。正直、今回もこの話し合いをしなければ、女性である自分に定年制のことはあまり関係ないと感じ、気にもしていませんでした。しかし、今回の授業ではじめて考えることなどもあり、他人事ではないと思いました。」
私は、学者じゃなく人材コンサルタントだということも影響(?)してか、学生のコメントの中に「損をしないためにも…」といったコメントが見られるけれど、コレも大切なこと。
学生たちが、「自分たちの身の回りで起こっているコトやルールはすべて自分にも関係しているということ」「自分も社会の一員であること」を理解し、自分事として捉えはじめてくれていることが嬉しい感想でした。

キャリアについて考える意味 Vol.5
キャリアについて考える意味 Vol.4
キャリアについて考える意味 Vol.3
キャリアについて考える意味 Vol.2
キャリアについて考える意味 Vol.1
キャリア開発論、終了!!
キャリアについて考える意味 Vol.4
キャリアについて考える意味 Vol.3
キャリアについて考える意味 Vol.2
キャリアについて考える意味 Vol.1
キャリア開発論、終了!!