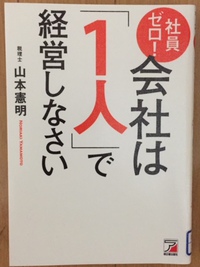2009年03月18日
フリーペーパーの衝撃
~稲垣太郎 著~
仕事柄、読んでみました。
フリーペーパーのビジネスモデルを知らない人にとっても、わかりやすく書かれています。
個人的には、業界の知人や当事者として働いていた会社、業務提携企業や旧知の社長が出てきたりと、結構楽しめたかな…?!
以下、備忘録代わりに気になった箇所を…
<無料誌の生命線は流通方法そのもの>
どんなに記事内容が優れていても、流通方法の最適化なしにはその効果は発揮できない←その通り。
1. ハンディング(手渡し)、2.ポスティング(宅配)、3.オフィスデリバリー(職域配布)、4。テイクワンラック(ラック置き)の4つの方法のうちで、最も適した方法を選んだり、組み合わせることが大切。
<AIDMAからAISASへ>
インターネットの登場で、メディア広告効果を推し量る考え方にも変化が見られる。
AIDMA:認知(Attention)→興味(Interest)→欲求(Desire)→記憶(Memory)→行動(Action)
↓ に加えて…
AISAS:認知(Attention)→興味(Interest)→検索(Search)→行動(Action)→意見共有(Share)
<読者の時間を広告主に売る>
『メトロ』のアンデション氏によれば、有料誌も無料誌も、同じものを売っている。記者は読者が読むための記事を読者に提供し、その引き替えに読者から読むために費やす時間をもらう。記事が面白いから、読者はそれを読むための時間を割く。
無料誌のビジネスも広告主の手にあるのではなく、間違いなく読者の手に委ねられている。読者の信頼と時間をもらえなければ、広告主に売るものは何もない。
最後に、「有料誌は読者が選ぶもの、フリーペーパーは読者を選ぶもの」の記載には、思わず納得です。

仕事柄、読んでみました。
フリーペーパーのビジネスモデルを知らない人にとっても、わかりやすく書かれています。
個人的には、業界の知人や当事者として働いていた会社、業務提携企業や旧知の社長が出てきたりと、結構楽しめたかな…?!
以下、備忘録代わりに気になった箇所を…
<無料誌の生命線は流通方法そのもの>
どんなに記事内容が優れていても、流通方法の最適化なしにはその効果は発揮できない←その通り。
1. ハンディング(手渡し)、2.ポスティング(宅配)、3.オフィスデリバリー(職域配布)、4。テイクワンラック(ラック置き)の4つの方法のうちで、最も適した方法を選んだり、組み合わせることが大切。
<AIDMAからAISASへ>
インターネットの登場で、メディア広告効果を推し量る考え方にも変化が見られる。
AIDMA:認知(Attention)→興味(Interest)→欲求(Desire)→記憶(Memory)→行動(Action)
↓ に加えて…
AISAS:認知(Attention)→興味(Interest)→検索(Search)→行動(Action)→意見共有(Share)
<読者の時間を広告主に売る>
『メトロ』のアンデション氏によれば、有料誌も無料誌も、同じものを売っている。記者は読者が読むための記事を読者に提供し、その引き替えに読者から読むために費やす時間をもらう。記事が面白いから、読者はそれを読むための時間を割く。
無料誌のビジネスも広告主の手にあるのではなく、間違いなく読者の手に委ねられている。読者の信頼と時間をもらえなければ、広告主に売るものは何もない。
最後に、「有料誌は読者が選ぶもの、フリーペーパーは読者を選ぶもの」の記載には、思わず納得です。

Posted by オルベア at 12:30│Comments(4)
│書評
この記事へのコメント
すごい!
勉強になります◎◎
勉強になります◎◎
Posted by しずおカードだら at 2009年03月18日 13:05
しずおカードだらさん
こんにちは、コメントありがとう。
参考にしていただけたのであれば、幸いです。
こんにちは、コメントありがとう。
参考にしていただけたのであれば、幸いです。
Posted by オルベア at 2009年03月18日 17:55
at 2009年03月18日 17:55
 at 2009年03月18日 17:55
at 2009年03月18日 17:55藤井大輔氏の『「R25」のつくりかた』と本書を併読すると、面白さ倍増です。
特に、第二章(フリーマガジン大国・日本)。
「不振にあえぐ有料誌」「地方の有料誌が次々に休刊」等を読んで、目から鱗でした。
出版不況、雑誌不況を表層的に捉えるのでなく、有料誌/無料誌という切り口も有ったのですね。
札幌のタウン情報誌『イエローページ』が、後発の無料誌『ホットペッパー』との競争に敗れ休刊する下り。
その『イエローページ』の先駆者として、地元には『ステージガイドさっぽろ』や『すすきのタウン情報』等の有料誌の栄枯盛衰があったことを思い出させてくれました。
第七章(有料と無料の違いって何だ? 吉良俊彦氏との対談)も、ユニークな出版文化論として参考になりました。
特に、第二章(フリーマガジン大国・日本)。
「不振にあえぐ有料誌」「地方の有料誌が次々に休刊」等を読んで、目から鱗でした。
出版不況、雑誌不況を表層的に捉えるのでなく、有料誌/無料誌という切り口も有ったのですね。
札幌のタウン情報誌『イエローページ』が、後発の無料誌『ホットペッパー』との競争に敗れ休刊する下り。
その『イエローページ』の先駆者として、地元には『ステージガイドさっぽろ』や『すすきのタウン情報』等の有料誌の栄枯盛衰があったことを思い出させてくれました。
第七章(有料と無料の違いって何だ? 吉良俊彦氏との対談)も、ユニークな出版文化論として参考になりました。
Posted by 豊平川 at 2009年04月17日 10:50
豊平川さま
こんにちは、豊平川さんって僕の存じている方でしょうか…?
「R25」のつくりかた、読もう読もうと思っていながら、実はまだ読んでいません。
早々(かどうかわかりませんが…)、読んでみたいと思います。
こんにちは、豊平川さんって僕の存じている方でしょうか…?
「R25」のつくりかた、読もう読もうと思っていながら、実はまだ読んでいません。
早々(かどうかわかりませんが…)、読んでみたいと思います。
Posted by オルベア at 2009年04月17日 17:24
at 2009年04月17日 17:24
 at 2009年04月17日 17:24
at 2009年04月17日 17:24