2008年11月21日
ルポ“正社員”の若者たち―就職氷河期世代を追う
小林 美希 著
就職氷河期時代に社会に出た若者たちのルポルタージュだ。
私自身、長い間、求人情報誌・人材派遣・人材紹介・再就職支援等の仕事に携わってきたこともあり、ルポされてる人材・SE・コンビニ・介護業界…等で仕事をする若者たちの悲惨な現状に対し、驚きというよりもリアルに目に浮かんでしまうのが辛い。
そもそも僕が起業した理由も、こんな悲惨な状況を少しでも変えていきたいという想いでのことだし…。
読んでいて胸が締め付けられちゃうけれど、大切なのはそこから!当事者はもちろんだけど当事者じゃないと思っているひとりひとりが、「自分に出来ることは何か?」を考え具体的な行動に移していくことなんだろうと思う。
若者だけでなく、むしろ経営者や親たちに読んで欲しい本だ!!

就職氷河期時代に社会に出た若者たちのルポルタージュだ。
私自身、長い間、求人情報誌・人材派遣・人材紹介・再就職支援等の仕事に携わってきたこともあり、ルポされてる人材・SE・コンビニ・介護業界…等で仕事をする若者たちの悲惨な現状に対し、驚きというよりもリアルに目に浮かんでしまうのが辛い。
そもそも僕が起業した理由も、こんな悲惨な状況を少しでも変えていきたいという想いでのことだし…。
読んでいて胸が締め付けられちゃうけれど、大切なのはそこから!当事者はもちろんだけど当事者じゃないと思っているひとりひとりが、「自分に出来ることは何か?」を考え具体的な行動に移していくことなんだろうと思う。
若者だけでなく、むしろ経営者や親たちに読んで欲しい本だ!!

2008年11月01日
仕事の裏切り
人間にとって「仕事とは何なのか?」を、歴史・哲学・経営学にオーバーラップして書かれている。
この本は3部構成になっており、第1部では「歴史と哲学を踏まえた仕事観」、第2部では「産業社会のなかにおける仕事」、第3部は「人生や生活そのもの」について書いてある。
いや~、とにかく深い。例えば、第1部では、「ギリシャの時代は、働くことは出来れば避けたい呪いだった。6世紀になると修道院では働くことは奉仕であり祈ることの方が大切なこと~宗教改革以降は働くことと祈りの位置づけが逆転…」等々。
働く目的は人それぞれ。キャリアカウンセラーやコーチ等、キャリアをサポートする仕事に就いている人はもちろん、「何故、働くのか?」と迷っているあなたも読んでみたらいかがでしょう。

この本は3部構成になっており、第1部では「歴史と哲学を踏まえた仕事観」、第2部では「産業社会のなかにおける仕事」、第3部は「人生や生活そのもの」について書いてある。
いや~、とにかく深い。例えば、第1部では、「ギリシャの時代は、働くことは出来れば避けたい呪いだった。6世紀になると修道院では働くことは奉仕であり祈ることの方が大切なこと~宗教改革以降は働くことと祈りの位置づけが逆転…」等々。
働く目的は人それぞれ。キャリアカウンセラーやコーチ等、キャリアをサポートする仕事に就いている人はもちろん、「何故、働くのか?」と迷っているあなたも読んでみたらいかがでしょう。

2008年10月03日
踊る大捜査線に学ぶ組織論入門
2005年9月初版なんで、だいぶ古いんですが、「経営学の権化(?)である金井寿宏先生が、『踊る大走査線』をどう料理するんだろう?」という興味で読んでみた。
う~ん、やっぱり金井先生、徒者じゃありません。難しい話をより難しく説明する学者は多いけれど、娯楽映画をモチーフに組織論を誰にでもわかるように解説しちゃうとことがスゴイです。
しかも、おもしろい。自分の身の回りで起きていることを、論理立て説明することの大切さを痛感させられました。
「組織論を学んでみたい人」「踊る大捜査線フリーク」「単にタイトルに惹かれた人」…、誰が読んでも満足できる一冊なんじゃないかな?!

う~ん、やっぱり金井先生、徒者じゃありません。難しい話をより難しく説明する学者は多いけれど、娯楽映画をモチーフに組織論を誰にでもわかるように解説しちゃうとことがスゴイです。
しかも、おもしろい。自分の身の回りで起きていることを、論理立て説明することの大切さを痛感させられました。
「組織論を学んでみたい人」「踊る大捜査線フリーク」「単にタイトルに惹かれた人」…、誰が読んでも満足できる一冊なんじゃないかな?!

2008年09月15日
ダイバーシティ
ここのところまとまった時間がとれなかったこともあり、この3連休、「本読みた~い!?」という気分になり、なんとなく手に取ったのがダイバーシティー関連の2冊。
<ダイバーシティ>
山口一男氏が社会学の先生だということも、どんな内容の本なのかということもわからず、『ダイバーシティ』というタイトルに惹かれて購入。
筆者創作の社会科学的ファンタジー「六つボタンのミナとカズの魔法使い」と筆者が教鞭をとっているアメリカでの日本文化論の1コマを、フィクションを交え書き綴った教育劇・日米規範文化比較論「ライオンと鼠」の2部構成。
この2つの作品が「ダイバーシティ=多様性」という点でリンクしており、これで1つの作品となっている。
「社会学が何たるか?」なんてことを全く理解していない僕が読んでもすっごくおもしろくて、『ダイバーシティ』ってそういうことなのね、と納得してしまった。これは僕的には★5つかな…。

<コーチングが組織(ダイバーシティ)を活かす>
タイトルにダイバーシティって入ってたんで、手を伸ばしたが、これ日産の人事企画部長西澤正昭氏の書いた人財開発に関する本ですね。
日産の復活劇の裏には、人財開発が大きく関わっていることを知る上ではすごくおもしろい本だけど、主には日産の人材開発についての考え方やコーチングについて書かれた本で、「ダイバーシティについて知りたい!」と思って読んだ僕にはちょいと期待はずれでした。
「あとがき」に、「特に女子大生の就職人気ランキング低迷を打破するために書いた」との記載に思わず納得!?実際に「日産は人財開発に積極的」を理由に応募する学生、増えたようです。

ということで、読書で終わった3連休でした。
<ダイバーシティ>
山口一男氏が社会学の先生だということも、どんな内容の本なのかということもわからず、『ダイバーシティ』というタイトルに惹かれて購入。
筆者創作の社会科学的ファンタジー「六つボタンのミナとカズの魔法使い」と筆者が教鞭をとっているアメリカでの日本文化論の1コマを、フィクションを交え書き綴った教育劇・日米規範文化比較論「ライオンと鼠」の2部構成。
この2つの作品が「ダイバーシティ=多様性」という点でリンクしており、これで1つの作品となっている。
「社会学が何たるか?」なんてことを全く理解していない僕が読んでもすっごくおもしろくて、『ダイバーシティ』ってそういうことなのね、と納得してしまった。これは僕的には★5つかな…。

<コーチングが組織(ダイバーシティ)を活かす>
タイトルにダイバーシティって入ってたんで、手を伸ばしたが、これ日産の人事企画部長西澤正昭氏の書いた人財開発に関する本ですね。
日産の復活劇の裏には、人財開発が大きく関わっていることを知る上ではすごくおもしろい本だけど、主には日産の人材開発についての考え方やコーチングについて書かれた本で、「ダイバーシティについて知りたい!」と思って読んだ僕にはちょいと期待はずれでした。
「あとがき」に、「特に女子大生の就職人気ランキング低迷を打破するために書いた」との記載に思わず納得!?実際に「日産は人財開発に積極的」を理由に応募する学生、増えたようです。

ということで、読書で終わった3連休でした。
2008年09月12日
ザ・ファシリテーター2―理屈じゃ、誰も動かない!
以前読んだ「ザ・ファシリティター」の続編。日本ファシリテーション協会理事の森時彦氏の著書だ。
副題の「理屈じゃ、誰も動かない!」っていうのがいいですね。全作同様、小説仕立てでファシリテーションが理解できるっていうのがおすすめです。
最近、ファシリテーション、コーチング、カウンセリング他、いろんな資格が生まれ、且ついろんな団体が出てきている。
「ファシリテーションとコーチングはココが違う!」とか「私の持っている資格は●●のお墨付きをもらっているから…」等の話を聞くことにうんざりしている私としては、森氏が小説の中で「大切なことは、仕事を進めるには何がいちばん効果的かということであり、実務に携わっている私たちにとっては、どうでもいい」という下りに妙に頷いてしまった。
本文中に『変革ファシリテーターの要件』という記載があったので、備忘録替わりに羅列しておこう。
・高い目的意識
・楽観力
・システム思考力
・変革プロセスに関する知識と経験
・前向き:対立のエネルギーを前進の糧に変革する気力
・未来志向:過去にこだわらない
・外向き:顧客志向
・行動力
・自分たちを客観視する力
要は、資格じゃなく羅列したような要件を持っているか否か?なんだよね。当たり前のことだけど…

副題の「理屈じゃ、誰も動かない!」っていうのがいいですね。全作同様、小説仕立てでファシリテーションが理解できるっていうのがおすすめです。
最近、ファシリテーション、コーチング、カウンセリング他、いろんな資格が生まれ、且ついろんな団体が出てきている。
「ファシリテーションとコーチングはココが違う!」とか「私の持っている資格は●●のお墨付きをもらっているから…」等の話を聞くことにうんざりしている私としては、森氏が小説の中で「大切なことは、仕事を進めるには何がいちばん効果的かということであり、実務に携わっている私たちにとっては、どうでもいい」という下りに妙に頷いてしまった。
本文中に『変革ファシリテーターの要件』という記載があったので、備忘録替わりに羅列しておこう。
・高い目的意識
・楽観力
・システム思考力
・変革プロセスに関する知識と経験
・前向き:対立のエネルギーを前進の糧に変革する気力
・未来志向:過去にこだわらない
・外向き:顧客志向
・行動力
・自分たちを客観視する力
要は、資格じゃなく羅列したような要件を持っているか否か?なんだよね。当たり前のことだけど…

2008年05月07日
ディズニーに学ぶ満足循環力
~「お客様満足」+「社員満足」の秘密~
著者の志澤秀一氏は、元オリエンタルランド人事部ユニバーサル課で、東京ディスニーランド開業前のキャスト教育を担当していた方。
で、昨今話題のCS(顧客満足)とES(社員満足)について、東京ディズニーランドのカストーディアル等を例にあげ、ご自身の考え方を述べられている。
で、志澤氏の論旨ですが、「CSとESの関係は、どちらがどちらを補完するのではなく、絶え間なく循環している関係」というもの。
うん、おっしゃるとおりだと思います。例も具体的でわかりやすいですしネ!?
特にディズニーランド好きのみなさんだったら、読む価値大ですよ。

著者の志澤秀一氏は、元オリエンタルランド人事部ユニバーサル課で、東京ディスニーランド開業前のキャスト教育を担当していた方。
で、昨今話題のCS(顧客満足)とES(社員満足)について、東京ディズニーランドのカストーディアル等を例にあげ、ご自身の考え方を述べられている。
で、志澤氏の論旨ですが、「CSとESの関係は、どちらがどちらを補完するのではなく、絶え間なく循環している関係」というもの。
うん、おっしゃるとおりだと思います。例も具体的でわかりやすいですしネ!?
特にディズニーランド好きのみなさんだったら、読む価値大ですよ。

2008年04月14日
紙飛行機が会議室を舞った
~人生を決める社会人基礎力~
みなさん、『社会人基礎力』ってご存じでしょうか?2006年2月、経済産業省が大学生や社会人に是非身に付けて欲しいと提唱した12の能力のコトを指します。
その12の能力は、アクション(一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力)、シンキング(疑問を持ち、考え抜く力)、チームワーク(多様な人々と共に、目標に向けて協力する力)と、大きく3つに分類されます。
で、僕自身、『社会人基礎力』をベースに企業・若者・学校等のつながりの強化や育成・評価に向けた一貫した枠組みが出来ればいいと常々思っていたのですが…。
そんな中、先日、横山征次さん(今回紹介する本の著者)にお会いする機会があって、「んじゃ、読んでみようかな…」と。
小説仕立てのこの本、物語の展開には少なからず無理があるけど、『社会人基礎力』の12の能力を小説の中に上手く盛り込んでわかりやすく表現している。この本を読んだからって『社会人基礎力』が身に付く訳じゃないけれど、『社会人基礎力』がどんなモノなのかを理解するテキストとしては良くできてるんじゃないでしょうか?!
『社会人基礎力』に興味がある人は、読んでみてみて…!?

みなさん、『社会人基礎力』ってご存じでしょうか?2006年2月、経済産業省が大学生や社会人に是非身に付けて欲しいと提唱した12の能力のコトを指します。
その12の能力は、アクション(一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力)、シンキング(疑問を持ち、考え抜く力)、チームワーク(多様な人々と共に、目標に向けて協力する力)と、大きく3つに分類されます。
で、僕自身、『社会人基礎力』をベースに企業・若者・学校等のつながりの強化や育成・評価に向けた一貫した枠組みが出来ればいいと常々思っていたのですが…。
そんな中、先日、横山征次さん(今回紹介する本の著者)にお会いする機会があって、「んじゃ、読んでみようかな…」と。
小説仕立てのこの本、物語の展開には少なからず無理があるけど、『社会人基礎力』の12の能力を小説の中に上手く盛り込んでわかりやすく表現している。この本を読んだからって『社会人基礎力』が身に付く訳じゃないけれど、『社会人基礎力』がどんなモノなのかを理解するテキストとしては良くできてるんじゃないでしょうか?!
『社会人基礎力』に興味がある人は、読んでみてみて…!?

2008年04月13日
ビジョナリーカンパニー②
~飛躍の法則~
遅ればせながら…、『ビジョナリーカンパニー②』を読んでみた。
1994年に出版され、経営書としてベストセラーになった『ビジョナリーカンパニー』も良かったけど、『ビジョナリーカンパニー②』はそれ以上!?ジェームス・C・コリンズ先生はこんな様なことを言ってます。
偉大な会社を作るためには、優れた経営幹部の存在が不可欠。とはいえ、ここで言う優れた経営者とは、強烈な個性の下で指導力を発揮し大胆な経営手法を駆使するジャック・ウェルチの様な経営者ではない。
優れた経営者は、職業人としての強い意志とねばり強さはあるけれど、控えめで物静かで謙虚…。異なる意見に耳を傾け、従業員とじっくり対話し、リアリティの持つ多面性を総合化していく。
う~ん、示唆に富んだコメントだ。やっぱりジェームス・C・コリンズ先生はスゴイです!?

遅ればせながら…、『ビジョナリーカンパニー②』を読んでみた。
1994年に出版され、経営書としてベストセラーになった『ビジョナリーカンパニー』も良かったけど、『ビジョナリーカンパニー②』はそれ以上!?ジェームス・C・コリンズ先生はこんな様なことを言ってます。
偉大な会社を作るためには、優れた経営幹部の存在が不可欠。とはいえ、ここで言う優れた経営者とは、強烈な個性の下で指導力を発揮し大胆な経営手法を駆使するジャック・ウェルチの様な経営者ではない。
優れた経営者は、職業人としての強い意志とねばり強さはあるけれど、控えめで物静かで謙虚…。異なる意見に耳を傾け、従業員とじっくり対話し、リアリティの持つ多面性を総合化していく。
う~ん、示唆に富んだコメントだ。やっぱりジェームス・C・コリンズ先生はスゴイです!?

2008年01月04日
デビルパワーエンジェルパワー
うわ~、ホントに久々の日記(何と昨年の12月21日以来)です。
ということで、先ずは、「明けまして、おめでとうございます」ですね。
年始の3日間は、とにかく「何もしない!」を心がけ(?)、やったことといったら本を1冊読んだだけ…。ということで、年初1回目の日記は『デビルパワーエンジェルパワー』(著者は、『にわとりを殺すな』のケビン・D・ワンさん)の書評です。
この本、マネジメントについて書かれた本だけど、ストーリー仕立てになっていてすっごく読みやすい。以前読んだ『仕事はたのしいかね?』(ティル・ドーテン著)にも似た感じかな…?
タイトルの『デビルパワー』とは、悪魔のような細心さ、悪魔のような執着性、悪魔のような徹底性、悪魔のようなきびしさを指し、何事かを成功させるときには不可欠な要素。とはいえ、マネジメントをする人間は、『デビルパワー』だけじゃ片手落ちであり、加えて『エンジェルパワー』(他人を認めること、愛情、相手の気持ちを考える等々)も必要とのこと。
「経営は人が財産、社員が自分の会社を愛し、ここで働くのが楽しいと感じ、動いてくれて、はじめてコトが成し遂げられる」ということが非常にわかりやすく書いてある。
バブル経済崩壊後、目先の利益だけに着目し、バランスを崩している多くの日本の経営者へのケビンさんのメッセージ…!?
新年早々、いい本を読んじゃいました。

ということで、先ずは、「明けまして、おめでとうございます」ですね。
年始の3日間は、とにかく「何もしない!」を心がけ(?)、やったことといったら本を1冊読んだだけ…。ということで、年初1回目の日記は『デビルパワーエンジェルパワー』(著者は、『にわとりを殺すな』のケビン・D・ワンさん)の書評です。
この本、マネジメントについて書かれた本だけど、ストーリー仕立てになっていてすっごく読みやすい。以前読んだ『仕事はたのしいかね?』(ティル・ドーテン著)にも似た感じかな…?
タイトルの『デビルパワー』とは、悪魔のような細心さ、悪魔のような執着性、悪魔のような徹底性、悪魔のようなきびしさを指し、何事かを成功させるときには不可欠な要素。とはいえ、マネジメントをする人間は、『デビルパワー』だけじゃ片手落ちであり、加えて『エンジェルパワー』(他人を認めること、愛情、相手の気持ちを考える等々)も必要とのこと。
「経営は人が財産、社員が自分の会社を愛し、ここで働くのが楽しいと感じ、動いてくれて、はじめてコトが成し遂げられる」ということが非常にわかりやすく書いてある。
バブル経済崩壊後、目先の利益だけに着目し、バランスを崩している多くの日本の経営者へのケビンさんのメッセージ…!?
新年早々、いい本を読んじゃいました。

2007年11月12日
フリーターにはゼッタイになるな!!
~高校生が自分で将来設計をするキャリアプランの本~
今年の夏、お話を聴かせていただき、すっかりFANになっちゃった高橋誠先生の書籍。
書籍というより、ワークブックという感じかな…?!
将来のこと、考えることもなく、進学や就職しちゃう高校生が多い現状を考えると、「こういった本は必要なんだろうな~」といろいろ考えちゃう。
わかりやすいし、使いやすい本です。まぁ、学生は一人じゃやらない可能性が高いので、先生のインストラクションは必要だとは思うけど…
キャリアカウンセラーがテキストとして使うには、最適なんじゃないでしょうか?!
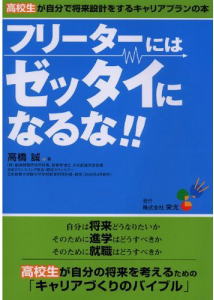
今年の夏、お話を聴かせていただき、すっかりFANになっちゃった高橋誠先生の書籍。
書籍というより、ワークブックという感じかな…?!
将来のこと、考えることもなく、進学や就職しちゃう高校生が多い現状を考えると、「こういった本は必要なんだろうな~」といろいろ考えちゃう。
わかりやすいし、使いやすい本です。まぁ、学生は一人じゃやらない可能性が高いので、先生のインストラクションは必要だとは思うけど…
キャリアカウンセラーがテキストとして使うには、最適なんじゃないでしょうか?!
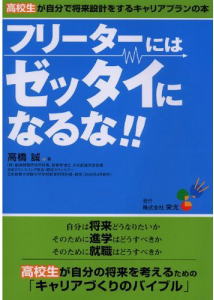
2007年11月01日
働く理由
~99の名言に学ぶシゴト論~
仕事柄、『働く』ってキーワードに弱い僕は、本屋さんで思いっきり平積みしてた『働く理由』を思わず購入。
キャリア・カウンセラーにはおなじみの、ドナルド・E・スーパー、ジョン・クルンボルツから、果てはニーチェに松坂大輔まで、著名人の名言を紹介しながら、著者なりのコメント(解説)を付けてくれるって事で、わかりやすいし、頭にもス~ッて入ってくる。
けど、大枚1,440円を支払う価値があるかと問われると?ちょっと言葉に詰まっちゃう。まぁ、キャリア・カウンセラーがクライアントと相対した際に使うトーク集として便利かもネ!?
とはいえ、mixiのレビューでの評価が高いのはよく理解できるし、いいこと書いてると思います。
ということで、僕の評価は★3.5(5.0満点で…)ってところでしょうか…?!

仕事柄、『働く』ってキーワードに弱い僕は、本屋さんで思いっきり平積みしてた『働く理由』を思わず購入。
キャリア・カウンセラーにはおなじみの、ドナルド・E・スーパー、ジョン・クルンボルツから、果てはニーチェに松坂大輔まで、著名人の名言を紹介しながら、著者なりのコメント(解説)を付けてくれるって事で、わかりやすいし、頭にもス~ッて入ってくる。
けど、大枚1,440円を支払う価値があるかと問われると?ちょっと言葉に詰まっちゃう。まぁ、キャリア・カウンセラーがクライアントと相対した際に使うトーク集として便利かもネ!?
とはいえ、mixiのレビューでの評価が高いのはよく理解できるし、いいこと書いてると思います。
ということで、僕の評価は★3.5(5.0満点で…)ってところでしょうか…?!

2007年10月08日
ビジョナリー・カンパニー
ジェームス・C・コリンズの名著。初版は1995年、「何を今更?」なんて言わないで。僕自身、何でもっと早く読まなかったんだって後悔してるんだから…。
著者も言うように、こまかな記述まで全て覚える必要はない。大切なことは、以下の4つ!?
1.時を告げる予言者になるな。時計をつくる設計者になれ
「時を告げる」のは素晴らしいビジョンを持ったカリスマ的指導者だけど、カリスマは必要ない。大切なのは、自分が去った後も永遠に時を告げる時計をつくるということ。う~ん、しびれる~
2.「ANDの才能」を重視しよう
ビジョナリーカンパニーの経営幹部は、「短期的な業績」または「長期的な成功」の二者択一なんてしない。長期的な成功を目指しながら、同時に短期的な業績にも拘る。う~ん、同感!?
3.基本理念を維持し、進歩を促す
世界は変化している。組織が対応するためには、企業として前進しながら、信念以外の組織のすべてを変える覚悟で臨まなくてはならない。う~ん、納得!?
4.一貫性を追求しよう
重要なのは、驚くほど広範囲に、驚くほどの一貫性を、長期にわたって保つこと。う~ん、そのとおり!?
てな具合に、特別なコトが書いてあるわけじゃないけれど、だからこそ、共感出来るんだろう。全編通して、上記4つを実証するため、いろんな角度から分析している本だけど、1冊読んだら、僕の本は、付箋とアンダーラインだらけになっちゃいました~。

著者も言うように、こまかな記述まで全て覚える必要はない。大切なことは、以下の4つ!?
1.時を告げる予言者になるな。時計をつくる設計者になれ
「時を告げる」のは素晴らしいビジョンを持ったカリスマ的指導者だけど、カリスマは必要ない。大切なのは、自分が去った後も永遠に時を告げる時計をつくるということ。う~ん、しびれる~
2.「ANDの才能」を重視しよう
ビジョナリーカンパニーの経営幹部は、「短期的な業績」または「長期的な成功」の二者択一なんてしない。長期的な成功を目指しながら、同時に短期的な業績にも拘る。う~ん、同感!?
3.基本理念を維持し、進歩を促す
世界は変化している。組織が対応するためには、企業として前進しながら、信念以外の組織のすべてを変える覚悟で臨まなくてはならない。う~ん、納得!?
4.一貫性を追求しよう
重要なのは、驚くほど広範囲に、驚くほどの一貫性を、長期にわたって保つこと。う~ん、そのとおり!?
てな具合に、特別なコトが書いてあるわけじゃないけれど、だからこそ、共感出来るんだろう。全編通して、上記4つを実証するため、いろんな角度から分析している本だけど、1冊読んだら、僕の本は、付箋とアンダーラインだらけになっちゃいました~。

2007年08月01日
奥山清行さんって、スゴ~イ!!
~フェラーリと鉄瓶~
フェラーリ創業55年記念モデル『エンツォ・フェラーリ』をデザインした工業デザイナー奥山清行氏の著、ということで読んだ本。
あの『エンツォ・フェラーリ』を日本人がデザインしたというだけで、驚きなのだが、奥山氏の凄さはそれだけじゃない。
日本の美大を卒業後、就職もせずにアメリカに渡った奥山氏は、アメリカの大学を卒業後GM、ドイツのポルシェ、再びGMで管理職を…。その後、イタリアのピニンファリーナでチーフデザイナー、アメリカの大学でデザインを教え、ピニンファリーナでデザインディレクター、その後独立というスゴイ経歴の持ち主だ。
で、そんな奥山氏に、「好きなことだったら、いくら努力してもつらいとは感じない」「自分にとって何が好きなのかを見つけること、そして途中からやり直してでもその道に進むことが、人生では重要だと思う」と言われちゃうと、妙に納得してしまう。
また、「日本では『自分のために働く』と宣言することは罪悪のように感じられるようだが、最初に『自分』があって、すべてのことはそれに付随するものでしかない。」というコメントにも…。
その一方で、「日本の一地方が、東京を経由せずに世界に文化を発信することを実現するための実験・実践のために『山形カロッツェリア研究会』を作り、山形のものづくりに活かそうと考える」等、僕のイメージする工業デザイナーの域を遙かに超えている。
この本は、奥山氏の生きざまを通し、『働くことの意味』『挑戦することの尊さ』を教えてくれる。

フェラーリ創業55年記念モデル『エンツォ・フェラーリ』をデザインした工業デザイナー奥山清行氏の著、ということで読んだ本。
あの『エンツォ・フェラーリ』を日本人がデザインしたというだけで、驚きなのだが、奥山氏の凄さはそれだけじゃない。
日本の美大を卒業後、就職もせずにアメリカに渡った奥山氏は、アメリカの大学を卒業後GM、ドイツのポルシェ、再びGMで管理職を…。その後、イタリアのピニンファリーナでチーフデザイナー、アメリカの大学でデザインを教え、ピニンファリーナでデザインディレクター、その後独立というスゴイ経歴の持ち主だ。
で、そんな奥山氏に、「好きなことだったら、いくら努力してもつらいとは感じない」「自分にとって何が好きなのかを見つけること、そして途中からやり直してでもその道に進むことが、人生では重要だと思う」と言われちゃうと、妙に納得してしまう。
また、「日本では『自分のために働く』と宣言することは罪悪のように感じられるようだが、最初に『自分』があって、すべてのことはそれに付随するものでしかない。」というコメントにも…。
その一方で、「日本の一地方が、東京を経由せずに世界に文化を発信することを実現するための実験・実践のために『山形カロッツェリア研究会』を作り、山形のものづくりに活かそうと考える」等、僕のイメージする工業デザイナーの域を遙かに超えている。
この本は、奥山氏の生きざまを通し、『働くことの意味』『挑戦することの尊さ』を教えてくれる。

2007年07月25日
創業者のコトバの重み
~“リクルートのDNA”読んじゃいました~
リクルート創業者、江副浩正氏の著書、“リクルートのDNA”を読んだ。
「リクルートが人材輩出企業だ!」というのは、よくいわれる話だし、多くのリクルート出身者が活躍していたり、その内容を本にしたりしていることも知っている(実際、僕も結構読んでるし…)。
けど、どんなにスゴイ活躍をしたところで、創業者には敵わない。成功事例を後から分析・評価したり、トレースしてグレードアップすることは、それほど難しいことではないが、“無から何かを生み出す!”というのは並大抵のコトじゃない。
そんなことを思いながら、一気に読んだ。「やっぱり、江副さんはスゴイ!」、僕の素直な感想だ!「へ~、そんなにスゴイの?」って思うんだったら、是非読んでみて欲しい。

心に残ったフレーズを書き留めておこう。
多面的な要素を求められるのが経営者の職能である。
したがって経営者は孤独である。
自ら起業した経営者はそのことを熟知している。
う~ん、納得!?
リクルート創業者、江副浩正氏の著書、“リクルートのDNA”を読んだ。
「リクルートが人材輩出企業だ!」というのは、よくいわれる話だし、多くのリクルート出身者が活躍していたり、その内容を本にしたりしていることも知っている(実際、僕も結構読んでるし…)。
けど、どんなにスゴイ活躍をしたところで、創業者には敵わない。成功事例を後から分析・評価したり、トレースしてグレードアップすることは、それほど難しいことではないが、“無から何かを生み出す!”というのは並大抵のコトじゃない。
そんなことを思いながら、一気に読んだ。「やっぱり、江副さんはスゴイ!」、僕の素直な感想だ!「へ~、そんなにスゴイの?」って思うんだったら、是非読んでみて欲しい。

心に残ったフレーズを書き留めておこう。
多面的な要素を求められるのが経営者の職能である。
したがって経営者は孤独である。
自ら起業した経営者はそのことを熟知している。
う~ん、納得!?
2007年06月22日
『静かなるホイッスル』、読んじゃいました!?
~第1章の主役は、東海大翔洋高校ラグビー部の倉津圭太君です~
聴覚障害者によるラグビーチームが日本に発足し、現在に至るまでの道のりを綴ったノンフィクション。
第1章の東海大翔洋高校ラグビー部、倉津圭太君のことが知りたくて読んでみた。「難聴者には無理だ」と言われたラグビーを続け、2005年全国高校ラグビーの全国大会(花園)に出場。彼は、ラグビーを通して、大切な仲間と一生の恩師を得、そしてあきらめなければ道は開けることを学んだ。
最初は、第1章だけのつもりだったけど、グイグイ引き込まれ、一気に第9章まで読んじゃった。で、僕が学んだことは…
■ 聴覚障害は、単に耳が聞こえないということではない
聴覚障害は「情報障害」と言われてるんだって。「聞こえる人なら当たり前に受けられる情報が、受けられない」ということで、周りにその気がなくても、当人は疎外されているように感じ、自分が他人より劣っているように思えてきちゃう。
■ 聞こえない健聴者
とはいえ、耳は聞こえても、相手の気持ちが聴こえないコトだってある。健聴者は、聴覚障害者を夢中で支援することで、相手の気持ちを傷付けちゃうことだってある。「支援の押し売りだ」、気をつけなくっちゃ!?
■ 障害者の中での差別?
難聴者と聾者は違う。難聴者は障害者であることが知られることを嫌い、難聴であることを隠して生きている人が多いんだって…。「自分たちは聾者とは違う!」って差別意識(?)を持っちゃうのかな~?
昔、マクセルのCMでスティービー・ワンダーが言ってたコメントを想い出した。こまかなコトは覚えてないけれど、「君には輝く太陽が見える、僕には君の心が見える…」とかいうCMだったと思うんだけど…
こんなこと言ってる人もいます。「物を見るのは魂であり、目それ自体は盲目である。物を聞くのは魂であり、耳それ自体は聾である」。う~ん、深い!

聴覚障害者によるラグビーチームが日本に発足し、現在に至るまでの道のりを綴ったノンフィクション。
第1章の東海大翔洋高校ラグビー部、倉津圭太君のことが知りたくて読んでみた。「難聴者には無理だ」と言われたラグビーを続け、2005年全国高校ラグビーの全国大会(花園)に出場。彼は、ラグビーを通して、大切な仲間と一生の恩師を得、そしてあきらめなければ道は開けることを学んだ。
最初は、第1章だけのつもりだったけど、グイグイ引き込まれ、一気に第9章まで読んじゃった。で、僕が学んだことは…
■ 聴覚障害は、単に耳が聞こえないということではない
聴覚障害は「情報障害」と言われてるんだって。「聞こえる人なら当たり前に受けられる情報が、受けられない」ということで、周りにその気がなくても、当人は疎外されているように感じ、自分が他人より劣っているように思えてきちゃう。
■ 聞こえない健聴者
とはいえ、耳は聞こえても、相手の気持ちが聴こえないコトだってある。健聴者は、聴覚障害者を夢中で支援することで、相手の気持ちを傷付けちゃうことだってある。「支援の押し売りだ」、気をつけなくっちゃ!?
■ 障害者の中での差別?
難聴者と聾者は違う。難聴者は障害者であることが知られることを嫌い、難聴であることを隠して生きている人が多いんだって…。「自分たちは聾者とは違う!」って差別意識(?)を持っちゃうのかな~?
昔、マクセルのCMでスティービー・ワンダーが言ってたコメントを想い出した。こまかなコトは覚えてないけれど、「君には輝く太陽が見える、僕には君の心が見える…」とかいうCMだったと思うんだけど…
こんなこと言ってる人もいます。「物を見るのは魂であり、目それ自体は盲目である。物を聞くのは魂であり、耳それ自体は聾である」。う~ん、深い!

2007年05月16日
モチベーション・ストラテジー(Blog編)
~小笹芳央 著~
リンクアンドモチベーション代表、小笹芳央氏の著書。
第1~2章は「組織の新陳代謝」に関して、第3~4章は「組織の病気や具体的な診断方法」について、第5~7章は「組織療法」、第8章では「組織変革のメカニズム」を紹介している。
会社と社員の関係が、『相互拘束』から『相互選択』の時代に移行していることも、組織の入り口を管理する『エントリーマネジメント』の重要性も、組織拡大に伴う各種症例も、小笹氏のおっしゃるとおり。
とはいえ、書いてる切り口が特別新しいと感じられなかったのも事実。小笹氏の著書は始めてだし、且つ個人的に結構注目していただけに、チョッピリ残念!?
まぁ、コンサルティングファームの社長が、書籍で手の内全てを明かすはずもなく、「続きは、個別コンサル契約で…」ってコトなんでしょうかね。

リンクアンドモチベーション代表、小笹芳央氏の著書。
第1~2章は「組織の新陳代謝」に関して、第3~4章は「組織の病気や具体的な診断方法」について、第5~7章は「組織療法」、第8章では「組織変革のメカニズム」を紹介している。
会社と社員の関係が、『相互拘束』から『相互選択』の時代に移行していることも、組織の入り口を管理する『エントリーマネジメント』の重要性も、組織拡大に伴う各種症例も、小笹氏のおっしゃるとおり。
とはいえ、書いてる切り口が特別新しいと感じられなかったのも事実。小笹氏の著書は始めてだし、且つ個人的に結構注目していただけに、チョッピリ残念!?
まぁ、コンサルティングファームの社長が、書籍で手の内全てを明かすはずもなく、「続きは、個別コンサル契約で…」ってコトなんでしょうかね。

2007年05月10日
原稿用紙10枚を書く力(blog編)
~齋藤孝 著~
静岡市出身の大学教授、齋藤孝先生の著書。最近、痛感する『書く力』の大切さ!思わず手を伸ばしてしまった。
私自身、企画書や報告書を書く機会も多い。そんな中、「あそこはもっと掘り下げた方がよかった」とか「まったく違った切り口で仕上げること、出来たかも…」等々、書き上げたあとに後悔することも数知れない。
また、学生のエントリーシート作成講座や転職者の職務経歴書指導の場面でも『書く力』の大切さを感じる。「うまく書けませ~ん」ってフリーズ状態になっちゃう人が如何に多いことか…。
で、この際チェックしなくちゃならないのが、「書きたいことはあるのに、うまく表現できない?」のか「書くこと自体が思い浮かばないのか?」ということ。前者の場合は、推敲を重ねることによって問題解決できるけれど、圧倒的に多いのは後者のパターン。
要は、エントリーシートにしても応募書類にしても、「どんな目的で書くのか?」「どう書けば、目的達成に近づくのか?」を、「な~んにも、考えていない」って人が多いということ。
そんなみなさんに、齋藤先生の著書から抜粋してプレゼント!?
■ 文字を書く力がつくということは、内容のある話ができるようになることでもある。なぜなら、それは考える力がつくからだ。
■ 考える力があるかどうかが、その人の人生を大きく左右するようになる。これからは、書く力をつちかって考える力を身につけることがますます重要になるのだ。
ですって、興味を持てたら文庫本552円に投資してみて…

静岡市出身の大学教授、齋藤孝先生の著書。最近、痛感する『書く力』の大切さ!思わず手を伸ばしてしまった。
私自身、企画書や報告書を書く機会も多い。そんな中、「あそこはもっと掘り下げた方がよかった」とか「まったく違った切り口で仕上げること、出来たかも…」等々、書き上げたあとに後悔することも数知れない。
また、学生のエントリーシート作成講座や転職者の職務経歴書指導の場面でも『書く力』の大切さを感じる。「うまく書けませ~ん」ってフリーズ状態になっちゃう人が如何に多いことか…。
で、この際チェックしなくちゃならないのが、「書きたいことはあるのに、うまく表現できない?」のか「書くこと自体が思い浮かばないのか?」ということ。前者の場合は、推敲を重ねることによって問題解決できるけれど、圧倒的に多いのは後者のパターン。
要は、エントリーシートにしても応募書類にしても、「どんな目的で書くのか?」「どう書けば、目的達成に近づくのか?」を、「な~んにも、考えていない」って人が多いということ。
そんなみなさんに、齋藤先生の著書から抜粋してプレゼント!?
■ 文字を書く力がつくということは、内容のある話ができるようになることでもある。なぜなら、それは考える力がつくからだ。
■ 考える力があるかどうかが、その人の人生を大きく左右するようになる。これからは、書く力をつちかって考える力を身につけることがますます重要になるのだ。
ですって、興味を持てたら文庫本552円に投資してみて…

2007年04月30日
う~ん、感動した!?
芸人学生-僕が学びつづける理由
そのまんま東
現宮崎県知事、東国原英夫氏が2年半ほど前に書いた本。芸能人の本なんて、興味も無いし読むつもりも無かったのだが…
不祥事を起こしてから自身の人生を振り返り、学ぶこと、生きることを問い直すために大学に入学。そして勉学に励む日々…。東氏のあまりのひたむきさに、一気に読破してしまった。
40歳過ぎると死を意識するっていうのもわかるし、「生きることは学び続けることなんだな~」とあらためて考えさせられた。
学生から、僕らみたいな中高年まで、みんなに読んで欲しいので敢えて細かい内容に関しては言及しないけど、読む価値大!!後期の授業の課題図書にしようかな~

そのまんま東
現宮崎県知事、東国原英夫氏が2年半ほど前に書いた本。芸能人の本なんて、興味も無いし読むつもりも無かったのだが…
不祥事を起こしてから自身の人生を振り返り、学ぶこと、生きることを問い直すために大学に入学。そして勉学に励む日々…。東氏のあまりのひたむきさに、一気に読破してしまった。
40歳過ぎると死を意識するっていうのもわかるし、「生きることは学び続けることなんだな~」とあらためて考えさせられた。
学生から、僕らみたいな中高年まで、みんなに読んで欲しいので敢えて細かい内容に関しては言及しないけど、読む価値大!!後期の授業の課題図書にしようかな~

2007年04月28日
新幹線ガール
22歳の新幹線パーサー、徳渕真利子さんのお話。
ホテルの仕事にあこがれて一流ホテルに就職するも、思い描いたイメージと現実のギャップに落胆し退職。
その後、求人情報誌で「新幹線パーサー」の仕事を見つけてアルバイトパーサーとして仕事をはじめ、2005年12月に正社員登用。その年、全社員パーサー300人中、売上げNo.1に輝いたというもの。
挫折を味わいながらも、現在、充実したシゴトをしている徳渕さんにすっごく共鳴できたし、新幹線という閉じられた空間の中で、平均売上げの3倍もの売上げを上げられる徳渕さんの凄さもよくわかった。
残念なのは、紙面の大半が「新幹線パーサー」のお仕事紹介に終始していたということ。個人的には、ホテルへの憧れから挫折、パーサーのシゴトへのプライドを持つに至るまでの心の機微にスポットを当ててもらいたかったのだが…
意図通りの本だったら、「授業のテキストに使えるかな~」と思ってたんだけど…。
まぁ、取材&構成者の意図は、僕と違うところにあったということで、しゃ~ないか?!

ホテルの仕事にあこがれて一流ホテルに就職するも、思い描いたイメージと現実のギャップに落胆し退職。
その後、求人情報誌で「新幹線パーサー」の仕事を見つけてアルバイトパーサーとして仕事をはじめ、2005年12月に正社員登用。その年、全社員パーサー300人中、売上げNo.1に輝いたというもの。
挫折を味わいながらも、現在、充実したシゴトをしている徳渕さんにすっごく共鳴できたし、新幹線という閉じられた空間の中で、平均売上げの3倍もの売上げを上げられる徳渕さんの凄さもよくわかった。
残念なのは、紙面の大半が「新幹線パーサー」のお仕事紹介に終始していたということ。個人的には、ホテルへの憧れから挫折、パーサーのシゴトへのプライドを持つに至るまでの心の機微にスポットを当ててもらいたかったのだが…
意図通りの本だったら、「授業のテキストに使えるかな~」と思ってたんだけど…。
まぁ、取材&構成者の意図は、僕と違うところにあったということで、しゃ~ないか?!

2007年04月25日
小泉官邸秘録
この手の本、ふだんはあまり読まないんだけど…。本屋さんで何故か手を伸ばしてしまった。
内容的には、「あ~、あんなこともあったな、こんなこともあったな~」ってことが書いてあり、『秘録』というより『記録』という感じだけれど…。きっちりまとめてあり、よろしいんじゃないでしょうか?
小泉さんの政策には賛否があると思うけど、官邸の政策決定機能を『調整型』から『トップダウン型』変えたってことにだけは、異論はないんじゃないだろうか?
一般的に官邸とは、総理大臣が指揮して、政策決定をする場と理解されているけれど、実質的な組織の頂点は官房長官で、総理大臣は承認の機能しか持たない。官房長官によって、政府・与党との調整も全て行われ、方向性が決まった時点で「うん、いいよ!」という具合だ。
まぁ、そういった意味では、小泉さんは「トップダウン型の政策決定」のリーダーシップを発揮した唯一(?僕の生まれる前のことは知りませんが…)の首相だと言えるんじゃないでしょうか。

内容的には、「あ~、あんなこともあったな、こんなこともあったな~」ってことが書いてあり、『秘録』というより『記録』という感じだけれど…。きっちりまとめてあり、よろしいんじゃないでしょうか?
小泉さんの政策には賛否があると思うけど、官邸の政策決定機能を『調整型』から『トップダウン型』変えたってことにだけは、異論はないんじゃないだろうか?
一般的に官邸とは、総理大臣が指揮して、政策決定をする場と理解されているけれど、実質的な組織の頂点は官房長官で、総理大臣は承認の機能しか持たない。官房長官によって、政府・与党との調整も全て行われ、方向性が決まった時点で「うん、いいよ!」という具合だ。
まぁ、そういった意味では、小泉さんは「トップダウン型の政策決定」のリーダーシップを発揮した唯一(?僕の生まれる前のことは知りませんが…)の首相だと言えるんじゃないでしょうか。







